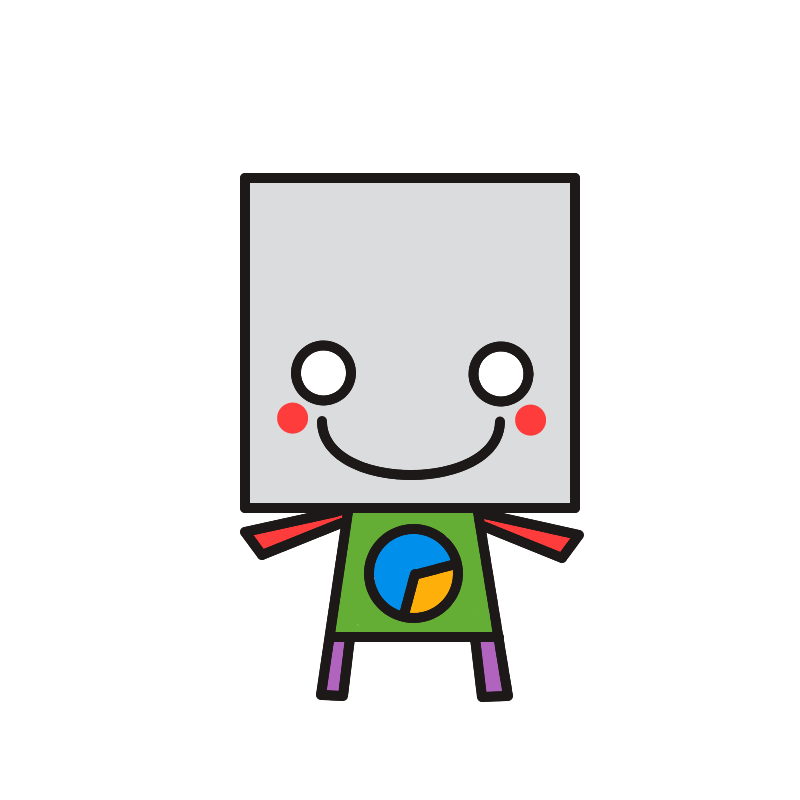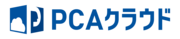個人事業主の確定申告の方法!経費・やり方などを簡単に解説

「確定申告」の言葉は知っていても、実際はどうすればいいのかわからない状態ではありませんか。そこで、今さら聞けない個人事業主の確定申告の基礎の基礎から解説します。
 | 1年間無料キャンペーン中! セルフプラン 年額26,000円/月1,857円 初年度は半額キャンペーン中! サポート付プラン 年額30,000円/月2,142円 >>お申し込みはこちら | 無料 白色申告機能+サポート付 年額4,000円/月333円 青色申告機能のみプラン 初年度無料 青色申告機能+サポート付 年額6,000円/月500円 >>無料体験する | ||||||||
目次を閉じる
- 確定申告とは
- 確定申告の対象者(個人事業主の場合)
- 確定申告の期間
- 青色申告と白色申告の違い
- 確定申告までの流れと手続き
- 1.「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出
- 2. 日々の取引を記帳
- 3. 書類の準備
- 4. 確定申告書を提出する
- 確定申告の注意点
- 帳簿作成は義務
- 帳簿の保存期間は7年・5年
- 押印義務はない
- 個人事業主の確定申告におすすめなサービス
- やよいの青色申告 オンライン
- マネーフォワード クラウド確定申告 - 個人の確定申告・会計から人事労務までを1アカウントで
- freee会計・確定申告 - 面倒な作業を複数回クリックでカンタン・口座連携で業務も短縮
- きちんとした知識を身に着けておけば確定申告は怖くない!
- BOXILとは
確定申告とは
確定申告とは毎年の1月1日から12月31日までに事業で得た所得を計算し、税務署に詳細を申告することです。確定申告によって納税額が決まるので、個人事業主を中心に対象者は申告が義務付けられています。
確定申告の対象者(個人事業主の場合)
個人事業主のうち確定申告を必要とする主な対象者は次のとおりです。なお、そのほかの特殊な条件については国税庁「確定申告が必要な方」にて確認できます。
- 事業所得が48万円以上の個人事業主
- 副収入が20万円以上の個人事業主
- 公的年金の受給額が400万円以上かつ源泉徴収を受けていない個人事業主
個人事業主における「副収入」とは、企業に勤めながら個人事業主を別にしている場合に発生する収入です。企業に勤めていて副収入となる所得が20万円を超えないのであれば、個人での確定申告は不要です。
確定申告の期間
確定申告の期間は2月16日〜3月15日です。この間に前年分の申告しましょう。もし申告期間内を過ぎてしまった場合、正当な理由がなければ遅延税が発生します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。基本的には白色申告が適用されますが、開業時に税務署に開業届とともに青色申告の申請書を提出していれば、青色申告が可能です。
白色申告は、ほとんど手間がかからないものの、特に節税効果がありません。一方、青色申告は、手続き上の手間はかかるものの、最大65万円の特別控除が受けられたり、事業の赤字を翌年以上の所得から差し引けたりするなどのメリットがあります。つまり、青色申告の方が節税になり、さまざまな優遇が受けられるのです。
確定申告までの流れと手続き
では、個人事業主の確定申告の流れと手続きを解説します。確定申告に必要な書類と申告の手順をしっかりと理解しておきましょう。
1.「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出
個人事業主として事業をスタートする際、まずは税務署へ「開業届」を提出します。また青色申告をする場合はあわせて「青色申告承認申請書」も提出します。
いずれも最寄りの税務署の窓口で受け取れるほか、国税庁の開業届と青色申告承認申請書のリンクよりダウンロード可能です。
2. 日々の取引を記帳
確定申告に向けて1年間の収支を記帳しておきましょう。売上と経費それぞれを特定の勘定科目に分類したうえで記載します。なお、領収書をはじめとした書類は証憑として必要であるため大切に保管しておきましょう。
仕訳は事業1年目の人にとっては難しく感じられるかもしれませんが、個人事業主向けの会計ソフト(青色申告ソフト)を活用すれば、簡単に仕訳作業ができるのでおすすめです。個人事業主向けの会計ソフトに関しては、次の記事も参考にしてください。

3. 書類の準備
年が明けて売上や経費が確定したら、申告に必要な書類を準備しましょう。確定申告には「確定申告書B」と「青色申告決算書(あるいは収支内訳書)」に加えて、税金の控除を受けるための証明書などが必要になります。
確定申告書B
個人事業主の場合、確定申告書Bを提出します。第一表と第二表があるので記入漏れに気をつけながら記載しましょう。
なお、確定申告書Aは会社員やアルバイトの人向けのもので、個人事業主の場合は不要です。e-TAXの場合はインターネットにて作成できるほか、郵送の場合は国税庁のホームページからダウンロードして作成できます。
青色申告決算書
青色申告決算書は青色申告をする際に提出するもので、事業の損益の状況と内訳、貸借対照表の内容を記載します。一般用と不動産所得、農業所得などの様式がありますが、通常の事業所得は一般用を使います。
一方、白色申告をする場合は、収支内訳書を作成しましょう。こちらも事業の売上や経費などの情報を記入し、所得金額を計算したものを提出します。
税金の控除に必要な書類
税金の控除を受ける場合には、証明するための書類が必要です。たとえば、ふるさと納税で税金の控除を受ける場合は、寄付をした自治体から送られた寄附金受領証書や該当する期間の源泉徴収票などが必要です。
ただし、一定の条件のもとで確定申告をする必要がないケースや、つみたてNISAのように申告が不要なケースもあるので、提出すべき書類については事前に確認しておきましょう。
4. 確定申告書を提出する
必要な書類を作成したら確定申告を行いましょう。申告書の提出には次の3つの方法があります。
- 税務署に申告書を持参する
- 税務署に申告書を郵送提出する
- e-Taxを使ってインターネットから申告する
初めて確定申告をする人で、細かい手続きや記入事項などがわからない場合は、税務署で申告をするとよいでしょう。署員に確認しながら申告書を作成できます。
e-Taxでの申告がおすすめ
できるだけ時間をかけずに申告をしたい人はe-Taxを活用しての申告がおすすめです。事前に電子証明書を取得して、e-Taxに登録作業をする必要がありますが、一度登録しておけば、それ以後の確定申告をインターネット上で行えるようになるので便利です。
また2020年度より複式簿記による記帳で受けられる控除は55万円に引き下げられましたが、e-Taxによる申告あるいは電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます※。控除額が最大になるため、e-Taxでの申告はメリットが大きいといえるでしょう。
※出典:国税庁「青色申告特別控除額が変わります!!」(2022年3月23日閲覧)
確定申告の注意点
帳簿作成は義務
ほとんどの個人事業主には「帳簿作成の義務」が課せられています。確定申告の有無は基準所得金額によって決定するものの、帳簿作成の義務は事業所得、不動産所得、山林所得におけるいずれかの所得によって発生。ゆえに、大半の個人事業主は帳簿の作成が必要といえます。
帳簿の保存期間は7年・5年
帳簿の保存期間は法定帳簿であれば7年間、それ以外の帳簿であれば5年間です。法定帳簿は収入や経費の金額を記した帳簿、それ以外の帳簿には売掛帳や買掛帳などが該当します。個人事業主であっても抜き打ちにて税務調査が発生するため、帳簿の保存は必須です。
押印義務はない
2022年確定申告より、税務関係書類に押印義務がなくなりました。これまで氏名記載のうえ、押印が必要でしたが、今後は不要になります。
個人事業主の確定申告におすすめなサービス
続いて、個人事業主の確定申告におすすめの会計ソフトを紹介します。いずれもクラウド型でスムーズに導入でき、使い勝手のよいサービスです。詳しい会計知識がなくても使いこなせる点も共通しています。それではクラウド型の申告書作成サービスについて紹介します。
| サービス名 | 対応デバイス | 価格(税抜) | お試し期間 |
|---|---|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | Windows, Mac, スマートフォン | 8,000円〜/年 | 1年間 |
| やよいの白色申告オンライン | Windows, Mac, スマートフォン | 0円〜/年 | 制限なし |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | Windows, Mac, スマートフォン | 9,600円〜/年 | 1か月間 |
| freee | Windows, Mac, スマートフォン | 11,760円〜/年 | 30日間 |
やよいの青色申告 オンライン
▼やよいの青色申告 オンライン【Sponsored】
■Point1:クラウド確定申告ソフトシェアNo.1
やよいの青色申告 オンラインはクラウド確定申告ソフトシェアNo.1で、2人に1人に利用されているサービス(公式サイト参照)。
■Point2:トータルプランは電話サポートが付帯
トータルプランでは、操作サポート・業務相談の電話サポートが付帯しています。操作方法はもちんのこと、申告業務全般に関する相談ができます。
■Point3:業界最大規模のカスタマーサポート
業界最大規模のオペレーター座席数700席、顧客満足度94%※とカスタマーサポートが充実しています。電話・メール・チャットでのサポートだけではなく、画面共有サポートで同じ画面を見ながら案内するサービスも用意されています。
※出典:弥生会計「やよいの青色申告 オンライン」(2022年3月23日閲覧)
■各プランの比較
やよいの青色申告 オンラインの価格
| プラン名 | 年額料金(税抜) |
|---|---|
| セルフプラン | 8,000円 |
| ベーシックプラン | 12,000円 |
| トータルプラン | 20,000円 |
※出典:弥生「やよいの青色申告 オンライン」(2022年3月23日閲覧)
やよいの白色申告 オンラインの価格
| プラン名 | 年額料金(税抜) |
|---|---|
| セルフプラン | 無料 |
| ベーシックプラン | 8,000円 |
| トータルプラン | 14,000円 |
※出典:弥生「やよいの白色申告 オンライン」(2022年3月23日閲覧)
マネーフォワード クラウド確定申告 - 個人の確定申告・会計から人事労務までを1アカウントで

マネーフォワード クラウド確定申告の価格
| プラン名 | 年額料金(税抜) |
|---|---|
| パーソナルミニ | 9,600円 |
| パーソナル | 11,760円 |
| パーソナルプラス | 35,760円 |
※出典:マネーフォワード「マネーフォワード クラウド確定申告」(2022年3月23日閲覧)
マネーフォワード クラウド確定申告は、経費精算システムや給与計算システムとの連携が便利なソフトです。3人までであれば追加料金なしで、バックオフィス業務までまかなえます。銀行口座やクレジットカードの登録によって入出金データを自動登録できるのも便利です。
freee会計・確定申告 - 面倒な作業を複数回クリックでカンタン・口座連携で業務も短縮

freeeの価格
| プラン名 | 年額料金(税抜) |
|---|---|
| スターター | 11,760円 |
| スタンダード | 23,760円 |
| プレミアム | 39,800円 |
※出典:freee「確定申告ソフト」(2022年3月23日閲覧)
数多くの企業が利用する会計ソフトfreeeの個人向け確定申告ソフトです。画面構成がわかりやすく、簿記の知識がないユーザーでも簡単に確定申告をできます。とくに勘定科目の登録はポップアップで簡単な説明が出てくるので、すぐに仕訳ができます。親しみやすいデザインも操作しやすいポイントのひとつです。口座との連携やスマートフォンでの入力にも対応しており安心して利用できるでしょう。
きちんとした知識を身に着けておけば確定申告は怖くない!
個人事業主は、とくに納税額が生活に大きく関わってくる可能性が高いです。本記事の内容を参考に、毎年必ず確定申告をして、税金対策は万全にしておきましょう。
また、帳簿をつけるのが面倒に感じられる方も多いかもしれませんが、帳簿をしっかりつけておけば、日々のお金の出入りが把握できて、ビジネスの改善点も見えてきます。最近の確定申告ソフトははじめての方も使いやすく、サポートも充実しています。ぜひ検討してみてくださいね。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査