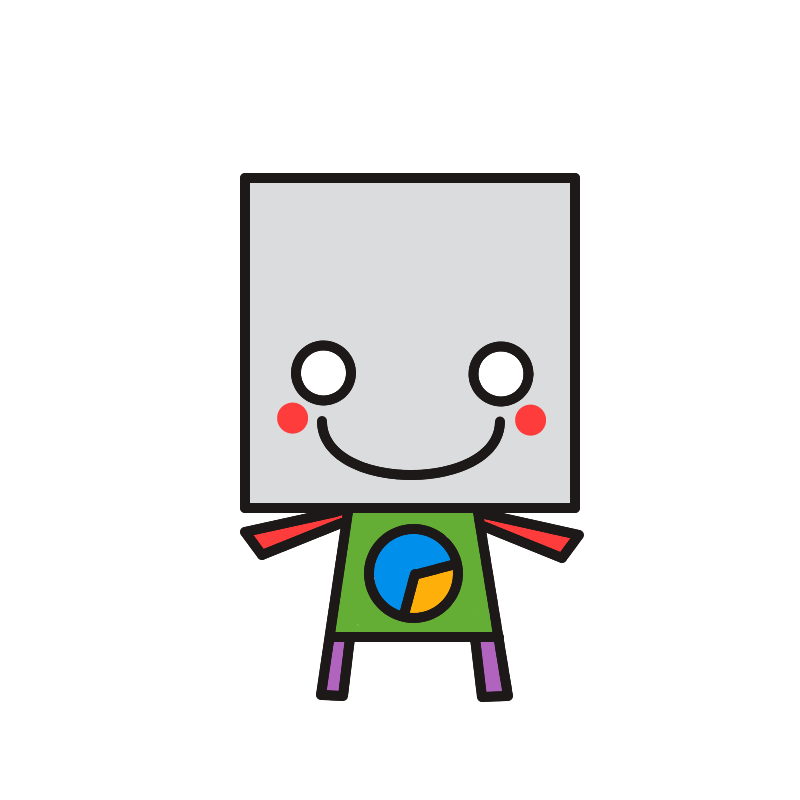エスノグラフィーとは?調査・活用方法、メリット - マーケティングにおける行動観察

エスノグラフィーとは本来は社会学や文化人類学といった学術的な分野の用語であり、あまりなじみのない言葉でした。
しかし、近年はこの手法が企業のマーケティングや商品開発に応用されはじめており、顧客の真のニーズを把握するための行動観察手法として注目されています。
そこで、このエスノグラフィーという手法について、基本的な用語の説明から実際の調査手法について解説をしていきます。
目次を閉じる
- エスノグラフィーとは
- エスノグラフィー調査とは
- エスノグラフィーの企業活動への利用
- 商品開発やマーケティングへの応用
- エスノグラフィー具体的な調査プロセス
- 仮説を立てる
- 顧客と同じ環境で行動観察をする
- 適宜ヒアリングをする
- 商品開発案・デザイン案などを修正する
- エスノグラフィー活用のメリット
- 顧客の日常的なニーズを把握できる
- インタビュー方式の欠点を埋められる
- リアルな現象として具体的なレポートを得られる
- 現場でどのようなことが問題になっているのかを理解できる
- エスノグラフィーの実例
- PARCとコピー機の事例
- インテルとyoutubeの動画の例
- 花王のアンチエイジング
- 京都大学ともの作りプロジェクト
- エスノグラフィーをマーケティングに応用する
- マーケティング担当者必見の記事
- BOXILとは
エスノグラフィーとは
エスノグラフィー(ethnography)とは、本来は社会学や文化人類学の用語であり、ある集団や組織、社会に所属する人々の行動様式をフィールドワークなどの実地調査によって記録していく手法のことをいいます。
語源的にはギリシア語の「ethnos(人々)」と「grapehin(描く)」という2つの言葉を組み合わせたものであり、主に文化人類学の研究において、さまざまな民族の生活・行動様式について現地調査をしながら詳細に記録していく方法のことを指していました。
しかし近年は、この手法がビジネス分野で注目され、企業のマーケティングやプロジェクトマネジメントに関する調査に有効な手法として応用されはじめています。
エスノグラフィー調査とは
エスノグラフィーを用いた調査では、調査員が対象となる集団やグループと生活をともにすることで、その生活習慣や行動様式を直に体験することが重視されます。
それによって、「ある国の民族がどういった暮らしをしているか」「どういう信条や価値観のもとで行動しているのか」といったポイントについて直感的に理解することを目的としています。
これによって噂や伝聞、あるいはマクロデータなどでは見えてこない、対象者の本当の姿を感覚として知ることができるようになるわけです。
エスノグラフィーの企業活動への利用
最近ではこの手法に注目した企業が、同じような方法で見込み客の生活について実地調査を行うようになってきました。
たとえば企業の調査員が顧客グループの生活に密着し、その考え方や行動を観察しながら、時折インタビューや座談会といったヒアリングをするといったやり方です。
これによって顧客の本音や考え方、行動パターンなどを把握しようという試みですが、実際にこの手法で成果を上げている企業も登場しはじめています。
エスノグラフィーは、学術分野のみならず、ビジネスでも有効であることが明らかになっているのです。

商品開発やマーケティングへの応用
事実、エスノグラフィー調査をマーケティングに用いると、なかなか表には出てこない彼らの本当の問題意識やニーズを発見しやすくなります。
顧客自身も自覚していない潜在意識下での行動を観察できる点が大きく、その部分にこそ真の顧客ニーズが現れるともいわれています。
これを自社の商品に活かすことができれば、一方的なアンケート調査をもとに開発をするよりも、圧倒的に顧客のを反映できるようになるわけです。
商品開発への応用
たとえば商品開発に応用する場合は、あらかじめ想定される見込み客の集団を割り出し、その人々に密着することで、当初のニーズ予想が本当に正しいのか、隠れたニーズはないかといった調査をすることができます。
その結果によって、商品企画に変更を加えたり、ターゲット層をシフトするといった対策をとることができます。
デザイン企画への応用
また、すでに発売している自社商品についてエスノグラフィー調査をすることで、ターゲット顧客が実際にどういう商品の使い方をしているのか、使ってみてどういう不便さを感じているかといった事柄について詳しく知ることができるでしょう。
その情報を新商品のデザインへと反映すれば、より顧客にとって使いやすい商品を開発することが可能になります。
エスノグラフィー具体的な調査プロセス

企業のマーケティングにおけるエスノグラフィー調査の具体的なプロセスとしては、以下のステップが考えられます。
仮説を立てる
顧客データや売上データなどを用いて、調査対象についての仮説を立てます。何も考えずに調査現場に行けば必要な情報が集まるということはありません。
観察を始める前の段階で、しっかりと「顧客は○○というニーズをもっている」とか「○○に不便さを感じている」といった仮説を立てておくことが重要です。
顧客と同じ環境で行動観察をする
調査対象と全く同じ環境で生活してみるなど、同じ視点で同じ体験をすることが重要です。これによって、顧客の行動の理由や考え方の傾向などを掴むことができます。
適宜ヒアリングをする
必要に応じて、聞き取り調査やアンケート、座談会などを開催してヒアリングを行うことが肝要です。これによって当初の仮説が本当に正しいのか、隠れたニーズはないかを確認していきます。
商品開発案・デザイン案などを修正する
調査によって得られた情報を商品開発やデザイン案などに反映します。当初の仮説と大幅に違っていたとしても、それが顧客の本当のニーズですから、真摯に受け止める必要があるでしょう。
エスノグラフィー活用のメリット
企業活動にエスノグラフィーを活用することにより、主に以下のメリットを得ることができます。
顧客の日常的なニーズを把握できる
これまで述べてきたように、顧客の日常的なニーズや顧客自身も気づいていないような隠れたニーズ・ウォンツについて把握できるようになります。
これは一方的なアンケート調査などでは決して得られない貴重な情報であり、これを商品開発やサービスに活かすことで、顧客の望みをダイレクトに叶えることが可能になるでしょう。
インタビュー方式の欠点を埋められる
企業のマーケティング活動のなかには、インターネットを用いたアンケートや、謝礼を払って見込み客にインタビューさせてもらうものがあります。
しかし前述のように、これだけでは見込み客の本当にニーズを知ることは容易ではありません。顧客はインタビュー用に「作られた回答」をしたり、一般的な常識に拠った模範回答に終始してしまう可能性が高いからです。
一方、エスノグラフィー調査では、実際に顧客と生活をともにしたり同じ体験を共有することができます。これによって、顧客の本当の行動を観察できますし、調査員自身も顧客視点で商品・サービスの評価ができるようになります。
リアルな現象として具体的なレポートを得られる
対象グループの視点や実際の生活状況を知ることにより、これまで開発側で無視されてきた要素や重視していなかったポイントについて発見することができます。
これによって、今まで仮説の領域を出なかった事柄や抽象的な概念に留まっていた要素について、現実に根ざした具体的な情報として共有することが可能になります。
現場でどのようなことが問題になっているのかを理解できる
実地で行動観察をすることにより、実際に商品が使われている現場やサービスが提供されている現場で何が問題となっているのかを理解できるようになります。
顧客アンケートなどからは見えづらい顧客の生の反応を観察することにより、隠れた問題点や改善ポイントを炙り出すことが可能になります。


エスノグラフィーの実例
最後にエスノグラフィーの実例について、企業がその手法をマーケティングに応用したケースを中心に簡単に紹介しておきます。
PARCとコピー機の事例
商品開発にエスノグラフィーの手法を取り入れた先駆けとして有名なのが、ゼロックス子会社のPARC(Palo Alto Research Center)です。
文化人類学者のLucy Suchmanは、同社でコピー機のユーザーが実際にどのように使っているのかをビデオ撮影し、フィルムにまとめました。それによって当時のコピー機の問題点を洗い出し、実際の商品開発に応用することで成功を収めました。
インテルとyoutubeの動画の例
半導体素子メーカーとして有名なインテルは、教室で子供達がパソコンをどう使うのかを観察し、その情報を応用することで「Classmate PC」を開発したことが有名です。その様子はYoutubeに「Research background of the new version of classmate PC」として投稿され、多くの反響を呼びました。
花王のアンチエイジング
日本企業では、花王が他社に先駆けてエスノグラフィーをマーケティングに取り入れたことで話題になりました。
同社は顧客がアンチエイジングに注目する背景について調査するため、エスノグラフィーの手法を使って半年にも及ぶ実地調査を行いました。それによって、一部の見込み客がどういう心境でアンチエイジングに取り組んでいるのかを明らかにし、それが一般消費者にも当て嵌まることを明らかにしました。
京都大学ともの作りプロジェクト
京都大学がモノに対する潜在的ニーズをの発見のため、エスノグラフィーを用いた調査を行ったこともあります。
学生達が大学構内を散策し、調査対象が実際に利用されている現場を観察・レポートすることによって、モノに対する潜在的なニーズを分析しようとした試みでした。
エスノグラフィーをマーケティングに応用する
近年、ビジネス分野でも注目されているエスノグラフィーについて、基本的な説明から実際の調査方法、そして実際の企業の事例を解説をしてきました。
対象グループと同じ体験や生活をするといった調査法は、これまで企業が用いてきた一方的な調査法よりも、顧客のリアルな行動やニーズを炙り出せる点で非常に有用といえるでしょう。
自社の状況に応じてさまざまな応用がきく手法でもありますから、企業のマーケティング担当の方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
マーケティング担当者必見の記事



BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査