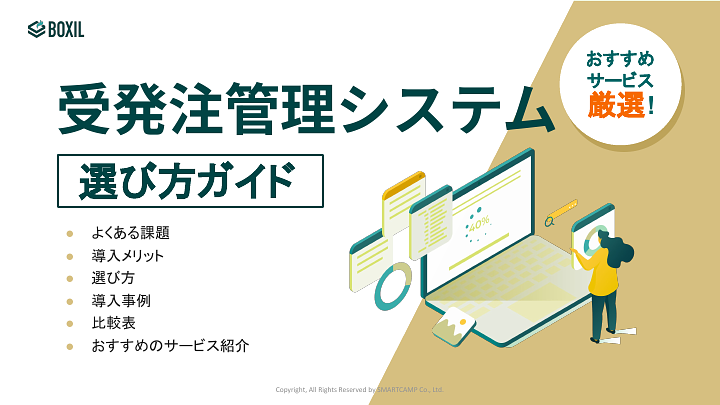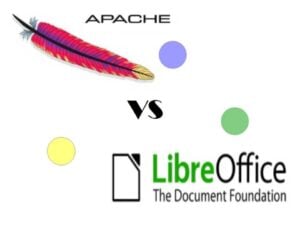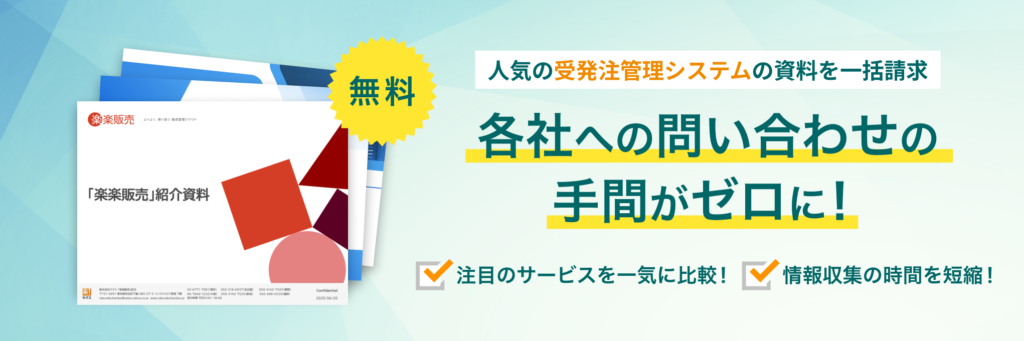発注管理とは
発注管理とは商品を製作するために、必要な資材や販売する商品を問屋から購入するといった仕入れを管理する業務です。代表的な業務は次のとおりです。
- 在庫状況の把握および補充
- 発注先の選定
- 発注スケジュール管理
- 発注フローの管理
発注管理が機能していない場合、原材料や商品を必要以上に仕入れたり、仕入れの数が少なかったりすることで、コストの増大や機会損失を招く恐れがあります。
利益の最大化やムダなコストの削減のために発注管理は重要な業務のひとつです。
発注管理と関連する業務領域
発注管理と関連する代表的な業務には次のものがあります。
- 在庫管理
- 生産管理
- サプライチェーン管理
発注業務は在庫状況に大きく左右されるため、適切な在庫把握なしの発注は過剰在庫や機会損失を招くリスクがあります。同様に、生産能力を考慮せずに発注すると、余剰資材による保管コストが増大する問題が発生します。
また、サプライヤー管理との連携不足はリードタイムの増加や人的リソースのムダ遣いといった課題を生み出すこともあります。
このように発注管理は他の業務と密接に関連しているため、各領域と効果的に連携させることが重要です。
発注管理のプロセスと業務フロー
発注管理のプロセスと業務フローは次の順番で行われます。
- 発注フローの整備
- 購買依頼書の作成
- 発注方式の決定
- 発注先の選定と契約
- 注文(発注)書の作成・送付
- 発注状況の管理
それぞれのフローについて、詳しく解説します。
発注フローの整備
発注をどのように進めていくかを整備する必要があります。担当者は誰なのか、どの発注先に何の発注を行うかをあらかじめ決めておかないと、金銭的、人的コストがムダに発生してしまいます。
実際に発注先との連絡手段を検討し、統一することでスムーズなコミュニケーションが可能です。発注フローの作成方法にはExcelの使用や、発注管理システムの利用などがあります。
Excelを利用する際は、テンプレートや各種機能を活用すると効率的ですが、発注管理システムを利用することで、より簡単に発注フローの作成が可能です。
購買依頼書の作成
発注フローを整備したら購買依頼書を作成します。購買依頼書とは、資材や商品を必要とする部門が購買部門へ購入依頼をする書類です。具体的には商品や資材の種類やロット数、希望納期、納入場所などを記載します。
作成する際は過去のデータを参考に需要を予測して数量や取引先、予算を決めるのが重要です。また、共通するフォーマットに沿って作成し、細かい条件も明示することでお互いの誤解を防ぎ、ムダな購買や不正を防げます。
発注方式の決定
次に発注方式を決定します。発注方式には定期発注方式と定量発注方式があり、企業規模や商品、需要に応じて適切な方式を選ぶのが重要です。
定期発注方式は、名前のとおり定期的に発注する方式です。たとえば、毎週月曜日に発注する、毎月月末に発注するといった方式になります。過去の需要や生産量に鑑みてどの程度の数量を発注するか決められるため、クリスマス商品のように季節によって需要が変動する場合に効果的です。
定量発注方式は、一定の決められた在庫量を下回ったら発注する方式になります。たとえば、在庫数が100を切ったら発注するといった形式です。在庫数量によって発注タイミングが変わるため、過剰発注を防げるといったメリットがありますが、需要の変動に弱い点がデメリットです。
発注先の選定と契約
購買依頼書にもとづいて発注先を選定し、契約します。契約時の注意点としては自社の要望を満たしているかを確認することです。とくに初めて取引をする発注先だと要望を満たせるかどうかの判断は困難です。
したがって、リスクを減らすために少ない発注量から始めて、問題がなければ少しずつ増やすとよいでしょう。
他にもこちらの意図を汲み取れるか、コミュニケーションに問題はないかといった点にも注意が必要です。
注文(発注)書の作成・送付
発注先が決まり、契約が終了したら発注書を作成し、送付します。発注先は送られてきた発注書を確認して資材や商品を用意するため、内容に不備がないか確認してから送付するのが重要です。
発注書は紙で作成することもあればメールで送付することもあります。発注先の同意があればどちらでも問題はありませんが、発注管理システムで管理しやすいため、メール添付が効率的です。
発注書は必ずしも発行しなければいけないわけではありませんが、発行されないと認識の違いが起きやすくなり、トラブルにつながる可能性があります。
発注状況の管理
発注書を作成し、取引先へ送付したら発注状況の管理をします。発注状況を管理することは、誤発注といったミスを防ぐためにも重要です。
発注状況を管理するには発注管理システムの導入が効果的です。発注管理システムを導入すれば、発注状況を把握するだけでなく、購買依頼書や発注書を作成できるため、発注業務を効率化できます。
発注管理の効率化におすすめの方法
発注管理の効率化には、主に次の2つの方法があります。
- Excelやスプレッドシートの活用
- 発注管理システムの導入
それぞれについて詳しく解説します。
Excelやスプレッドシートを活用した効率化
Excelやスプレッドシートを活用するのが効率化の方法のひとつです。注文書の作成や購買依頼を行った部署の明記、発注した品目や数量をまとめて管理します。
Excelやスプレッドシートは低コストで導入可能、運用が容易である、スプレッドシートの場合は共有も可能といったメリットがあります。一方で、シートを1から作成しなければならない、セキュリティ面に不安がある点がデメリットです。
発注管理をExcelやスプレッドシートで行う場合はテンプレートを活用すると作成の負担を減らせます。無料でダウンロードできるテンプレートがあるため、コストもかかりません。
また、「SUMIF関数」や「VLOOKUP関数」「INDIRECT関数」といった関数を利用することで効率的に運用できます。一部の数値を入力することで自動で計算して数値を増減してくれるため、入力ミスを減らせるでしょう。
発注管理システムの導入
発注管理システムを導入することで、発注管理を効果的にできます。発注管理システムとは発注先や注文内容、納期などの情報を一元化し、業務の流れを可視化できるシステムです。
取引先の管理や購買依頼書の作成、在庫管理機能、発注データのリアルタイム確認機能を備えています。
システムを導入する際は自社の課題を洗い出し、必要な機能を備えているかを確認するのが重要です。また、操作が直感的であるか、サポート体制が充実しているかも確認しておきましょう。
システム選びで失敗しないために、無料トライアルがあるシステムを選び、自社の課題を解決できるかを確認して導入しましょう。
発注管理システムを導入するメリット
発注管理システムを導入するメリットは次のとおりです。
- 作業効率の大幅な向上とミス削減
- リアルタイムの情報共有と意思決定の迅速化
- コスト削減と在庫の最適化
それぞれ詳しく解説します。
作業効率の大幅な向上とミス削減
発注管理システムを導入すると作業効率が大幅に向上し、ミスの削減が可能です。
たとえば、手作業で発注管理を行った場合、Excelやスプレッドシートにデータを入力する必要があります。データ入力作業自体が時間のかかる業務であることや、頻繁にデータ入力を行うことで数値の入力ミスが発生する懸念もあります。
発注管理システムを導入すれば、データを自動で入力してくれるため、データ入力の手間と時間を削減できます。また、正確なデータを作成できるため、修正の時間が必要ありません。
他の機能も同様に、在庫切れや発注漏れが起きないようにアラートで知らせてくれるため、作業効率が向上します。
リアルタイムの情報共有と意思決定の迅速化
発注管理システムを導入することで、発注に関する情報をリアルタイムで把握でき、企業全体の意思決定が迅速化します。各部門の従業員が在庫状況や発注状況を即座に確認できるため、必要なアクションを素早く判断できるようになるでしょう。
たとえば、発注部門は常に最新の在庫データにもとづいて適切な数量を発注できるほか、在庫管理部門と購買管理部門も正確な情報をもとに効率的な購買依頼書を作成可能です。
発注は企業のコストに直結する重要な業務です。リアルタイムの情報共有によって状況を正確に把握できれば、過剰発注や発注遅れといったリスクを回避し、ムダのない経営判断につなげられます。
コスト削減と在庫の最適化
発注管理システムの導入により、企業はコスト削減と在庫の最適化の二つの重要な効果を同時に実現できます。システムがもたらすリアルタイムの在庫状況の可視化によって、過剰在庫か不足状態かを即座に判断可能です。
たとえば、定量発注方式で発注点を100と設定している場合、正確な在庫数の把握により、100を下回る直前に適切なタイミングで発注できるようになります。緊急発注や余分な在庫確保といった非効率な発注行動が不要となり、調達コストの大幅削減につながるでしょう。
さらに、市場需要の変化に応じて発注数量やタイミングを柔軟に調整できるため、資金を拘束する過剰在庫の防止と、売上機会を失う欠品リスクの両方を効果的に低減できます。これにより、限られた資源を最大限に活用した経営を実現できます。
発注管理システムで業務フローの最適化
発注管理システムを導入することで発注に関する情報を一元化し、リアルタイムで流れが把握できるため、業務フローの最適化が可能です。
また、取引先の管理や購買依頼書の作成などの業務もシステム上で行えます。そのため、ミスを削減し、意思決定を迅速化できます。
システムを選ぶ際は各サービスを比較し、気になるシステムの資料をダウンロードして自社に合うのか検討してみましょう。
\料金や機能を資料で比較する!/