目次を閉じる
如月とは
古来の日本では、各月を季節感のある言葉で表現しました。英語でも2th Monthといわず、Februaryと呼びますよね。それと同じです。12か月あるうち、2月は「如月」でした。
それから時は経ち明治6年。陽暦が採用され各月は「2月」のように数字で表され始めました。当時の呼び方は現在でも親しまれ続けています。如月も和風月名として今なお、2月を表現しています。
如月の読み方
如月は「きさらぎ」と読みます。中国でも2月の異称に「如月」が使われており、その漢字をあてた説があります。
ところが中国では如月を「にょげつ」と読むので、日本の「きさらぎ」とは読み方が異なります。そのため「如月」の意味や由来には諸説あります。
如月の意味と由来・語源
もっとも有力な説は、「衣更着(きさらぎ)」が転じた説です。衣更着には、厳しい寒さに備え重ね着をする季節(衣を更に重ねる)という意味があります。
ほかにも、陽気が更に来る月だから「気更来(きさらぎ)」になった説、春に向けて草木が生えはじめるから「生更木(きさらぎ)」になった説があります。
如月の別名・異称
如月には、さまざまな別名・異称があります。いくつか紹介しましょう。
初花月(はつはなづき)
年が明けて最初に咲く梅の花を「初花(はつはな)」といいます。新暦3月にあたる如月では、梅の花が咲く月なので「初花月」と呼ばれます。
仲春(ちゅうしゅん)
陰暦では1月から3月が春です。陰暦2月の如月は春の真ん中にあたるため「仲春」と呼ばれます。同じ理由で「仲の春(なかのはる)」「中の春(なかのはる)」とも呼ばれます。
雪消月(ゆききえづき)
1月に残っていた雪も2月には消えるので「雪消月」と呼ばれます。
雁帰月(かりかえりづき)
冬に日本へ渡ってきた雁が、春にシベリアへ帰るため「雁帰月」と呼ばれます。
そのほかの別名・異称
そのほかにも以下のような別名・異称があります。
- 殷旬(いんしゅん)
- 梅見月(うめみづき)
- 建卯月(けんうづき)
- 令月・麗月(れいげつ)
- 小草生月(をぐさおひつき)
如月は陰暦・旧暦の2月
如月は陰暦の2月を意味します。しかし、陰暦の2月は陽暦の2月ではありません。陰暦と陽暦は1か月ほどずれています。そのため陰暦の2月は、新暦の2月下旬から4月上旬ごろになります。
如月のまとめ
新暦を採用した現代の日本では、まだ厳しい寒さで春を遠く感じるのが2月。しかし暦では、2月4日「立春」に春が到来します。
もしかしたら古来の日本人の方が、季節に敏感だったのかもしれませんね。
月の異名一覧
働き方改革メディア「Beyond」でさらに詳細解説
Beyondは、ビジネスリーダーのための働き方メディアです。
経済成長の鈍化、労働人口の減少が進む日本。この地で経済活動を営む私たちが希望を持って豊かな生活を送るためには、これまでの非効率な働き方を変え、一人ひとりの生産性を高めることが重要です。
Beyondでは、政府・民間企業による働き方改革の取り組みを中心に、経営戦略、テクノロジー、キャリア、経済まで、幅広い分野の情報を配信します。
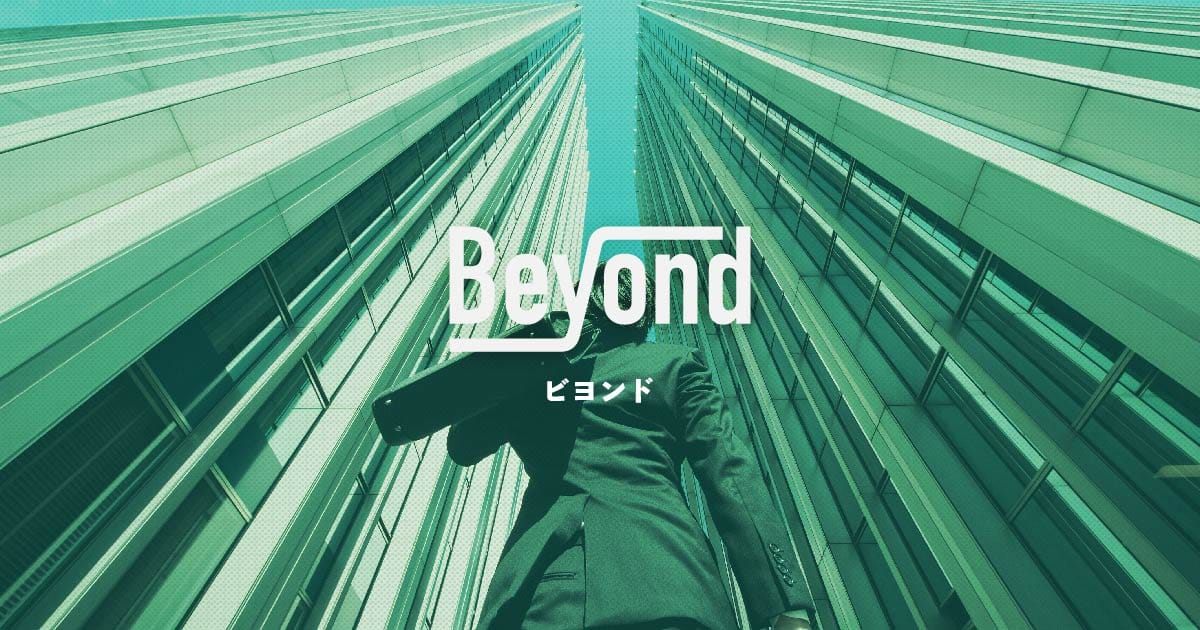
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL SaaS質問箱とは
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。






