目次を閉じる
文月とは
明治初頭より陽暦(新暦)を採用した日本では、12か月を1月〜12月の数字で表しています。しかし、それ以前は、季節感がわかるような和風月名で各月を表現しており、その7番目の月を「文月」としていました。現在では、これを陽暦(新暦)7月に当てはめ「文月=7月の和風月名」として用いています。
陰暦の7月は、陽暦の7月と時期が違います。陽暦は陰暦から1か月ほど遅れています。陰暦の7月は、陽暦の7月下旬から9月上旬頃に当たるのです。
文月の読み方、意味・由来・語源
文月は「ふづき、ふみづき」と読み、その意味・由来・語源には諸説あります。なかでも、「文被月(ふみひろげづき、ふみひらきづき)」が略されて「文月」に転じたという説は有力です。
この文被月とは、書道の上達を祈って、短冊に歌や願い事などを書く、七夕の行事にちなんだ呼び方だといわれています。しかし奈良時代に中国から伝わった七夕は、古来日本にはなかった行事であり、疑問視する声もあります。
ほかにも、収穫が近づくにつれて稲穂が膨らむことから「穂含月(ほふみづき)」「含月(ふくむづき)」が転じて「文月(ふづき)」になったという説、稲穂の膨らみが見られる月であることから「穂見月(ほみづき)」が転じたという説もあります。
文月の別名・異称
文月には、別名や異称で表されるさまざまな呼び名があります。そのいくつかを紹介しておきましょう。
初秋(しょしゅう、はつあき)
陰暦では、7月から9月が「秋」になります。このため、7月である「文月」が、秋の最初の月になるため「初秋」とも呼ばれます。
親月(おやづき、しんげつ)
陰暦7月の文月にはお盆があります。このため、親の墓参りをする月ということから「親月」とも呼ばれているようです。
涼月(りょうげつ)
文月の終わりには暑さもやわらぎ、涼しい風を感じることもあるため「涼月」とも呼ばれていたようです。
愛逢月(めであいづき)
織姫と彦星が年に一度再会する七夕を含む文月では、お互いが愛して逢う月ということから「愛逢月」とも呼ばれました。
そのほかの別名・異称
- 女郎花月(おみなえしづき、をみなえしづき)
- 建申月(けんしんげつ)
- 七夕月(たなばたづき)
- 桐月(とうげつ)
- 七夜月(ななよづき)
- 蘭月(らんげつ)
文月のまとめ
7月7日が七夕なのにもかかわらず、8月に七夕が催される地域があります。これは陰暦に関係があったのかもしれませんね。陰暦を知っておくと、より季節感を感じられるという良さがあるのではないでしょうか。
月の異名一覧
働き方改革メディア「Beyond」でさらに詳細解説
Beyondは、ビジネスリーダーのための働き方メディアです。
経済成長の鈍化、労働人口の減少が進む日本。この地で経済活動を営む私たちが希望を持って豊かな生活を送るためには、これまでの非効率な働き方を変え、一人ひとりの生産性を高めることが重要です。
Beyondでは、政府・民間企業による働き方改革の取り組みを中心に、経営戦略、テクノロジー、キャリア、経済まで、幅広い分野の情報を配信します。
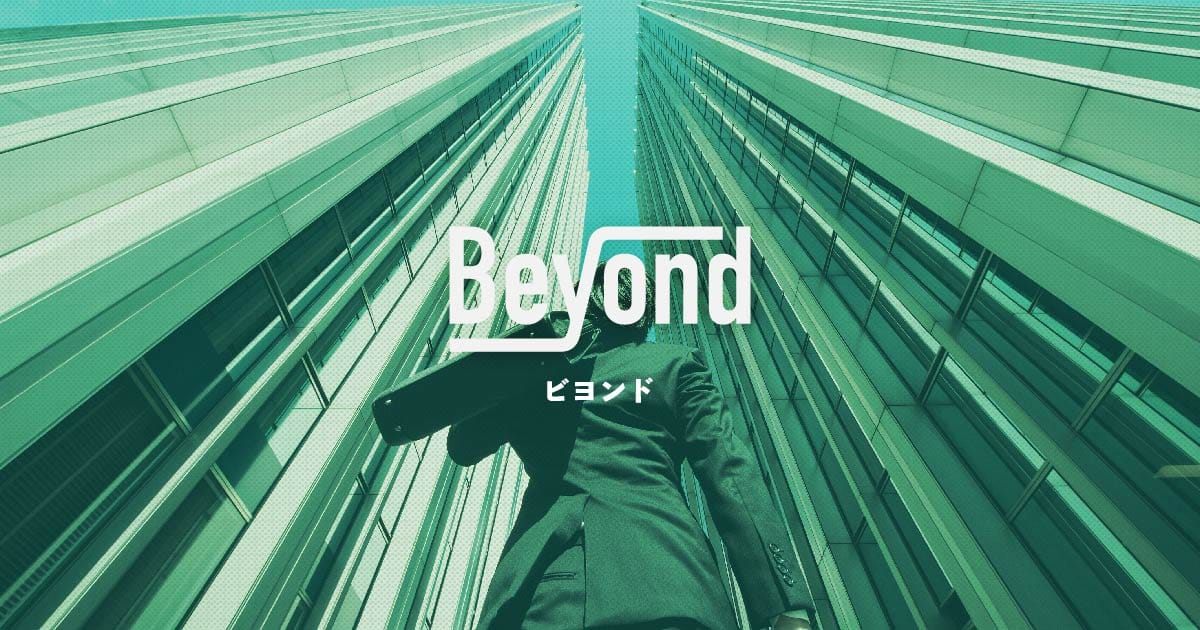
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL SaaS質問箱とは
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。






