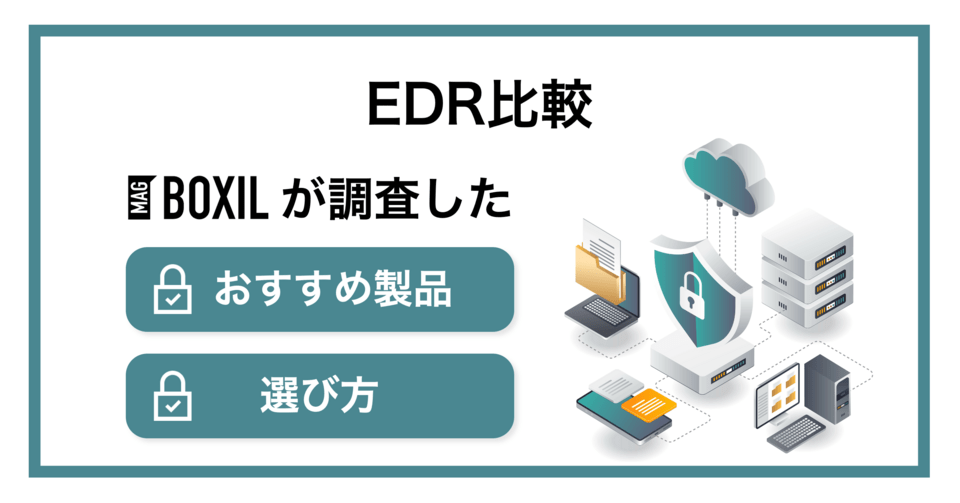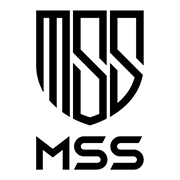EDRとは
EDR(Endpoint Detection and Response)とは、PCやサーバー、スマートフォンなどのエンドポイント(端末)を常時監視し、サイバー攻撃や不審な挙動をリアルタイムで検出・対応するセキュリティ対策です。
EDRは端末に侵入したマルウェアを検知し、感染した端末の隔離やプロセスの停止などの処理により、被害の拡大を防ぎます。従来のアンチウイルスやファイアウォールでは防ぎきれない高度な脅威に対処するため、EDRの導入が進んでいます。
従来はマルウェアの感染自体を防ぐための対策が主流でしたが、EDRはマルウェアの侵入を前提とした対策です。万が一の侵入時にも被害を最小限に抑えることを目的とし、エンドポイント上の挙動を常時監視し、異常があれば即座に検出・対応します。現在では、こうしたEDRの必要性が多くの組織に認識されるようになっています。
EDRとEPPの違い
EDRとよく比較されるセキュリティ対策にEPPがあります。
EPP(Endpoint Protection Platform)とは、エンドポイントのマルウェア感染を未然に防ぐための「予防型」セキュリティ対策です。
EPPはあらかじめ登録されたマルウェア情報をもとに、マルウェアの特徴(シグネチャ)を照合して脅威を検出します。
EDRは、マルウェアの侵入後を想定した「検知と対応」に重点を置き、EPPでは防ぎきれない未知の攻撃や高度な脅威に備えるために使用されるのが大きな違いです。
EPPとEDRは競合する技術ではなく、相補的に組み合わせることで多層防御が実現できます。EPPで既知のマルウェアを防ぎ、EDRで未知の攻撃を素早く検知して封じ込めるといった運用が一般的でしょう。
MSSとは
MSS(マネージドセキュリティサービス)とは、企業のセキュリティ運用・管理をセキュリティ専門企業に委託するサービスのことです。
MSSを提供するベンダーがEDRのログを常時監視し、インシデントや異常な振る舞いをいち早く検知して、依頼企業のセキュリティチームやSOC(Security Operation Center)に通知します。MSSベンダーによっては監視・アラート通知に加え、インシデント発生後の対応まで担うサービスもあります。
EDR製品の中には、MSSが付帯しているものもあるので、必要に応じて確認するとよいでしょう。
EDRの機能
EDRの機能について詳しく解説します。
常時監視による異常の早期検知
EDRは、PCやサーバーなどのエンドポイントにおけるすべての挙動をリアルタイムで監視します。ファイルの作成や削除、ネットワーク通信、プロセスの起動や終了といった詳細な動作を記録し、通常と異なる振る舞いがあれば即座に検知します。これにより、マルウェアや不正アクセスなどの兆候を早期に発見可能です。
脅威の分析とアラート通知
EDRは、収集した情報をもとに脅威の有無を分析します。既知のマルウェアのパターン(シグネチャ)だけでなく、ファイルレス攻撃やゼロデイ攻撃のような未知の脅威にも対応できるよう、振る舞い検知やAI(人工知能)と機械学習による異常検知アルゴリズムを活用。疑わしい動作や攻撃の兆候を検知した際には、管理者に対して即座にアラートを発信し、対応を促します。
感染端末への対処と被害の封じ込め
攻撃が確認された場合には、EDRは対象のエンドポイントをネットワークから切り離したり、マルウェアのプロセスを強制終了したりといった対処を行います。これにより、被害の拡大を防ぐと同時に、他の端末への感染リスクを低減可能です。必要に応じて、対応を自動化することで、インシデント発生時の初動を迅速化できます。
詳細なログ取得と追跡調査
EDRは、通常の運用ログに加えて、セキュリティインシデントに関する詳細な情報も収集可能です。どの端末がいつどのような通信を行い、どのファイルにアクセスしたかといった情報を時系列で記録し、攻撃の全体像を明らかにします。これにより、インシデント発生後の原因分析や再発防止策の検討が容易になります。
復旧支援とシステムの回復
一部のEDR製品では、攻撃によって変更されたファイルや設定を復元する機能が提供されています。たとえば、感染前の状態にロールバックする機能を使えば、迅速に業務を再開できます。被害の影響を最小限に抑えるための復旧支援も、EDRの重要な役割です。
可視化とレポーティング機能
EDRは、収集したデータや対応状況をわかりやすく可視化するダッシュボードを提供します。これにより、管理者は複数の端末にまたがるセキュリティ状況を一元的に把握可能です。また、検知されたインシデントに関する詳細なレポートを自動生成することで、対応の振り返りや報告業務を効率化します。
EDRの選び方
EDRの導入を検討する際は、次のポイントに注意して選ぶことをおすすめします。
- 検知能力と対応スピード
- 運用のしやすさと管理画面の直感性
- 自社環境との適合性
- サポート体制と運用支援サービスの有無
- 他のセキュリティ製品との連携性
- 初期費用と運用コストのバランス
検知能力と対応スピード
EDRで最も重要なのは、未知のマルウェアや不審な挙動を検知し、それに対して迅速に対応できる能力です。EDR製品によっては、AI(人工知能)や機械学習を活用して高度な分析を行うものもあります。同時に、検出精度が高いだけでなく、誤検知を減らす仕組みを備えているかどうかも確認すべき要素です。
また、インシデント発生時の自動隔離やプロセス停止といった初動対応のスピードと柔軟性も、EDR製品を選定するうえでの重要なポイントです。
運用のしやすさと管理画面の直感性
EDRは継続的な監視と分析を前提とした運用型のセキュリティ製品です。導入後の運用負荷を抑えるためには、操作がわかりやすく、視覚的に状況が把握しやすい管理画面やダッシュボードを備えていることが求められます。
EDR製品のアラート設定の柔軟性、検索機能の使いやすさ、インシデントレポートの見やすさなども、日常的な運用に大きく関わる要素となります。
自社環境との適合性
EDR製品には、クラウド型とオンプレミス型があり、自社のインフラ環境やセキュリティポリシーに適した導入形態を選ぶ必要があります。
また、自社で利用しているOSや端末に対応しているかも必ず確認しましょう。Windowsだけでなく、macOSやLinux、モバイル端末にも対応しているEDR製品であれば、社内の多様なデバイスを一元的に保護できます。
サポート体制と運用支援サービスの有無
EDRの運用には、専門知識が求められる場面も少なくありません。そのため、ベンダーからの技術サポートや、導入時のトレーニング支援が充実しているかどうかも確認する必要があります。
MSS(マネージドセキュリティサービス)のように、外部のセキュリティチームが監視・対応を代行してくれるサービスが利用可能であれば、自社の運用負担を大幅に軽減できます。
他のセキュリティ製品との連携性
EDR製品が、EPPやSIEM(セキュリティ情報イベント管理)、ファイアウォールなど既存のセキュリティ製品と連携が可能かどうかも、効果的な脅威対策体制を構築するための大きなポイントです。
また、EDR製品に、今後の拡張や端末数の増加にも柔軟に対応できるスケーラビリティがあるかどうかも確認しておきましょう。
初期費用と運用コストのバランス
EDRは高機能な分、一定のコストが発生します。初期費用だけでなく、ライセンス形態(月額制・年額制など)や追加機能の料金、インシデント対応に関する課金体系も把握することが大切です。
導入後にかかる人的リソースや教育コストも含め、総合的な TCO(Total Cost of Ownership) を考慮したうえでEDR製品を選定するように努めましょう。
EDRの価格相場
EDRの導入・運用にかかる費用はベンダーによって異なります。クラウド型かオンプレミス型か、あるいは定額制か課金制かなどで費用は変動します。費用の目安として、クラウド型EDRはライセンス料として1万円〜100万円、オンプレミス型EDRは100万円〜1,000万円程度。セキュリティ性やシステム構築・運用の柔軟性が高いオンプレミス型の方が高額になるケースが多いです。
定額制は、「ユーザー10名につき月額5,000円」「月額2万円で範囲内の機能を使い放題」といった内容です。一方の課金制では、「1名あたり1,000円」「オプション機能追加で1万円」など、ユーザーや機能を追加するごとに課金されます。
おすすめのEDR比較
それでは、おすすめのEDRを紹介していきます。上記の選択基準を参考にしながら、環境にマッチした製品・サービスを選びましょう。
MSS for EDR
- 24時間365日でセキュリティ専門アナリストが監視
- アラートの解析から影響度の判断、ブロックまで対応
- 国内の主要なEDR製品から要件に合わせて選択可能
MSS for EDR は、日本国内でセキュリティ監視を行うEDRのセキュリティ監視サービスです。EDR製品導入済みでも利用でき、EDR製品により検出したアラートから影響度を判定し、端末のプロセス停止といった一次対処を任せられます。
緊急度に応じ電話やメールで、解析したアラートの影響度や一次対処の内容・対策などを通知してくれます。海外拠点のセキュリティ監視も依頼でき、英語による対応が可能です。
SentinelOne
- マルウェアのブロックから検出、封じ込め、修復まで対応
- オフラインでも動作するオンデバイスAIを搭載
- 1ライセンスから購入可能
SentinelOne は、ファイル検査やふるまい検知にも対応できる自動対応型EDRです。ファイル隔離やロールバック、AI分析、自動修復などに自動対応でき、ネットワークダウンタイムを最小限に抑えられます。
自律型の多層防御により、ゼロデイ攻撃やサプライチェーン攻撃などに対策可能です。1台から購入できるうえ、macOSとWindows端末を一元管理できるので、中小企業にもおすすめのサービスです。
LANSCOPE サイバープロテクション
- 高いセキュリティ水準が求められる組織での導入実績
- 高い検知率でマルウェアの特徴を判定
- 安心のサポート体制
LANSCOPE サイバープロテクション は官公庁や金融業界、通信業界など、高いセキュリティ水準を求められる多くの企業で導入されている、AIアンチウイルスです。まだ広まっていないマルウェアでも、ファイルの特徴からAIが判定し、高い検知率で社内のシステムを守れます。
海外ベンダーの製品ですが、エムオーテックス株式会社による充実した国内サポートが受けられるほか、運用代行も依頼可能です。社内環境に合わせて、サポートを選択するとよいでしょう。
Symantec Endpoint Security
- オンプレミス、ハイブリッド、クラウドで提供
- モバイルデバイスのエンドポイントも保護
- インテリジェント自動化とAI主導のポリシー管理
Symantec Endpoint Security は、業界最高レベルのエンドポイントセキュリティを実現できるサービスです。EDRとしての役割に加えて、独自機能を搭載することで、より多くの標準型攻撃を検出できるのが特徴です。
クラウド上で従来のエンドポイントとモバイルデバイスをまとめて管理でき、人工知能(AI)を利用してセキュリティに関する意思決定を最適化します。環境に合わせてクラウドとオンプレミス、ハイブリッドでの運用ができるのも魅力です。
Cybereason EDR
- マルウェアの状況を直感的に可視化
- 侵入後のダメージを制御
- 数万台ものエンドポイントに対応
Cybereason EDR はマルウェアの侵入後の振る舞いを検知し、攻撃を封じ込めるEDRです。クラウド上のAIエンジンにより攻撃を分析し、わかりやすく可視化できるのが特徴です。数万台ものエンドポイントをリアルタイムに監視でき、Windows・macOS・Linuxのすべてに対応しています。
独自の分析エンジンにより取得したログを横断的に分析し、異常な行動の証拠を収集して攻撃パターンを見極められるのが特徴です。日本語の管理画面も使いやすく、直感的に状況を把握できます。
Cisco Secure Endpoint
- エンドポイントを全体的に可視化
- 業界最高水準の検知率
- 無料トライアルが利用可能
Cisco Secure Endpoint はユーザーのエンドポイント全体をスムーズに可視化し、マルウェアの侵入範囲の特定と封じ込め、修復を自動で行ってくれるセキュリティソリューションです。業界最高水準の検知率を誇っており、マルウェアの感染前後における多層的なシステム防御を実現できます。
感染経路は自動的に追跡・確認され、被害を受けた端末を高速で特定し、迅速な封じ込めとシステムの修復が可能です。EssentialsとAdvantage、Premierの3つのプランが用意されており、30日間の無料トライアルも利用できます。
Trend Micro Apex One
- 高度なマルウェアをより正確に検出
- 既知および未知のぜい弱性に仮想的にパッチを適用
- SaaSとオンプレミスの導入が可能
Trend Micro Apex One はファイルレスやランサムウェアなど、近年増え続けている脅威へ多角的に対応できるエンドポイントセキュリティです。ふるまい検知や機械学習型の検知によりマルウェアの侵入を防止し、復旧と緊急パッチによるダウンタイムを削減できます。
AI技術を活用した高度な検出精度を誇っており、機械学習を繰り返すことで、さまざまなマルウェアを正確に判断可能です。多様な攻撃に対して効果的なシステム防御を実現できるので、社内のセキュリティ体制を刷新したい企業におすすめです。
KeepEye
- 監視運用サービス付き国産EDR
- 通信量が低く動作が快適
- 直感的でわかりやすい管理画面
KeepEye は、監視運用サービス付き国産EDRです。高度な検知・防御能力を有しており、不審な挙動をAIが素早く検知し、アナリストに通知してくれます。通信量が低く快適に動作するのが特徴で、HTTPS通信のためファイアウォールの設定変更も不要です。
だれにでもわかりやすい画面設計で、稼働状況やアラートの発生状況を一目で確認でき、管理画面上から製品サポートやアナリストとのやり取りが可能です。
EDRの導入メリット
EDRの導入メリットについて詳しく解説します。
侵入後の脅威を迅速に検知し、被害を最小限に抑える
従来のアンチウイルスソフト(EPP)は、既知のマルウェアをシグネチャベースで検出することに特化していましたが、EDRは未知のマルウェアやファイルレス攻撃など、巧妙化するサイバー攻撃に対しても対応可能です。
EDRはエンドポイントの挙動をリアルタイムで監視し、不審な動作を検知すると即座にアラートを発信し、感染端末の隔離やプロセスの強制終了などの対処を行うことで、被害の拡大を防ぎます。これにより、侵入されることを前提とした強固なセキュリティ体制を確立できます。
インシデント発生時の迅速な調査と封じ込めができる
EDRは端末ごとの挙動ログや通信履歴などを詳細に記録しており、攻撃の痕跡や経路を把握するための分析に役立ちます。インシデントが発生した際にも、感染端末の特定や影響範囲の把握が迅速に行えるため、初動対応が遅れるリスクを軽減できます。
さらに、端末の隔離やプロセスの停止といった封じ込め措置も即時に実行できる点が強みです。
テレワーク環境でも一貫したセキュリティ対策が可能
テレワークや多拠点での業務が一般化する中、社内ネットワークの境界で守る従来の防御策だけでは不十分になっています。
EDRはクラウドベースの運用が可能であり、社外で利用される端末でも同等の監視・防御体制を維持可能です。これにより、働く場所に関わらず、企業全体で一貫したセキュリティポリシーを適用できるようになります。
セキュリティ運用の効率化と人材不足への対応
EDRは脅威の検知から対応までを自動化・省力化できるため、セキュリティチームの負担を軽減します。
また、MSS(マネージドセキュリティサービス)などの外部の運用支援サービスと連携することで、自社に十分な専門人材がいない場合でも、高度な分析や運用支援を受けられます。結果として、限られたリソースでも高度なセキュリティ体制を維持できるようになるでしょう。
EDRを導入するデメリット
EDRを導入する課題として、次のものがあげられます。
コストがかかる
EDRの導入には、ライセンス料や月額費用などコストがかかります。費用はエンドポイント端末数やユーザー数、機能の範囲などによって異なりますが、けっして安くはありません。
オンプレミス型でセキュリティ性と柔軟性の高いシステムを選べば、数百万円単位でコストがかかる場合も。予算や人的リソースを加味したうえで導入を検討する必要があります。
運用リソースがかかる
EDRは、導入だけでなく「運用」までを視野に入れる必要があり、運用にもリソースがかかります。費用を支払えばEDRの堅牢(けんろう)な機能を使えますが、EDRの運用を任せられるセキュリティ人材がいなければ意味がないでしょう。
もしEDR運用に精通した従業員がいなければ、研修を行う、あるいは外部のセキュリティベンダーに運用サービスを委託するといった対応が必要です。
EDRを導入して脅威からビジネスを守ろう
EDRは、日々進化しているサイバー攻撃やマルウェアの脅威から、自社の事業や資産を守るために必要なセキュリティ対策です。EDRの導入を検討する際は、次のポイントに注意して選ぶことをおすすめします。
- 検知能力と対応スピード
- 運用のしやすさと管理画面の直感性
- 自社環境との適合性
- サポート体制と運用支援サービスの有無
- 他のセキュリティ製品との連携性
- 初期費用と運用コストのバランス
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査