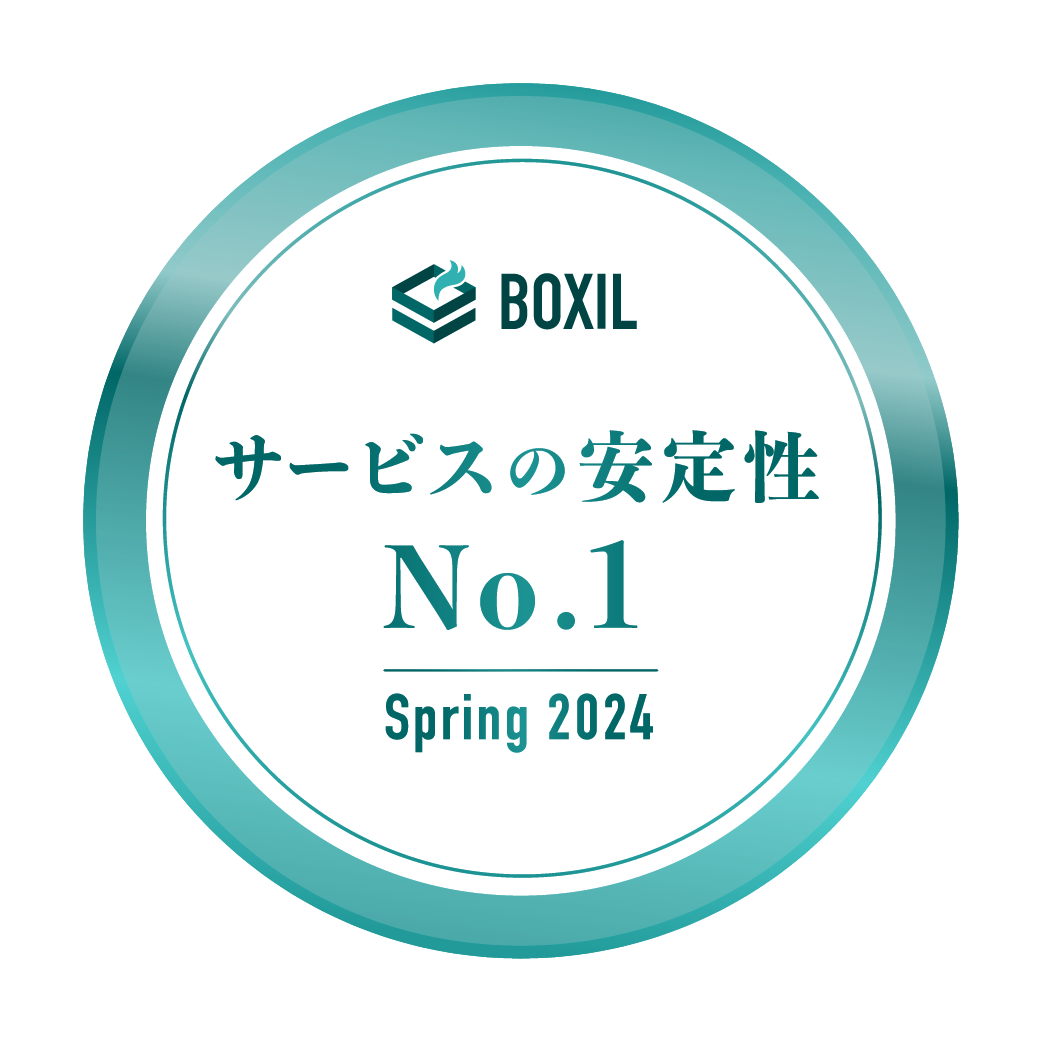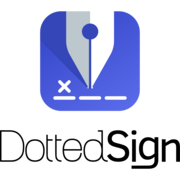【比較表】電子契約システム比較!おすすめサービスの選び方・料金 2024年最新

電子契約システムの比較にお困りですか?「SaaS導入推進者が選ぶサイト第1位※」のBOXILからダウンロードできる各社のサービス資料で、電子契約システムの選定を成功させましょう!
⇒【特典比較表つき】電子契約システムの資料ダウンロードはこちら(無料)
※ 2020年9月実施 株式会社ショッパーズアイ「SaaS比較メディアに関するイメージ調査」より
目次を閉じる

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
電子契約システムとは
電子契約システムとは、インターネット上でPDFといった電子文書ファイルを用いて契約締結するシステムをいいます。紙の契約書で用いられてきた署名押印に代わり、電子署名とタイムスタンプを用いることでなりすましや改ざんの防止が可能です。
政府や関係省庁をはじめ、流通・小売業、建設業、製造業、不動産業、個人事業主などBtoBからBtoCまで幅広い業界で導入が進んでいます。
電子契約システムの選び方
電子契約システムを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。この流れで確認することにより、電子契約システムの導入失敗を避けられます。
- 電子契約システムの導入目的を確認する
- 電子契約システムの機能を確認する
- 電子契約システムを導入する際の注意点を確認する
- 電子契約システムの料金・価格相場を確認する
- 要件に当てはまる電子契約システムがどれか、BOXILの比較表で絞り込む
STEP1. 電子契約システムの導入目的を確認する
電子契約システムの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。
| 導入目的 | おすすめサービス |
|---|---|
| 手軽に電子契約をしたい | 立会人型の電子契約システムや無料の電子契約システムがおすすめ |
| セキュリティを重視して電子契約をしたい | 当事者型の電子契約システムがおすすめ |
| 契約書の管理まで行いたい | 契約書管理に特化した電子契約システムがおすすめ |
総務省・法務省・経済産業省が連名で出した「電子契約サービスに関するQ&A」にも、電子契約サービスを選択する際の留意点として次のように記載されています。契約書の種類やセキュリティに準じて導入するサービスの検討を進めましょう。
当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当
引用:総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」
STEP2. 電子契約システムの機能を確認する
電子契約システムでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。
【基本的な機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 署名の設定 | 署名や先方の名前、フリーテキストなどの入力箇所を設定する機能 |
| 署名していない文書へのリマインド | 署名依頼を送付したあと、一定期間署名されていない場合にシステム上やメールにてリマインド送付をできる機能 |
| 契約書のひな型 | 契約書・秘密保持契約・雇用契約書などのテンプレートが用意されていたり、自社のひな型を登録したりできる機能 |
| ワークフロー | 承認者を設定し、契約書を承認しなければ契約締結先に送付できないようにする機能 |
| 合意締結証明書の発行 | いつ・誰が・どの書類に合意したのか、署名の詳細やタイムスタンプを確認できる証明書を発行できる |
| スマートフォンブラウザでの署名 | スマートフォンブラウザから署名し、契約締結できる機能 |
【特定の課題・用途・業界に特化した機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 印鑑画像や印影の登録 | 本来電子契約では印影は不要だが、慣習的に必要な会社に向けて印影画像を登録して契約書に貼付できたり、テキストを設定して印影のように貼付できる機能 |
| 契約書管理・保管 | 締結した電子契約書を管理し、契約終了のリマインドをしてくれたり、自動で破棄してくれる機能。一部サービス提供会社では紙原本の保管もしてくれる。 |
| 過去の契約書の電子化・スキャン | 過去に紙で締結していた契約書をスキャンし、電子化してくれるサービスを提供する企業も |
| マイナンバー本人確認 | マイナンバーカードを使用して、本人確認ができる機能 |
| 文書や署名画面のカスタマイズ | 文書に入れるロゴや色などをカスタマイズし、自社のブランドカラーに合わせられる機能 |
電子契約システムに登録されているひな型は、弁護士が監修していることも多いため、内部統制を強化したい場合はひな型の種類が豊富な電子契約システムがおすすめです。
STEP3. 電子契約システムを導入する際の注意点を確認する
電子契約システムを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。
| 確認事項 | 詳細 |
|---|---|
| 当事者型か立会人型か | 電子契約システムには、立会人型と当事者型が存在します。いずれも電子契約の効力としては有効ですが、本人確認の程度が異なります。電子契約サービスを導入する際に厳密な本人確認を求めるのであれば、立会人型ではなく当事者型を選択するでしょうし、大量処理が必要である程度本人確認リスクに目をつぶるのであれば立会人型でコストを抑えるなど、想定する契約類型、企業規模、業界によって最適なサービスは異なります。 |
| グローバルでの導入実績があるか | 海外企業との取引や契約締結が多い場合は、海外企業での導入実績を確認することが重要です。グローバルでの実績があることで、取引先とも手間なく締結できます。 |
| 相手方のアカウントが必要か | 電子契約システムでは、相手方のアカウントが必要ない場合と必要な場合があります。立会人型であればアカウント不要、当事者型であればアカウントが必要な傾向にあります。 |
| 取引先が電子契約に対応しているか | 電子契約ではなく、従来どおりの書面契約を希望する企業も存在します。主要取引先が電子契約に対応してくれそうかを確認しておきましょう。 |
| 現在の締結フローとどのように変化するか確認する | 今の契約業務とフロー、管理方法 |
| セキュリティレベル | 通信と保管ファイルの暗号化、ファイアウォール、IPアドレス制限、ブロックチェーン、EV SSL証明書、二段階認証、二要素認証などのセキュリティを確認しておきましょう。 |
| 電子帳簿保存法対応 | 電子データを7年間保存することや、検索要件を満たしているかなど、電子帳簿保存法に対応できるサービスか確認しましょう。 |
| サポート体制 | 導入までの初期設定代行や承認経路設定、取引先へのシステム説明など、サポート体制はどのようになっているか確認しましょう。 |
| アプリ対応 | スマートフォンアプリに対応しているかどうか確認しましょう。外出先からでも素早く署名や文書の確認ができます。 |
| 連携サービス | 自社の顧客名簿やSalesforce、ジョブカン、kintoneといった業務改善プラットフォームと連携させることで、さらなる業務効率化も可能です。 |
当事者型と立会人型、それぞれのメリット・デメリット
現在の電子契約システムは、当事者型と立会人型の2種類に分けられ、それぞれにメリットとデメリットがあります。
| 種類 | 概要 | メリット | デメリット | サービス例 |
|---|---|---|---|---|
| 当事者型 | 電子認証局による本人確認後発行される電子証明書を利用して、契約当事者がみずから電子署名を付するタイプ | 第三者である電子認証局による本人確認がなされる | 当事者それぞれが電子証明書を取得・維持する必要あり。場合によっては取得のための稟議決裁が発生する | 電子印鑑GMOサイン やWAN-Sign(両サービスとも立会人型にも対応) |
| 立会人型 | 利用者の指示に基づいて、電子契約サービス提供業者が電子署名を付するタイプ | ・サービス利用者が電子証明書を取得する必要なし ・相手方(受け取り側)がアカウントを保有していなくても利用可能 |
・電子認証局による本人確認はされず、主な本人確認手段がメールアドレス認証 ・相手方もアカウントを作成するサービスの場合、社内稟議決裁や手続きによって時間がかかることも |
CLOUD SIGN、電子印鑑GMOサイン、DocuSign、freeeサイン |
なお、総務省、法務省、経済産業省の連名で出された2020年9月4日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」では、立会人型であっても一定の要件を満たすものは電子証明法による推定効が働くとの見解が示されました。立会人型のクラウドサービスを導入する際は、営業担当者にこの点をヒアリングすることも重要です。
STEP4. 電子契約システムの料金・価格相場を確認する
電子契約システム導入時にかかる費用
電子契約システム導入時にかかる費用には、主に次のようなものが挙げられます。
| 費用 | 詳細 |
|---|---|
| 従量課金 | 契約書の送信や締結1件ごとにかかる費用 |
| 月額固定費 | システム利用料。安いプランはユーザー数制限かかっていることも多い。 |
| アカウント課金 | 1ユーザーごとにかかる費用。サービスによっては月額固定費内で利用できるアカウント数が変動したり、無制限で使えたりするものがある。 |
他にも、オプションで次のような料金がかかる場合もあります。
| 費用 | 詳細 |
|---|---|
| 電子証明書発行料 | 契約の真正性を証明する証明書を発行する際にかかる料金 |
| 書類の保管費用 | 契約書1件ごと、契約書◯件まで、ストレージ○GBあたりなど、締結した電子契約書の件数や容量に応じて発生する料金 |
| 過去の契約書のスキャン | 過去に紙で締結した契約書をスキャンし、電子化をしてくれる作業の料金 |
| セキュリティ関連の機能 | セキュリティをさらに高めるための機能や、本人確認・認証のオプションでかかる料金 |
| 導入サポート | 初期設定をはじめ運用に関するサポートにかかる料金 |
電子契約システムの料金相場
電子契約システムの料金は、月額従量課金タイプか月額固定費用タイプ、アカウント数課金タイプで異なります。従量課金タイプであれば、契約締結1件につき100円〜200円がかかります。
一方で、固定費用の場合は月額1万円程度から始められるサービスが一般的です。固定費用タイプの場合、ユーザー数(アカウント数)や機能などが制限されていることも多いので、どこまでの機能を求めるか確認する必要があります。
想定される締結件数を事前に算出しておくと良いでしょう。
| 料金体系 | 月額費用の比較のポイント |
|---|---|
| 月額従量課金タイプ | 月額費用+契約1件締結ごと料金がかかる。月間の契約締結数が少ない企業におすすめ。 |
| 月額固定費用タイプ | どれだけ契約締結しても固定の料金。契約書の原本保管やデータでの保管などは追加料金になることがある。月間の契約締結数が多い企業におすすめ。 |
| アカウント数課金タイプ | 1ユーザーあたりの料金×ユーザー数で料金が決まるタイプ。機能によって1ユーザーあたりの料金が変動することが多い。 |
STEP5. 要件に当てはまる電子契約システムがどれか、BOXILの比較表で絞り込む
これまで確認した内容を踏まえて、要件に当てはまるサービスがどれか電子契約システムの比較表で絞り込みましょう。比較表の後では、各電子契約のサービスの特徴や機能、価格、BOXILに寄せられた口コミを紹介していきます。
【特典比較表つき】『電子契約システムの資料12選』 はこちら⇒無料ダウンロード
一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。
【特典比較表つき】『電子契約システムの資料12選』 はこちら⇒無料ダウンロード
※ダウンロード可能な資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。
電子契約システムのおすすめ比較【有名なサービス】
ボクシルおすすめ電子契約システム 【Sponsored】
| 電子印鑑GMOサイン |
|---|
 ・導入企業数No.1※1 ・契約社数No.1※2 ・安全な電子契約、仕事が楽になる、法務選ぶNo.1※3 |
 |
※1 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※2 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※3 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」日本マーケティングリサーチ機構の2020年2月期の調査(2023年6月1日閲覧)
ドキュサインの電子署名 - ドキュサイン・ジャパン株式会社
ドキュサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
180か国以上※で電子契約サービスを提供しているDocuSign Inc.(2003年設立)により運営。
ドキュサインは2023年9月時点で導入企業が100万社※に達し、海外取引を想定する場合におすすめの電子契約サービスです。シヤチハタと提携し、印影の作成、アップロードも可能。スタンプ機能を用いて印影画像を貼付できるため、印影を求める国内の取引先との契約にも利用できます。
電子帳簿保存法に沿った契約書管理体制まで整えるには、検索性要件を備えた他の文書管理システムと連携させる必要があるため注意しましょう。
※出典:ドキュサイン「ドキュサイン」(2023年9月11日閲覧)
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
相手方がアカウントを持っていなくとも利用できる立会人型サービスですが、本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証によるため、電子証明書による厳格な本人確認を必須とする場合には、他サービスを検討しましょう。
- 不動産業向けプランが別途用意されているが、料金はPersonal、Standardと変わらない
- Personal、Real Estate Starterは契約書ファイルを送信できるのが月5回に制限されている
- API、SSO、ユーザー管理機能を追加するには別途見積もりが必要
- 30日間の無料トライアル
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金(年契約の場合) |
|---|---|---|
| Personal(個人向け) | 要問い合わせ | 1,100円 |
| Standard(企業向け) | 要問い合わせ | 2,800円 |
| Business Pro(企業向け) | 要問い合わせ | 4,400円 |
| Real Estate Starter | 要問い合わせ | 1,100円 |
| Real Estate | 要問い合わせ | 2,800円 |
BOXILに投稿されたドキュサインを利用した人の口コミは次のとおりです。「UIがわかりやすい」「署名者は個人ID(運転免許やパスポートなど)の登録が必須だから安心できる」といった良い点がある一方で、「送信失敗時にも料金が発生し取り消しができない」「機能説明やマニュアルがところどころ英語しか対応していない」などの評判も見られました。
ドキュサインやクラウドサインなど、主要電子契約サービスの比較はこちらの記事でも行っています。
マネーフォワード クラウド契約 - 株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド契約の特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
株式会社マネーフォワード(2012年5月設立)が提供するマネーフォワード クラウド契約は、契約に関するワークフローの承認から、紙・電子契約書の保管や管理までをワンストップで行えるサービスです。ワークフローは自由にカスタマイズでき、承認者を固定可能です。既存のワークフローはそのままに、内部統制を強化できます。
電子契約の締結では、ワークフローでの決裁後、取引先に自動で契約締結依頼が送信されます。取引先のメールアドレスさえあれば、マネーフォワード クラウド契約のアカウントがなくても電子契約を締結できるため、電子契約導入のハードルを下げられるでしょう。
紙の契約書と電子契約は一元管理され、契約書の種類や取引先、契約締結日などの共通の項目で検索可能です。システム上で紙の契約書を検索し、内容を確認したり他ユーザーに共有したりできます。
- 契約書を作成し、社内ワークフローにて決裁
- メールにより、取引先に自動送信
- 取引先の合意締結後、クラウドに自動保管
取引先の登録は不要で、メールアドレスさえあれば電子契約を締結できます。自動送信や自動保管により、業務を効率化させながら、人的ミスを減らせます。また、電子押印の位置をカスタマイズ可能です。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたマネーフォワード クラウド契約を利用した人の口コミは次のとおりです。「料金が安価である」「マネーフォワード製品との連携で使いやすい」といった良い口コミが多く見られました。
一方で、「同一企業への契約をまとめたい」「操作や管理画面のわかりづらさ」を指摘する口コミもあります。基本的な機能や連携が充実しており、できることが多いためわかりづらいと感じる方もいるのではないでしょうか。
LegalOn Cloud - 株式会社LegalOn Technologies

LegalOn Cloudの特徴
署名方法と使い方
料金表
法務実務をサポートするソフトウェアを開発、提供している株式会社LegalOn Technologies(2017年4月21日設立)により運営。
LegalOn Cloudは、契約書のレビューから契約管理、電子契約、法務分析など、法務業務をサポートするリーガルテックプラットフォームです。ニーズや課題に合わせ、必要なサービスを組み合わせて利用できます。
- 日本語、英語問わず、契約書の作成から管理、保管までまとめて対応
- アップロードした契約書の契約情報を自動で抽出
- 連携した電子契約サービスからの締結版契約書データも取り込み可能
LegalOn Cloudは、電子契約だけでなく、法務業務を広範囲でサポートするサービスです。契約書のレビューや法令リサーチ、契約管理などを、AIテクノロジーで支援してくれます。詳細な署名方法ついては要問い合わせ。
- 必要に応じ機能を組み合わせられるため、料金については要問い合わせ
- 案件管理に対応したワークマネジメントサービス、契約書レビューをサポートするレビューサービス、契約後の管理に対応のコントラクトマネジメントサービスを提供
クラウドサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
弁護士検索、法律相談サービスを提供する弁護士ドットコム株式会社(2005年7月設立)が運営。
クラウドサインはマニュアルや裁判所向け説明資料などが充実しており、決裁資料としての活用も可能です。また、合意締結証明書が発行されるので、関係者の不安感を払拭させやすいという特徴もあります。
署名時にはチェックボックスやフリーテキスト欄を設定できますが、相手方が予期せぬ内容を入力しないよう留意する必要があるため注意しましょう。
印影を模した画像を貼付できますが、印影画像の貼付機能はないので、印影を活用する場合は元の契約書ファイルに印影データを貼付しておく必要もあります。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
クラウドサインは相手方がアカウントを持っていなくとも利用できますが、本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証による立会人型サービスのため、電子証明書による厳格な本人確認を必須とする場合には向いていないため注意しましょう。
書類のインポート機能を備えており、ワークフローといった外部サービスとも連携可能です。英語対応をしていること、セキュリティに関する機能が充実していることからクラウドサインは海外企業との取引でも安心して利用できます。
- Standardプランで基本的な機能はすべて利用できる
- 紙の書類をインポートして保管するにはStandard Plusプランの契約が必要
- BusinessプランではIPアドレス制限やSSOなどセキュリティ面をグレードアップ可能
- 契約書の送信件数ごとに200円の従量課金が発生
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| フリープラン | - | 0円 |
| Light | 無料 | 10,000円〜 |
| Corporate | 無料 | 28,000円〜 |
| Business | 無料 | 要問い合わせ |
| Enterprise | 無料 | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたクラウドサインを利用した人の口コミは次のとおりです。「取引先で導入していることが多く説明が不要」「UIが簡単ですぐに署名できる」といった良い口コミが多く見られました。
一方で、「署名ができる期限が短い」といった口コミもあります。セキュリティにも力を入れているサービスなので、署名期間も考慮されているのではないでしょうか。運用面でカバーできるよう、契約相手にフォローする体制を作っておけば万全な状態で利用できるでしょう。
クラウドサインの導入事例
クラウドサインの導入事例をまとめました。気になる会社の導入事例を無料でダウンロードしていただけます。
| パーソルキャリア株式会社 | 株式会社メルカリ | ラクスル株式会社 |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 契約締結のリードタイムを圧縮することで 機会損失を防いでいます。 | 紙だとできない「一括処理」がクラウド化により実現。 70 倍速の効率化です! | クラウドサインで 「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」 |
電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子印鑑GMOサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
国内インターネット大手GMOグループでIoT、クラウド、セキュリティ事業などを営むGMOグローバルサイン・ホールディングスクラウド(1993年12月設立)が運営。
電子印鑑GMOサインは、自社の電子証明書を用いた署名方式を選択できるため、厳格な印章管理規程、署名権限管理が設けられている企業でも導入を進めやすいサービスです。ワークフロー機能があるため、内部統制の観点から他社サービスから乗り換える企業もあるようです。機能の充実に伴うコストと、対処すべきリスクを比較して検討することが必要です。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
- 立会人型では相手方がアカウントを持っていなくとも利用可能
自社は電子証明書を用いた当事者型、相手方はメールアドレス認証を用いた立会人型の併用が可能。契約書の内容や重要度によって柔軟性を持たせたい企業に適しています。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| お試しフリープラン | 無料 | 0円 |
| 契約印&実印プラン(立会人型&当事者型) | 無料 | 8,800円(税抜) |
BOXILに投稿された電子印鑑GMOサインを利用した人の口コミは次のとおりです。「テンプレートからの作成や登録が簡単」と、テンプレートに関する良い口コミが多く見られました。他にも「無料トライアルがのお試しプランがあるので使い方がイメージできた」といった評判もあります。
一方で、マニュアル面や価格面を指摘する口コミも。多機能かつ連携も豊富であり、立会人型・当事者型両方に対応できること、セキュリティや内部統制での対策も万全なことを考えると、妥当な金額だと言えます。大量の契約がある場合はディスカウントがあったり、サポート体制やサポートコンテンツがあったりするので、導入した際にはぜひ活用しましょう。
SMBCクラウドサイン - SMBCクラウドサイン株式会社
SMBCクラウドサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
SMBCクラウドサイン株式会社が提供する電子契約システム。国内でも高いシェアを誇る「クラウドサイン」をベースに、SMBCグループへの導入ナレッジをいかしてサポートを行ってくれます。
電子契約システムを円滑に利用してもらえるよう、導入から活用まで、顧客の要望に応じ、専門スタッフによる継続的なサポートを強みとしています。
また、AI契約書管理を利用すると、契約金額や契約期間などを自動で読取り、SMBCクラウドサインに自動登録できます。契約書管理の手間の削減、電子帳簿保存法の対応も容易になります。
- SMBCクラウドサインにブラウザでログイン
- 承認者を設定(複数人での承認も可)
- 確認依頼メールを送付
- 相手方がメールに記載されているリンクをクリック
- 承認者が確認ボタンを押す 合意締結完了メール受信
- 送信件数ごとの費用200円(税込220円)〜
- ユーザー数、送信件数はどのプランも無制限
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Light | 要問い合わせ | 11,000円 |
| Corporate | 要問い合わせ | 30,800円(税込) |
| Business | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Enterprise | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたSMBCクラウドサインを利用した人の口コミは次のとおりです。サービスとしての信頼性や操作性といった面への口コミが多く集まりました。
BOXILに寄せられた口コミの中では、機能への細かな要望はあるようですが、大きく改善してほしい点や不満はないようです。
COMPACT IN - セイコーソリューションズ株式会社
COMPACT INの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
タイムスタンプ、電子署名をはじめさまざまなサービスや機器を提供するセイコーソリューションズ株式会社(2012年12月設立)が運営。
同社は多種多様なサービスを提供しており、これらと連携させることで一貫したシステム構築可能なCOMPACT IN(要問い合わせ)。格納ファイルに電子署名とタイムスタンプを付すサービス「eviDaemon」とあわせて導入することで、契約書管理体制も強化できます。
サービス自体にはワークフローがなく、管理権限を設定したい場合は他のシステムと組み合わせて導入する必要があるため注意しましょう。
- 相手方の情報を入力
- 契約書ファイルをアップロードして送信
- 契約書ファイルは1契約につき1ファイルアップロード可能
- 添付資料や別紙を1ファイルにまとめておく必要
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
COMPACT INは相手方がアカウントを持っていなくても利用できますが、本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証によるため、電子証明書による厳格な本人確認を必須とする場合は従来のサービスである「かんたん契約書」の利用も検討する必要があります。立会人型。当事者型については要問い合わせ。
- 有料プランは利用可能人数が無制限
- 送信ごとに1件100円の従量課金
| プラン名 | 従量課金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| フリープラン | 無料 | 無料 |
| コンプリートプラン | 無料 | 25,000円(税抜) |
BOXILに投稿された、COMPACT INを利用した人の口コミは次のとおりです。契約ステータスの進捗管理画面のわかりやすさを評価する口コミが多く集まっています。
一方で、検索や機能面での操作性の改善や、相手方のアカウントが必要なことに対する口コミも。相手方のアカウントが必要な電子契約の場合、その分真正性が高まる点はメリットだと言えます。
DagreeXの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
保管プランを未成約でも、署名された書類は保存されるため、データをダウンロードできます。取引先も締結契約書の一覧検索と詳細参照、取り出しが可能。
- 署名プランは、従量課金制で電子署名料金が別途必要
- 保管プランの利用時は、「Box」の契約が必要
- 保管プランの利用時は、従量課金制でタイムスタンプ料金が別途必要
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 署名プラン(ライト) | 要問い合わせ | 11,000円(税込) |
| 署名プラン(スタンダード) | 要問い合わせ | 88,000円(税込) |
| 保管プラン | 要問い合わせ | 88,000円(税込) |
BOXILに投稿されたDagreeXを利用した人の口コミは次のとおりです。サービスとしての安全性を高く評価する口コミが多く集まりました。検索性や誤送信防止機能についても高い評価を獲得しています。
一方で、他社と比較して利用料金がやや高く感じるといった口コミも集まりました。セキュリティが強固で機能が充実している分、料金がかかるのは仕方がない部分かもしれません。
DocYou - 日鉄日立システムソリューションズ株式会社
DocYouの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
ソフトウェアの提供や導入支援を行っている日鉄日立システムソリューションズ株式会社(1988年4月設立)が運営。
DocYou(ドックユー)は電子契約や電子取引、書類配信をできるサービスです。オプションのドキュメント管理機能で契約に紐づく書類をまとめて管理可能。統合帳票基盤システムのPaplesと連携すれば、電子帳簿保存法への対応も同時に進められるためおすすめです。取引先へのサポートとしてオンライン説明会や動画説明もあります。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロード
- 相手方に確認依頼が届き、必要に応じて項目入力し同意
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
DocYouは立会人型電子契約サービスです。取引先は利用を開始する際にユーザー登録が必要ではあるものの、「ご招待ライト」以外のプランなら費用を負担してもらわずに利用してもらえます。
- 2か月間の無料トライアル※
- 登録数が50ユーザーを超える場合は要問い合わせ
- 書類配信時は送信料や保管料が別途必要
※月10通まで
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| トライアル | 無料 | 0円 |
| スタンダード | 無料 | 22,000円(税込) |
| エンタープライズ | 無料 | 33,000円(税込) |
BOXILに投稿されたDocYouを利用した人の口コミは次のとおりです。「サポートが手厚い」といったサポートに対する口コミに加え、「入力作業や管理画面が簡単」といった操作性に関する良い口コミが多く見られました。
一方で、マニュアル面や操作面で細かな改善点があると感じるユーザーもいるようです。細かなニーズにも対応できるように改善を進めているため、導入時に困ったことや感じたことがあれば伝えてみるといいかもしれません。
Biz Connection - 株式会社フォーカスシステムズ

Biz Connectionの特徴
署名方法と使い方
料金表
ITインフラからアプリケーションに至る技術分野まで公共、民間、業種業態問わず幅広くサポートする株式会社フォーカスシステムズ(1977年設立)により運営。
Biz Connectionは、企業間取引のペーパーレス化をサポートするBtoBプロセスプラットフォームです。
PDFフォーマットの取引書類の企業間受け渡しを電子化できるパッケージシステムのため、電子契約のほか、取引先管理やQA、申請承認などの機能を備えています。電子書面の授受だけでなく前後のプロセスを含む進捗管理に対応し、複数の業務プロセスを紐づけて、取引書類をまとめて管理できます。
- 契約業務に関わる取引先情報を登録し取引先へ依頼送信
- 依頼通知を受け取った取引先はシステム上で書類の内容に応じ必要な処理を実行
- 関連する複数の業務プロセスや帳票などを紐づけ可能
電子契約にも対応した、書類受渡しのプロセス全体を管理できるサービスです。連携する他システムからデータを自動で取込めるので、データ入力やファイル添付などの手作業を削減できます。
取引先ごとに電子取引か電子取引対象外かを区別でき、相手先の運用方法に合わせ紙書類の送付も可能です。契約書の受け渡しのほか、見積依頼書や発注書など多様な書類の受け渡しに利用でき、期限管理や自動督促などの設定にも対応しています。
- 年間利用料の定額制
- 買い切りのオンプレ、定額制のクラウドとSaaSから導入方法を選択可能
DottedSign(ドットサイン) - 株式会社 Kdan Japan
DottedSignの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
シリコンレビューの「ベストソフトウェア企業10社」に選出された株式会社 Kdan Japanが提供する電子契約システム。
TLS/SSL、AES-256、RSA-2048の暗号化で通信が保護されており、2要素認証も搭載しています。すべての署名者のアクティビティの詳細を確認でき、署名の有効性を担保できます。
- 署名箇所を設定
- 双方で署名を確認
| プラン名 | 初期費用 | 料金 |
|---|---|---|
| フリー | 要問い合わせ | 無料 |
| プロ | 要問い合わせ | 月額8ドル/1ユーザー |
| ビジネス | 要問い合わせ | 月額15ドル/1ユーザー |
| エンタープライズ | 要問い合わせ | 問い合わせ |
BOXILに投稿されたDottedSignを利用した人の口コミは次のとおりです。海外ベンダー提供サービスであるものの、操作性は簡単でわかりやすい点が評価されているようです。
対応しているファイル形式の拡充やモバイルアプリの操作性に関しては、改善要望の口コミが集まりました。
電子取引サービス@Sign - 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
電子取引サービス@Signの特徴
署名方法と使い方
料金表
ネットワーク構築やサイバーセキュリティ対策などを提供する、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(2014年10月設立)が運営。
電子取引サービス@Signは、電子取引から契約、検認まで管理できる電子契約システムです。
見積書や注文書など契約書以外の授受やファイル保存に対応でき、電子検認機能により、社内での上長承認や検認にも対応可能です。また、簡易ワークフローや電子印影機能も搭載しています。
- 事業者と取引先それぞれに開通メールを送信し、利用者登録※
- ログインし、契約書をアップロード
- 事業者署名を行うと取引先にメールで通知
- 相手側もログインし署名
取引先からの文書送付も可能ですが、初回のみ契約企業からの文書送付が必要です。当事者型と立会人型に対応し、両プラン併用にも対応しています。相手側へのメール通知は、メール認証とアクセスコードの設定も可能です。
※立会人型プランは、利用者登録を不要とする利用方法も可能。細かな利用方法は、署名形式によって異なるため、詳細は要問い合わせ。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 0円 | 8,800円~/1契約あたり |
※契約は1年単位。
WAN-Sign - 株式会社NXワンビシアーカイブズ
WAN-Signの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
NXグループで情報管理サービスを提供する株式会社ワンビシアーカイブズ(1966年4月設立)が運営。
WAN-Signは、フォルダごとのアクセス権限、IPアドレス制限、承認者設定など、内部統制の強化に有用な機能を備えている点が特徴です。ログインパスワードの桁数、文字列組合せなどの設定も可能なため、自社セキュリティポリシーにより準拠させた運用が可能です。
テンプレートに記名と印影画像の位置を固定できるため、送信のたびに設定する事務処理を削減。紙の契約書のスキャン機能については、機密情報の抹消まで可能なので、文書の発生から消滅まで一貫したシステムで管理できます。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
- 立会人型では相手方がアカウントを持っていなくても利用可能
WAN-Signでは、「自社は電子証明書を用いた当事者型」「相手方はメールアドレス認証を用いた立会人型」といった併用も可能です。よって、契約書の内容や重要度によって柔軟性を持たせたい企業に最適。
- 実印版と認印版では従量課金額が異なる
- 実印版は1件300円
- 認印版は1件100円
- 電子データ管理料は10,000円/月で5,000件ごと
- 書面契約を扱う全件電子化プラン、オンデマンド電子化プランも
- 無料プランあり
| プラン名 | 電子契約締結(有料) |
|---|---|
| 実印版 | 300円/件(税抜) |
| 認印版 | 100円/件(税抜) |
BOXILに投稿されたWAN-Signを利用した人の口コミは次のとおりです。当事者型と立会人型の両方を使えること、アクセス権限の柔軟性を評価する口コミが多く見られます。
機能面で改善してほしい点や不満は見られませんでしたが、料金に関する口コミもありました。従量課金の料金形態のため契約件数が増えるとコスト増になること、電子データの管理が月で5,000件を超えるとプラスで料金がかかることは注意しておきましょう。
ContractS CLM - ContractS株式会社
ContractS CLMの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
元弁護士が代表のContractS株式会社(2017年3月設立)により運営。
電子契約機能はContractS CLM 電子締結、クラウドサイン 締結、Docusign締結から選択可能です。プロジェクト単位での進捗管理が可能で、幅広く契約業務を一元管理できるのがContractS CLMの特徴です。また、一斉締結機能があるため、複数の雇用者に一括でまとめて契約を締結したい場合におすすめです。
- 相手方の情報を入力
- 契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
ContractS CLMは相手方がアカウントを持っていなくとも利用できます。本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証による立会人型のサービスのため、電子証明書による厳格な本人確認を必須とする場合には他のサービスの導入を検討しましょう。
ContractS CLMの料金は、月額基本料金が使用量に応じて変動する可能性があります。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたContractS CLMを利用した人の口コミは次のとおりです。契約書の締結・管理フローがわかりやすい点を評価する口コミが多く集まりました。
改善してほしい点については、コメント機能が挙げられるようです。
freeeサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
中小企業の法務を中心とした、バックオフィスに広くサービスを提供しているfreeeサイン株式会社(2013年4月設立)が運営。
freeeサインは、契約ごとに電子サイン(従量課金なし)と電子署名(従量課金あり)を選択できる点が特徴で、締結可能件数が無制限な立会人型のサービスです。アカウントを増やすと料金が高額になるため、大人数のチームで事務処理にあたっている企業には導入ハードルが高いかもしれません。
ドラフトレビュー機能を使い、契約交渉からプラットフォーム上で可能、契約書の修正履歴を保存できます。また、内部統制のため権限設定機能を利用するにはProプランの契約が必要でしょう。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
ドラフトレビュー機能を利用する場合、ワークフロー機能でレビュー依頼を起票する必要があります。相手方がアカウントを持っていなくても利用できます。
- 契約書送信数による従量課金がなく定額で利用可能※
- アカウント数に上限がある
- 大人数で利用するためにはLight+プランで契約のうえ、必要に応じてアカウントを追加する必要あり
- アカウント追加は別途費用が必要
- 無料プランあり
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| スターター | 無料 | 無料 |
| Light | 無料 | 4,980円 (税込5,478円) |
| Light Plus | 無料 | 19,800円 (税込21,780円) |
| Pro | 330,000円(税込) | 50,000円 (税込55,000円) |
※電子サインを選択した場合
BOXILに投稿されたfreeeサインを利用した人の口コミは次のとおりです。誰でもわかりやすいUIで、素早く締結が可能な点を評価する口コミが多くありました。また、有効期限以内に署名・合意されていない場合や有効期限が切れのリマインド機能も高く評価されています。
一方で、「テンプレートの種類を増やしてほしい」「機能を増やしてほしい」「動作が重いときがある」といった口コミもありました。
DX-Signの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
電子契約サービス「DX-Sign」 の開発、提供やDXに関するメディアの運営を行う株式会社バルテックサインが運営。
DX-Signは、低価格で電子契約の標準機能を利用できる電子契約システムです。基本プランに契約書の作成や送信、電子署名、タイムスタンプといった電子契約の標準機能が搭載されているため、アップグレードや追加費用は必要ありません。作業環境を問わず、見やすい配色とフォントの大きさを意識。直感的に扱いやすい操作性で、初めて電子契約システムを導入する企業におすすめです。
- 契約書をクラウド上にアップロード
- 契約書を相手方へ送付し、契約書受信者は電子署名を対応して契約締結
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Normal | 0円 | 8,800円(税込) |
| Enterprise | - | 55,000円(税込) |
BOXILに投稿されたDX-Signを利用した人の口コミは次のとおりです。無料で使えるにも関わらず、機能が充実している点に口コミが集まりました。
DX-Signに改善を求める点はほぼありませんでしたが、「連携やオプションを増やしてほしい」といった要望がありました。
ジンジャーサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
人事、マーケティングなど多方で業務効率化につながるツールを提供するjinjer株式会社が(2021年10月設立)が提供。
ジンジャーサインは、一般財団法人日本データ通信協会認定のタイムスタンプを自動付与できる電子契約システムです。PDFの表示や編集ができるAdobe Acrobatを運営するAdobe社が認定するルート証明書での署名を実施していることに加え、データの自動バックアップ・SSL/TLSを用いた暗号化通信によって、安全面に配慮しつつ契約を締結できるでしょう。
- 管理画面から相手先企業を指定して締結する契約書をアップロード
- 署名箇所・締結日・氏名・住所・署名者などの入力内容と記入箇所を設定
- メールアドレスを指定して署名依頼メールを送信
- 相手先企業の担当者が指定箇所に必要事項の記入を実施
契約相手(書類受信者)は、ジンジャーサインのユーザーである必要はありません。
- 書類送信費用は、1件200円(全プラン共通)
- アカウント数・書類送信件数無制限(全プラン)
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金(税抜) |
|---|---|---|
| ライト | 50,000円 | 10,000円 |
| ライトプラス | 100,000円 | 28,000円 |
| ベーシック | 250,000円 | 50,000円 |
BOXILに投稿されたジンジャーサインを利用した人の口コミは次のとおりです。直感的にわかりやすい、見やすいUIなど、操作のしやすさに評価が集まっています。
一方で、クラウドサービスの利用に慣れていないと、使いづらさを感じる方もいるようです。
ConPass - 株式会社日本パープル

ConPassの特徴
署名方法と使い方
料金表
情報セキュリティ事業やデジタルアーカイブ事業などを運営する株式会社日本パープル(1972年5月設立)が運営。
ConPassは、契約書の作成から締結、保管までの契約業務を一元管理できる契約書管理サービスです。Adobe Acrobat SignとのAPI連携によって電子契約機能を利用でき、別途手続き不要で年間1件の電子署名から利用可能です。
また、契約期限が迫った契約書情報や関連タスクをダッシュボードで管理できます。ユーザーIDは無制限に発行でき、閲覧や操作権限を設定できます。
- Adobe Acrobat SignとのAPI連携により電子契約が可能
- Adobe Acrobat Signで締結された契約書データをConPassへ自動保存
- 契約書をアップロードするだけで台帳作成が完了
別途の問い合わせや契約手続き不要でAdobe Acrobat Signを利用でき、システム連携までサポートしてくれます。契約書をアップロードすると、契約書名や相手先、契約日など全10項目をAIが自動抽出※してくれ、管理台帳を作成できます。
※出典:日本パープル「契約管理DX ConPass[コンパス] | 株式会社日本パープル」(2024年6月7日閲覧)
- Adobe Acrobat Signは、1締結単位で利用でき、月額料金の別途負担なし
- 原本保管料金は無料
- 紙契約書の電子化にかかる料金については、仕様によるため要問い合わせ
| プラン名 | 初期費用(税抜) | 月額料金(税抜) |
|---|---|---|
| ライトプラン | 100,000円 | 30,000円 |
| スタンダードプラン | 100,000円 | 50,000円 |
| スタンダードプラス | 100,000円 | 要問い合わせ |
CONTRACTHUB - 日鉄ソリューションズ株式会社
クラウドサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
情報システム関連サービスを提供する日鉄ソリューションズ株式会社(1980年10月1日設立)が運営。
CONTRACTHUBは、従業員規模1,000人以上の電子契約サービス市場で7年連続シェアNo.1※の電子契約サービスです。請負契約や物品売買、秘密保持など、さまざまな契約に対応でき、見積依頼書といった関連書類のやりとりにも対応可能です。
取引先への案内や利用承諾書ひな形を提供するなどのサポートを受けられます。日本語と英語に対応しており、金融向けと建設不動産向け契約システムも提供しています。
※出典:日鉄ソリューションズ「電子取引・契約サービスCONTRACTHUB|NSSOLのデジタルテクノロジー&ソリューション」(2024年6月7日閲覧)
- 電子捺印、立会人型署名、当事者署名など5種類の署名方法に対応
- 検索性向上に役立つ属性項目は100件登録可能※2
- 承認や電子捺印完了、電子署名完了など管理文書の状態を色分け表示
CONTRACTHUBは、5種類の署名型に対応し運用に応じて利用可能です。契約書データへのアクセスURLを含む通知メールを契約相手へ送付でき、指定期間を経過すると督促メールを自動送付してくれます。
金額や日付に加え、連携システム上の管理番号といった独自の属性情報を設定できるので、検索管理に役立ちます。既存の基幹システムと連携し、契約データの登録、署名、通知を自動化可能です。
※出典:BOXIL掲載資料(2023年1月閲覧)
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 | 署名文書登録料 |
|---|---|---|---|
| ライトパック | 要問い合わせ | 50,000円~ | 100円/1文書~ |
| システム連携版 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
Adobe Acrobat Sign - アドビ株式会社
Adobe Acrobat Signの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
Acrobat Reader、PhotoshopやIllustratorを提供するアドビ株式会社(1992年設立)が運営。
Adobe Acrobat Signは多言語対応しており、DocuSignと並び海外企業との取引で活用できる点が特徴です。すでにAdobe製品を利用している企業はスムーズな導入が期待できるでしょう。1ユーザーあたりの署名数上限が年間150件までなため、それ以上の大量の処理を行う場合には別製品を検討した方がいいかもしれません。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
Adobe Acrobat Signは手書きサインも可能で、スタンプ機能を用いて印影画像の挿入もできるため、印影を求める取引先との契約でも対応可能なサービスです。相手方がアカウントを持っていなくとも利用できますが、本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証による立会人型のサービスのため、電子証明書による厳格な本人確認を必須とする場合には他サービスの検討も必要です。
- 個人版(1ユーザー)Adobe Acrobatに含まれる
- 2ユーザー以上であれば小規模企業版以上の契約が必要
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金(税抜) |
|---|---|---|
| Acrobat Standard(個人版) | 無料 | 1,518円(税込)〜 |
| Acrobat Pro(個人版) | 無料 | 1,980円(税込)〜 |
| Acrobat Standard(法人版) | 無料 | 1,848円(税込)〜 |
| Acrobat Pro(法人版) | 無料 | 2,380円(税込)〜 |
| Acrobat Sign Solutions | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたAdobe Acrobat Signを利用した人の口コミは次のとおりです。Adobe関連製品で契約があればすぐに使い始められる点、グローバルで幅広く使われているため安心して利用できる点などが評価されています。
一方で、費用や使いづらさ、動作の重さに関して言及する口コミも見られました。そして、国内では若干知名度が低く取引先への説明が必要になるケースも多いようです。
paperlogic電子契約 - ペーパーロジック株式会社
ペーパーロジック電子契約の特徴
署名方法と使い方
料金表
経理、総務、法務領域におけるペーパーレスソリューションを提供するペーパーロジック株式会社(2011年4月設立)が運営。
同社が提供する電子稟議(ワークフロー)、電子書庫(クラウドストレージ)とペーパーロジック電子契約を連携させ、稟議から契約書の保管まで一貫したシステムを構築できます。すでに製品を利用している企業は導入しやすいでしょう。当事者型・立会人型として活用でき、厳格な本人確認を要する業界でも導入しやすいサービスです。
- 契約書ファイルをシステムにアップロード
- 相手方の情報を設定して送信
- 相手方は承認依頼メールを受領後承認
- 関係者全員が承認すると電子署名済み契約書ファイルがダウンロード可能
当事者型、立会人型いずれも対応可能。相手方も電子証明書を用いる方式、メール認証による方式、単に受領し確認するだけの方式と、書類の内容や重要性によって手続を変更可能なため、厳格な本人確認を要する契約から一方的な通知まで、幅広い用途が想定される会社でも導入しやすいでしょう。
- 契約締結ごとの従量課金はされないが、月の締結可能上限が定められている
- 電子証明書は年3,500円で利用可能
- 電子証明書を利用しない簡易署名は無料(回数制限なし)
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 月25契約まで | - | 20,000円 |
| 月50契約まで | - | 35,000円 |
| 月75契約まで | - | 50,000円 |
| 月100契約まで | - | 65,000円 |
契約大臣の特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
専門性の高い市場に特化したウェブサービスを展開している株式会社TeraDox(2008年設立)により運営。
契約大臣は、リーズナブルかつ直観的に使える操作性を追求した電子契約システムです。
契約書はPDFのアップロードだけではなく、あらかじめ用意されている複数のテンプレートからでも作成できます。グループ機能では、契約書の閲覧や作成の範囲を自由に設定可能です。グループごとに、操作できるユーザーを指定したい企業におすすめです。
- 契約書を作成し、取引先へ締結依頼メールを送付
- 取引先は、メールのURLにアクセスして契約書の内容を確認
- 社名や担当者名などの必要事項を入力後、「合意」ボタンをクリック
- 双方のメールに締結済みの契約書PDFと合意締結証明書が送付され、締結完了
プレミアムプラン以上を希望の場合、要問い合わせ
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金(年契約の場合) |
|---|---|---|
| フリープラン | 0円 | 0円 |
| スタータープラン | 0円 | 2,200円(2,020円) |
| ベーシックプラン | 0円 | 6,600円(6,050円) |
| プレミアムプラン | 0円 | 9,900円(9,075円) |
※税込価格
BOXILに投稿された契約大臣を利用した人の口コミは次のとおりです。無料プランが使える点やマニュアルなしでも契約締結が簡単な点が評価されています。契約締結数が少ない方にはもってこいのサービスです。
BOXILに投稿された口コミの中では、改善を希望する点はまだありませんでした。
その他の電子契約システム
ONEデジDocument - リーテックス株式会社
ONEデジDocumentの特徴
署名方法と使い方
料金表
リーテックス株式会社(2019年9月設立)により運営。
ONEデジDocumentは、電子契約と電子記録債権を併用することで、法人の意思確認を担保している点が特徴です。
電子記録債権の指定機関であるTranzax電子債権株式会社と連携し、電子記録債権を利用可能。POファイナンス(Purchese Orderファイナンス:電子記録債権化された注文書を担保に、提携している金融機関から資金調達ができるシステム。Tranzax株式会社、Tranzax電⼦債権株式会社が提供。)を活用する企業に向いています。
3者間以上の契約には2021年1月時点では対応しておらず、テンプレート機能、API連携機能などはないため、厳格な本人確認や電子記録債権の活用に拘らない企業での導入は、少しハードルが高いかもしれません。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
相手方も登録が必要であり、登録の際に必要書類(登記事項証明書、取引担当者本人確認書類、法人印)を用意して申し込み作業が必要な当事者型のサービスです。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| エントリー | 無料 | 0円 |
| シンプル | 無料 | 3,667円〜 |
| トータル | 無料 | 55,000円 |
| プレミアム | 要問い合わせ | 110,000円 |
Dropbox Sign - Dropbox Japan 株式会社
Dropbox Signの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
オンラインストレージを提供するDropbox Japan 株式会社(2014年9月設立)が日本では運営。
Dropbox Signは、数百万人ものユーザーが利用しているシステム連携に優れた電子署名サービスです。オンラインストレージDropboxとの連携を強みにしていて、DropboxのほかSalesforceやGoogle Workspaceから送信や署名が行えます。22か国の言語にも対応しており国外での取引にも利用可能。
- ドキュメントをDropbox Signにアップロード
- 相手の名前とメールアドレスを入力
- ドキュメント内の署名ほか、記載事項を指定
- [署名を依頼]ボタンをクリック
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Essentials | 0円 | 1,600円 |
| Dropbox One | 0円 | 2,900円 |
| Standard | 0円 | 2,800円 |
| Premium | 0円 | 要問い合わせ |
BOXILに投稿されたDropbox Signを利用した人の口コミは次のとおりです。安価なプラン設定、無料でもある程度使える点で評価されています。
日本語表記が文字化けする、不自然な場合があるといった口コミが寄せられています。
しくみs・サインハンコ(エンタープライズ版) - 合同会社ナソリ
しくみs・サインハンコの特徴
署名方法と使い方
料金表
システム開発やインフラ構築といったエンジニアリングサービスのほか、業務提携している顧客管理システムパッケージの提案をしている合同会社ナソリが運営。
しくみs・サインハンコ(エンタープライズ版)は、長期にわたり署名検証できる国際規格に対応した電子契約システムです。有効期限切れが起こる前にタイムスタンプを再度付加することで、10年20年と延長できます。
- 事前に印鑑画像を登録
- 契約書フォーマットに沿って契約書を作成
- 承認フローを設定してメールにて承認を依頼
- クラウド上で契約書をアップロードして顧客へ送付
- 顧客が電子署名をすると契約締結
アカウントを持っていない顧客には、ExcelまたはPDFファイルにしてメールでやりとりできるため、顧客の環境を問わず使えるシステムです。
| プラン名 | 初期費用 | 料金 |
|---|---|---|
| エンタープライズ版・プラベートクラウド | - | 250,000円/月(税込) |
| エンタープライズ版(カスタマイズ) | - | 3,000,000円(税込) |
| パプリッククラウド版 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
鈴与の契約書管理ソリューション - 鈴與株式会社

鈴与の契約書管理ソリューションの特徴
署名方法と使い方
料金表
物流を切り口としたサービスを提供する鈴与株式会社(1801年創業)が運営。
鈴与の契約書管理ソリューションは、契約書や議事録などの文書管理はもちろん、外部サービスと連携し電子契約、契約書作成、リーガルチェック機能も利用できる文書管理システムです。
スキャニングやデータ入力、書類保管、機密抹消サービスなども利用でき、課題や運用に合わせ選択利用できます。文書の管理台帳、原本、PDFデータを紐づけ管理し、文書の作成から廃棄までを管理可能です。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| - | 330,000円〜(税込) | 43,780円〜(税込) |
上記で紹介した電子契約システムの口コミやランキング、料金詳細の一覧はこちらからで掲載しています。
電子契約システムのおすすめ比較【不動産業界向け】
デジタル改革関連法が施行され、不動産業界でも電子化が活性化しはじめています。
不動産業界向けの電子契約サービスは申し込みから締結後の更新業務まで一貫して対応していることが多く、不動産業界での業務全体をカバーできるでしょう。
いえらぶ電子契約の特徴
署名方法と使い方
料金表
不動産業務を効率化し、成果を最大化するオールインワンシステム「いえらぶCLOUD」を提供する株式会社いえらぶGROUP(2008年1月設立)により運営。
いえらぶサインは、不動産契約に特化した電子契約システムです。不動産の申し込みから契約締結、更新業務までWeb上で契約が完結します。契約の種類および不動産会社の業態、扱う物件に関わらず電子契約できる、賃貸契約や売買契約、不動産管理などに幅広く対応。契約書のデータは、管理機能と連携しているため、不動産に関する多くの業務に活用できます。
- 申し込み時に取得した顧客データから契約書を作成
- 契約書はクラウド上に自動保管
- 更新時期が近づくと、該当する契約を自動で抽出
- 更新の意思がある契約者に、更新契約書を自動で作成し送付
| プラン名 | 初期費用 | 月額(基本料) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 100,000円(税抜) | 15,000円(税抜) |
月額(従量課金):200円(税抜)/契約
PICKFORMの特徴
署名方法と使い方
料金表
- PDFの契約書類をアップロード
- 宅建士による署名
- 重要事項の説明
- 電子契約
- 締結完了
PICKFORMは、同時署名方式を採用しているので、署名者全員が好きなタイミングで押印可能です。関係者が多い不動産契約のスムーズな締結に役立ちます。
- 初回登録から5通分までは、月額料金含め無料
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 要問い合わせ | 33,000円(税込) |
Release - GOGEN株式会社

Releaseの特徴
署名方法と使い方
料金表
住宅購入支援サービスといった不動産売買に係るサービスを提供するGOGEN株式会社(2022年設立)により運営。
Release(レリーズ)は、不動産売買に特化した電子契約サービスです。不動産売買契約の電子化に求められる規定に完全対応しているため、業務フローやマニュアルを新たに作成する必要がありません。
案件名や部屋番号、決済日など、不動産特有の項目で契約を管理可能です。顧客はマイページから、契約書や契約概要を確認できます。
- 契約書や関連書類をアップロードして相手方へ送信
- 相手方は、受信した書類のリンクから内容を確認し同意
- 関係者全員が同意すると、ファイルに電子署名が施され、クラウド上に保存
電子署名と書類保管にはクラウドサイン、SMBCクラウドサインを利用します。相手側のサービス登録は不要です。
- クラウドサイン、SMBCクラウドサインの利用料金を含む
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| - | - | 17,600円(税込)~ |
日本情報クリエイトの不動産専用 電子契約 - 日本情報クリエイト株式会社
日本情報クリエイトの不動産専用 電子契約の特徴
署名方法と使い方
料金表
不動産会社の各業務に沿った製品、サービスを提供する 日本情報クリエイト株式会社(1994年8月設立)が運営。
日本情報クリエイトの不動産専用 電子契約は、不動産の管理業務に特化したサービスです。不動産の契約業務に合った自由度の高いフローを設定可能。従来の紙で行っていた賃貸借契約の流れを変えることなく、スムーズに電子契約へ移行できます。今までExcelやWord、PDFで作成していた契約書のひな型もそのまま利用でき、一から契約書を作成する手間を省けます。
- 相手方の情報を入力し、契約書ファイルをアップロードして送信
- 相手方には確認依頼が届き、当事者情報を入力して承諾
- 関係者全員が承諾すると契約締結が完了
日本情報クリエイトの不動産専用 電子契約は立会人型(事業者署名型)を採用。メールやSMSで署名ができるため、一般入居者でも電子契約を簡単に行えます。また、電子証明有効期限10年の長期署名にも対応しています。
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ |
ベクターサイン - 株式会社ベクター

ベクターサインの特徴
署名方法と使い方
料金表
- 文書をアップロードし、社内承認と署名を完了
- 相手方に署名依頼を送信
- 相手方は、メールに記載されたURLから文書の内容を確認
- 確認画面にて署名を実行
- 署名がすべて完了するとメールで通知
認証コードによるメールアドレス認証とワンタイムパスワード認証に対応した立会人型サービスです。署名がすべて完了すると、メールで通知され、記載されたURLから締結証明書をダウンロードできます。
- 7日間の無料トライアル
| プラン名 | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 要問い合わせ | 11,000円(税込) |
※文書送信件数100件分を基本料金に含む。101件からは60件ごとに3,300円(税込)で追加可能。
Shachihata Cloud - シヤチハタ株式会社
Shachihata Cloudの特徴
署名方法と使い方
料金表
利用した人の口コミ
シヤチハタ印、スタンプ台、朱肉などの文房具を製造販売するシヤチハタ株式会社(1941年9月24日設立)が運営。
Shachihata Cloudは、契約書の作成から回覧、承認、締結まで一連のプロセスを電子化するサービスです。決裁状況をリアルタイムで把握できるワークフローを搭載し、ルートは申請者にて設定可能です。
エントリープランをベースに必要な機能を選択追加でき、電子帳簿保存法に対応する機能をまとめたセットプランの提供もしています。定額制のプランのため、送信数に影響されずに定額で利用可能です。
- 文書をシステムへアップロードし、社内承認を受ける
- 取引先へ文書を送信
- 取引先がシステム上で承認することにより契約を締結
取引先はアカウント登録不要、無料で利用できます。立会人型での署名に対応し、タイムスタンプで非改ざん性を担保可能です。使用している印鑑や手書きサインなどをそのまま電子化して捺印できます。
| プラン名 | 初期費用 | 料金 |
|---|---|---|
| エントリープラン | 無料 | 110円(税込)~/人/月 |
| ベーシックプラン | 無料 | 330円(税込)~/人/月 |
| プレミアムプラン | 無料 | 440円(税込)~/人/月 |
| エンタープライズプラン | 無料 | 550円(税込)~/人/月 |
- 30日間の無料トライアルあり
BOXILに投稿されたShachihata Cloudを利用した人の口コミは次のとおりです。シンプルで安価な価格が日高く評価されています。必要に応じてグループウェアのような使い方もできる点にも口コミが集まりました。
一方で、承認順や検索機能を含めた、細かな仕様に関する改善を希望する口コミもありました。
不動産業界向け電子契約システムは、こちらの記事でも詳しく解説しています。よくある課題や、その課題をどのように解決できるのかも説明しています。

電子契約サービスのおすすめ比較【無料】
ラクラク電子契約
ラクラク電子契約の特徴
署名方法と使い方
株式会社デジタルストレージが運営。ラクラク電子契約の毎月30件まで無料とされている立会人型の電子契約サービスですが、料金ページを閲覧できないため確認が必須です。
- 契約書ファイルをアップロード
- メールアドレスといった送信先の情報を入力して送信
- 相手方に承諾依頼のメールが届き、関係者全員が承諾すると締結が完了(相手方がアカウントを持っていなくとも利用可能)
本人確認は主にパスワード、メールアドレス認証によります。
無料で使える電子契約システムや、電子サインを無料で行う方法はこちらの記事で解説しています。


電子契約システムとあわせて導入したいサービス【番外編】
電子契約システムを導入する際に、あわせて導入を検討したい契約書管理システム・契約書レビューシステム・電子契約導入代行サービスを紹介します。
LegalForce - 株式会社LegalOn Technologies
LegalForceの特徴
機能・詳細
- AIによる自動の契約書レビューで業務を効率化
- レビュー品質のばらつきを解消するデータベースを作成
- 弁護士が監修したひな形を活用して業務品質を向上
LegalForceは、AIで瞬時に契約書を自動レビューするクラウド型レビュー支援ソフトウェアです。契約書にある不利な条文や欠落条項、抜け漏れをAIがチェックして見落としを防ぎます。
自社のひな型や過去の契約書を自動でデータベース化し、必要な条文を簡単に取り出せます。また、法律事務所が作成した契約書のひな形や書式を250点以上搭載。企業法務に特化したひな形や書式は、弁護士が作成した実用的なもので法改正にも適時に対応できます。
| タイムスタンプ機能 | 契約書管理 | ワークフロー機能 | テンプレート機能 | 合意締結証明書の発行 |
|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
LegalForceキャビネ - 株式会社LegalOn Technologies
LegalForceキャビネの特徴
機能・詳細
- 紙の契約書をAIでデータ化
- 契約書情報を自動抽出し検索できるデータベースに
- 終了日や更新日など契約期限の確認が簡単
LegalForceキャビネは、AI技術を活用した入力不要の契約書管理システムです。紙の契約書をデータ化して、締結済みの契約書情報を自動で抽出。契約書の情報を手入力する作業と目的の契約書を探す時間を削減します。
| タイムスタンプ機能 | 契約書管理 | ワークフロー機能 | テンプレート機能 | 合意締結証明書の発行 |
|---|---|---|---|---|
| - | ◯ | - | - | - |
- 建設工事業種における契約の電子化をサポート
- 丁寧なヒアリングですぐに運用できる環境を設定
- 専任のコンサルタントが導入・運用をサポート
DD-CONNECTは、電子契約サービス「CONTRACTHUB」の導入から運用までをサポートする電子契約導入代行サービスです。導入企業や取引先に対して、現状の課題や導入後の運用について説明し、電子契約サービス導入時の不安を解消します。
準備や設定など運営維持のために必要な煩わしい業務を代行するため、導入に関する作業や工数がかかりません。導入後の運用サポートも充実していて、電話とチャットで問い合わせに対応し、設定変更やマスタの登録も代行可能です。
電子契約システムの口コミ数ランキング
BOXILでまとめている電子契約システムのレビュー数のランキングを紹介します。サービス選びの参考にしてみてください。
| 順位 | サービス名 | 料金プラン | 説明文 |
|---|---|---|---|
| 1位 |  クラウドサイン クラウドサイン | 月額10,000円〜 | クラウドサインは、法律に対する高い専門性を強みとして弁護士ドットコム株式会社が開発・運営を行っており、電子帳簿保存法に対応する仕様、弁護士監修の運営体制など、法的に安心して利用できます。 |
| 2位 |  freeeサイン freeeサイン | 月額4,980円〜 | freeeサインは契約に関するお悩みをクラウド上で解決する電子契約システムです。契約の作成から管理まで、freeeサインのみで完結できます。 |
| 3位 |  電子印鑑GMOサイン 電子印鑑GMOサイン | 月額8,800円〜 | 電子印鑑GMOサインは、法的に有効なクラウド型の電子契約サービスです。契約締結・管理の業務効率化や印紙税などのコスト削減、コンプライアンス強化を実現します。 |
| 4位 |  ドキュサインの電子署名 ドキュサインの電子署名 | 月額1,100円〜 | ドキュサインの電子署名は、世界で最も使われている電子署名サービスです。 契約文書の印刷や郵送などの手間がなくなり、場所やデバイスを問わずに契約書や申請書への承認や合意できるので、業務の大幅な効率化を図れます。 |
| 5位 |  Adobe Acrobat Sign Adobe Acrobat Sign | 月額1,518 円(税込)〜 | Adobe Acrobat Signはアドビが提供する電子契約サービスです。世界中で年間60億回以上の電子契約がAdobe Acrobat Signを通じて行われています。 |

「BOXIL SaaS AWARD Summer 2024」の受賞サービス
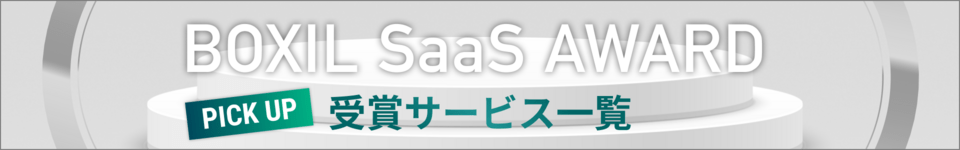
「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」が毎年3月4日を「SaaSの日(サースの日)」と定め、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。
今回の「BOXIL SaaS AWARD Summer 2024」は、2023年4月1日から2024年3月31日までの1年間で新たに投稿された口コミ約18,000件を審査対象としており、計333サービスに、ユーザーから支持されるサービスの証としてバッジを付与しました。
| freeeサイン | DocYou | DottedSign(ドットサイン) |
| Shachihata Cloud | ドキュサインの電子署名 | Adobe Acrobat Sign |
| 電子印鑑GMOサイン | SMBCクラウドサイン | クラウドサイン |
【Good Service】:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。
| 料金の妥当性No.1 | 電子印鑑GMOサイン |
| 初期設定の容易さNo.1 | SMBCクラウドサイン |
| サポートの品質No.1 | SMBCクラウドサイン |
| 営業担当の印象No.1 | SMBCクラウドサイン |
| サービスの安定性No.1 | LegalForce |
| 機能満足度No.1 | ONEデジDocument |
| お役立ち度No.1 | ONEデジDocument |
| 使いやすさNo.1 | マネーフォワード クラウド契約 |
【口コミ項目別No.1】:「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たしたうえで、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。
>>BOXIL SaaS AWARD Summer 2024の詳細はこちら
迷ったらBOXILで口コミや資料請求が多いサービスをチェック
近年、テレワーク・リモートワーク推奨といった影響により、電子契約サービスを導入する企業は増えてきています。しかし、ボクシルに寄せられる評判・口コミを調べると、電子契約サービスを「導入する前に情報収集を徹底しておけばよかった」という意見は少なくありません。
システム導入時に情報収集を念入りに行った企業では導入後の満足度が高く、反対に情報収集に時間をかけなかった企業では社内の利用率が低くなりやすいです。そのため、システム導入で失敗しないためには各サービスの情報収集を念入りに行い、料金や機能、特徴を比較することが重要です。
ぜひ、電子契約システムの導入を検討する際は、ボクシルの無料でダウンロードできる資料を参考に情報収集し、気になるサービスを比較してください。
| DocuSign eSignature | freeeサイン | クラウドサイン |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 188か国、43言語への署名へ対応 2億を超えるユーザー数 |
作成、レビュー、締結まで一元管理可能 | 電子契約利用企業の約80%が利用する累計登録者数No.1サービス(※矢野経済研究所調べ) |
上記3サービスも含め、記事中で紹介した電子契約システムのおすすめの詳細資料は、こちらから無料でダウンロード可能です。サービスをまとめて比較する際にお役立てください。
執筆者

司法修習修了後、法律事務所において中小企業、新規事業関連法務の経験を経て大和リビングマネジメント株主会社へ入社。国内不動産法務全般、海外進出案件に従事しつつ、不動産取引の電子化を推進。 その後、OYO TECHNOLOGY & HOSPITALITY JAPAN株式会社へ入社し、新規事業開発法務、不動産取引の電子化普及活動等を行う。 2020年4月より現職。エンターテイメント×テクノロジー分野の法務、コーポレート業務等全般を扱う。 個人として、宇宙ビジネスをはじめとするスタートアップ複数社の法務や宇宙法の研究に従事。 著書: Q&Aでわかる業種別法務不動産(中央経済社) 即実践!!電子契約(日本加除出版) 宇宙ビジネス参入の手引き〜New Spaceに向けた技術活用・参入検討〜(情報機構)