電子署名とは? 基礎知識と仕組みやメリット、電子サインとの違い

目次を閉じる
電子署名とは
電子署名とは、わかりやすく説明すると紙の文書における「押印」や「サイン」に相当する電子的な署名のことをいいます。電子文書の作成者を明確にし、改ざんされていないことを証明するデジタル的な仕組みです。
デジタルデータに署名するので、印鑑(ハンコ)のように書類を印刷して押印する必要はなく、オンラインでの署名が可能です。また、印影も必要としません。
電子署名の取得方法は厳密に決まっているため、安心して利用が可能です。電子署名は本人認証と厳しい審査を経て第三者機関によって発行され、かつ公開鍵暗号基盤といった暗号通信技術を用いているため、書類の信頼性を担保できます。テレワークの普及に伴ってハンコに代わる本人証明の方法として注目を集めています。
電子署名と電子サインの違い
電子署名と類似する言葉に「電子サイン」があります。電子署名は電子サインの一種と覚えておいて問題ありません。電子サインは電子文書に関する本人認証手続き全般のことを指します。従来の書類手続きにおける押印のような役割です。
一方で電子署名は、従来の契約における実印のようなもので、信頼性と法的効力が強固なため、主に重要な契約や手続きで使用されます。


電子印鑑と電子署名の違い
電子署名は、電子文書に行われる署名のことを指す言葉です。一方で、電子印鑑は、電子文書で用いるためのデジタル化した印鑑のことをいいます。電子署名とは異なり、電子印鑑は証拠力が低く、ビジネスにおいては電子署名を用いるのが一般的です。
ただし、電子印鑑には2種類あり、単純に印鑑の印影を画像としてデータ化したものと、電子上で本人識別情報を含めたものがあります。印影を画像データ化しただけのものは複製が容易できてしまうため、悪用されるリスクがあり、見積書のような社外との取引には使用されません。
ただし、印影のデータ内に識別情報が含まれたものは改ざんや悪用の防止機能などのセキュリティが強化され、所有者の正当性を証明できる機能が付与されているため、実印と同様の効力をもちます。
電子署名法とは
電子署名は、電子署名法により定義とルールが定められています。電子署名法の正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」であり、2001年に施行されました。
同法第3条によれば、契約書に本人による電子署名が行われているときは真正性を推定することが規定されています。この電子署名法により、電子署名が、手書きの署名や押印と同様の法的効力をもつことが認められました。
なお、実際は電子署名には公開鍵暗号基盤を使用することが多いものの、法律の定義上は公開鍵暗号基盤を用いることは求められていません。そして、電子的に署名が行われていれば印影は必ずしも必要ありません。
電子契約の有効性
日本の多くの契約は当事者間の意思表示だけで成立します。理論上は当事者が書面を交わしていなくても、意思表示だけで有効な契約とみなされます。よって、電子契約書でも電子署名がなかったとしても有効な契約として認められるのです。
ただし、電子署名を用いた契約書が訴訟になったとき証拠になりえるかには注意しなければなりません。電子契約や電子署名の有効性について真っ向から争った判例は存在しないため、今後の判例蓄積が求められます。
電子署名の仕組み
電子署名では電子契約の当事者を本人認証し、改ざんされていないことを確認するために、公開鍵暗号基盤(PKI:Public Key Infrastructure)を活用します。
公開鍵暗号基盤では、データを暗号化する公開鍵と復号するための秘密鍵と2種類の暗号鍵を使用します。この2種類の鍵により、データの内容が途中で改ざんされていない、そして不正取得されても秘密鍵を知らなければ第三者が復号できないように通信が可能です。
公開鍵暗号基盤には、途中で鍵をすり替えられた可能性がないことの確認方法となる、電子証明書があります。電子証明書は公開鍵とそれに対応する持ち主の関係を証明するものであり、第三者機関である認証局が発行するものです。
また、データ自体がすり替えられる可能性を考慮して、「ハッシュ関数」と呼ばれる数値化技術によりデータの同一性を担保しています。
公開鍵と秘密鍵、2種類の暗号鍵を使用し第三者機関が持ち主を証明することにより、情報送信者はだれでもデータを暗号化が可能です。そして、暗号を復号できるのは秘密鍵をもったユーザーのみと、高い安全性を実現したデータの原本性を高めます。
また、発行日時の証明となるタイムスタンプを付与することにより、文書の同一性がさらに強化される仕組みとなります。
電子署名の当事者型と立会人型
電子署名には、「当事者型」と「立会人型」の2つの署名方法があります。
当事者型署名とは、認証局が事前に本人認証をして電子証明書(実印における印鑑証明のようなもの)を発行し、本人だけが利用できる環境で署名する方法です。
立会人署名型とは、契約を交わす双方が電子契約書をオンライン上にアップロードし、立会う電子契約サービス提供事業者が締結を確認して電子署名を行う方法です。
当事者型署名は、契約者双方が電子証明書を保有する必要があり、都度認証を受ける必要があるので手間と費用がかかります。一方の立会人型では、本人性の要件が不十分な可能性はあるものの、何度も認証を受ける必要がないため、電子署名として行われるケースが多いです。
電子署名法においては、当事者型、立会型のどちらでも電子署名として法的に有効だと考えられます。

電子署名のメリット
電子署名には「原本性を高められる」「契約に関わるコストを削減できる」「契約業務を効率化できる」と、3つのメリットがあります。それぞれについて詳しく説明します。
原本性を高められる
電子署名を活用すれば、データの原本性を高められます。公開鍵暗号基盤を活用することにより、通信過程における文章の改ざんを困難にしているためです。電子署名を活用してデータを送受信することで、信頼性も原本性も高くなります。
重要な契約書や手続きの際には電子署名を活用して、原本性が高い状態で情報を受け渡しできます。
紙の契約書を用いる場合、紛失や改ざんなどのリスクへの考慮が必要です。しかし、電子署名は、契約書の内容を電子化しクラウド上で管理されるため、これらのリスクを低減できます。閲覧範囲の設定のような情報漏えい対策も可能なため、紙文書と比べ大きく安全性が高まります。
契約に関わるコストを削減できる
電子署名を活用することで、契約に関わるコストを削減できます。電子署名を用いる電子契約では、物理的な紙の書類の必要がないため、印刷や郵送費用が必要ありません。契約書データをメールに添付したりクラウドにアップしたりすることで、契約者双方がオンラインで契約を締結できます。
また、電子契約には印紙税がかかりません。紙の契約書では収入印紙を貼付しなければならないケースでも、電子契約は課税文書にはならないため、収入印紙が不要です。

契約業務を効率化できる
電子署名を活用することで、契約業務を効率化できます。電子署名の場合はデジタルデータを送受信するだけなので、遠隔でもほぼリアルタイムで契約が可能です。
双方が契約書に押印しなければならない場合、印刷された書類を郵送のための期間が必要です。そして、当事者が増えれば増えるほど契約にかかる期間と手間は増加します。書類に不備があれば、訂正のために何度も書類を郵送することにもなりかねません。
契約業務を効率化することは、企業経営のスピードアップにもつながります。
電子署名のデメリット
電子署名は原本性の向上やコスト削減、業務効率化のメリットがありました。一方で、適用できる取引が限定されている、取引先にも一定のリテラシーが求められるといった注意点もあります。
適用可能な取引が限定される
電子契約はどのような契約でも締結できるわけではなく、一部適用できない取引も存在します。たとえば、定期借地契約や特定商品取引法で書面交付が義務付けられている取引は、電子契約で締結できません。
ただし、時代の変化に伴い、電子署名が活用できる取引は徐々に増加していくものと考えられます。
取引先にも一定のリテラシーが求められる
電子契約を活用するには、一定のリテラシーが求められます。自社のリテラシーは十分でも、取引先がやり方をわからず使いこなせなかったり、導入に難色を示したりすることもあるかもしれません。
契約には、契約する相手がいます。どれほどリテラシーがあっても、顧客、取引先が導入してくれなければ電子契約は成立しません。これには相手のアカウントの有無や必要性だけの問題だけではなく、心理的障壁や業務フローといった問題もあります。
「印鑑を押印しないのに契約は成立するのだろうか」と漠然と心理的抵抗を感じる方もいるので、取引先によっては導入が難航する可能性もあります。
サイバー攻撃のリスクがある
オンラインでデータをやり取りする以上、電子契約にはサイバー攻撃のリスクもあります。
公開鍵暗号によって通信中のデータに関しては強固なセキュリティで保護されています。ただし、秘密鍵が使用される側の端末のセキュリティが甘く、サイバー攻撃により情報が流出する可能性はゼロではありません。
公開鍵暗号基盤を活用しているからといって安心せず、さまざまな角度からセキュリティ対策をしていきましょう。
電子署名の利用例
デジタルデータでの情報コミュニケーションが増加したことで、電子署名が用いられるケースも増えました。電子署名の利用方法として、「官公庁とのやりとり」「重要な書類の保護」の2つの切り口から紹介します。
官公庁とのやりとり
電子署名が活用される代表的な事例として、納税申告に用いられるe-Taxが挙げられるでしょう。納税に関するデータは重要かつ真正性が求められるため、本人認証および改ざんされていないことを証明するために電子署名の技術が活用されています。
ほかにも、公共案件に対する電子入札でも、機密性や信頼性を担保するために電子署名が活用されています。
重要な書類の保護
金融や医療といった分野では、情報の流通に真正性と信頼性が求められるため、電子署名が活用される傾向にあります。たとえば、オンラインで融資手続きを行う場合や、臨床カルテを電子カルテとして保存する場合は、電子署名を使用する必要があるでしょう。
重要な書類を保護し、改ざんのないことの確認が求められる場合は、さまざまな業界・シチュエーションで電子署名がさらに活用されていくと考えられます。たとえば、電子署名を活用した電子契約では、契約に関係する業務の効率化と契約の信頼性の担保が両立できます。
電子署名を活用してスムーズな電子契約を
働き方改革やリモートワークの推進により物理的な印鑑から電子署名に切り替える企業が増えています。また、企業に限らず公的手続きも徐々にデジタル化することが予想されます。実際、2021年のマイナンバーカードの手続きはデジタル化されました。
電子署名を活用することにより、電子契約のコスト削減、業務効率化が可能になるでしょう。
電子署名が可能な電子契約システムの詳細はこちらから参照できます。あわせて参考にしてください。

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査























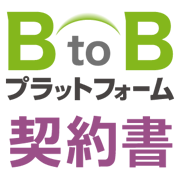

 目次
目次
