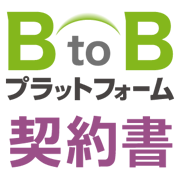建設業界で電子契約システムは活用できる?法律やシステムを含めて解説

目次を開く

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
電子契約システムとは?
電子契約システムとは、これまで書面で行っていたものをデジタル化し、オンラインですべて完結させるシステムのことです。書面の場合契約書の作成、印刷、郵送、返送、保管などの工程がありますが、これをデジタル化することで簡略化できます。
通常オンライン上の文書は、改ざんやなりすましがしやすいことで知られています。しかし、捺印署名を電子署名やタイムスタンプで代用するといったように、電子契約システムはこの問題をクリアできることから、書面に代わる契約として認められているのです。
建設業界でも電子契約システムは使える?
建設業界においても電子契約システムは活用できます。以前は書面契約が義務付けられていたものの、2001年の建設業法改正により、電子契約書の使用が可能になりました。
建設業界では、紙の媒体での契約が多かったものの、その業務効率の高さ、コスト削減の観点から徐々に建設業者の間に普及しつつあります。国土交通省も電子契約を推進していることもあり、注目が集まっているといえるでしょう。
建設業法における法解釈
2001年建設業法改正で電子契約が可能に
2000年、IT書面一括法が施行されました。IT書面一括法は、民間の商取引おける書面の交付が義務付けられている関係法律50本について、相手側の了承さえあれば書面に記載すべき事項を電磁的措置によって行うことを可能にする法律です。
これによって、各商取引に関する法律が見直されて2001年4月1日から改正建設業法が施行。それまで書面の交付が必要だとされていた建設請負は、この改正により電子契約で建設請負契約を結ぶことも可能となりました。
建設業法とは1949年に制定された法律で、建設工事の適正な施工を確保、発注者に対する保護、建設業界の健全な発達促進を目的にしています。建設業における契約は民法や商法などの一般的な法律が適用されるだけではなく、建設業法の適用も受けます。
請負契約が電子契約可能な根拠条文
建設業法19条には、次のように記載されています。
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
※出典:e-GOV法令検索「建設業法19条」(2022年6月6日閲覧)
よって基本的には請負契約は書面を交付、署名または記名押印しなければならないのですが、同3項には
建設工事の請負契約の当事者は、(中略)当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。
と定められています。
この文言によりリフォームも含め建設業の請負契約の電子契約が可能になりました。「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術」とは、コンピューターやインターネットなどのことを指します。
これらの技術を活用している電子契約システムであれば、建設業法によって規制されている建設工事の請負契約も電子契約可能なのだと理解できます。
建設業の電子契約で必要な3つの要件
建設業は依頼する額が大きいため、発注者を保護する目的で電子契約にも3つの要件を課しています。3つの要件は次のとおりです。
- 見読性
- 原本性
- 本人性
どれか1つでも抜けてしまうと、法律や規制に違反する可能性があるため、しっかりと確認してください。
見読性
見読性とは、わかりやすく言えば「契約書がいつでも読める状態にある」ことです。契約後ディスプレイでいつでも契約書の内容が確認できたり、データを印刷できたりと、発注者の都合で契約書の確認をできることが重要になります。
また契約には複数の関係者が存在することから、アクセスの管理や読み出し不能、破壊などのトラブルを未然に防ぐシステムが必要です。
原本性
見読性とは、わかりやすく言えば「契約書が本物で、改ざんされていない」ことです。署名が本人のものでなりすましがなく、内容も改ざんされておらず、コピーでないと推定できることが重要です。
しかし冒頭でも紹介したように、デジタル化された書面はなりすましや、改ざんがされやすいことで知られています。そのため、システムとしては公開鍵暗号方式や、タイムスタンプなどを活用することで、原本性を証明します。
公開鍵暗号方式とは
公開鍵暗号方式とは、契約書のデータを送受信する際にセキュリティを高める手法のことです。送信の際データ暗号化を行うために「公開鍵」を使い、暗号化された契約書閲覧のために「秘密鍵」で複号化します。
本人性
本人性とは、わかりやすく言えば「電子署名が本人のものである証明」のことです。本人か確認するには、当人のメールアドレスに送ったリンクをクリックしてもらう方法があります。
ただし、より重要な書類を扱う場合は第三者機関に電子証明書を発行してもらい、本人証明を行うこともあります。
建設業に導入する電子契約システムの選び方
建設業に電子契約システムを導入する場合、選び方としては上記の「見読性・原本性・本人性」を満たしており、法的効力を持っていることが重要です。
見読性の見分け方としては、パソコン画面と書面のどちらでもはっきり契約書の内容が確認されているかをチェックしてください。原本性に関しては、公開鍵暗号方式を採用していることと、第三者機関による電子証明書に対応していることが重要です。
またそのほかにも、システムとしてセキュリティにどの程度力を入れているか、改ざん対策として実施していることなども確認しましょう。本人性は電子署名の本人確認方法として「当事者型」か「立会人型」の2種類があります。
当事者型とは認証局が本人確認を行う方法、立会人型はクラウド上で署名を行う方法です。これはどちらでも問題ないため、自社に適した方法を選んでください。
建設業における電子契約システム導入のメリット
建設業は下請け・元請け業者との契約や、土地や資材の売買などに関わる契約といった一般的な契約書だけではなく、建築確認をはじめとするさまざまな行政手続きを含めて、書類仕事が発生します。
これらの書面仕事を電子契約システムに置き換えることによって、次の4つメリットが期待できます。
- 収入印紙のコスト削減
- 書類の管理コストの削減
- 手続き時間の短縮
- コンプライアンスの強化
それぞれについて詳しく説明します。
収入印紙のコスト削減
紙の書類であれば収入印紙の貼り付けが必要な契約であっても、電子契約であれば収入印紙は必要ありません。よって、契約を紙から電子契約に変えるだけで収入印紙分のコストカット効果が期待できるでしょう。
建設業で収入印紙が必要になる契約としては、不動産譲渡契約、建設工事請負契約などが考えられます。
また、建設業に関係なく事業一般に、金銭消費貸借契約や領収書などにも金額によっては収入印紙を貼り付けなければならないので、積み重ねると意外と大きなコストとなります。電子契約に移行することで、大幅なコスト減が期待できるかもしれません。

書類の管理コストの削減
電子契約では、書類の管理コスト削減効果が期待できます。書類は契約が対象とする工事が終了した後も証憑として保存しなければならないこともあるため、多数の建設工事に携わっている建設会社の場合、大量の契約関係書類を保存しなければならないケースも考えられます。
家賃が高い土地にオフィスを構えている場合は、坪数あたりの家賃で契約書をはじめとする保管スペースのコストを算出すると、保管にコストがかかっているケースは少なくありません。
また、特定の契約書を数多くの書類の中から探してくるのには手間がかかりますし、物理的に書類を紛失してしまうリスクも発生します。電子契約システムを使っていれば、日付・担当者・キーワードなどで検索をかけられるので、管理負担が減らせます。
手続き時間の短縮
紙の書類に押印する形で契約手続きを進める場合は、郵送ならば往復で最低2〜3営業日は必要なうえに、どちらかのオフィスに訪問して契約書類を完成させるためにはスケジュールを合わせなければなりません。このような理由から、紙の契約書を締結するのには手続きに時間が必要となります。
一方で電子契約の場合、契約書面さえ完成すれば、すぐに相手と契約を締結でき、時間も場所も制限されません。電子契約システムを導入することにより手続き時間を短縮し、スムーズな契約締結が可能となります。
コンプライアンスの強化
書面による契約の場合、保管されている契約書は従業員や第三者が不正に閲覧するのを完全に防ぐのは難しく、最悪そのまま盗み出される可能性すらあります。また不正閲覧の把握や、盗難があった場合に犯人を探し出すのも簡単ではありません。
しかし電子契約システムでは、契約書ごとに閲覧権限に制限をかけられるため未然に不正閲覧が防げます。くわえて誰が契約書を閲覧したか、アクセスログの取得も可能。万が一改ざんが起こった場合でも、電子署名やタイムスタンプにより犯人を突き止めやすく、被害を最小限に抑えられるでしょう。
電子契約のメリットや概要をさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

電子契約システムが利用可能な建設業関係の契約
電子契約システムは定期借家契約といった一部の例外を除けば、ほとんどすべての建設業で締結しうる契約に適用できます。
代表的な契約としては、業務委託契約を含む次のものが挙げられるでしょう。それぞれの電子契約化について詳しく解説します。
- 請負契約
- 売買契約
- 賃貸借契約
- 保証契約
- 発注書、発注請書
請負契約
冒頭で説明したとおり、2001年の建設業法改正において建設工事の請負契約の電子契約が可能となりました。請負契約には収入印紙も必要なので、電子契約化でコスト削減効果も期待できます。
とくに下請け・元請けなど、複数の工事業者が絡む工事に携わることの多い建設業者は、電子契約システムを導入することによって、請負契約をスピーディーにかつコストを削減して締結できるようになります。
売買契約
建設資材の発注では売買契約を締結する場合がありますが、この売買契約も電子契約化可能です。
建設業に絡む売買としては不動産売買も想定され、この場合は宅建業法35条で規定されている重要事項説明が電子契約で可能なのかがネックとなります。これに関して国土交通省が運用実験を進めているので後述します。
賃貸借契約
賃貸借契約とは、モノの貸し借りにまつわる契約のことです。建設業においては重機の貸し借りの際に用いられることや、広い意味では土地や賃貸物件の契約が関係する可能性もあるでしょう。
基本的には電子契約で締結可能かつ、国土交通省も不動産の賃貸借契約の電子化を推進しようとしています。しかし定期借地契約や定期建物賃貸借契約のように、電子化できない賃貸借契約の類型も存在します。
保証契約
物件や土地の賃貸借、あるいは銀行融資などに際して保証人を設定する場合は保証契約を締結しなければなりません。
保証契約については民法446条に規定されており、第3項では「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」としているので電子契約化可能です。
発注書、発注請書
発注書、発注請書も電子契約化できます。発注書も契約書として課税文書の対象となるので、収入印紙が必要になる場合もあり注意が必要です。なお、発注書だけではなく発注請書も発行する場合は、発注書ではなく発注請書の方に収入印紙を貼らなければなりません。
いずれにしても発注書、発注請書の契約書類については金額に応じて収入印紙を貼らなければならない可能性が考えられます。そのため必要に応じて、電子契約システムを導入してコストカットを図るべきです。
電子契約とグレーゾーン解消制度
基本的には有効だと考えられる電子契約ですが、裁判になったときに有効な契約として認められるのか、どのような要件を満たせば真正性が高いとみなされるのかなど未確定の論点はいくつかあります。
そのため、自社の電子契約システムが建設請負契約において有効なのかを、グレーゾーン解消制度を活用していくつかの会社が確認しています。
グレーゾーン解消制度とは?
グレーゾーン解消制度とは、産業競争力強化法に基づき事業者が現行の規制範囲が不明確な場合、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制適用の有無を官庁に確認できる制度のことを指します。
官庁の見解が裁判になったときにそのまま認められるわけではありませんが、グレーゾーン解消制度を活用して適用の有無に関する官庁の見解がわかれば、ひとまず安心して事業を行えます。
建設業の電子契約のグレーゾーン
建設業において電子契約が認められうるのは、建設業法19条3項のとおりです。また、3項で記載されている基準はさらに詳しく建設業法施行規則第13条の4で示されていますが、具体的にどのシステムがこの基準に適合しているかは明確ではありませんでした。
建設業請負契約に有効な電子契約システム
本記事で紹介するサービスは、以下年度にグレーゾーン解消制度を活用して、建設業法施行規則13条の4に技術的に適合することを確認しています。
国土交通省による電子契約システムの普及推進
電子契約システムに関しては国土交通省も普及を推進しています。国土交通省の電子契約推進の取り組みについては、賃貸契約の完全電子契約化、電子契約システムを活用した公共工事の契約が挙げられるでしょう。それぞれについて説明します。
賃貸契約の完全電子契約化
賃貸借契約や土地・建物の売買契約は、重要事項説明書をはじめとする書面があるので完全電子化は規制により難しいとされてきました。しかし国土交通省が、2020年に賃貸取引における重要事項説明書をはじめとする書面の電子化についての社会実験を実施。2021年からは、売買取引における重要事項説明書をはじめとする書面の電子化に関する社会実験も行っています。
どちらの取り組みもまだ実験段階で、完全電子化できるように法改正をされるめども立っていませんが、国土交通省が重要事項説明書をはじめとする書面の完全電子化に意欲的なことが読み取れます。
電子契約システムを活用した公共工事の契約
公共工事の入札や契約においては、すでに電子契約システムが実用化されています。国土交通省は2018年8月から電子契約システム GECSの試行運用を開始。電子入札システムで公共工事・コンサルタント業務を落札した事業者が、そのまま電子契約で契約から支払いまでの一連の手続きを行えるような仕組みを構築しました。
また政府だけではなく、地方自治体でも相次いで公共調達のために電子契約システムを導入しています。
建設業で活用できる電子契約システム
建設業で活用できる電子契約は数多ありますが、グレーゾーン解消制度により建設業法に適合していると認められた電子契約システムを紹介します。
- 電子署名法に準拠したクラウド型電子契約サービス
- ISMS、SOC2を含めて50以上のセキュリティ項目をチェック
- さまざまな外部システムと連携可能
クラウドサインは弁護士監修のクラウド型電子契約サービスで電子署名法に準拠、グレーゾーン解消制度により建設請負契約にも使用可能なことが示されています。ISMS、SOC2を含めて50以上のセキュリティ基準を設定しており、厳重なセキュリティが期待できるでしょう。またkintone、Slack、Sansan、LINE WORKSなどさまざまな外部サービスとも連携可能。ベンチャー企業から大手企業まで130万社以上※が使用しています。
※クラウドサイン公式サイトより(2022年10月30日閲覧)
DocYou - 日鉄日立システムソリューションズ株式会社
- 建設業界の請負契約をはじめとした各種契約の電子化に対応
- 契約や取引に関連する書類を電子化し一元管理
- 出来高請求といった実績ベースでの電子取引にも
DocYouは、グレーゾーン解消制度に基づいた照会において、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすと回答を得られた電子契約サービスです。
PDFやWord、Excelなどのフォーマットのファイルに対応したうえで、設計図をはじめとした各種データの電子化と一元管理に対応できます。発注元発行の書類に対し、受注先で出来高請求金額を記入後、発注元が同意するといった電子取引も可能です。
WAN-Sign - 株式会社NXワンビシアーカイブズ
- 紙と電子の契約書を一元管理
- 当事者型署名、立会人型署名など、あらゆる署名に対応
- 関係各所へのシステム説明や管理の最適化支援などを無料でサポート
WAN-Signは、グレーゾーン解消制度を活用し、国土交通省より建設業法における適法性が確認された電子契約サービスです。他社の電子契約サービスで署名した電子データも格納できるシステムで、特許を取得しています。
電子契約の締結や契約管理、ユーザー管理などの機能を標準搭載しており、金融機関や官公庁の求めるセキュリティレベルにも対応しています。日本語はもちろん英語にも対応し、通知メールと管理画面を切り替え可能です。
上記で紹介したサービス以外のおすすめ電子契約システムが知りたい方は、次の記事をご覧ください。0円でトライアルができるシステムも多く紹介しています。

建設業も電子契約システム活用で業務効率化を
建設業のように一つの工事でも多くの協力事業者やサプライヤーが関わりうる事業の場合、それに伴う契約書の枚数も膨大になります。契約書の数が増えると収入印紙代や保管のためのコストなども発生しますし、契約に時間がかかったり、書類の紛失リスクがあったりと事業の安定した遂行を妨げる可能性もあるでしょう。
しかし電子契約システムを使用することにより収入印紙代や保管、契約書郵送などのコストを削減しながら、書類紛失リスクを軽減し、契約書の検索作業も速やかに行えるようになります。ルールの整備やマニュアルづくりは必要になりますが、それ以上のメリットが期待できます。
業務効率化、生産性向上に取り組もうとしている建設事業者はぜひ電子契約システムの導入を検討しましょう。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査