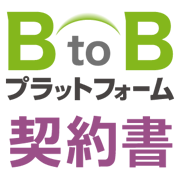電子契約で印紙税が不要になる理由は?収入印紙と課税文書の基礎知識

目次を閉じる
- 印紙税とは
- 収入印紙は印紙税の証票
- 収入印紙が必要な課税文書とは
- 契約書・領収書の金額に応じた印紙税
- 印紙税のかかる契約書作成時の注意点
- 収入印紙がなくても契約自体は有効
- 複数あるすべての契約書に収入印紙が必要
- 収入印紙が必要な場合、不要や免除になる場合
- 契約書の金額記載に注意
- 印紙税が不要になる電子契約とは
- 電子契約の仕組み
- 電子署名とタイムスタンプ
- 電子契約書の有効性が担保されるために
- スピーディーな契約締結と業務効率化を実現
- 電子契約で収入印紙が不要となる理由
- 電子領収書も収入印紙は不要
- 電子契約導入の課題
- 電子契約が扱えないケースがある
- 取引先の理解が必要
- ボクシルおすすめ電子契約システム 【Sponsored】
- 印紙税を不要にできる電子契約サービス比較7選
- ドキュサインの電子署名
- Adobe Acrobat Sign
- クラウドサイン
- 電子印鑑GMOサイン
- freeeサイン
- BtoBプラットフォーム 契約書
- LAWGUE
- 【番外編】電子契約導入代行サービス
- DD-CONNECT
- 電子契約サービスで印紙税を節約し業務を合理化
- BOXILとは
印紙税とは
印紙税とは、経済取引に伴って作成される「課税文書」を対象にした日本の税金です。不動産売買や賃貸契約書、売買契約書、領収書、手形、株券などを扱うときに課税されるので、身近な税金といえるでしょう。
しかし、印紙税の仕組みや金額を正確に把握している方は多くないのではないでしょうか。
印紙税を徴収する仕組みや、対象になる課税文書とは何かを解説していきます。また、従来の契約書に必要とされていた印紙税が不要になる電子契約と、不要になる理由・根拠を紹介します。
収入印紙は印紙税の証票
一部の例外を除き、印紙税の納付は、作成された課税文書に契約金額に応じた額の収入印紙を貼り、消印して届け出ることで行われます。収入印紙の額面には1円から10万円までの31種類があり、郵便局や法務局、一部のコンビニなどで購入できます。適切な印紙代のものを購入し、課税文書に貼付するのが通常です。
つまり収入印紙は、印紙代の形で税金を事前に支払うためのものであり、税金を支払った事実を証明する証票となります。
収入印紙が必要な課税文書とは
印紙税徴収の対象になるのは、印紙税法で定められた課税文書とされています。対象となる課税文書は20項目に分類され、収入印紙貼付の必要・不要を明記しているのが、国税庁の定める「印紙税法 別表第一 課税物件表」です。
課税文書に該当するかどうかの最終的な判断は、文書に記載された内容によります。不動産関連や消費貸借に関する契約書、一般的なビジネスシーンで作成される契約書、売上代金の領収書は、ほとんど印紙税の対象になるといっていいでしょう。
ただし、取引額が一定金額に満たない場合は、印紙税の対象文書でも非課税となり、収入印紙が貼付不要となるケースもあります。
契約書・領収書の金額に応じた印紙税
私たちに一番身近な印紙税は、企業の経済取引に伴う売買契約、不動産契約、消費貸借、運送などが該当する「印紙税法別表第1号」および、売上代金の領収書や有価証券の受取書などが該当する「印紙税法別表第17号」でしょう。
下表は、印紙税の金額を表にしたものです。
印紙税額第1号
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書
| 課税文書に記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上〜10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え〜50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え〜100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え〜1千万円以下 | 10,000円 |
| 1千万円を超え〜5千万円以下 | 20,000円 |
| 5千万円を超え〜1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円を超え〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え〜10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円を超え〜50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
出典:国税庁「 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(2023年10月5日閲覧)
印紙税額第17号
[売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]
| 課税文書に記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え〜300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え〜1千万円以下 | 2,000円 |
| 1千万円を超え〜2千万円以下 | 4,000円 |
| 2千万円を超え〜3千万円以下 | 6,000円 |
| 3千万円を超え〜5千万円以下 | 10,000円 |
| 5千万円を超え〜1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え〜2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え〜3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え〜10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
出典:国税庁「 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(2023年10月5日閲覧)
領収書の収入印紙に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

印紙税のかかる契約書作成時の注意点
ほとんどの企業では、取引先との売買契約を締結する際、文書としての契約書を作成しています。しかし、実際には契約書として書面に残さない口約束のみであっても、契約自体は成立したと認められます。
口約束でも契約は成立するのに、なぜわざわざ契約書を作成する必要があるのでしょうか。理由はさまざまですが、契約書が残っていれば不要なトラブルを回避できるからです。
正式な文書として金額や売買条件を明文化したうえで、契約を締結しておけば、「言った・言わない」や認識の相違で揉めることも少なくなるでしょう。契約書はいつでも確認できるので、契約内容の根拠となるのです。
用紙によるほとんどの契約書は金額が記載された課税文書となり、印紙税が必要になります。では、収入印紙を貼る場合に気を付けるべき注意点はあるのでしょうか。
収入印紙がなくても契約自体は有効
口約束でも契約は有効だと認められることからもわかるように、収入印紙を貼っていなくても、契約書に記載された契約内容自体は有効です。
しかし、印紙税の課税対象となる契約書に収入印紙が貼られていないことは、「脱税」を意味します。この場合、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する「過怠税」が徴収されます。
そのため、契約の有効性だけではなく、収入印紙を貼り、印紙税を払った記録をきちんと残すことが、企業の社会的信用維持のために大切です。
複数あるすべての契約書に収入印紙が必要
2社間で締結される契約では、双方が契約書の原本や副本を保管するため、複数の契約書が作成されます。契約書が複数ある場合、作成されたすべての契約書に収入印紙を貼付しなければいけません。また、契約延長の際に覚書を契約書に交える場合にも、収入印紙の貼付が必要になります。
契約で複数の契約書が必要になる場合、管理が大変ですが、収入印紙が貼られているかどうかは企業の信用に関わる重要なポイントです。漏れがないよう、しっかり確認するようにしましょう。
収入印紙が必要な場合、不要や免除になる場合
また、発注書に対して発行される請書は、契約書にあたるか迷う方もいるかもしれません。しかし発注書と請書は2通セットで1つの契約書を形成する課税文書と見なされるので、注意しましょう。
一方で、注文書の場合基本的に印紙税は必要ありませんが、「注文書の交付によって契約が成立する同意をしている」「見積書に対して承諾の意志表示をする」場合は、収入印紙が必要になることがあります。
収入印紙が必要かどうかは、契約状況によって異なる場合も多いので、よく確認することをおすすめします。
契約書の金額記載に注意
収入印紙の金額は、契約書に記載されている金額に応じて決定されます。金額の記載方法に気を付けないと、高額な収入印紙代が必要になってしまうかもしれません。
たとえば、500万円の契約の場合、「うち10%が消費税」と書くと、記載されている「500万円」が課税対象となり、1万円の収入印紙が必要となります。
一方で、「うち消費税37万円」と記載すると、課税対象は「500万円 − 37万円 = 463万円」と判断されます。500万円未満の契約書に貼付する収入印紙は2,000円です。契約書の書き方が少し違うだけで、印紙代が8,000円も異なってきます。
契約書の印紙税についてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。必要以上に印紙税を払うことのないよう、よく注意して確認しておきましょう。

印紙税が不要になる電子契約とは
従来の商取引では当たり前であった紙の文書による契約書に対し、近年ではPDFの電子文書で締結する「電子契約」のシェアが拡大しています。
電子契約であれば、印紙税や保管スペースが不要になり、契約書の郵送費や印刷代もかかりません。テレワーク推進の流れもあり、導入する企業はどんどん増えてきています。
電子契約は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が普及を進めていることもあり、すでに国内の多くの企業が採用しています。
2023年5月に発行された「JIPDEC IT-Report 2023 Spring」の調査結果によれば、電子契約の国内企業普及率は73.9%になっており、将来的に電子契約サービスの導入を考えている企業を合わせると、87.1%に達することがわかりました。
出典:JIPDEC「IT-Report 2023 Spring」(2023年12月4日閲覧)
電子契約の仕組み
電子契約では、作成した契約書をPDF化する際に「電子署名」と「タイムスタンプ」を生成し、埋め込みます。電子契約書の送付・確認後、相手方も電子署名とタイムスタンプを埋め込み、返送することで契約が完了する仕組みです。
電子文書のやり取りはメール添付で行われる場合が多いものの、プロセス全体をクラウドで管理するサービスも登場しています。クラウド型の電子契約サービスは、強固なセキュリティと管理のしやすさで注目を集めています。
電子署名とタイムスタンプ
電子契約書を交わすのに欠かせないのが「電子署名」と「タイムスタンプ」です。
電子署名は、電子署名法によって従来の押印・署名と同等の効力を持つとされています。事前に認証機関へ届け出て自身の「秘密鍵」を取得することで、実行可能となります。この秘密鍵と「電子署名生成プログラム」を利用することで電子署名が生成され、契約書のPDF文書に埋め込めるようになるのです。
さらに、電子署名と同時に「タイムスタンプ」も埋め込むことで「だれが」「いつ」認証したのかが明確になり、契約書の信頼性が担保されます。
電子契約書の有効性が担保されるために
現在では、上述した電子署名法のほかにも、電子署名に関するさまざまな法律があります。
- 帳簿を電子データで保管することを認めた「電子帳簿保存法」
- 契約締結書面を電子メールやFAXで行うことを容認した「IT書面一括法」
- 商法・税法で義務付けられていた文書を電子保存できるようにした「e-文書法」
法整備が進められたことにより、要件にあわせた手順を踏んでさえいれば、電子契約の法的な根拠が担保されるようになりました。電子契約を利用する場合は、ひととおり上記の法律に目を通しておくとよいでしょう。
スピーディーな契約締結と業務効率化を実現
用紙ベースの従来の契約書では、契約内容・条件が決定した後の書類のやり取りは郵送で行われることが多く、押印の手間も含め、最終的な契約締結までに時間と手間がかかっていました。
また、物理的に保管しなければならない紙の契約書は作成や管理の手間が大きく、人的リソースといった見えにくいコストも無視できませんでした。
電子契約では、契約書を電子化できるため、契約交渉以外の事務的要素を簡略化でき、結果的に契約締結のスピードアップが期待できます。郵送代や保管スペースの削減にもつながる電子契約は、契約に関するさまざまな要素を合理化でき、大幅な業務効率化をもたらすでしょう。

電子契約で収入印紙が不要となる理由
電子契約書は印紙税の対象となる課税文書ではないため、収入印紙を貼る必要がありません。この根拠として、国税庁のホームページによると、印紙税法の対象となるのは「紙の課税文書」であり、電子文書である電子契約書は対象にならないことが挙げられています。
従来の紙の契約書と電子契約書の主な違いや、電子契約と印紙税の関係性は、次のとおりです。
| 従来の契約書 | 電子契約書 | |
|---|---|---|
| 媒体 | 印刷された紙 | PDFの電子データ |
| 署名 | 署名、押印 | 電子署名・タイムスタンプ |
| 収入印紙 | 必要 | 不要 |
| 受け渡し | 原本の郵送、持参 | インターネットを介した電子データ受け渡し |
| 保管方法 | 倉庫、書庫などで物理的に原本を保管 | 自社サーバー、外部データセンターでの保管・管理 |
なお、電子契約書をコピーしたりプリントアウトしたりしても「課税文書の作成」には該当せず、印紙税はかかりません。
電子領収書も収入印紙は不要
前述の印紙税額第17号に含まれる領収書ですが、電子取引で発行された電子領収書も「紙の課税文書」ではないため、印紙税はかからず、収入印紙の貼付は不要です。
電子契約導入の課題
一方、いいことばかりのように思える電子契約にも、課題がまったくないとはいえません。
電子契約が扱えないケースがある
投資信託契約の約款、定期借地契約、労働条件通知書の交付など、法的に書面での締結が義務付けられている契約が存在しており、こうしたケースでは電子契約を利用できません。
現在では、基本契約や秘密保持契約をはじめ、ほとんどの契約で電子契約が認められているものの、電子的に置き換えたい契約の種類によっては、導入の際に注意が必要です。
取引先の理解が必要
社内で運用する契約関連はともかく、売買契約の相手となる取引先に電子契約の強制はできません。
電子契約を提供するサービスによっては、サービス利用者同士のみが契約できるものもあるため、電子契約を強制することは相手方へのサービス加入を強制することにつながります。電子契約のメリットを取引先と共有し、活用を理解してもらう努力が必要でしょう。
ボクシルおすすめ電子契約システム 【Sponsored】
| 電子印鑑GMOサイン |
|---|
 ・導入企業数No.1※1 ・契約社数No.1※2 ・安全な電子契約、仕事が楽になる、法務選ぶNo.1※3 |
 |
※1 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※2 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※3 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」日本マーケティングリサーチ機構の2020年2月期の調査(2023年6月1日閲覧)
印紙税を不要にできる電子契約サービス比較7選
印紙税を不要にしてコスト削減と業務効率化を実現する、電子契約サービスのおすすめを厳選して比較紹介します。
ドキュサインの電子署名 - ドキュサイン・ジャパン株式会社
- 契約や合意にかかわる時間やコストを削減
- 世界標準の厳しいセキュリティをクリア
- 数百ものエンタープライズソリューションと連携可能
ドキュサインの電子署名は、世界180か国以上・100万社以上※で利用されている電子署名サービスです。申請や署名捺印を電子化し、契約や合意にかかる時間やコストを削減。世界基準の厳しいセキュリティ基準を満たし、44言語の電子署名を利用可能。
30日間無料トライアルで、法人向けサービスも利用できるため、実際の使用感を試してから導入が行えます。また、Microsoft 365、Google Workspace、Salesforceといった、数百ものエンタープライズ・アプリケーションと接続できる柔軟なプラットフォームを用意しています。
※出典:ドキュサイン「ドキュサイン | 世界No.1の電子署名とクラウド型合意・契約管理システム」(2023年12月4日閲覧)
Adobe Acrobat Sign - アドビ株式会社
- Microsoft推奨の電⼦サインソリューション
- 契約締結までの時間とコストを大幅削減
- さまざまなソリューションと連携可能
Adobe Acrobat Signは、世界中の企業に幅広く利用されている電子契約システムです。契約書PDFの送信や署名の取得、トラック、ファイリングをデジタル化。パソコンやモバイルデバイスがあれば、いつでもどこにいても契約や承認作業が完了できます。
Adobe Acrobat Signの電子サインは、電子署名法における「本人性の確認」と「非改ざん性の確保」の法的要件を満たしています。本人認証についてはメールアドレスの認証に加え、ワンタイムパスコードによる2段階認証にも対応しているので安心して利用可能です。また、Microsoft 365やSalesforce、kintoneをはじめとする、さまざまなシステムとの連携機能を標準搭載しています。
- 導入社数250万社以上※
- 契約締結をスピードアップ
- 契約書を含めた文書をクラウドで一元管理
クラウドサインは、紙で進めてきた契約作業を、わずか数分間で完結させるクラウドベースの電子契約サービスです。締結頻度の高いNDA(秘密保持契約書)のような契約書や、毎月発生する取引先との受発注書のやりとりの手続きを簡略化し、相手側がサービスに加入しなくとも契約締結が可能です。雇用契約書や身元保証書といった入社書類も社内文書として電子化でき、管理を容易なものにします。
また、月間3件までの送信は無料で利用できるフリープランも用意。契約書の郵送にかかっていた事務手続きやコストの低減が期待できます。
※出典:弁護士ドットコム「クラウドサイン | 国内シェアNo.1の電子契約サービス」(2023年12月4日閲覧)
クラウドサインの導入事例
クラウドサインの導入事例をまとめました。気になる会社の導入事例を無料でダウンロードしていただけます。
| パーソルキャリア株式会社 | 株式会社メルカリ | ラクスル株式会社 |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 契約締結のリードタイムを圧縮することで 機会損失を防いでいます。 | 紙だとできない「一括処理」がクラウド化により実現。 70 倍速の効率化です! | クラウドサインで 「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」 |
電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
- 300万社以上※1の導入実績
- 電子署名と電子サインを併用した契約締結
- 電子帳簿保存法に標準対応
電子印鑑GMOサインは、300万社以上の導入実績を誇る電子署名と電子サインを併用した契約締結ができる電子契約システムです。累計1,500万件以上※2の送信数を誇り、政府機関や大手企業でも利用されている認証局のGlobalSignと直接連携しています。
電子署名と電子サインを併用した契約締結もできるので、自社は電子署名で法適合性や署名権限を限定しつつ、相手方は電子サインで簡単に利用可能。税法上で要求される検索機能を標準で実装しており、締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま保存できます。月間5件まで無料で送信できるお試しフリープランも提供しています。
※1,2 出典:GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子契約なら電子印鑑GMOサイン|導入企業数No.1の電子契約サービス」(2023年12月4日閲覧)
- アカウント課金型、定額で使いやすい
- 法務のやり取りもワークフロー機能で可視化
- タイムスタンプで安心のセキュリティ体制
freeeサインは、契約書の作成からレビュー、締結、管理までクラウド上で行える弁護士監修の電子契約サービスです。締結した契約書はクラウド上に保管。レビューを含め、複雑な法務とのやり取りも可視化し一元管理できます。申込書をはじめ相手方の記入が必要な書面にも対応、タイムスタンプ機能で改ざんも防げます。
料金は月額固定で、契約締結数や送信数に制限はありません。また導入後も、ヘルプデスクやユーザーコミュニティといったサポートを受けられます。
BtoBプラットフォーム 契約書 - 株式会社インフォマート
- ブロックチェーン技術による契約の信頼性担保
- 90万社以上※の利用企業数による対応工数削減
- 業界唯一 見積〜請求までのすべての商取引が電子化可能
BtoBプラットフォーム契約書は、電帳法改正対応の電子契約システムです。契約書の締結業務を電子化し、時短・業務軽減と郵送代・印紙税のコスト削減を実現します。最新のブロックチェーン技術を採用し、契約内容の信用性・機密性を確保可能です。
また、90万社以上の利用企業数があるため、取引先がBtoBプラットフォーム契約書を利用している可能性が高く対応工数の削減が期待できます。
※出典:インフォマート「電帳法改正対応の電子契約システムで契約書を電子化|BtoBプラットフォーム契約書」(2023年12月4日閲覧)
- 法務文書の作成を効率化するエディター
- LAWGUE上で直接コメントや編集が可能
- クラウドサインとの連携で契約締結までを完結
LAWGUEは、法務・コンプライアンス分野の文書作成やレビューをスムーズに進められるクラウドサービスです。編集作業やコメントはLAWGUE上にて可能。Wordやメールでのやりとりによる工数を削減します。クラウドサインとの連携により、契約書の作成から契約締結まで、1つのツールで完結できます。
【番外編】電子契約導入代行サービス
- 電子帳簿保存法や電子署名法の法改正対応をアドバイス
- 丁寧なヒアリングですぐに運用できる環境を設定
- 専任のコンサルタントが導入・運用をサポート
DD-CONNECTは、電子契約サービスの導入から運用までをサポートする電子契約導入代行サービスです。導入後の運用について説明し、電子契約サービス導入時の不安を解消します。
準備や設定など運営維持のために必要な煩わしい業務を代行してくれるため、自社に合った環境で電子契約サービスの運用を開始可能。契約業務をすべてクラウド上で行うため、契約業務をペーパーレス化し、コスト削減も実現します。
電子契約サービスで印紙税を節約し業務を合理化
紙の契約書を利用していた従来の契約締結は、取引金額が高額になるほど高額な印紙税の支払いが必要になります。郵送にかかるコストや契約書作成に必要な人的リソースも無視できないものでした。
印紙税や輸送費、保管スペースの削減により、コストを大幅に削減できます。電子契約は、人的・金銭的コストを削減し、契約締結までを迅速に行える画期的なシステムといえるでしょう。
大幅なコスト削減と業務効率化を実現し、商取引開始までのリードタイムも最小化する電子契約は、変化の激しい現在の市場経済にマッチした仕組みともいえます。ビジネスの形態によっては電子契約の導入が難しい場合もありますが、契約書の電子化メリットは、非常に大きいので導入を検討してみることをおすすめします。

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
電子契約に関してはこちらの記事で比較して紹介しているので、あわせて参考にしてください。

BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査