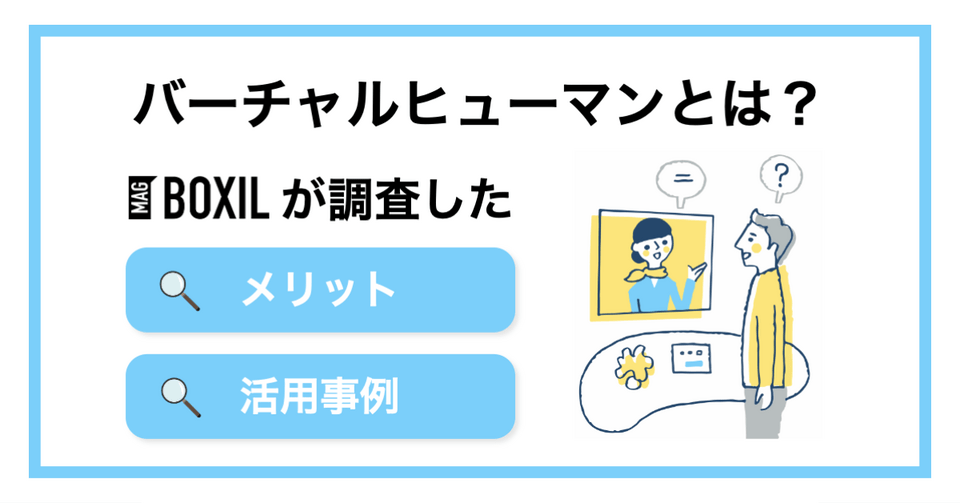※バーチャルヒューマンをビジネス活用する際の注意点のみ監修
バーチャルヒューマンとは
バーチャルヒューマンとは、コンピューターグラフィックス(CG)をはじめとする技術を用いて作成された、人間のような外見をもつデジタル上のキャラクターのことです。バーチャルヒューマンに映像データを学習させることで自然な表情を作り出したり、音声認識や音声生成などのAI技術と組み合わせることで多言語を話したり、人間と遜色ないコミュニケーションをデジタル空間で実現します。
バーチャルヒューマンは、すでにさまざまな分野で活用されています。
- 広告塔やインフルエンサーとしてSNSでプロモーションを行う
- 店舗やイベントで受付・案内業務を行う
- 教育分野で教師やインストラクターの代わりを務める
- 医療分野で患者のカウンセリングを行う
近年、人手不足の深刻化や働き方改革の推進、そして社会情勢の変化に伴い、企業は業務効率化や非接触型サービスの提供を迫られるようになりました。このような状況下で、24時間365日稼働可能で多様な業務に対応できるバーチャルヒューマンの必要性はますます高まっており、今後さらなる普及が期待されています。
バーチャルヒューマンと似た言葉との違い
バーチャルヒューマンと似た言葉として、AIアバターやVTuberなどが挙げられます。これらの言葉は混同されがちですが、それぞれ異なる特徴を持っています。
AIアバターとの違い
バーチャルヒューマンとAIアバターの違いは、モデルが実在するかどうかという点です。
AIアバターとは、人工知能(AI)によって生成されるバーチャルキャラクターのことで、多くの場合は実在する人物の写真やデータをもとに作成されます。一方で、バーチャルヒューマンは完全に架空の人物として創造されるケースが多いです。また、バーチャルヒューマンはAIによって自律的に会話したり、自然な動きを表現したりできる点も異なります。
AIアバターは、既存の人物をデジタル空間で表現する手段として用いられることが多いです。たとえば、広報担当者がAIアバターとしてオンラインイベントに参加したり、著名人のAIアバターがファンとの交流イベントを行ったりするケースがあります。
一方、バーチャルヒューマンは、特定の人物に依存しない独立したキャラクターとして活動することが多いです。広告キャンペーンのキャラクターや、企業のブランドイメージを代表する存在として活用されることがあります。
VTuberとの違い
バーチャルヒューマンとVTuberの違いは、アバターを人間が操作しているかどうかという点や活躍する分野です。
VTuber(バーチャルYouTuber)は、アニメ調の2Dキャラクターや3Dモデルなどの形態のアバターを使い、YouTubeをはじめとする動画配信プラットフォームでライブ配信や動画投稿を行う配信者のことです。バーチャルヒューマンと異なり、実在する人間の動きをモーションキャプチャーで捉えて投影しています。
また、VTuberはエンターテイメント分野で広く活躍しているという点でも異なります。ゲーム実況や歌ってみた動画、雑談配信など、その活動内容はさまざまです。一方で、バーチャルヒューマンはビジネス分野での活用が注目されています。企業の受付やカスタマーサポート、教育分野でのインストラクターなど、人間が行う業務の一部を代替する役割を担うことが期待されています。
バーチャルヒューマンをビジネス活用する4つのメリット
バーチャルヒューマンをビジネスに活用することには、さまざまなメリットがあります。うまく活用すれば人材採用や教育、マーケティングなど、多岐にわたる分野でメリットを享受できるでしょう。
- 目的に合わせた理想の人材を作れる
- 人間の従業員よりも低コスト
- 欠勤や退職、トラブルのリスクがない
- 注目を集めやすい
メリット1. 目的に合わせた理想の人材を作れる
ブランドイメージに合わせた容姿や声をもつバーチャルヒューマンを作成したり、特定の業務に特化した知識やスキルをAIに学習させたりできる点は大きなメリットです。
バーチャルヒューマンは、外見や声だけでなく、性格や能力なども自由に設定できます。これは、CG技術とAI技術の進歩によって可能になりました。
これにより、従来の採用活動では困難だった理想の人材を、デジタル空間で具現化できます。多言語対応可能なグローバル人材や、専門知識をもつエキスパート人材をバーチャルヒューマンとして作成することで、人材不足の解消や業務効率の向上につなげられるでしょう。
メリット2. 人間の従業員よりも低コスト
バーチャルヒューマンは、人間の従業員を雇用する場合に発生する次のようなコストを削減可能です。
- 人件費
- 福利厚生費
- 教育や研修にかかるコスト
結果として、長期的なコスト削減が可能です。とくに、カスタマーサポートや受付業務などの定型的な業務をバーチャルヒューマンに代替させることで、人件費の削減効果は大きくなります。また、複数の言語に対応できるバーチャルヒューマンを導入することで、翻訳や通訳にかかるコストも削減できます。
メリット3. 欠勤や退職、トラブルのリスクがない
バーチャルヒューマンは、システム障害のような技術的な問題を除けば、人間の従業員を雇う際のリスクを回避できることもメリットです。たとえば、生身の人間でありがちな次のような課題を解決できます。
- 病気や個人的な事情による欠勤
- キャリアアップや家庭の事情などを理由とした退職
- 人間関係のトラブルや不正
- 人的ミスによる情報漏えい
リスクを回避することで、安定した業務運営を実現できるでしょう。バーチャルヒューマンは常に一定の品質で業務を遂行するため、サービス品質の維持にも役立ちます。
メリット4. 注目を集めやすい
バーチャルヒューマンを広告やプロモーションに起用する事例は、まだそれほど多くありません。そのため、バーチャルヒューマンを活用するだけで話題性を生み出し、注目を集められるかもしれません。
企業は従来の広告手法とは異なるアプローチで、ターゲット層にアプローチできます。たとえば、SNSでバーチャルインフルエンサーとして活動させたり、イベントでバーチャルアンバサダーとして登場させたりすることで、大きな反響を得られるでしょう。デジタル技術への関心が高いZ世代以降の世代に対しては、とくに効果的です。
また、バーチャルヒューマンは年齢や性別、人種などに制約がないため多様なターゲット層に訴求できます。
バーチャルヒューマンをビジネス活用する際の注意点
バーチャルヒューマンは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっていくつかの注意点も存在します。これらの注意点を十分に理解し、適切な対策を講じることで、バーチャルヒューマンのビジネス活用を成功に導いていけるでしょう。
- 開発・維持にコストがかかる
- 著作権侵害のリスクがある
- システム障害や不正アクセスのリスクがある
注意点1. 開発・維持にコストがかかる
バーチャルヒューマンの開発には、高度なCG技術やAI技術が必要となるため、相応のコストがかかる点には注意しましょう。また、開発後もシステムの保守やアップデート、コンテンツの追加などに維持コストがかかります。
これらのコストを十分に考慮せずに導入を進めてしまうと、予算超過や費用対効果の低下を招きかねません。事前に十分な予算計画を立て、長期的な視点でコストを評価しましょう。予算感がわからない場合は、バーチャルヒューマンの提供会社にあらかじめ何にコストがかかるのかを問い合わせてください。
注意点2. 著作権・肖像権・パブリシティ権侵害のリスクがある
バーチャルヒューマンのデザインや使用する素材によっては、著作権侵害のリスクがあります。たとえば、既存のキャラクターや人物に酷似したデザインを採用した場合、著作権、肖像権侵害に該当するおそ恐れがあります。また、使用する音楽や画像などの素材についても、著作権の確認が必要です。この他、著名人の容貌や声を顧客誘引力を利用することを目的として利用する場合、必要な許諾を得ていないときはパブリシティ権侵害に該当するおそれがあります。
著作権・肖像権・パブリシティ権侵害を起こしてしまうと、法的なトラブルに巻き込まれるだけでなく、企業のイメージダウンにもつながります。バーチャルヒューマンのデザインや使用素材については、学習に使うものも含めて、著作権・肖像権・パブリシティ権侵害がないか十分に確認しなければなりません。必要に応じて専門家の意見を求めることも重要です。
類似のデザインや実在の人物がないかや実在の人物を想起させるものでないかを必ず確認するようにしましょう。
注意点3. バーチャルヒューマンが誤った情報を提供するリスクがある
バーチャルヒューマンは、生成AIを用いて回答を行うものであるため、生成AIのリスクの一つである誤った情報を提供するリスクがあります。場合によっては、提供された誤った情報に対する責任を負う可能性があります。たとえば、商品の販売にバーチャルヒューマンによる接客を用いたところ誤った割引情報が消費者に提供され、消費者がその割引情報を信じて商品を購入した場合、商品を販売する企業は消費者に対しそのような割引を提供することが法的に求められる可能性があります。
このようなリスクは、法的な責任だけでなく、顧客からの信頼や企業イメージの低下につながりかねません。技術的に誤った情報が提供されないようにすることには一定の限界もあるため、バーチャルヒューマンの回答に際し消費者に対して商品や割引情報に関するウェブサイトの正しい情報を確認することを促すなど、誤った情報が提供される可能性を考慮した上でUI全体を検討することも重要です。
注意点4. システム障害や不正アクセスのリスクがある
バーチャルヒューマンはコンピューターシステム上で動作するため、システム障害や不正アクセスのリスクがあります。たとえば、サーバーのダウンやネットワークの障害によって、バーチャルヒューマンの動作が停止してしまうかもしれません。また、可能性は低いですがシステム提供会社への不正アクセスによって、バーチャルヒューマンのデータが改ざんされたり、ユーザーと対話して収集した個人情報が漏えいしたりするリスクもあります。
これらのリスクを放置しておくと、業務停止や顧客への不利益、企業イメージの低下などを招きかねません。また、個人情報の漏えいは、場合によっては個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要となります。システム安定稼働のための対策や、セキュリティ対策をしっかりと行いましょう。具体的には、サーバーの冗長化やバックアップ体制の構築、ファイアウォールの設置、不正アクセス検知システムの導入などが必要です。

AIに関しては、各国で規制の整備が進んでいます。
EUのAI法(AI Act)は、リスクベースアプローチに基づき、重大なリスクに対しては厳格な規制を設け、違反に対しても高額な制裁金を設けています(但し、施行は段階的であり、完全施行は2027年8月を予定)。EU AI法は、EU域内に拠点を有しない事業者に対しても、事業者がEU域内でAIシステムを市場に投入する場合など、一定の場合には適用があるため注意が必要です。
日本でも、AI推進法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が成立しました。日本のAI推進法は事業者に対してAIの提供を直接制限するものではありませんが、今後もAIに関し様々な法改正が議論されることが予想されるため、今後も最新の動向に注視する必要があります。
バーチャルヒューマンの6つの活用例
バーチャルヒューマンは、その特性を活かしてさまざまな分野で活用が拡大している最中です。顧客対応から教育、エンターテイメントまで、幅広い分野で活躍が期待されています。バーチャルヒューマンの活用事例を紹介します。
活用例1. 接客
バーチャルヒューマンは、店舗やイベントなどで受付や案内業務へ展開可能です。たとえば、商業施設のインフォメーションカウンターにバーチャルヒューマン(画面)を配置し、顧客からの問い合わせに対応したり、館内案内を行ったりできます。
それにより待ち時間の短縮や人件費の削減などが可能です。また、多言語対応のバーチャルヒューマンを配置することで、外国人観光客への対応も容易になります。
活用例2. カスタマーサポート
バーチャルヒューマンは、チャットボットのように顧客からの問い合わせに対応できます。たとえば、製品の使い方やトラブルシューティングに関する質問に、24時間体制で対応可能です。
顧客はいつでも必要なサポートを受けられるようになり、顧客満足度の向上につながります。また、人間の従業員が行っていた定型的な問い合わせ対応をバーチャルヒューマンに代替することで、業務効率の改善にも貢献するでしょう。
活用例3. 教育
オンライン教育や研修などで、バーチャルヒューマンに教師やインストラクターの代わりを務めさせられます。たとえば、歴史の授業で過去の偉人に扮したバーチャルヒューマンが講義を行ったり、語学学習でネイティブスピーカーのバーチャルヒューマンと会話練習を行ったりといった活用方法です。
このような方法を取れば、人件費をかけずにインタラクティブな学習体験を提供できるでしょう。また、時間や場所に制約されないオンライン教育の利点を最大限に活かせます。
活用例4. バーチャル試着
バーチャルヒューマンは、ECサイトで洋服やアクセサリーなどのバーチャル試着を可能にします。たとえば、自分の体型に近いバーチャルヒューマンにさまざまな服を着せて、サイズ感やコーディネートを確認できます。
オンラインショッピングにおける試着の課題を解決し、購入後の返品率を軽減できるでしょう。また、店舗に在庫がない商品でもバーチャルで試着できるため、顧客の購買意欲を高める効果も期待できます。
活用例5. バーチャルインフルエンサー
SNSや動画サイトなどで、バーチャルヒューマンがインフルエンサーとして活動し、商品やサービスをPRしている事例もあります。たとえば、ファッションブランドのバーチャルモデルが新作の洋服を着てSNSに投稿したり、ライブ配信を行ったりといったケースです。
企業は従来のインフルエンサーマーケティングとは異なるアプローチで、ターゲット層にアプローチできます。また、私生活がないバーチャルヒューマンは、リアルな著名人と比べ、炎上やスキャンダルのリスクが低いです。
活用例6. バーチャルアナウンサー
ニュース番組や情報番組などで、バーチャルヒューマンがアナウンサーとして情報を伝えられます。バーチャルヒューマンは人間と異なり、拘束時間を気にする必要がなく移動もありません。そのため、天気予報やニュース速報などをリアルタイムで伝えられます。
バーチャルヒューマンを活用することで、24時間体制での情報提供が可能になります。また、災害時をはじめ、緊急性の高い情報を迅速に伝える手段としても有効です。
少しずつ身近になるバーチャルヒューマン
バーチャルヒューマンはまだ比較的新しい技術といえますが、すでに多くの先進的な企業がその可能性に着目し、積極的に活用を始めています。顧客対応や広報活動、教育分野など、さまざまな分野でバーチャルヒューマンの導入が進んでおり、その活躍の場は着実に広がっています。
今後バーチャルヒューマンは私たちの生活の中で、少しずつ身近な存在になっていくでしょう。技術の進歩に伴い、より自然で人間らしい表現が可能になり、活用シーンもさらに多様化していきます。
バーチャルヒューマンへの注目が高まっている今こそ、その活用を検討する絶好の機会といえます。今のうちからバーチャルヒューマンを活用することで、競合他社に先駆けて自社のブランドイメージ向上や、革新的な企業としての注目を集められるでしょう。