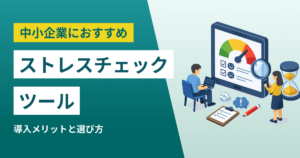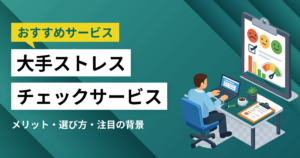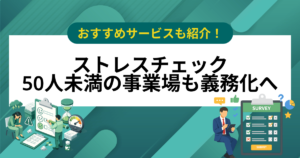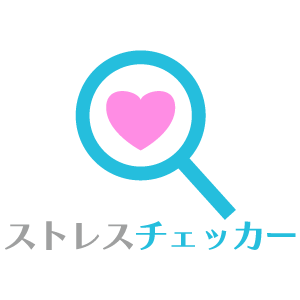ストレスチェックの実施を支援する助成金(小規模事業場産業医活動助成金のストレスチェック関連助成)は令和5年度末で廃止され、現在は新規受付を行っていません。この記事ではなぜストレスチェック助成金が廃止されたのか、また代わりに導入された助成金制度の内容や、助成金を受け取るには何をしたらよいかなどについて紹介します。
ストレスチェック助成金の目的
ストレスチェック助成金とは、小規模な事業場でストレスチェックの実施を促進するために、実施にかかる費用の一部を助成し、負担を軽減するための制度です。従業員数が50人未満の事業場(企業)が対象で、ストレスチェックや医師による面接指導を実施すると次の金額が支給されました。
|
助成対象
助成額 (上限)
|—|—|
|ストレスチェックの実施|500円/従業員|
|ストレスチェックにかかる医師による活動|21,500円/1活動・1事業所(上限3回)|
そもそもストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する目的でつくられた制度です。定期的に労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスに対する気づきをうながすとともに、経営者が働きやすい職場づくりや環境改善に活用します。
強いストレスを原因とした精神性障害を発病し、労災認定される労働者が増加したことで、従業員数が50人以上の事業場での、ストレスチェック実施が平成27年に義務づけられました。また従業員数が50人未満の事業所においては、現在ストレスチェックの実施は努力義務とされ、必ず行う必要はありません。
ストレスチェックの義務化についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしましょう。
ストレスチェックにおける助成金の意義
しかし令和6年9月に、厚生労働省は今後すべての企業でのストレスチェック実施を義務づける方針を明らかにしました。開始の時期はまだ発表されていないものの、今後は従業員が50人未満の企業でも必ずストレスチェックを実施しなければならないでしょう。また企業として成長するためには、従業員の心身の健康を維持することは非常に重要なことです。
しかしストレスチェックの実施や制度の導入、産業医との契約にはある程度費用が必要であり、中小企業や零細企業は予算が足りず、実施したくてもできないケースは少なくありません。助成金制度はこういった企業に対し、ストレスチェック制度の導入にかかる費用を補助し、実施をうながす目的があります。
令和4年11月にストレスチェック助成金の廃止が決定した理由
一方で令和4年(2022年)11月、助成金の運営を行っている独立行政法人労働者健康安全機構から、ストレスチェック助成金を含む産業保健関連の助成金を廃止すると発表され、翌年令和5年より新規受付が廃止されました。廃止の理由としては、近年のメンタルヘルス関連の問題によって産業保健関連への注目度が高まり、申請数が急増したことを挙げてます。
ストレスチェック助成金でも紹介しているように、助成金の対象になるのは従業員数が50人未満の事業場(企業)です。しかし事業場単位で受付を行っていたために、申請数が急増したことで迅速な審査が難しくなり、不正受給問題も相まって廃止が決定されました。
廃止された産業保健関連助成金一覧
産業保健関連助成金では、ストレスチェック助成金を含め次の助成金制度が廃止されました。
- 小規模事業場産業医活動助成金
- ストレスチェック助成金
- 職場環境改善計画助成金
- 心の健康づくり計画助成金
- 治療と仕事の両立支援助成金
- 副業・兼業労働者の健康診断助成金
- 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
新たに導入された「団体経由産業保健活動推進助成金」
独立行政法人労働者健康安全機構では、令和5年から廃止した制度に代わる新たな制度として「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始しています。制度の概要やストレスチェック助成金との違いについて紹介します。
団体経由産業保健活動推進助成金の概要
団体経由産業保健活動推進助成金は、企業の健康管理活動を支援する目的でつくられた助成金制度です。事業主団体や労災保険の特別加入団体を対象に、産業医・保健師・産業保健サービスの提供事業者と契約し、労働者に対して産業保健サービスを提供すると、活動費用の90%を助成してくれます。
産業保健関連助成金(ストレスチェック助成金)との違い
産業保健関連助成金との違いとしては、支給の対象者や助成金の支給方法が挙げられます。産業保健関連助成金の対象者は「従業員50人未満の事業所」でしたが、団体経由産業保健活動推進助成金の対象者は「事業主団体等や労災保険の特別加入団体」です。
これはたとえば商工会議所や企業組合といった団体のことであり、一社ごとの申請はできなくなりました。代わりに企業は団体から提供される産業保健サービスを受ける形で、助成金の恩恵を受けられる仕組みです。
またストレスチェック助成金では、ストレスチェックの実施1人あたりや活動あたりで助成の上限額が定められ、人数・回数に応じて金額が支給されていました。しかし団体経由産業保健活動推進助成金では、年に1回活動にかかる費用の90%が支給されるように変化しています。
団体経由産業保健活動推進助成金の対象団体
前述したように、団体経由産業保健活動推進助成金の対象団体は次の2つです。
- 事業主団体等
- 労災保険の特別加入団体
しかしこれだけでは、どういった団体なのかがわかりにくいため、もう少し具体的に説明します。
事業主団体等
事業主団体等は、次の条件をすべて満たした団体・組織のことです。ストレスチェック助成金のように、一社ごとの申請はできないため注意が必要です。
下記のいずれかに該当している事業主団体であること
- 事業主団体またはその連合団体(事業協同組合や商工会議所、一般社団法人など)
- 都道府県事業主団体
- 共同事業主
サービスを提供する事業主が、労働者を雇用する事業主であること
労災保険の適用および中小企業の占める割合について、下記要件を満たすこと
- 申請する事業主団体等が、労働者災害補償保険の適用事業主である
- 中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている
下記の条件をすべて満たすこと
- 事業主団体等の事業活動状況に問題がない
- 事業主団体等の財政が健全である
- 過去に補助金等の不正使用等事案がない
- その他、事業実施上の問題がない
より詳細な情報については、 「団体経由産業保健活動推進助成金」の手引(令和6年度版) で紹介しているため、こちらも参考にしましょう。
また助成対象に該当するかどうかは、「 助成対象となる事業主団体等の確認フロー図 」でもチェックできるため、こちらを利用するのもおすすめです。
労災保険の特別加入団体
労災保険の特別加入団体とは、労働者災害補償保険法の第33条第3号または第5号に該当する団体のことです。また1年以上の活動実績があり、次の要件を満たす必要があります。
- 特別加入団体の事業活動状況に問題がないこと
- 特別加入団体の財政が健全であること
- 過去に補助金等の不正使用等事案がないこと
- その他、事業実施上の問題がないこと
※出典:労働者健康安全機構「 『団体経由産業保健活動推進助成金』の手引(令和6年度版) 」(2024年12月25日閲覧)
団体経由産業保健活動推進助成金の対象事業・助成金額・申請方法
次に団体経由産業保健活動推進助成金における対象事業や助成金額、申請方法についてそれぞれ紹介します。これらについても、詳細は 「団体経由産業保健活動推進助成金」の手引(令和6年度版) での確認が、おすすめです。
対象事業
助成の対象となる産業サービスは次の7種類です。医師・看護師・保健師もしくは産業サービスの事業者と契約してサービスを提供します。
- 健康診断結果の意見聴取
- 保健指導
- 面接指導・意見聴取
- 健康相談対応
- 医師や社会保険労務士などによる治療と仕事の両立支援
- 職場環境改善支援
- 健康教育研修・産業保健に関する周知啓発
このうちストレスチェックに関連するのは、「職場環境改善支援」です。ストレスチェック実施後の結果を活用して職場環境改善を実施した場合に、助成金の対象となります。なおストレスチェック助成金のように、ストレスチェック制度の導入・実施だけでは支給の対象にはならないため、注意が必要です。
各産業保険サービスの詳細については、「 団体経由産業保健活動推進助成金とは 」でもわかりやすく紹介されているため、そちらも参考にしましょう。
助成金額
助成対象である産業保健サービスの費用や事務費用を合計した金額のうち、90%の金額が助成されます。上限額は500万円ですが、一定の要件を満たすことで上限を1,000万円まで引き上げ可能です。
1団体ごとに毎年1回のみ申請できます。ただし、参加の企業に参加費を求める場合は負担額によって助成金額が変わるため注意しましょう。対象になる具体的な経費項目は次のとおりです。
- 謝金:指導や助言を依頼した専門家への謝礼
- 旅費:調査や打ち合わせ、指導、助言を依頼した専門家に支払う旅費
- 会議費:会議やセミナーを開催するのにかかった費用
- 印刷製本費:研修資料やパンフレット、ポスターなどを制作するのにかかった費用
申請方法
団体経由産業保健活動推進助成金を申請する際には、次のような手順で行います。
- 実施計画書といった必要な書類の準備
- 計画の承認
- 計画の実施
- 申請書を提出
- 助成金の支給開始
実施計画書とは、実施予定の産業保健活動の目的や具体的な内容、期待される効果、予算などをまとめた資料のことです。この計画書を各種証明書類とともに、郵送・電子申請・Googleフォームから選択して申請します。
30日間以内に審査が終了し、計画が承認されたら実際に産業保健活動を行い、終了後に証明書類とともに助成金支給の申請書を提出します。30日以内に審査結果が出て、合格すれば助成金が支給される流れです。
メンタルヘルス対策で利用できるその他の支援
団体経由産業保健活動推進助成金のほかにも、メンタルヘルス対策で利用できる支援制度はいくつか存在します。これらを活用すると、費用をかけずにストレスチェック制度の導入や実施がしやすくなるため、団体経由産業保健活動推進助成金の申請が難しい場合には、こちらも検討しましょう。
厚生労働省のストレスチェック実施プログラム
厚生労働省が無料で提供している、パソコンにインストールするタイプのストレスチェック実施システムです。ストレスチェックの受検はもちろん、ストレスチェックの結果出力や手段分析といったことまででき、必要な機能はひととおり揃っています。
また従業員が回答する調査票も紙版・Excel版・アプリ版が用意されており、分析機能の活用方法や「高ストレス者」の選定方法まで紹介されています。これらを活用すれば費用や時間をかけず、従業員のストレス傾向を理解できるでしょう。
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センターとは労働者健康安全機構が運営する、全国47都道府県に設置された産業保健活動の支援センターです。メンタルヘルス対策を含め産業保健に関する相談や研修、情報提供、経営者向けセミナー、労働者向けセミナーの開催などをすべて無料で行っています。
また希望があれば、専門スタッフが直接事業場を訪問し、メンタルヘルスも含めた労働衛生管理における総合的な助言・指導も可能です。そのためこれらを活用することで、職場環境の改善を進めやすくなるでしょう。
地域窓口(地域産業保健センター)
地域窓口(地域産業保健センター)も同じく全国に存在し、従業員数50人未満の企業や労働者のさまざまなメンタルヘルス対策を無料で支援しています。主な活動としては、次のようなものが挙げられます。
- 長時間労働者への医師による面接指導の相談
- 健康相談窓口の開設
- 個別訪問による産業保健指導の実施
- 産業保健情報の提供
上3つの活動に関しては、医師や保健師が行ってくれます。そのため、産業医との契約が難しいといった場合には、活用を検討するといいでしょう。
ストレスチェックを支援するツール
ストレスチェックに役立つツールを紹介します。有料ではあるものの、より効率的かつ柔軟に利用できるためぜひ検討しましょう。
M-Check+
- パソコンやスマホ、紙などすべてに対応
- 厚労省の推薦事項をベースに構成
- 集団分析の軸を自由に設定
M-Check+ は、メンタルヘルスの専門機関が監修した、安全性もコスパも高いストレスチェックサービスです。このサービスはパソコンといったデジタルと紙のアナログを組み合わせて利用できます。そのため、スマホをよく操作する方にはデジタルで、パソコン利用が不得意な方には紙で回答を依頼するといった使いわけができます。またアンケートの質問内容は厚労省が推薦しているものをもとに、それぞれの企業に合わせたカスタマイズが可能です。
助成金や支援制度の利用でストレスチェックの義務化に備えよう
これまで従業員数50人未満の企業では、ストレスチェックの実施は努力義務とされてきました。しかし令和6年9月に厚生労働省は今後すべての企業で実施を義務づける方針を決定しており、今後は必ず実施しなければならなくなるでしょう。
一方で団体経由産業保健活動推進助成金や、厚生労働省が提供する無料システムといった支援制度も多く、相談できる窓口も存在します。ぜひこれを機会に専門家や医師に相談してストレスチェック制度を導入し、いずれ来る義務化に備えましょう。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査