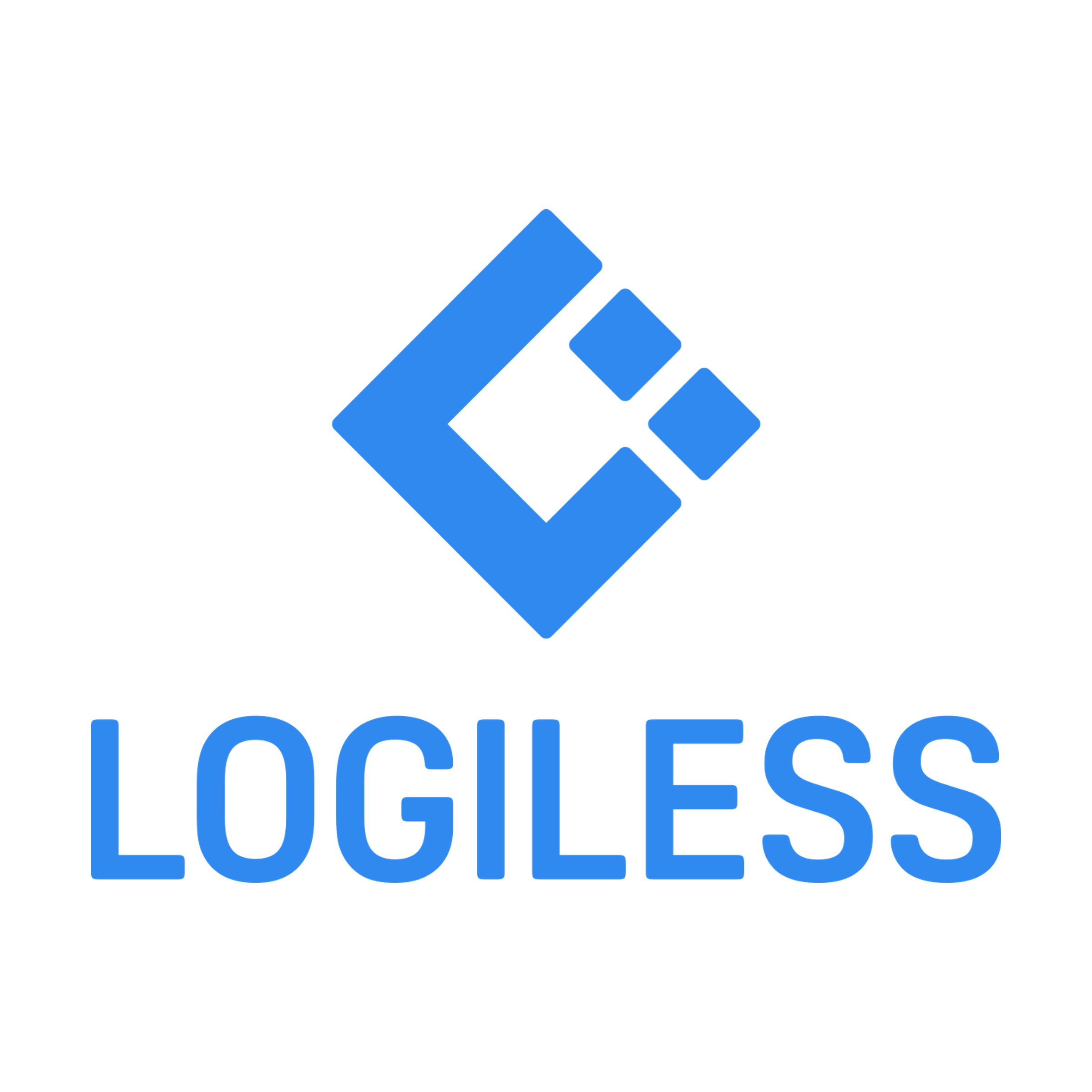倉庫業とは
倉庫業とは、荷主から預かった荷物を倉庫で保管する事業のことです。預かる荷物は、食品や衣料品、家電製品など、多岐に渡ります。また、保管だけでなく、荷物の入出荷、仕分け、ピッキング、梱包、配送といった物流加工業務を行うことも多いです。
近年、EC市場の拡大や企業の物流効率化ニーズの高まりから、倉庫業の重要性が増しています。倉庫業は、荷主と消費者の間をつなぐ、物流における重要な役割を担っているといえるでしょう。
倉庫業法とは
倉庫業法とは、倉庫業を営むうえで守るべきルールを定めた法律です。倉庫業法は、荷主の財産を守ることを目的としており、倉庫の構造設備基準や、倉庫業者が遵守すべき事項などを定めています。
倉庫業法は、倉庫業を営むうえで必ず遵守しなければならない法律です。違反した場合には、罰則が科せられる可能性があります。
倉庫業の仕事内容
倉庫業と聞くと、荷物をただ保管しておくだけの仕事というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、実際には保管以外にもさまざまな業務を行っています。
倉庫業の仕事内容には、具体的に次のようなものがあります。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 検品 | 荷物の数量や状態をチェックし、破損や不良品がないかを確認します。 |
| 入荷 | 入荷した荷物を検品した後、所定の場所に保管します。 |
| 保管 | 荷物を適切な環境で保管し、品質を維持します。 |
| ピッキング | 出荷指示に基づき、必要な商品を倉庫から集めます。 |
| 梱包 | 出荷する商品を保護するため、適切な資材で梱包します。 |
| 出荷 | 梱包した商品をトラックに積み込み、配送業者に引き渡します。 |
| 在庫管理 | 倉庫内の在庫状況を把握し、適切な在庫レベルを維持します。 |
倉庫業は荷主から荷物を預かるだけでなく、入荷から出荷まで、物流に関する幅広い業務を担っています。荷主にとっては、物流業務を外部に委託することで、業務負荷を軽減できるメリットがあります。
倉庫の種類
倉庫には、大きく分けて自家倉庫と営業倉庫の2種類があります。自社の製品や原料を保管するための倉庫が自家倉庫、荷主から預かった荷物を保管するのが営業倉庫です。
自社の製品や原料を保管する自家倉庫
自家倉庫とは、自社の製品や原料を保管するための倉庫です。企業が自社の敷地内に建設・保有する倉庫が一般的ですが、外部から借りている場合もあります。
自家倉庫は、自社のニーズに合わせて自由に設計・運用できる点がメリットです。ただし、建設費用や維持管理費用などのコストがかかるというデメリットもあります。
倉庫業登録が必要な営業倉庫
営業倉庫とは、荷主から預かった荷物を保管する倉庫のことです。倉庫業者は、荷主から保管料を受け取って荷物を保管します。
営業倉庫は、倉庫業法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局長の登録を受けなければなりません。また、荷主の財産を守るために、倉庫の構造設備や管理体制などについて、倉庫業法で定められた基準を満たす必要があります。
倉庫業の種類
倉庫業は、保管する貨物の種類や倉庫の形態によって、いくつかの種類に分けられます。代表的な3つの倉庫業について解説します。
普通倉庫業
普通倉庫業とは、最も一般的な形態の倉庫業です。衣料品、家具、家電製品、書籍など、さまざまな貨物を保管できます。普通倉庫業は、さらに次の種類に分けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1類倉庫 | 耐火構造、防水・防湿・遮熱性能を備えた倉庫です。火災や水害のリスクが高い貨物を保管する際に利用されます。 |
| 2類倉庫 | 1類倉庫に比べて防火性能が低い倉庫です。燃えにくい貨物を保管する際に利用されます。 |
| 3類倉庫 | 2類倉庫に比べて防水・防湿性能が低い倉庫です。水濡れや湿気に強い貨物を保管する際に利用されます。 |
| 貯蔵槽倉庫 | 液体や粉状の貨物を貯蔵するための倉庫です。石油、化学薬品、穀物などを保管する際に利用されます。 |
| 野積倉庫 | 屋根や壁がない、屋外に設置された倉庫です。木材、鉄鋼、建設資材など、雨風に強い貨物を保管する際に利用されます。 |
| 危険品倉庫 | 火薬類や毒物など、危険物を保管するための倉庫です。消防法に基づいた厳格な基準を満たす必要があります。 |
| トランクルーム | 家具や家電製品など、個人の家財道具を保管するための倉庫です。近年では、収納スペースの不足を解消するために、利用者が増加しています。 |
水面倉庫業
水面倉庫業とは、水面を利用して貨物を保管する倉庫業です。主に、原木や木材などの乾燥に弱く、水面保管が必要な貨物に利用されます。水面倉庫業は陸上輸送が難しい地域において、水上輸送と組み合わせることで、効率的な物流を実現します。
冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫業とは冷凍・冷蔵設備を備えた倉庫で、生鮮食品や医薬品など、10度以下で貨物を保管する倉庫業です。冷蔵倉庫業は貨物の品質を維持するために、温度や湿度を厳密に管理する必要があります。
倉庫業を運営する際の注意点
倉庫業を運営する際には、倉庫業法や関連法規を遵守し、適切な管理体制を構築しなければなりません。法令違反や管理不備は、荷主とのトラブルや事業の継続に悪影響を及ぼす可能性があります。
倉庫業を運営する際の注意点を3つ解説します。
注意点1. 倉庫業登録をしなければならない
営業倉庫を運営する場合、倉庫業法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局長に倉庫業の登録をしなければなりません。自家倉庫のように自社の荷物を保管する場合には登録不要ですが、荷主から荷物を預かって保管・管理する営業倉庫は登録が必須です。
倉庫業登録をせずに営業倉庫を運営すると、倉庫業法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。また、荷主からの信頼を失い、事業の継続が難しくなることも考えられます。
注意点2. 倉庫業登録の審査は厳しい
倉庫業登録の審査は厳しく、倉庫の構造設備や管理体制などが倉庫業法の基準を満たしているか厳格に審査されます。具体的には、倉庫の耐火性、防湿・防水性、セキュリティ対策などが審査対象です。
審査基準を満たしていない場合は、登録が認められない可能性もあります。倉庫業登録を取得するためには、事前に倉庫業法の内容を理解し、必要な準備をしておきましょう。
注意点3. 登録せずに営業すると罰則がある
前述のとおり、倉庫業登録をせずに営業倉庫を運営すると倉庫業法違反となり、罰則が科せられます。具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
※参考:「 倉庫業法 | e-Gov 法令検索 」(2025年1月9日閲覧)
また、罰則以外にも、荷主からの信頼を失墜させ事業の継続が困難になるなど、さまざまな影響が生じるでしょう。営業倉庫を運営する際には、必ず倉庫業登録を取得し、法令を遵守しましょう。
荷主から見た営業倉庫の4つのメリット
荷主にとって、営業倉庫を利用するメリットは数多くあります。物流業務の効率化やコスト削減だけでなく、安全性の確保や業務負担の軽減など、さまざまなメリットが期待できます。
メリット1. 厳しい基準をクリアしている
営業倉庫は、倉庫業法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局長の登録を受けなければなりません。登録には倉庫の構造設備や管理体制など、さまざまな基準をクリアすることが求められます。つまり、営業倉庫を利用することで、荷主は一定の品質基準を満たした倉庫に安心して荷物を預けられます。
これにより、荷物の盗難や破損のリスクを低減し、安全な保管が可能です。また、倉庫の品質が高いことは、荷主の企業イメージ向上にもつながります。
メリット2. 倉庫寄託約款がある
倉庫寄託約款とは、倉庫業者と荷主の間で事前締結される契約のようなものを指します。倉庫業者はこの約款を国土交通大臣に届け出なければなりません。
約款は利用者に対する契約条項のことで、個別の契約書に記載されていない事項に対しても、約款に記載された事項に対しては、約款の記載に基づいた対処が行われます。
倉庫寄託約款があることで、荷物の保管に関するトラブルを未然に防げます。また、万が一トラブルが発生した場合でも、約款に基づいて解決を図り、荷主の権利を守れるでしょう。
メリット3. 火災保険が倉庫業者負担
営業倉庫では、火災保険料が倉庫業者の負担となります。荷主は、火災保険に加入する必要がなく、保険料を負担する必要もありません。
万が一、火災が発生して荷物が焼失した場合でも、倉庫業者が加入している火災保険によって、損害を補償できます。これにより、荷主は火災リスクに対する経済的な負担を軽減できます。
メリット4. 貨物の管理や入出荷の負担がない
営業倉庫を利用することで、荷主は貨物の管理や入出荷といった物流業務を倉庫業者に委託できます。これにより、荷主は自社で倉庫を保有する必要がなくなり、倉庫管理にかかる人員やコストを削減可能です。
また、物流業務を専門家に任せることで業務効率が向上し、人材不足の解消にもつながります。荷主は本来の業務に集中でき、事業の成長を促進できます。
営業倉庫を運営するなら登録は必須
荷主にとっての営業倉庫を利用するメリットは、安全性の確保、コスト削減、業務効率化など、多岐に渡ります。その一方で、倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づいた営業倉庫としての登録が必須であり、厳しい基準をクリアしなければなりません。
荷主は、倉庫業登録がされているかを確認することで、安心・安全な倉庫に荷物を預けられます。倉庫選びの際には、倉庫業登録の有無を必ず確認しましょう。
\料金や機能を資料で比較する!/