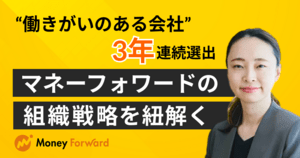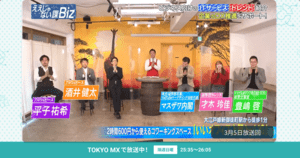「タイパ」重視の学生たちの負担をいかに減らすか?求人倍率6.5倍の超・売り手市場の今、中小企業が取るべき新卒採用戦略とは

2025年、企業にとって採用市場は厳しさを増す一方。
その原因は少子高齢化による労働人口の減少にあります。
リクルートワークス研究所の「Works Report 2023 未来予想図2024」では
2030年には341万人、2040年には1,100万人の労働供給不足を予測。

出典:リクルートワークス研究所「Works Report 2023 未来予想図2024」
このような働き手不足から売り手市場が進み、新卒の求人倍率はコロナ禍で一時下がったものの、2025年は1.75倍へと増加傾向。
中でも300人未満の中小企業では6.5倍にまで上がっており、企業規模による格差が大きくなっています。

出典:リクルートワークス研究所「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」
しかしそのような状況下でも中小企業が採用を成功させる方法があると話すのは、
株式会社人材研究所の曽和 利光(そわ としみつ)氏。
本記事では、二万人を面接した元人事部長/組織人事コンサルタントの曽和氏が、今中小企業が取るべき採用戦略について具体的な方法を交えて紹介します。
※本記事は、株式会社人材研究所 代表取締役社長の曽和 利光(そわ としみつ)氏が「BOXIL EXPO 人事・総務展 2024 秋」にて講演した内容をまとめています。

株式会社人材研究所 / 代表取締役社長愛知県豊田市生まれ、関西育ち。灘高等学校、京都大学教育学部教育心理学科。在学中は関西の大手進学塾にて数学講師。卒業後、リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っている。著書に「人事と採用のセオリー」「人と組織のマネジメントバイアス」「できる人事とダメ人事の習慣」「コミュ障のための面接マニュアル」「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか?」他。現在、Y!ニュース、日経、労政時報、Business Insider、キャリコネ等、コラム連載中
目次を閉じる
実は新卒は、中途や高卒よりも採用しやすい
新卒よりも中途の方が採用しやすいのではないかと、中途採用に力を入れる企業は多いです。
しかし実際は、中途採用の方が求人倍率が高く採用しにくいのが現状。
2025年の新卒の求人倍率1.75倍に対し、中途は2.74倍というデータが出ています。

出典:転職サービスdoda「転職求人倍率レポート(データ)」
また、高卒採用の人気も近年うなぎのぼりに高まっており、2025年の求人倍率は3.52倍。
若い人材を大卒よりも低い賃金で採用できることから高卒者の需要が増えています。
そのため、採用に課題がある中小企業は大学卒の新卒採用に注力しましょう。
学生の就職活動量が低下し、企業がアピールする機会が減っている
求人倍率が高い売り手市場の今、それに伴い学生の就職活動量は下がっています。
必死に何社もの説明会に参加したりエントリーシートを書かなくても内定がもらえるためです。
例えばOB・OG訪問をする学生は今や全体の14.5%しかいません。
プレエントリーの数も、10年前であれば100社程度プレエントリーするのが一般的でしたが、現在では平均26.30社です。

出典:リクルート 就職みらい研究所「就職白書2025」
対面の企業説明会への参加も平均でたった5.31社のみ。巷では「説明会はオワコン」だという声も上がっています。また、対面の面接選考数も同じく5.31社です。
このように学生の就職活動量が減ることで、企業が学生にアピールする機会が減り、学生との接点を持ちづらくなってきています。
「タイパ」重視の学生たち。いかに学生の負担を減らすかがカギ
学生の就職活動量が減っている点に加えて、就職活動への参加方法や態度にも変化が見られます。
企業説明会は対面からオンラインへ移行が進み、特にオンデマンド形式での説明会参加が増えています。
オンデマンド説明会は、会社説明の動画をホームページやYouTubeなどの誰もが見られる場所に設置しておき、学生が好きなときに視聴するというもの。
オンデマンドが最も見られているのは夜の11時頃。しかも2倍速で見ている学生が多いといいます。
きっと部屋のベッドで寝転びながらスマホで見ているのでしょう。
わざわざ企業に出向いて1〜2時間座って説明を聞くよりも、自宅のベッドで2倍速で動画を見るほうが圧倒的に手間も時間も少なく済みます。

説明会の参加数も、対面だと平均5社程度ですが、Web開催だと平均約11社の参加があります。
説明会や面接をオンラインで実施することで、学生に参加してもらえる確率は上がるでしょう。
また、エントリーシートの提出数も2024年、2025年と12〜13社程度で推移しています。
エントリーシートは企業ごとに独自の項目や提出課題があるなど時間がかかるものも多く、学生に敬遠されがちです。
そこで、最近ではエントリーシートを選考フローから無くしている企業も少なくありません。
このように「タイパ」重視の学生たちと少しでも接点を持つためには、「学生の負担をいかに減らすか」という視点を持つことが重要です。
中小企業が取り組むべきは「スカウト型採用」
売り手市場で学生の就職活動量が減っている今、
知名度が低い中小企業が新卒採用を成功させるのは難しくなってきています。
そこで取り組むべきは「スカウト型採用」です。
従来のオーディション型採用と異なる点は、企業側からターゲットとなる学生にアプローチをかけて、自社の魅力付けをしたり、選考に進むよう働きかける点です。
手間がかかるものの合格率が高く、有名企業ではなくても学生にリーチできるため、「スカウト型採用」は中小企業こそが取り組むべき施策です。

①ターゲットの明確化
オーディション型採用は学生からの応募を待つ受動的な採用方法であるため、多様な人材が集まります。しかしスカウト型採用は「企業側が会いたい人にだけ会う」という能動的な方法です。
効率の良さがメリットとしてはありつつ、「会いたい人」の定義が間違ってしまうとかえって非効率になってしまいます。
まずはコミュニケーション能力・チャレンジ精神・協調性など、いくつかの採用したい人材の要件を設定するのがファーストステップです。
そしてそれらの要件をなるべく具体的に定義しましょう。
例えば「コミュニケーション能力」という要件はまだ抽象的です。
それは筋道を立てて分かりやすく説明する「論理性」を指すのか、相手の感情を想像して集団の空気を読むことができる「感受性」を指すのかなど、より具体的に定義しましょう。
下図は曽和氏が5つの人材要件をさらに細分化したものです。ぜひ参考にしてみてください。

②ペルソナを作ってフリーワード検索
スカウトは一般的にスカウトメディアを使っておこないます。
スカウトメディアに多数の学生がプロフィールを登録しているので、その情報をもとにターゲット像に合う学生にスカウトメッセージを送ります。
学生を探す際には検索機能を使いますが、大学、学部、志望業界など一般的な情報で検索をすると、他社も同じように検索しているのでターゲットが被ってしまいます。
そこでおすすめなのが、ペルソナを作ってフリーワード検索をすること。
そのためにまずはペルソナを具体的に想像してみましょう。
「論理的思考能力」を人材要件に設定しているとすると、論理的思考能力が高い学生はどんなアルバイトをしているだろう?と想像します。飲食店かな?家庭教師かな?塾の先生かな?といった具合です。
あるいは趣味を想像します。論理的思考能力が無い人物がやらないであろう趣味、例えば将棋かな?と想像します。

このように人材要件を満たす具体的な人物イメージを様々な角度から想像してキーワードを拾っておきます。そのキーワードでフリーワード検索をかけると、例えば趣味の欄に「将棋」と書いている学生がヒットするわけです。
フリーワード検索を使って学生を探す企業は極めて少ないので、他社にはまだ見つかっていない、かつ自社が求めている学生を見つけられます。
③一人ひとりのニーズに合うコンテンツ
採用ホームページに採用動画などを載せる場合、多数の人が見ることを考慮する必要があるため無難な内容になりがちです。
しかしスカウト型採用であれば、その学生一人ひとりの属性や興味に応じたコンテンツを送ることができます。会社説明の動画やハイパフォーマー社員のインタビュー動画など、様々なパターンを用意しておくとスカウトへの反応が高まります。

そしてコンテンツ動画は1分以内が鉄板。30分の長編動画はまず見られません。
「いかに学生の負担を減らすか」という考えはここでも忘れないでください。
また、スカウトメールでインターンシップの案内をするのも非常に有効です。
就職活動量が減っている中でもインターンへの参加だけは活発化しており、12月の時点で約90%の学生がインターンシップに参加しています。
中小企業の場合は、半日〜1日程度の短いインターンシップがおすすめ。
大企業では5日間ほどのインターンシップを開催することもありますが、中小企業だと参加者を集めるのが難しくなります。
また、インターンシップの内容としてよくあるのは仕事の疑似体験型コンテンツですが、それはあなたの会社に十分な興味がないと参加してもらえません。
ある不動産企業では、自己分析やキャリアを考えるワーク、模擬面接などの一般的な就活支援コンテンツをインターンシップで実施して大成功を収めました。
一般的なコンテンツにしてしまうと、自社への興味が少なくターゲットとは違う学生が多く参加するのではないか?という懸念はもっともで、実際にそのような学生も多く集まります。
しかし、まずは学生との接点をもつことが重要。会社の魅力付けはその後におこないましょう。
中小企業でも超・売り手市場で勝ち抜ける
このように、求人倍率が6.5倍と非常に厳しい中小企業の新卒採用であっても、
スカウト型採用をうまく活用することで自社に合う良い学生を採用できます。
- 学生の負担を減らす意識を持つ
- ターゲットを明確化する
- ペルソナをもとにしたキーワード検索で学生を探す
- コンテンツを最適化する
スカウト型採用ではこれらのポイントを押さえながら、
新たな時代でも他社に負けない人材採用戦略を打ち立て、明日から実践していきましょう。