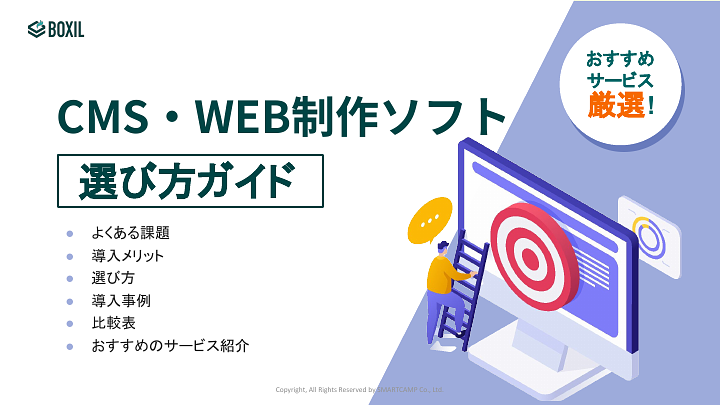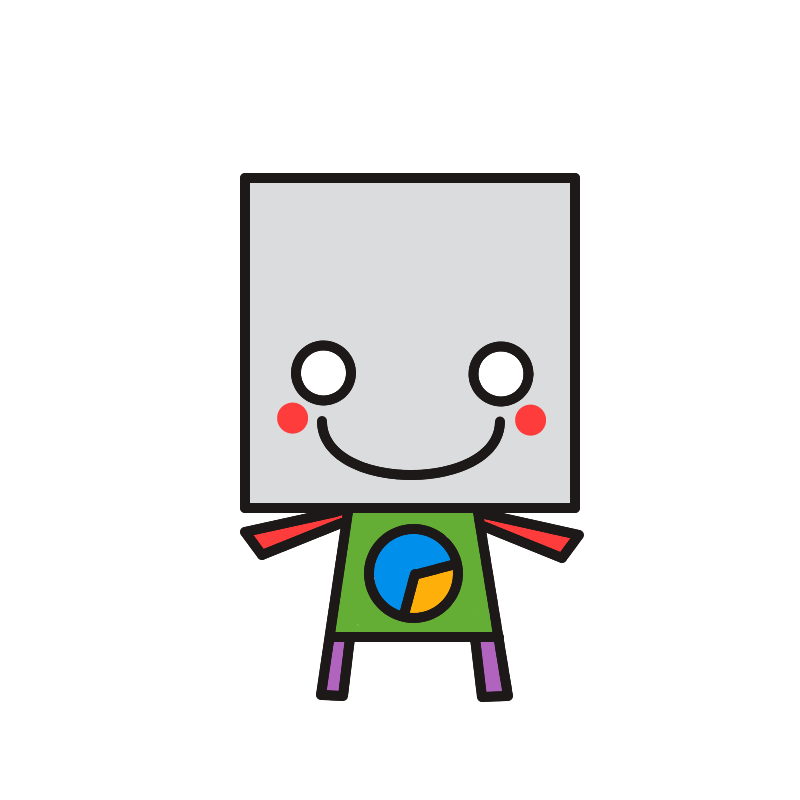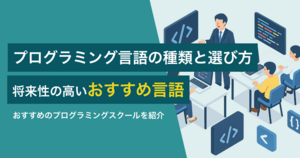今さら聞けないコンテンツSEOとは?基本をポイント解説・メリット・手順
CMS・WEB制作ソフトには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
⇒CMS・WEB制作ソフトの資料をダウンロードする(無料)
目次を閉じる
- コンテンツSEOとは?
- コンテンツSEOの重要性
- かつてのSEOテクニックが通用しなくなった
- Googleが求める「E-E-A-T」とは
- 検索エンジン側とユーザー側の両方の視点が必要
- コンテンツSEOのメリット
- 潜在層にアプローチできる
- 長期的な集客につながる
- Webサイトが資産化する
- ブランド力向上につながる
- SNSとのシナジーが期待できる
- 営業資料としても活用できる
- コンテンツSEOのデメリット
- 短期的な成果は期待できない
- コンテンツ作成の負担が大きい
- コンテンツのアップデートが必要
- コンテンツSEOの手順
- 3C分析する
- キーワードを選定する
- 記事の構成案を作成する
- 原稿を執筆する
- 内部対策や外部対策
- 記事の順位を計測する
- リライト
- 施策をスムーズに進めるためのポイント
- 制作ルールをマニュアル化する
- SEO施策の目的をKPIで可視化する
- 一覧管理でテーマと進捗を一元化する
- PDCAを回す機会を設ける
- コンテンツSEOに対応するおすすめのCMS・オウンドメディア構築サービス
- dino
- 月間3,000CV!ボクシル編集長監修『コンテンツSEO完全ガイド』
- コンテンツSEOによって長期的な集客につなげよう
- BOXILとは
コンテンツSEOとは?
コンテンツSEOとは、良質なコンテンツ(主に記事)を積み上げることで、検索エンジンへの上位表示を目指すSEO施策です。
良質なコンテンツとは、簡単にいえば「ユーザーのニーズを満たした記事」のことをいいます。
Googleの検索エンジンからの高い評価を受けるために、ペルソナの設定やキーワード選定、内部対策などを通して、コンテンツの最適化を図ります。
コンテンツSEOの主な目的は、Webサイト経由で見込み顧客を獲得して問い合わせ件数を増やし、売上アップを図ることです。
コンテンツを上位表示させるためには、ユーザーと検索エンジンの双方から評価されるコンテンツを配信する必要があります。
コンテンツSEOを含む「SEO」については、次の記事でくわしく解説しています。

コンテンツSEOの重要性
なぜコンテンツSEOが重要とされるのか解説します。
かつてのSEOテクニックが通用しなくなった
コンテンツSEOがとくに重要視されるようになったのは、2011年から2012年頃といわれています。
Googleのパンダ・アップデート(2011年)※1やペンギン・アップデート(2012年)※2により、質の低いコンテンツやブラックハットSEOが淘汰されました。
そして、良質なコンテンツが求められるようになりました。
以前からSEOの概念は存在していたものの、当時は「ブラックハットSEO」と呼ばれる手法が主流でした。ブラックハットSEOとは、いわば「小手先のテクニック」です。
たとえば次のような例があげられます。
- 記事の流れが不自然なのにもかかわらず、むやみに当該キーワードを入れる
- 被リンクを売買し、他サイトとリンクさせ合う
- コピーしたコンテンツをWebサイトに量産する
今でこそ信じがたい内容ですが、当時はこのような「ブラックハットSEO」が横行しており、Googleも評価の対象としていました。
しかし、こうした質の低いコンテンツが増えたことを受けて、Googleは数回にわたってアルゴリズムを大幅に変更しました。
今では、被リンクの売買やコピーされたコンテンツはほとんど姿を消し、良質なコンテンツのみが上位表示されています。
コンテンツSEOを実施する企業としても、ブラックハットのようなやり方では通用しないため、良質なコンテンツを作ることが、上位表示への最短ルートといえます。
※1出典:google「Google 検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになりました」(2025年7月25日閲覧)
※出典2:google「良質なサイトをより高く評価するために」(2025年7月25日閲覧)
Googleが求める「E-E-A-T」とは
コンテンツSEOを進めるうえでは、Googleのアルゴリズムや評価基準を理解することが重要です。
Googleはコンテンツに対して「E-E-A-T」を求めています。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略です。
とくに医療、金融、法律といったYMYL(Your Money or Your Life)ジャンルでは、Googleがこの4つの要素を重視する傾向があります。
この4つを満たすことで、「良質なコンテンツ」の評価を受けやすくなります。
検索エンジン側とユーザー側の両方の視点が必要
コンテンツSEOでは、Googleをはじめとする検索エンジンからの評価も重要です。
たしかに、検索上位を目指すために「E-E-A-T」は欠かせません。しかし、検索エンジンの評価を意識するあまり、コンテンツが機械的になったり、ユーザーの潜在ニーズに気付けなかったりするケースもあります。
検索エンジン側とユーザー側の両方の視点をもったうえで、コンテンツSEOを進めることが大切です。
コンテンツSEOのメリット

続いて、コンテンツSEOのメリットを紹介します。
- 潜在層にアプローチできる
- 長期的な集客につながる
- Webサイトが資産化する
- ブランド力向上につながる
- SNSとのシナジーが期待できる
- 営業資料としても活用できる
潜在層にアプローチできる
コンテンツSEOでは、ユーザーが求めているキーワードを模索して記事に反映させるため、潜在層へのアプローチが可能です。
ユーザーには、すでに欲しいものや情報がわかっている「顕在層」と、興味関心はあるものの具体的に欲しいものや情報がわからない「潜在層」がいます。
3C分析やペルソナの設定、検索意図の調査によって、「潜在ニーズ」が浮き彫りになり、多くの潜在層にリーチ可能です。
長期的な集客につながる
コンテンツSEOでは、Web広告やSNSと比べて長期的な集客が可能です。
たとえば、リスティング広告の場合、ユーザーが検索したキーワードと関連性の高い広告を出稿できます。
ただし、集客力は高いものの、広告のインプレッションが増えたり、クリックされたりするごとに費用がかかります。
短期的な集客にはおすすめですが、長期的な流入を狙うためには、膨大なコストがかかることを考慮しなければなりません。
コンテンツSEOでは、一度作成したコンテンツは半永久的に残ります。上位表示をキープし続けられれば、過去のコンテンツが自走してくれるため、長期的な集客が可能です。
Webサイトが資産化する
Webサイトが資産化するのも大きなメリットといえます。コンテンツSEOでは、Webサイトの信頼性を高めるために、ニーズに沿ったコンテンツを量産するのが基本戦略です。
本格的にオウンドメディア運営をする場合、百本単位でコンテンツを作成します。
作成に負担はかかるものの、一度公開したコンテンツは検索エンジン上に残り続けます。
仮に上位に表示されなくても、正しい方法で記事のリライトや内部対策、外部対策により、評価を受けられる可能性が高いでしょう。
ブランド力向上につながる
検索結果の上位を自社のWebサイトやコンテンツで占有できれば、ブランド力向上につながります。コンテンツSEOでは、メインとなるキーワードを軸に、関連キーワードの記事を公開するのが基本です。
たとえば、ユーザーが「ノートパソコン 相場」を調べた場合、関連キーワードとして「ノートパソコン 選び方」や「ノートパソコン ランキング」が表示されます。
サイト運営者は「相場」だけでなく「選び方」や「ランキング」の記事も公開することで、Webサイト自体の権威性が高まります。
「ノートパソコン」に関するコンテンツで検索エンジン上位を占有できた場合、ブランド力は大幅に高まるでしょう。
SNSとのシナジーが期待できる
コンテンツSEOと同時並行でSNSも運用すれば、シナジー効果が生まれやすくなります。コンテンツSEOは記事を資産化して長期的な集客を狙うマーケティング施策なので、短期的な集客にはつながりにくいでしょう。
そこで、拡散力の高い「SNS」に記事のリンクを貼り付けて投稿します。ユーザーにとって有益な情報が書かれていれば自然と「いいね」や「シェア」がされ、一気に拡散されるでしょう。
営業資料としても活用できる
コンテンツSEOは、BtoBの営業資料としても活用可能です。商材と関連性の高いキーワードの記事が上位表示されていれば、商談時のプレゼン資料としてコンテンツを活用できます。
読者にとってわかりやすく、作り込まれたコンテンツであれば、顧客からの信頼も高まるでしょう。
しっかりと作り込まれたコンテンツは、営業資料だけでなく、社内向けの教材としても応用可能です。
コンテンツSEOのデメリット
コンテンツSEOには多くのメリットがある反面、デメリットも存在します。とくに次の3つには注意しましょう。
- 短期的な成果は期待できない
- コンテンツ作成の負担が大きい
- コンテンツのアップデートが必要
短期的な成果は期待できない
コンテンツSEOは、Webサイトに質の高い記事を蓄積することで、長期的な成果を得られるマーケティング手法です。
そのため、コストをかけて一気に広範囲にリーチできるWeb広告や、いわゆる「バズ(大きく拡散される)」を狙えるSNSのような短期的な成果は狙えません。
地道にコンテンツを公開し、検索エンジンやユーザーからの信頼を積み上げる必要があります。
コンテンツ作成の負担が大きい
コンテンツ作成では、ペルソナやキーワードを選定し、ユーザーニーズを踏まえたうえで構成案を作成、記事を執筆する必要があります。
1本の記事ならまだしも、数十本や数百本になると、膨大な社内リソースが必要です。コンテンツSEOにリソースを割きすぎてコア業務に集中できない、といった事態にならないよう注意しましょう。
社内でコンテンツの作成やWebサイトの維持が難しい場合は、ライターやディレクターに業務を依頼するといった方法もあります。
コンテンツのアップデートが必要
定期的なアップデートが必要なのも、コンテンツSEOの難点といえます。コンテンツを無事に公開できても、上位表示されるとは限りません。
すでにブランド力のあるWebサイトを運用していれば別ですが、立ち上げたばかりのWebサイトの場合、信頼を獲得するのに時間がかかります。
したがって、記事の修正や情報更新をする「リライト」が必要です。リライトによって、ユーザーニーズに沿った、かつ情報鮮度の高い記事にアップデートできれば、検索エンジンからの評価も受けやすくなります。
コンテンツSEOの手順
続いて、コンテンツSEOの具体的な手順を解説します。
- 3C分析する
- キーワードを選定する
- 記事の構成案を作成する
- 原稿を執筆する
- 内部対策や外部対策
- 記事の順位を計測する
- リライト
3C分析する
コンテンツSEOを進めるにあたって、最初にすべきなのが「3C分析」です。3CとはCustomer(顧客・市場)、Competitor(競合)、Company(自社)の頭文字をとったものです。
この3つはマーケティングの基本とされています。
Customer(顧客・市場)の分析
コンテンツSEOにおける顧客・市場とは、「ユーザー(読者)」のことで、自社の商材やWebサイトのターゲットとなる「ペルソナ」を分析、決定します。ペルソナとは「仮想的な人物像」のことです。
ペルソナ設定では、どのようなユーザーにWebサイトを見てほしいのかを具体化します。BtoCの場合は、ユーザーの年齢や性別、家族構成などをイメージして、1人の人物像を作り上げます。
BtoBの場合は、企業規模や業界業種、決裁のプロセスなどです。
ペルソナを設定することで、ユーザーが抱える課題や悩みが浮き彫りになり、より刺さるコンテンツを作成できます。
Competitor(競合)の分析
コンテンツSEOでいう競合とは、常に検索上位に表示されるような、信頼性や権威性の高い他社サイトです。
他社サイトがどういったビジネススタイルなのか、どの程度の売上を出しているのか、強みや弱みは何かなどを分析します。
競合を分析することで、自社と他社の「違い」を把握でき、コンテンツ作成に活かせます。
Company(自社)の分析
競合分析だけでなく、自社の分析も必要です。自社商品・サービスの特徴を理解するのはもちろん、企業としての強みや弱み、他社にはない魅力は何なのかなどを分析しましょう。
深掘りすることで、他社との差別化戦略やユーザーに刺さるコンテンツが見えてきます。
キーワードを選定する
3C分析を終えたら、コンテンツ作成のステップに進みましょう。コンテンツ作成で最初にするのが「キーワード選定」です。キーワード選定は次のような手順で進めます。
- ユーザーの検索意図を汲み取る
- 候補となるキーワードを洗い出す
- キーワードの「絞り込み」をする
- 競合が狙うキーワードを調べる
- コンテンツの方向性を決める
ユーザーの検索意図を汲み取る
3C分析で設定した「ペルソナ」をもとに、主軸となるキーワードを決めましょう。
コンテンツSEOの最終的な目標は、Webサイトの集客力向上であり、さらにいうとユーザーに商品やサービスを購入してもらうことです。
ユーザーはどのようなことに悩み、どういった情報が欲しいのか深く考えてみてください。検索意図を汲み取ることで、おのずと「ニーズのあるキーワード」が見えてきます。
候補となるキーワードを洗い出す
ユーザーの検索意図を掴めたら、候補となるキーワードを洗い出しましょう。
たとえば、主軸となるキーワードが「北海道 観光」だった場合、候補となるキーワードとして「北海道 観光 1月」「北海道 観光 子連れ」などが出てきます。
この例でいう「1月」や「子連れ」といったワードは「サジェストワード」と呼ばれ、ユーザーのニーズを知るうえで重要です。
キーワードの「絞り込み」
候補を洗い出したら、キーワードに優先順位を付けて「絞り込み」をしましょう。
Webサイトの方針によって優先順位の付け方は異なりますが、おすすめは「ビッグキーワード」と「ロングテールキーワード」で判断する方法です。
なかでも、今からコンテンツSEOを始める企業は、「ロングテールキーワード」をおすすめします。
ビッグキーワード:検索ボリュームの多いキーワード
例)「北海道 観光」「ベビー用品 レンタル」などロングテールキーワード:検索ボリュームの少ないキーワード
例)「北海道 観光 恋愛」「ベビー用品 レンタル 北海道」など
ビッグキーワードで上位表示された場合、膨大なアクセスを集められます。しかし、多くのユーザーが検索しているため難易度が高いといえます。
すでに信頼性や権威性のあるWebサイトを運営している場合は上位表示を狙えますが、運営を始めたばかりのWebサイトの場合、難易度はきわめて高いでしょう。
対してロングテールキーワードは、ビッグキーワードのように多くのアクセスを集めるのは難しいですが、比較的容易に上位表示を狙えます。
競合が狙うキーワードを調べる
キーワードを絞り込んだら、競合がどういったキーワードを狙っているかも調査しましょう。
これは、上位表示されている競合のキーワードには、それだけメリット(アクセスやコンバージョンが集まっている)があるためです。
具体的には、「Keywordmap(キーワードマップ)」といった競合サイトの調査・分析ツールを用います。競合サイトのURLを入力することで、流入推移やキーワードの内容を把握可能です。
コンテンツの方向性を決める
続いて、「この記事ではこういった内容を述べる」といったコンテンツの方向性を決めましょう。方向性は「記事のテーマ」ともいえます。
構成案の作成にも役立つため、競合やユーザーニーズ、キーワードを見ながら、どういった方向性でコンテンツを作成するか決めましょう。
記事の構成案を作成する
対策キーワードが決まったら、記事の構成案を作成しましょう。
構成案は住宅でいう「設計図」であり、良質なコンテンツを作るために必要不可欠です。構成案は次のようなステップで作成します。
- サジェストや関連ワードをもとに検索意図を探る
- 検索エンジンの1ページ目に表示される競合ページを分析する
- 関連ワードや競合の内容をもとに見出しを作成する
ユーザーのニーズを満たした見出しが入っているか、見出しの順序がスムーズかどうかなどを意識しながら、入念に構成案を作成しましょう。
原稿を執筆する
構成案を作成したら、いよいよ原稿の執筆です。原稿を執筆する際は次のポイントを意識しましょう。
| 意識すべきポイント | 内容 |
|---|---|
| 上位ページの傾向 | 上位サイトの見出しや含まれるキーワードを分析して傾向を掴む。検索上位に表示される=ニーズを満たしたコンテンツといえるため。 |
| オリジナリティ | 記事内に「オリジナリティ(=自社ならではの内容)」を盛り込む。競合の真似をするとコンテンツが埋もれ、検索エンジンからも評価されにくくなる。実際にGoogleは「独自性を重視する」と公言している。 |
| 可読性 | ユーザー目線に立った場合、可読性(=読みやすさ)の高さが重要。検索上位に表示されても、しっかりとコンテンツが読まれ、コンバージョンにつながらなければ成果は出ない。執筆後の校正や入念な校閲チェックが大切。 |
| 網羅性 | SEOにおける「網羅性」は検索エンジンから評価を受けるために重要。どのような検索意図をもったユーザーが読んでも満足してもらう工夫が必要といえる。 |
内部対策や外部対策
ライティングに加えて、コンテンツに「内部対策」や「外部対策」を施しましょう。たとえば次のような対策内容があげられます。
| 対策の種類 | 内容 |
|---|---|
| 内部対策 | ・内部リンク(ページ同士をつなげるリンク)を設置する ・レスポンシブ対応(デバイスの画面サイズに応じたレイアウトやデザインの最適化)をする |
| 外部対策 | ・他社のWebサイトに自社コンテンツのリンクが掲載される「被リンク」を獲得する ・インターネット上に企業名やサイト名、サービス名などが掲載される「サイテーション」を増やす |
文章の読みやすさだけでなく、スマートフォン画面でも見やすいか、簡単に関連ページに遷移できるかなど、ページ全体の閲覧性や導線を考えることが大切です。
記事の順位を計測する
記事の公開後は、定期的にキーワードの順位を計測しましょう。すべての記事が上位表示されるわけではなく、記事によっては圏外になる場合もあります。
検索圏外の記事はほとんどアクセスされないため、定期的に順位を計測し、課題点を探すことが大切です。
リライト
記事の課題点をもとにリライトします。リライトとは、既存の記事を修正、アップデートすることです。競合やサジェストを分析しながら、記事の見出しを追加・削除したり、情報の鮮度を高めたりします。
上位表示されていないページを洗い出し、定期的にリライトしましょう。
施策をスムーズに進めるためのポイント
SEOコンテンツの施策をスムーズに進めるためのポイントについて紹介します。
制作ルールをマニュアル化する
コンテンツ制作を複数人で進める場合、文章トーン・構成・使用キーワードなどがバラつきやすくなります。そこで、コンテンツ制作ルールをマニュアル化することで、誰が担当しても一定の品質を保てるでしょう。
見出しの付け方や画像の使用方針、メタ情報の入力ルールなども明文化しておくと、工数削減にもつながります。
SEO施策の目的をKPIで可視化する
コンテンツSEOは長期的な施策であるため、KPI(重要業績評価指標)を明確に設定することが不可欠です。PV数、検索順位、CV数、直帰率、滞在時間など、目的に応じた指標を選びましょう。
チーム内で目標を共有して進捗を可視化することで、施策の精度を高めるだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。
一覧管理でテーマと進捗を一元化する
作成中や公開済みのコンテンツが増えると管理が煩雑になりやすいため、コンテンツ一覧シートの作成が有効です。
タイトル、URL、キーワード、担当者、進捗状況、更新日などを一覧で管理することで、作業の抜け漏れを防ぎ、運用の効率化が図れます。また、重複テーマの回避やメンテナンス時の指標整理にも役立ちます。
PDCAを回す機会を設ける
コンテンツSEOは一度作って終わりではなく、定期的な分析と改善を繰り返す仕組みづくりが成功のカギです。
分析結果をもとに改善案を話し合う場を月次や四半期単位で設け、PDCAサイクルを組織的に回しましょう。
数字だけでなくユーザーの行動傾向や検索意図も踏まえることで、コンテンツの精度と成果が向上していきます。
コンテンツSEOに対応するおすすめのCMS・オウンドメディア構築サービス
おすすめのCMS・オウンドメディア構築サービスを紹介します。
dino - 株式会社リボルバー

- 独自CMSで手軽にオウンドメディア構築
- ソーシャルメディアや外部広告との連携機能
- Web広告配信システム連携機能によるマネタイズ
dinoは、クラウドCMSやコンテンツ配信ネットワーク、ネイティブアドサーバーなどを一貫して提供するシステムです。
月額のサブスクリプション制なので、自前でサーバーを用意したり、CMSをインストールしたりといった手間は一切かかりません。セキュリティ対策や新機能追加のアップデートも自動な点も安心です。SNSや外部広告との連携による集客も実現できます。
ネイティブアドの掲載による広告収益、会員限定記事の課金ビジネス、EC連携の物販モデル、優良顧客を店舗へ誘導するO2Oなど、作成した記事のマネタイズ手段が豊富です。
コンテンツSEOに対応したWeb制作ソフトやCMSに興味がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
月間3,000CV!ボクシル編集長監修『コンテンツSEO完全ガイド』
効率的にリードを獲得したい・サービスのPRをしたい・SEOで検索上位を取りたい、、、といったご要望はありませんでしょうか。オウンドメディアを使ったコンテンツマーティングで効率的に見込み顧客を獲得することが可能ですが、ノウハウがないと何から手をつけて良いかわからないですよね。
「コンテンツSEO完全ガイド」ではコンテンツマーティング、SEO集客に関するポイントや手順について解説しています。
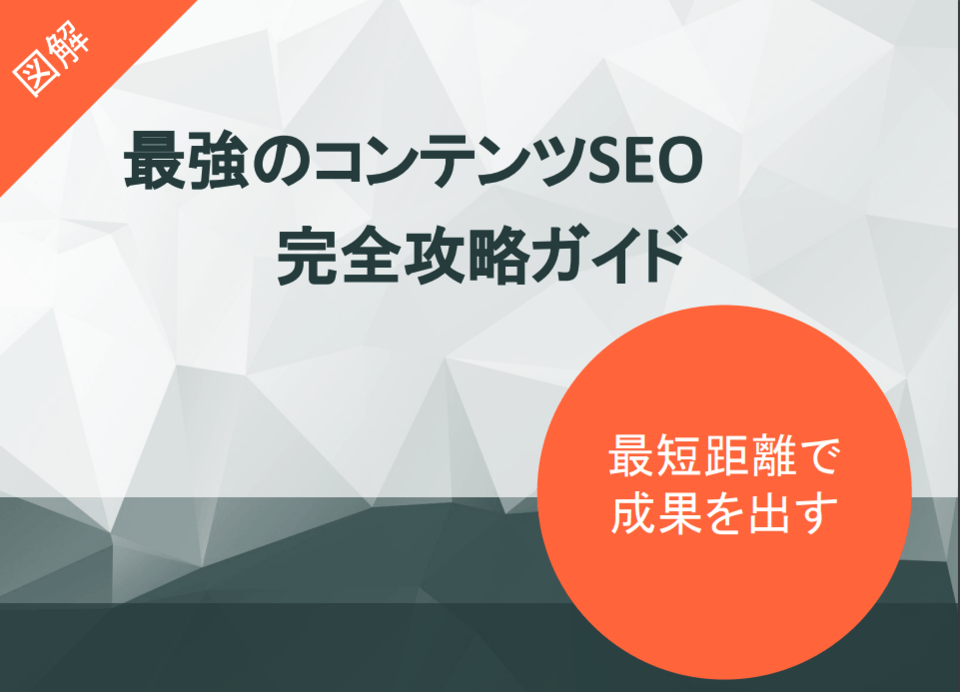
コンテンツSEOによって長期的な集客につなげよう
コンテンツSEOには、潜在層にアプローチできたり、Webサイトが資産化したりと、多くのメリットがあります。
ただし、成果が出るまでには時間がかかり、良質なコンテンツを作るためには、検索エンジンとユーザーの両方からの評価を意識した記事作成が必要です。
3C分析やキーワード選定など事前準備を入念に行ったうえで、ニーズに沿ったコンテンツを作成しましょう。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査