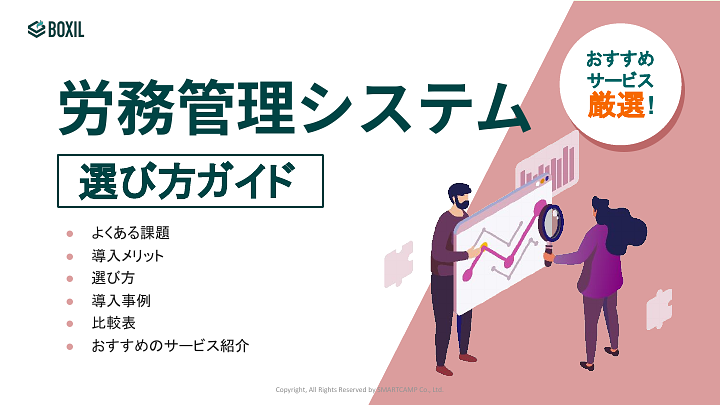労務業務を行う上で、このような課題を感じていませんか?
- 人事書類作成・確認・電子申請など労務に関する業務を効率化したい
- 住所変更や扶養変更を簡単に行いたい・ペーパーレス化したい
- データの可視化や分析で組織課題の洗い出しや改善を実現したい
これらの課題をお持ちの方は、労務管理システムの活用がおすすめです。
そこで「SaaS導入推進者が選ぶサイト第1位」のボクシルが、おすすめ労務管理システム11選を厳選しました。さらに、各サービスの機能・料金をまとめた『比較表』もプレゼント ! 労務管理システムが気になる方は、『比較表』を使って自社に合うサービスを探してみましょう。
労務管理システムとは
労務管理とは、就業規則や福利厚生の管理、給与計算を通じて、働きやすい環境を整える業務です。人事評価や人材の配置、採用を行う人事管理とあわせて「人事労務管理」と呼ぶこともあります。
労務管理システムとは、紙やエクセルで行っていた勤怠管理や給与計算などの労務管理業務をシステムで自動化し効率化するサービスです。勤務状況や就業規則に応じて書類を自動で作成できます。情報は一度入力すれば完了するものが多く、都度作成する必要はありません。
労務管理システムのタイプ
労務管理システムは、導入目的に応じて次の2つのタイプに分類できます。
| タイプ | 導入目的 | 内容 |
|---|---|---|
| タイプA (シリーズ連携タイプ) | 入社手続きや従業員情報の管理がしたい | まずは入社手続きなどの基本業務を効率化し、徐々にシステムでの対応範囲を広げたい企業 |
| タイプB (サービス単体タイプ) | 人事労務全般の作業を効率化させたい | 勤怠管理や給与計算などの人事労務全般の作業を効率化したい企業 |
自社に当てはまるタイプを確認したら、『比較表』で要件に合うサービスを探してみましょう。
\ 選定に便利な『比較表』はこちら ! /
労務管理システムの機能
労務管理システムの基本機能は次のとおりです。
- 入社・退社の手続き
- 従業員情報の一括管理
- 就業規則や福利厚生の管理
- 勤怠管理・給与計算の機能
労務管理システムの機能では、役所に提出する雇用保険や社会保険の資格取得届の書類作成、従業員のマイナンバーや住所などの情報管理、年末調整に必要な保険料控除申告書や源泉徴収票などの書類の作成と提出が行えます。
労務管理システムのメリット
労務管理システムを導入するメリットは次の3つです。
- 書類作成を効率化できる
- 従業員の情報を一元管理できる
- 役所への書類提出の手間を削減できる
労務管理システムを導入すると、従業員は空いている時間でパソコンやスマートフォンから必要なデータを入力できるため、労務管理の負担を軽減できます。労務担当に書類を提出する手間もかかりません。
労務管理システムの導入は、労務担当と従業員の双方にメリットがあります。
\ 各サービスの特徴・メリットはこちら /
労務管理システムの失敗しない選び方
労務管理システムの選び方で迷わないよう、自社に合ったサービスを探せる手順をまとめました。
1.必要な機能を洗い出す
労務管理システムを選ぶ際は、自社に必要な機能の要件を洗い出してから比較するのがおすすめです。以下のリストを使って洗い出しておきましょう。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 帳票の作成でミスが起きてるか確認する | 帳票作成でのミスが多い場合、社会保険手続きなどで必要な帳票を従業員情報を基にして自動作成してくれるサービスを検討しましょう。 |
| 行政手続についての申請・届出を出す機会があるか確認する | 行政手続きの申請や届出が多い場合は、電子申請への切り替えがおすすめです。総務省が運営する電子申請窓口「e-Gov」と連携対応しているサービスを検討しましょう。 |
| システム上で労務関連の承認・申請を行うことはあるか確認する | 有給や残業申請などのワークフロー管理などを行う場合は、対応した機能を搭載したサービスを検討しましょう。 |
| マイナンバーを管理する必要があるか確認する | 従業員情報の管理時にマイナンバー情報の管理も行っている場合は、マイナンバー提供依頼や従業員自身によるマイナンバー入力、本人確認書類のアップロードが可能なサービスを検討しましょう。 |
| 年末調整でミスや手戻りが発生したことがあるかを確認する | 年末調整でミスや手戻り、出し忘れが多発している場合は、一括メール送信や年末調整に関わるタスクをお知らせできたり、申請書の記入・回収をオンラインで行えるサービスを検討しましょう。 |
| 出勤やシフト、労働時間の管理方法を確認する | 出勤やシフト、労働時間の管理を紙やExcelで管理している場合は、勤怠管理の機能を搭載したサービスを検討しましょう。 |
| 自社の打刻方法を確認する | 紙やタイムカードで打刻している場合は、勤怠管理の機能を搭載したサービスを検討しましょう。 |
| 経費精算や交通費精算の方法を確認する | 手入力で計算している場合は、経費精算の機能を搭載したサービスを検討しましょう。ツール利用している場合は、連携対応しているか確認しておくとよいです。 |
2.社内で使用している勤怠管理システムや給与計算ソフトを調べる
労務管理システムは、勤怠管理システムや給与計算ソフトと連携しているサービスが多いです。自社ですでに導入しているサービスがある場合は、検討している労務管理システムと連携しているか確認しておきましょう。
サービスによってEXCEL・CSV読み込みやAPI連携など、連携方法は異なります。予め連携方法を調べておくとよいです。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 現在利用している労務管理関連のシステムを確認する | 給与計算ソフトや勤怠管理システムなど、労務管理と関連するシステムは、どのツールを使用しているか確認しましょう。 |
| 連携方法を確認する | EXCEL・CSV読み込みやAPI連携など、サービスによって連携の仕方は異なるので、予め連携方法を調べておきましょう。 |
3.予算を決める
労務管理システムの料金は1人あたり100〜800円です。機能の充実度によって料金が変わります。労務管理システムの導入に使える予算を確認しておきましょう。
※料金相場は本記事に掲載しているツールの料金を参考にしています。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 労務管理システムの導入に使用できる予算を確認する | 労務管理システムの料金相場を把握し、導入に使用できる予算を確認しましょう。 |
4.要件に合う企業へ資料請求する
これまで確認した内容を踏まえて、『比較表』で要件に合う労務管理システムを探しましょう。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 機能の要件を満たすサービスはあるか確認する | 各サービスの特徴や搭載機能を確認し、条件に合うシステムを探します。なければ必要な機能を見直しましょう。 |
| 連携の要件を満たすサービスはあるか確認する | 利用しているシステムと連携できるサービスを確認し、条件に合うシステムを探します。 |
| 予算内で導入できるか確認する | 機能、連携の要件を満たすツールの料金を確認し、条件に合うシステムを探します。予算を超えてしまう場合は、予算の調整か各種機能、連携の必要性を再度検討しましょう。 |
| 要件に合うサービスの資料請求をする | 各要件を満たすツールの口コミ評価の投稿と点数を確認し、要件に合うサービスの資料請求をしましょう。 |
| 試験導入するサービスを数社に絞り込む | 資料の内容で改めて要件と合っているのかを確認し、試験導入するサービスを数社に絞り込みましょう。 |
5.試験導入で社内評価を確認し、本導入するサービスを決める
絞り込んだサービスを試験導入し、実際の使用感を確かめてください。従業員からの評価も併せて確認し、本導入するサービスを選定しましょう。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 絞り込んだサービスを試験導入して使用感を確認する | 資料請求したサービスのトライアルに申し込み、実際に社内で使ってみましょう。 |
| 従業員からの評価は高いか確認する | 入社手続きやワークフロー申請は簡単にできたかをヒアリングしましょう。 |
| 本導入するツールを決める | 従業員の評価に問題がなければ公式サイトに問い合わせて導入手続きを進めましょう。 |
導入前に念入りな情報収集を!
日々の経済活動を行っていくうえで、定型化されたルーティンワークをこなすことは決して悪いことではありません。しかし、定型化された業務だからこそ効率化できる余地が存在し、それを実現することによって多くのリソースをコア業務に割り振るといった有効活用が可能となるのです。
なかでも定型業務が多くなりがちな労務では、書類手続きや給与計算等を効率化する労務管理システムの導入がとても有効です。ぜひこの機会に検討されることをオススメします。まずは、『比較表』を使って自社に合うサービスを探してみましょう。
各サービスの導入実績や特徴、よくある質問がまとまった資料は下記ボタンから無料でダウンロードできます。導入前の下調べにぜひお役立てください。
\ 社内提案・稟議にも使える『比較表』付き ! /