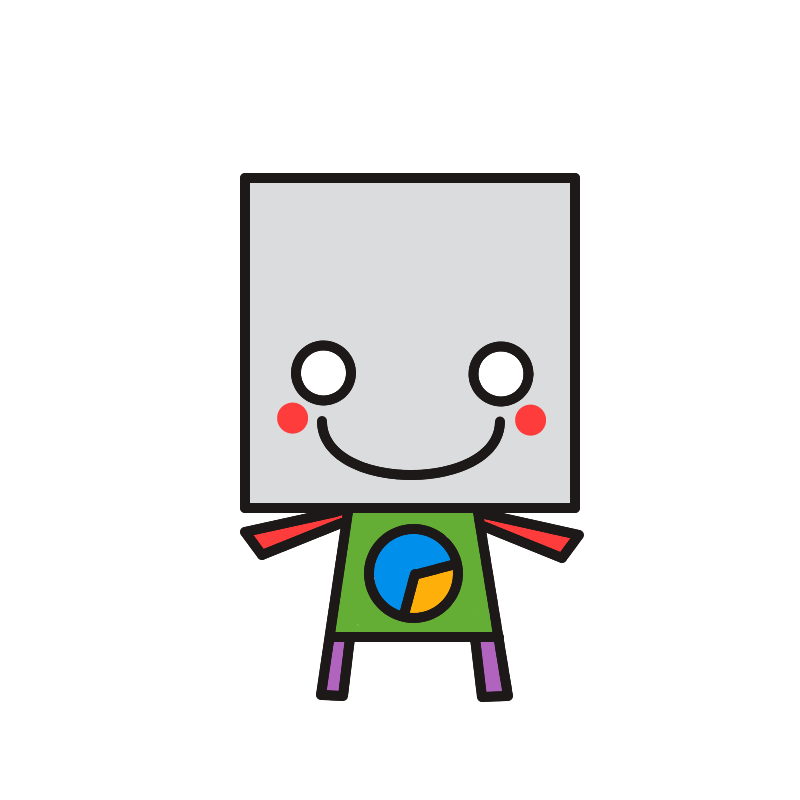チームビルディングとは?方法や目的、成功事例

目次を閉じる
チームビルディングとは
チームビルディング(Team Building)とは、日本語に翻訳すると「チームを構築する」という意味の言葉です。わかりやすく言えば、メンバーのスキルや能力を最大限に発揮する形で、チームを作り上げていく取り組みのことです。
チームを作る過程においては、仲間と連携して課題を克服したり、マネジメント能力を磨いたり、リーダーシップを育んだりします。このように経験を積むことにもなるため、チームビルディングは人材育成にも役立つと考えられているのです。社員や従業員の育成はもちろん、内定者の研修として活用されることもあります。
チームとグループの違い
チームは「少人数で連帯責任を果たしながら、共通の目標・目的を持って進んでいく集合体」のことです。チームの特徴は、共通の目的がある点です。たとえばスポーツチームのように、「試合に勝利する」「優勝する」といった共通の目標に対してメンバーが協同します。
一方、グループは「複数の人数で集まった集合体」のことです。共通の目標はなく、グループの存在目的もありません。
グループの状態だと、「誰が何をするか」といった役割も決まらず、ダラダラと時間を消費してしまいます。ビジネスの世界において時間を浪費するのは、経営的損失です。そのためチームビルディングのマネジメントを行い、グループをチーム化することが大切です。
チームビルディングの目的
チームビルディングの目的には、次の5つがあります。
- チームとしてのパフォーマンス向上
- チームとしてのマインドセットを育む
- チームとしてビジョンを持つ
- チームメンバーの関係性を強化
- 人材配置を適切に行う
チームとしてのパフォーマンス向上
チームビルディングを行うことで、チームとしてのパフォーマンスが上がります。
チームワークを形成するためには、メンバーが互いの長所や短所、価値観を理解しなければなりません。チームビルディングを通して相互理解を深めることで、個人の長所が生きる役割分担を実現できます。
またチームメンバーの関係性が良くなれば、チーム内の心理的安全性も高まります。心理的安全性が高まれば、益々活動しやすい環境になるでしょう。チームとしてのパフォーマンスが上がれば、業務効率の向上や生産性のアップが期待できます。
チームとしてのマインドセットを育む
マインドセットを目的にチームビルディングを行うこともあります。
たとえば、質よりスピードを優先したい企業文化においては、質にこだわる人材はチームワークを乱してしまうことがあります。一方、全メンバーの意識が揃っていれば、仕事をスムーズに進められます。
このように仕事で意識すべきマインドを醸成することもチームビルディングの目的の1つです。
チームとしてビジョンを持つ
チームビジョンの浸透もチームビルディングの目的の1つです。チームが機能するためには、メンバーの向かうべき方向性を一致させるのも必要なことです。
しかし普段の仕事では、短期的な視点に終始してしまいます。その結果、場当たり的に働く人材が増え、仕事の質が下がってしまうことも少なくありません。
もしチームビジョンがしっかりと浸透していれば、チームメンバーは指示がなくても自発的に行動できます。このように、チームビルディングを通して、自発的な人材を増やせます。
チームメンバーの関係性を強化
チームビルディングを通してメンバーが交流を行えば、自然とその関係性は強化できます。関係性が強化できればチームとしての結束力が上がり、共に課題を解決する意識で仕事に臨むようなるでしょう。これにより、それぞれのスキルや経験の相乗効果が期待できます。
またチーム力が上がり気軽にコミュニケーションができるようになれば、新たなアイディアも生まれやすくなります。
人材配置を適切に行う
チームビルディングを行っていく過程では、それぞれメンバーのスキルや経験、価値観がわかるようになります。これにより、チームとして実務を行う際にもそれぞれの作業を、最も適した人材が担当できるようになるでしょう。
またマネジメントする側としても、チームメンバーへの理解が進めば、人材配置が行いやすくなります。
チームビルディングのメリットや効果
チームビルディングを行うメリットや効果は、次の3つです。
- コミュニケーションの活性化
- モチベーションの向上
- 新しいアイデアやイノベーションの促進
コミュニケーションの活性化
チームビルディングを行うことで、チーム内のコミュニケーションを活性化できます。
チームで活動するにあたってコミュニケーションの量と質は、成果に影響を与える重要な要素です。とくに仕事に対する積極的なコミュニケーションは、チームメンバーに良い影響を与えます。会話頻度が増えれば、ノウハウや悩みを共有でき、PDCAのサイクルをより早く回すことも可能です。
チームビルディングを行うことで、コミュニケーションの質と量を改善し、チームの生産性を高められます。
モチベーションの向上
チームビルディングはモチベーションの向上にも役立ちます。モチベーションが高い状態をキープするためには、チームのビジョンやマインドの共有が欠かせません。
チームビルディングを行えば、関係性改善だけでなくビジョンやマインドの共有も可能です。また、チームビルディングの機会を定期的にマネジメントすることで、モチベーションが高い状態を維持できます。
新しいアイデアやイノベーションの促進
チームビルディングを通して新しいアイデアを育んだり、イノベーションを促進したり、組織に新しい風を吹き込むことも可能です。
たとえば、グループワークを通してアイデア出しを行えば、課題をクリアするためのさまざまなアイデアを集められます。またそれらのアイデアをチームメンバーと検討する中で、一人では思いつけないアイデアが出てくることもあります。
イノベーションには、小さなアイデアの実践が欠かせません。アイデアを発見し、育み、イノベーションが起きる組織に変化させられることも、チームビルディングを行うメリットです。
チームビルディングの形成プロセス「タックマンモデル」
チームビルディングを提唱したのは、心理学者でもあったタックマンです。タックマンモデルでは、次の5つのプロセスでチームが形成されるとされています。
- 形成期
- 混乱期
- 統一期
- 機能期
- 散会期
チームがゴールに向かうには段階を進むごとにチームが結束することが大切です。それぞれのプロセスについて具体的にみていきましょう。
形成期
形成期とは、チームが形成されて間もないタイミングのことを指します。
メンバーは、互いについて知らず、一人ひとりが独立しています。目標やビジョンも模索中なことが多く、すべてのメンバーが手探り状態です。
方向性について上から与えられた場合でも、メンバーによって目標に対する認識や意味付けが異なり、実質的に何も決まっておらず、何もわからない状態と言えます。
混乱期
混乱期は、メンバー間に対立が生じるタイミングです。
目標やあり方、仕事の進め方についてメンバー間で意見を交わすなかで、互いの違いが明らかになります。このタイミングでは、意見を出しつつも互いを尊重し合うこと、理解し合うことが大切です。
お互いの理解が深まれば、チーム内の関係性が改善され、統一期に移行できます。
統一期
統一期は、メンバーの足並みが揃い始めた状態です。共通の目標やビジョンを共有できており、メンバー同士の強みや弱みも把握できています。
統一期に入れば、チームにおける問題も自然に解消できるようになります。そのため、チームを成功させるためには、混乱期をいち早く乗り越え、統一期に入れるよう工夫するのが大切です。また、統一期で十分にコミュニケーションが取れていなければ、混乱状態に戻ってしまうこともあるため注意が必要です。
機能期
機能期とは、チームの結束力が高まっている状態のことです。メンバーが互いの強みだけでなく、価値観を知り、尊重し合うことで、ムダなストレスなく力を発揮できます。
機能期に入るとメンバーの主体性が高まり、お互いのフォローもスムーズに行われます。機能期はチームのパフォーマンスが最も高い状態なので、機能期を維持できるよう工夫するのが大切です。
散会期
散会期はチームが解体されるタイミングのことです。このタイミングでは、チームで形成した関係性を次に生かせるように計らうのが大切です。
たとえば、学びを言語化しシェアすることで、各メンバーが次のチームで反省を活かせます。また関係性をキープできるような仕組みを整えておくことで、解散後も互いをリソースとして活用できます。
チームビルディングを行う際のポイント
スムーズなチームビルディングを行ううえで、大切なポイントは次の4つです。
- チーム目標を明確化する
- 十分にコミュニケーションをとる
- 多様な価値観を受け入れる
- メンバーの役割を明確にする
チーム目標を明確化する
チームビルディングを行う目的や、どのような効果を得たいかをチームで共有しなければ、メンバーは「遊んでいるだけ」という印象を持ちます。モチベーションも維持しにくく、チームワークも発揮しにくいでしょう。
チームビルディングを実施する前には、なぜこれを行うのか、そして目指すべき目標がどこにあるかをメンバーに伝え、共有することが大切です。また、目標を伝えることでメンバーの自主的な行動も促せます。
十分にコミュニケーションをとる
チームで活動するときは、コミュニケーションを十分に取ることを心がけましょう。とくにチームでの活動が始まったタイミングでは、メンバー間に信頼関係が無く、衝突が発生しやすい状態です。
コミュニケーションをしっかりと取れるようになれば、ムダな衝突は起きず、建設的な議論ができるようになります。そのためコミュニケーションを積極的に行うことで信頼関係を築き、維持することが大切です。
多様な価値観を受け入れる
チームメンバーが力を発揮するためには、お互いの価値観を受け入れ合うことが大切です。チームが機能するためには、多様な価値観を受け入れ、認め合うことが欠かせません。そのためにも業務報告だけでなく、普段のちょっとした会話からお互いの価値観を理解するよう努めましょう。
もちろん、会社によって方針や大切にしてほしいマインドは異なります。しかし、価値観が固定化されてしまうと新しいアイデアが生まれず膠着状態に陥ってしまいます。それぞれの価値観を受け入れる柔軟な姿勢を持つことを心がけましょう。
メンバーの役割を明確にする
メンバーの役割を明確にすることもチームビルディングにおいて大切なポイントの一つです。
とくに重要なのは、業務処理範囲に対する役割だけでなく、チームワークにおける役割を設けることです。たとえば、ムードメーカーや批判者など、さまざまな役割をもった方がチームにいると、チームで動く価値は高まります。
また役割は、チームでの活動が始まってしばらくしてから、変更が必要になる可能性があることも覚えておきましょう。「当初はムードメーカーだと思っていた人が、実際には無理をしていた」といったような課題が出てくることがあるためです。
チームビルディングを行う際の注意点
チームビルディングを行う際は、チーム編成と、メンバーの気持ちに注意することが大切です。まず、チームビルディングは関係性の強化が目的ですが、チーム編成を適当にすると逆効果になる可能性があります。
2チームに分ける方法も、くじ引きやじゃんけんなどランダムに行うのではなく、それぞれのスキルや能力、そして関係性を考えたうえで組んでください。
また後程紹介しますが、チームビルディングにはアクティビティやスポーツなどを活用する方法もあります。しかし人によって運動が苦手で、不快感や恥ずかしさを感じる可能性もあります。
くわえて、そもそもゲームやイベントなど、実務と関係ない活動に参加すること自体を好まない人もいるでしょう。そのため、事前にニーズを調査したうえで一定の配慮を行うことが大切です。
チームビルディングの方法・やり方
チームビルディングのメリットやポイントがわかっても、実際には何をするのか、どのようなやり方があるかわからない方も多いでしょう。そこで次にチームビルディングの方法について、それぞれ研修に使えるよう具体的なルールややり方とともに紹介。
大まかに「ゲーム・ワークショップ」「アイスブレイク」「オンライン形式」「アクティビティ・イベント」「スポーツ・運動」の5つの項目にわけて紹介します。予算をかけずに無料でできるものや、短時間で簡単にできるものも多くあるため、ぜひ参考にしてください。
ゲーム・ワークショップ
ゲーム・ワークショップ形式のチームビルディングは種類が豊富で、5段階プロセスのどの時期にも対応できます。まずは、おすすめの3つについて紹介します。
THE商社(カードゲーム)
株式会社HEART QUAKEが発売している、チームビルディング用のカードゲームです。1グループ3~6名のチーム戦で、ビジネスカード、資源カード、資金の3つを使って事業の立ち上げを行います。ほかのグループと交渉を行っていき、最終的に利益と事業の数が多いグループの勝ちです。
「計画タイム」「行動タイム」「決算タイム」の3つの時間があり、戦略を練ることや役割分担を行うことで組織運営が実体験できます。
NASAゲーム
「混乱期」におすすめのゲーム。「宇宙船の故障で不時着した宇宙飛行士が、約320km離れた母船にたどり着くため、残った15のアイテムの中から重要なアイテムを見極める」というルールのゲームです。アイテムは次のようなものが、15枚のカードに書かれています。
- 宇宙食
- 酸素ボンベ(45kg)2本
- ナイロン製のロープ(15m)
- 粉ミルク(1箱)
- 水(19L) など
はじめに5~10分程度個人でアイテムを優先度の高い順番に並べ、次にグループで15~20分程度話し合い、1つの回答を出して発表します。その後NASAによる模範解答と比較して点数を付け、最も模範解答に近いグループが勝ちとなります。
大切なのは勝つことではなく、意見の異なるメンバーの考え方を理解することです。ゲームの後に振り返りを行うことで、協調的に問題解決を行う重要性を学びます。
地図ゲーム
こちらも混乱期におすすめのゲームで、地図を言葉だけで伝えてどれだけ正確に再現できるかを競います。ルールとしては、まず4~5人1グループとなり、その中の1人が書記、書記以外の全員が伝達者となります。
伝達者は順番を決めて、1人ずつ遠く離れた場所に貼られた地図を90秒間で記憶。伝達者は覚えた情報を言葉だけで書記に伝え、書記はペンと紙を使って再現します。実際の地図の形に最も近いグループの勝ちです。
地図は見るポイントが多いため、作戦タイムで誰がどこを担当するかしっかり話し合うことが大切。このゲームでは、相手の価値観や、よりよい伝え方を考えるなかで相互理解が深められます。
アイスブレイク
アイスブレイクとは、研修を行う前に行う簡単なゲームのこと。メンバーの緊張をほぐす効果があることから「形成期」におすすめで、どれも無料で簡単に行えます。ではおすすめのゲームを4つ紹介します。
他己紹介
グループ内で2人1組になり、相手の紹介を行うゲームです。まず1人1~2分で、互いに名前や出身地など、あらかじめ決められた項目のとおりに自己紹介を行います。自己紹介が終わった後は、グループメンバーに向けてそれぞれパートナーについて紹介します。
ニックネームや、24時間以内に起こった幸せな出来事などを項目に盛り込むと、盛り上がります。自己紹介の代わりに行うと相手に対する理解が深まり、コミュニケーションも活発になるでしょう。
ウソ、ホント?(人狼ゲーム)
自己紹介の中にウソのの情報を混ぜて、ほかのメンバーがそれを見破る簡易的な人狼ゲームです。自分のことに関して4つ箇条書きを行い、その中に1つウソの情報を入れて、自己紹介します。
メンバーはどれがウソの情報なのかをあてます。通常の人狼ゲームよりも簡単かつ短時間ででき、相手に対する理解を深められるでしょう。意外な回答があれば、よりコミュニケーションも活発化します。
共通点探しゲーム
自己紹介を行いながら、グループメンバーの共通点を探すゲームです。2~5人1グループでそれぞれに自己紹介を行います。その後メンバー同士で質問を行い、グループメンバーにどのような共通点があるかを探します。
最後に各グループの共通点を発表し終了です。時間制限を設ければよりゲーム性が高められます。通常の自己紹介よりも相手を深堀りしていくので相互理解が深められ、共通点が見つかれば一体感も感じられるでしょう。
質問ゲーム
短時間でできる限り相手のことを知るゲームです。2人1組のペアをつくり、1~3分の時間制限のなかで簡単な質問を行い、どれだけの質問に答えられたかを競います。最も多く答えられたペアの勝ちです。
相手に対する理解を深められるのはもちろん、質問する側は質問力も鍛えられるでしょう。「統一期」「機能期」のほか、「形成期」にもおすすめです。
オンライン形式
2020年に新型コロナウイルス感染症が流行して以降、テレワークで業務を行う企業も大幅に増えました。そこで次に、ZoomやGoogle Meethingを使ってオンラインでできるワークショップ・ゲームについて紹介します。
謎解き
近年オンラインでできる謎解きゲームが増えており、これを研修に活用できます。たとえば株式会社IKUSAが提供する「リモ謎」は、リモートワークでもチームビルディングができる謎解き脱出ゲームです。
また「マーダーミステリー」を研修に使うのもおすすめ。「マーダーミステリー」とは、メンバーが架空の事件に巻き込まれた登場人物になりきり、謎解きをするゲーム。パッケージとして販売されているものもありますが、Web上で無料公開されているものも多く、画面共有やチャットツールを使えばオンラインでも実施できます。
もちろん謎解き・脱出ゲームは対面式で行うことも可能。対面のみのものでも、株式会社HEART QUAKEの「消えた提案書の謎」、会議室からの脱出を目指す株式会社SCRAPの「リアル脱出ゲーム研修&懇親会」などがあります。
アクティビティ・イベント
実際に体を動かす体験型のアクティビティやイベントは「混乱期」「統一期」「機能期」におすすめ。そこで次に人気のチームビルディングアクティビティを紹介します。
マシュマロ・チャレンジ
マシュマロ・チャレンジは、乾燥パスタや紐、テープ、マシュマロを使って自立可能なタワーをつくるゲームです。4人1グループで、できるだけ高いタワーをつくり、最も高いタワーをつくれたグループの勝ちです。
共通の目標を目指すなかで、役割分担やコミュニケーションの重要性が学べます。「形成期」におすすめのゲームです。
レゴ シリアスプレイ
NASAやグーグルでも採用されている、レゴブロックを使ったワークショップです。はじめに「お題」が提示され、そのお題に基づいてレゴブロックで作品作りを行います。
次にグループのほかメンバーに対し、作品を通して自身のお題に対する考えや想いについて発表します。最後にグループ内から「ここはなぜ黄色いんですか?」といった質問を受け、これに答えていくことで作品の意味を深く掘り下げていきます。
これを半日~1日程度繰り返すことで、相互理解と自己理解を促進できます。「形成期」「混乱期」におすすめのワークショップです。
スポーツ・運動
チームビルディングは、スポーツを活用することでも構築できます。おすすめのスポーツは次の2つです。
ブラインドサッカー
パラリンピックにも採用されているパラスポーツで、目隠しをした状態でサッカーを行います。ボールは転がると音が鳴り、これを頼りに視覚以外の感覚を研ぎ澄ましてゴールを狙います。
目が見えないことから、通常のサッカーよりもしっかりとコミュニケーションを取らなければならないため、信頼関係を深められるでしょう。「機能期」におすすめのスポーツです。
カーリング
北海道や長野県などで盛んなスポーツで、オリンピックでも注目を集めました。ストーンを交互に投げ、最も円の真ん中に近い場所に自身のグループのストーンを置いたチームの勝ちです。
カーリングは4人で1つのショットを決めるもので、ミスが出てもチームのコミュニケーションで最善の結果が出せます。他の競技以上にチームワークとコミュニケーションスキルが求められるため、「機能期」におすすめのスポーツです。
チームビルディングの成功事例
社員旅行は昔から日本で行われてきたチームビルディングの方法です。しかし最近では、新興のIT企業によって、新しいチームビルディング手法が続々と開発されています。「メルカリ」「サイボウズ」「グーグル」の成功事例を見てみましょう。
メルカリ
メルカリは、多国籍人材を採用している背景から、チームビルディングを重視している会社の1つです。
メルカリでは異文化コミュニケーション施策として「Intercultural Team-building(IBT)」を導入しています。
IBTの特徴は、「チームビルディングであること」「参加するチームにあわせてワークショップの内容が変わること」、そして「参加するまで誰もワークショップの内容を知らないこと」です。
ワークショップの開始時点では、誰もワークシップの内容を知らないため、白紙の状態から協同する機会を体験できます。メルカリでは、このような経験を通して、「今後チームとしてどのようにして活動したいのか」を感じられるようなワークショップが行われています。
サイボウズ
チャットワークやその他SaaSのアプリケーションを開発・提供しているサイボウズでは、チームビルディングのための研修・ワークショップを実施しています。
サイボウズの理念は、「チームワークあふれる社会を創る」こと。その目的のために、チームワークに関するさまざまな文献や論文を研究し、独自のノウハウやフレームワークを作っています。
たとえば、「サイボウズの企業研修プログラム」は、サイボウズは企業のチームワーク向上のために作成したプログラムの1つです。
グーグル
グーグルは、日常的にできるチームビルディングへ積極的に取り組んでいます。さまざまな角度からチームビルディングについて研究し、成果の一部を「「効果的なチームとは何か」を知る」にて公開しています。
グーグルの調査にもとづくと、良いチームをつくるためには「心理的安全性」「相互信頼」「構造と明確さ」「仕事の意味」「インパクト」の5つの要素が大切です。
また、チームの取り組みを共有する際は「共通認識を持つ」「チームの力学について話し合う場を作る」「チームの強化と改善にリーダーを巻き込む」の3ステップが必要だとも言われています。
チームビルディングに役立つ人気の本
チームビルディングについて書かれた本はさまざまあります。それらチームビルディングに関する本の中から、人気のある代表的な4冊を紹介します。
ほとんどがIT企業におけるチームビルディングの実例をもとにした本ですが、書かれている内容は、どのような業種にも応用可能です。
『Team Geek』
『Team Geek』は、「エンジニアが他人とうまく仕事をするにはどうすれば良いのか」について書かれた本です。
グーグルのプログラマーからリーダーになった著者の講演を書籍化した本なので、翻訳本でありながら読みやすいのが特徴です。
また、エンジニアのチームビルディングについて書かれた本ではありますが、理念や手法は、普遍的に通用します。そのため、非IT企業でも充分に参考にできます。
『あなたのチームは、機能してますか?』
『あなたのチームは、機能してますか?』は、小説の形式でチームビルディングについて学べる書籍です。物語は、「順風満帆なベンチャー企業が2年後に業績不振となり、取締役会が37歳のCEOを解雇。代わりにブルーカラー企業出身の57歳の女性がやってきた」という設定でスタートします。
この本の特徴は、チームビルディングの天才である彼女の手法を、物語形式で勉強できる点です。物語形式なので、チームワークに関する専門知識を気軽に学べます。
『チームのことだけ、考えた。』
『チームのことだけ、考えた。』は、サイボウズの代表取締役である青野氏がチームワーク・ビルディングについて書いた本です。
現在こそ優れたチームワークを持っていると言われているサイボウズですが、青野氏が社長に就任した当初は「社員の離職率28%」と極めて厳しい状況でした。
原因の1つは労働環境で、青野氏がどのようにこの状況を改善し、現在のサイボウズをどのように作り上げたのかが書かれています。
『宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話』
『宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話』は、約20年にわたって3,000回を超えるチームビルディングをしてきた著者、長尾彰による「チームビルディング」の教科書です。
主人公が宇宙飛行士を目指す人気漫画『宇宙兄弟』を題材にしていることがポイント。主人公たちやチームの成長ストーリーを分析し、自分の得意なスタイルで今いる仲間をリードする方法が学べます。
チームリーダー育成に必要な研修・セミナーサービス
プロジェクトを成功に導き、新しいリーダーを育成できる研修プログラムやセミナーサービスを紹介します。
- 評価制度の導入をトータルサポート
- 運用サポートを通してノウハウ蓄積
- 各段階のサポート内容が充実
あしたのチームは、人事評価制度の導入から運用までをトータルサポートするサービスです。評価制度の運用ルール考察や目標シート案作成などのスタートアップから、各種コンピテンシー作成や評価ランク決定などの制度構築、社員と評価者への説明会といった導入から運用までをサポートします。
サポートを受けながらノウハウを蓄積し、自社運用を目指せます。人事評価制度をはじめて導入・運用する企業でも安心して利用できるのが魅力です。
Schoo for Business - 株式会社Schoo
- 7,000本以上の研修動画が1,500円/IDで見放題※1
- 研修動画は毎月50本ペースで追加される※2
- 生放送ならコミュニケーションしながら学習
Schoo for Businessは、最先端のITスキルからビジネススキルまで幅広く学べるオンライン研修サービスです。
生放送授業では、講師に質問したり、ほかの受講者と解釈を確認しあったりできます。疑問や不安をその場で解決できるため、単なる映像授業より学習内容を充実させられます。また、個人の学習傾向を分析し興味や関心をランキング形式で表示する機能も搭載。一人ひとりの興味や関心を明らかにすることで、個人の強みを活かした組織作りに役立てられます。
※1 出典:Schoo for Business「法人向けサービス TOPページ」(2022年10月27日閲覧)
※2 出典:Schoo for Business「コンテンツの特長」(2022年10月27日閲覧)
- 組織心理学をベースとした参加型オンラインイベントを開催
- 参加者満足度97%※、導入実績500社以上※
- オンラインと対面を組み合わせた開催に対応
バヅクリは、オンラインイベントを通じ社員の関係構築を支援するサービスです。学びと遊びの要素をベースに考案された100種類以上※のプログラムがあり、体験を通じた関係構築をサポートしてくれます。
ワークショップやレクリエーション、チームビルディング向け研修を日程調整と企画を選ぶだけで、当日の運営から実施後の報告、結果をもとにした企画提案まで一括代行してくれます。
※バヅクリ公式サイトより(2022年10月27日閲覧)
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査