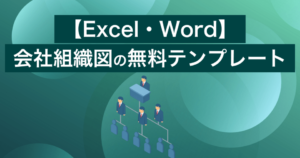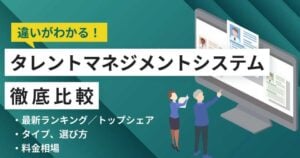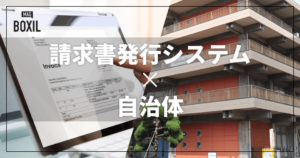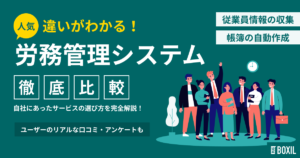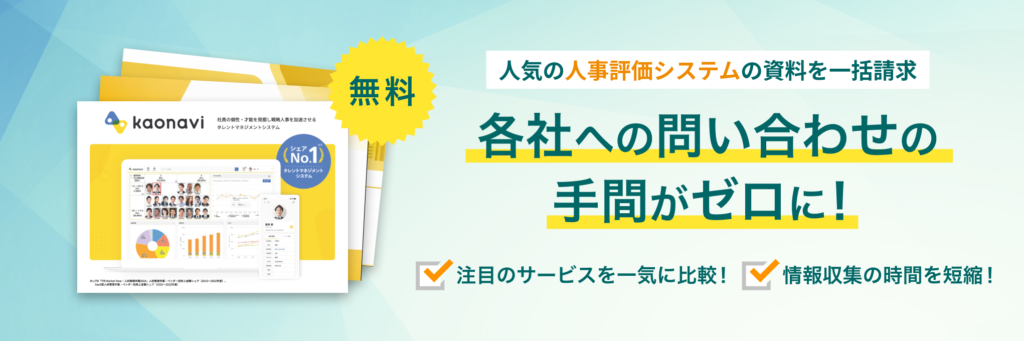タレントマネジメントシステムには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
⇒
【料金・機能比較表つき】タレントマネジメントシステムの資料をダウンロードする(無料)
これまで、人材マネジメントに関してさまざまな手法が提唱、実践されてきました。近年は人と組織のパフォーマンスを最大化するための、パフォーマンスマネジメントの概念が世界的に注目されていることをご存じでしょうか?
これまでの 目標管理制度(MBO) や、 OKR(Objective & Key Result) といった手法に取り組む企業が多くあります。一方で、組織全体の目標と従業員の目標をリンクさせ、事業の新しい成果を生み出すために一人ひとりのパフォーマンスに注目する企業も増えています。
パフォーマンスマネジメントとは
パフォーマンスマネジメントとは、従業員一人ひとりの能力やモチベーションを向上させ、成果創出にいたるまでの一連のマネジメントを継続的に行う手法のことです。
従業員の成果を明確に定義し、それが創出されるまでのプロセスを管理し、改善するといった工程を繰り返します。
従業員のパフォーマンスについて、目標達成につなげるにはどのような行動を取ればよいのかをマネジャーが一緒に考え、具体的なアクションの成果について評価やフィードバックを行います。
管理者と従業員のコミュニケーションを密にして、問題解決や目標達成をサポートしながら組織全体の能力と生産性を高めていくわけです。
パフォーマンスマネジメントの歴史
もともとパフォーマンスマネジメントの概念は、組織の従業員がみずから立てた目標を実際の結果に結びつけるための人材マネジメントの手法として、アメリカのコンサルタントによって提唱されたものでした。
従業員一人ひとりの仕事のパフォーマンスに注目し、具体的なアクションがどれほどの成果に結びついているかを計測、フィードバックします。それによって、チーム内において望ましい行動を増やしていくアプローチとして紹介されました。
これが各国の企業に受け入れられ、生産性向上が重要視されるようになってきた日本でも注目されはじめ、これまでの単純な目標管理の手法に代わる新しい人材マネジメント手法として広がってきています。
パフォーマンスマネジメントが必要とされる理由
日本でこういった従業員のパフォーマンスに注目する管理手法が必要とされるのは、長引く不況や人材不足による業績の低迷が背景として挙げられるでしょう。
とくに少子高齢化に起因する人材不足のなか、刻一刻と変化するビジネス環境についていくためには、既存の人材の生産性を向上させるしか方法がありません。
また、柔軟な対応が求められるビジネス環境では、当初の計画に固執するよりも、日々移り変わる顧客のニーズに対応する力が求められます。
そうした厳しい環境のなかで、組織としてどのようなアクションを取るのが望ましいかを明らかにし、それを従業員の個人的な目標とリンクさせることで、組織全体の生産性を向上させようと考える企業が増えてきました。
パフォーマンスマネジメントとMBOの違い
人材マネジメントの手法として、パフォーマンスマネジメントの他に「MBO(目標管理制度)」があります。
MBOとは、社員が主体となり目標を定め、進捗や達成度によって評価を行うマネジメント手法です。目標設定・行動・結果・評価を1年の長期サイクルで運用します。
MBOとパフォーマンスマネジメントには共通する点もあるものの、両者には「重視する点」と「フィードバック頻度」に明確な違いがあります。
MBOは過去の実績を重視して評価する手法ですが、パフォーマンスマネジメントは未来を重視して、短期的なスパンでフィードバックを行う手法です。つまり、過去の行動ではなく、今後どのように業務に取り組むかを重視して短いスパンで頻繁にフィードバックすることで成長を促す、といった点でMBOとは異なります。
旧来のマネジメントの問題点
旧来のマネジメント手法は、上述のように、組織の目標を定めて一定期間ごとに達成度合いを評価するMBOや、OKR(Objective & Key Result)といった手法が一般的でした。
これらの手法も効果的ではありますが、変化の激しいビジネス環境においては、半年あるいは1年前に立てた目標と実態にズレが生じてしまうこともあります。また、当初の目標が必ずしも組織全体にとって望ましいものではないといった、弊害が指摘されるようになってきました。
詳しくは後述しますが、組織としての柔軟性の欠如や、評価自体が目的化してしまうなどの問題点が浮き彫りになってきたわけです。
パフォーマンスマネジメントの特徴
パフォーマンスマネジメントの特徴として、次の4つが挙げられます。
- 未来に向けたアドバイスを行う
- 部下の強みを重視する
- 上司と部下のコミュニケーションが多い
- リアルタイムのフィードバックを行う
未来に向けたアドバイスを行う
パフォーマンスマネジメントでは、過去を評価せず、「今後どうすべきか」を重視して未来につながる話し合いを行うのが大きな特徴です。
上司と部下で話し合いをする際には、過去の振り返りをしたり過去の失敗を責めたりするのではなく、今後取るべき行動や目標設定などに多くの時間を割きます。
過去の失敗について話す場合でも、「どのように改善して今後に活かすか」「目標を達成するために今後どのように行動するか」など未来の目標達成に向けたコーチングを行うためです。
それにより、部下は仕事へのモチベーションを高め、業務に対する前向きな姿勢を維持できるようになるでしょう。
部下の強みを重視する
部下個人の強みを重視することも、パフォーマンスマネジメントの特徴です。
たとえば、周囲からは強みと見られていることでも、本人はそれを当たり前に行っているため強みだと認識しておらず、十分に活かせていないことは多くあります。
しかし、パフォーマンスマネジメントでは、強みを特定し活かせるよう促すことが目的のひとつです。「自身の強みに気づいていない」「強みがない」などと思っている部下が、強みを把握して発揮できるように導くため、部下のモチベーションアップ、さらには業績アップなどの効果につながります。
ただし、適切なフィードバックを行うためには、部下の特性を理解することが必要です。部下への理解が深まらないままフィードバックを行うと、逆にモチベーション低下にもつながりかねないため注意しましょう。
上司と部下のコミュニケーションが多い
パフォーマンスマネジメントでは上司と部下の対話を重視しており、短いスパンでフィードバックを行うため上司・部下のコミュニケーションが増えることも特徴です。
パフォーマンスマネジメントにおいては、定期的に上司と部下が面談を行ってコミュニケーションを取り、部下と対話しながら目標設定を行います。
上司が一方的に部下へ自身の考えや目標を押しつけるのではなく、両者で話し合いながら目標を決め、目標達成の進捗について定期的にフィードバックやアドバイスを行います。定期的に上司と部下が面談を行い、業務の進捗を確認することで、良好な人間関係を構築でき、お互いへの信頼感を高められるでしょう。
リアルタイムのフィードバックを行う
パフォーマンスマネジメントでは、1週間~数か月といった短いサイクルでリアルタイムにフィードバックを行います。そのため、年に1回のような長期的なスパンでフィードバックを行う場合とは異なり、部下は行動や結果への記憶が薄れないうちにフィードバックを受けられるため、高い納得度を与えられることも特徴です。
また、短いスパンでコミュニケーションを取り、目標設定から進捗確認や評価・フィードバックのサイクルをリアルタイムで行うため、上司は部下の行動を確認しながら目標修正や適切なコーチングを行えます。
部下にとっても、状況にあわせて目標の再設定やアクションプランの変更などを行うことで、細かな軌道修正をしながら成長度を高められます。
パフォーマンスマネジメントのメリット
パフォーマンスマネジメントを導入するメリットとして、次の3つが挙げられます。
- エンゲージメントの向上
- 部下の成長を促進できる
- 部下の主体性を育てられる
エンゲージメントの向上
パフォーマンスマネジメントの導入により、社員エンゲージメントの向上が可能です。
昨今の労働人口不足により問題となりがちな優秀な人材の流出や人材不足などの課題解決には、従業員エンゲージメント向上への取り組みは不可欠です。
パフォーマンスマネジメントでは、上司が部下の現状や強みを把握したうえで、部下と話し合って達成可能な目標を設定します。上司が頻繁にコミュニケーションを取り、部下の行動をサポートするため、部下は安心感をもって業務を行えるはずです。
そのため、部下の仕事へのモチベーションアップやパフォーマンス向上、エンゲージメント向上につながります。
組織への愛着や貢献意欲が高まれば、離職による人材流出を回避できます。さらに、組織全体の生産性向上や採用コスト削減などの効果が期待できるでしょう。
部下の成長を促進できる
パフォーマンスマネジメントは、部下の強みを深く把握したうえでリアルタイムのフィードバックを行うため、個人の成長を促進できることもメリットです。
上司が部下と面談を行う際には、多くのコミュニケーションを取りながら部下の特性や強みを把握し、それを活かすよう指導します。そのため、部下は自身も気づいていなかった強みを把握できます。さらに、上司から的確なアドバイスを受けられ、個人の成長や組織の成果を最大化させられるでしょう。
また、1年ごとのような長いスパンではなく、1週間から数か月の短いスパンでフィードバックを受けるため、スムーズに軌道修正を行えるようになりよりよい成果へとつなげられます。
部下の主体性を育てられる
パフォーマンスマネジメントの導入により、部下の自主性を育てられるといったメリットもあります。
パフォーマンスマネジメントでは、上司と部下が話し合いを通じて目標設定を行うのが大きな特徴です。つまり、上司からの一方的な指示・指導ではなく、部下自身の意見や強みを尊重して目標設定するため、部下自身の主体的な行動を促します。
それにより、部下は業務に対して前向きな姿勢で、責任感や当事者意識をもって取り組めるようになるでしょう。
部下に主体性がかけていると、上司は部下に都度指示を出す必要があり、上司の業務負担が増えてしまいます。しかし、パフォーマンスマネジメントで部下自身がみずから考え課題や問題解決できるようになれば、組織全体の生産性向上につながります。
パフォーマンスマネジメントの役割
人材不足の課題を解決できるパフォーマンスマネジメントには、次の3つの役割があります。
- 環境整備や人材育成につながる
- 組織内の偏った目標設定を回避する
- 目標設定をサポートする
環境整備や人材育成につながる
パフォーマンスマネジメントの役割には、人材育成と環境整備があります。パフォーマンスマネジメントは、従業員一人ひとりの成果を最大限に引き出すことを目的とした手法です。
自分で立てた目標を達成するために行動を起こし、成果や結果について分析して仕事への意欲を高めていきます。
しかし、すべての従業員がはじめから自主的に目標を立てて行動できるわけではありません。パフォーマンスマネジメントを導入するにあたり、従業員が自主的に取り組めるように社内でサポートできる環境を整える必要があります。
組織内の偏った目標設定を回避する
パフォーマンスマネジメントでは、従業員が立てた目標の進捗状況を、上長と人事の担当者で確認することが理想です。
フィードバックする際に人事部の担当者が参加することで、部署内の偏った目標設定を回避できるメリットがあります。
また、人事部の担当者は企業視点で意見を伝えられるので、従業員の目標が企業の方向性と大きく外れることもありません。
目標設定をサポートする
パフォーマンスマネジメントを実施するにあたって、従業員一人ひとりのサポートも欠かせません。思うように目標を達成できない従業員もいます。
能力を存分に発揮して成果や結果を出すには、直属の上司や人事部の担当者が親身にサポートすることが大切です。
また、コーチング手法を活かして従業員のよき相談相手になれれば、パフォーマンスマネジメントの効果をより高められます。
パフォーマンスマネジメントの進め方
パフォーマンスマネジメントの概要について説明したところで、パフォーマンスマネジメントの具体的な進め方について説明します。一般的に、次のプロセスにしたがって実行されることが多いようです。
STEP1.業務の進行状況を詳細に把握する
まず、現在の業務の進行状況を知ることで、従業員一人ひとりが目指すべき方向を明確にします。
個人の目標とチーム全体の目的・目標との整合性を取るためには、何よりも個人の現在の立ち位置を確認しなければなりません。それによって、どういう基準でパフォーマンスを測定すべきかが明らかになります。
STEP2.チーム全体の目標を明確にする
続いて、チームとして個人が期待される役割や目標を明確にし、従業員がお互いどう支援し合うのかを確認します。
パフォーマンスマネジメントでは従業員と管理者の密なコミュニケーションとフィードバックが肝となるため、どのような基準で何が評価の対象となるのかを双方が納得できるかたちで明確にしておかなければなりません。
STEP3.フィード・フォワードのコーチング
設定された目標にしたがって、実際に起こしたアクションに対するフィードバックを行います。これにより、現在の立ち位置と目標のズレを指摘し、なぜそれが生じたのか、原因は何かを明らかにします。
ただし、否定的なフィードバックでは従業員のモチベーションを下げてしまう可能性があるでしょう。
そこで重要となるのが、過去ではなく将来に意識を向けながら、成功のポイントを明らかにしていくフィード・フォワードといった手法です。
否定的な評価ではなく、目標の達成につながるアイデアを従業員とともに話し合い、客観的なアドバイスとして受け入れてもらいます。これによって、従業員みずからが目標に向かって軌道修正しようとする意欲が高まるとされています。

パフォーマンスマネジメントの課題
このように、従来の組織管理方法に代わる新しいマネジメント手法として注目されている、パフォーマンスマネジメントですが、当初はいくつかの課題も指摘されていました。
下記では、より組織の実態に見合ったマネジメントをしていくために、従来型のパフォーマンスマネジメントの課題について説明しておきます。
スタッフのエンゲージメントの低下
パフォーマンスマネジメントは、従業員と管理者が信頼し合い、エンゲージメントを向上させることが狙いのひとつです。しかし、過度な評価やレーティングによって、むしろスタッフのモチベーションを下げてしまう可能性があることも指摘されています。
従業員が評価されることを好ましく思わず、管理者側も評価することに苦手意識をもっている組織が少なくなかったわけです。
ある調査では、管理者の大半が採用されたパフォーマンスマネジメントのシステムに不満をもっていると回答しています。
コストと効果が釣り合わない
パフォーマンスマネジメントでは、一人ひとりの従業員を適切に評価するために時間をかけますが、それが必ずしも組織としての成果に結びつかないことが指摘されていました。言い換えれば、人材評価にかかるコストと効果が釣り合っていないといった問題があります。
日本の企業でも、きちんと人材を評価しようとすればするほど、どうしても仕組みが複雑化してしまい、場合によっては評価制度そのものが形骸化してしまうといった声もありました。
組織強化につながらない
また、個人の成果を評価していくパフォーマンスマネジメントでは、従業員が自己のパフォーマンスに集中してしまうため、組織全体の強化につながらないことがあるといった指摘もなされています。
コストをかけてまでマネジメントを行ったにもかかわらず、組織力の強化につながらないことで、従業員と管理者の関係も悪化してしまう可能性があります。
ビジネスの実態に合わない
本来、めまぐるしく変化するビジネス環境に対応しながら、組織全体の生産性を向上させるのがパフォーマンスマネジメントの目的です。しかし、とくに変化の激しい現代では、年に1回、2回程度の評価では間に合わないといった指摘も出ています。
頻繁なコミュニケーションとフィードバックが必要で、個人の取り組みよりも周囲への協力が求められる環境では、個人の成果創出を難しくしてしまうケースがあるようです。
パフォーマンスマネジメントを導入する際の注意点
パフォーマンスマネジメントを導入する際には、次のポイントに注意が必要です。
- 管理者のコーチングスキルが必要
- 全社的な取り組みを行う
管理者のコーチングスキルが必要
パフォーマンスマネジメントを行うためには、マネージャーやリーダーのコーチングスキルが必要です。
パフォーマンスマネジメントでは、部下との対話により、管理者は部下の目標達成や主体性を促します。そのため、部下のモチベーションを高め、成果につながるフィードバックを行えるよう、管理者はコーチングスキルを身につけていなければいけません。
上司が適切なフィードバックを行えなければ、逆に「部下のモチベーションを低下させてしまう」「信頼関係を損ねてしまう」など、パフォーマンスマネジメントの失敗につながりかねません。
そのため、管理者は部下の能力を把握し、わかりやすくフィードバックを行えるよう、フィードバックスキルやコーチングスキル・傾聴力など自身のスキルアップを図ることが大切です。
全社的な取り組みを行う
パフォーマンスマネジメントを成果に結びつけるには、会社全体で取り組みが必要です。
目的を明確にして組織全体で取り組みを行わなければ、制度が浸透せず、導入しても効果につながらなくなる可能性があります。
また、パフォーマンスマネジメントで企業全体の生産性を上げるには、社員の目標は、経営目標と連動したものであることが必要です。つまり、経営目標を細分化することで、個人の目標へとつながります。
そのためには、経営ビジョンや経営目標を伝え理解してもらうことが必要です。そのうえで、全社的にパフォーマンスマネジメントに取り組む環境を整えれば、成果に結びつきやすいでしょう。
パフォーマンスマネジメントを活用する際のポイント
上述の課題を踏まえ、実際に成果の出るパフォーマンスマネジメントを行うためには何が重要なのでしょうか?
下記では、従来型のパフォーマンスマネジメントの課題を克服しつつ、実際に効果の出るマネジメントをしていくためのポイントについて説明します。
ランクよりもフィードバックに重きをおく
フィード・フォワードのフィードバックについては説明しました。ただし、実際には一方的なフィードバックしか与えられておらず、従業員のモチベーションが下がってしまっている組織は少なくありません。
とくに過度なランク付けやふるい分けは、従来型のマネジメント手法の弊害をもたらしてしまうでしょう。
序列やランクを決定するのではなく、組織の従業員一人ひとりが目標に向け、そのためのプロセスを理解したうえで、目標に従事できる環境を作っていくことが重要です。
パフォーマンスマネジメントにおけるフィードバックは従業員と管理者の信頼が前提となるため、管理者はとくにモチベーションに配慮したフィードバックを心がける必要があります。
コーチングを徹底する
フィードバックのなかにコーチングの視点を取り入れることも重要です。トップダウンで一方通行の指摘や注意では、従業員に当事者意識をもってもらうことは難しくなります。
従業員が自身の強みを活かし、主体的にみずからの生産性を向上させることに意識を向けてもらうには、管理者による適切なコーチングが不可欠です。
的を射たコーチングは双方に信頼関係をもたらし、従業員は本心を打ち明けやすくなるため、これまで人材評価にかかっていた時間的コストを削減し、適材適所の人材配置や業務分担を可能にします。
また、組織のなかで自分がどれだけ重要な役割を担っているのかを理解できれば、従業員は自分だけではなく組織全体の生産性を意識して行動できるようになります。
タレントマネジメントの視点をもつ
近年は、人材の短所を指摘して改善に終始するよりも、個人の生まれもったスキルを発掘し、最大限に引き出す手法が効果的であるといわれています。
これをタレントマネジメントといいます。組織のパフォーマンスを向上させるうえで、この視点は非常に重要です。
変化に対応できる企業とは、従業員一人ひとりがみずからの強みを、最大限発揮できる環境を構築している組織であり、強みを自発的に全体の目標に整合できる人材がいる組織です。
タレントマネジメントによってそういった環境を備えることで適応力の高い組織ができあがっていきます。タレントマネジメントについて詳しくは、次の記事を参考にしてください。
管理職者への意識改革を推進する
パフォーマンスマネジメントを実施する際は、管理職の意識も重要です。
とくに、パフォーマンスマネジメントは従業員へのサポートが必要になる場面が多いため、管理職みずから積極的にコミュニケーションを取らなければいけません。
しかし、管理職の対応によっては仕事への意欲が低下することもあるので、コミュニケーションを取るときは十分に配慮しなければいけません。
うまくサポートできていない場合は、管理職向けの研修を実施して意識改革を行いましょう。
マネジメントに人材管理システムを活用する
最後に、パフォーマンスマネジメントをサポートしてくれる人材管理システムについて紹介します。
人材管理システムとは組織の抱える人材を効率的に活用するためのサポートツールですが、これを積極的に利用することで、パフォーマンスマネジメントの実践にも役立ちます。
次で詳しく解説しているので、ぜひこちらも参照ください。
パフォーマンスマネジメントで計画的な組織改革を!
現在、世界的な潮流となりつつあるパフォーマンスマネジメントについて解説してきました。とくに日本ではさまざまな業界で深刻な人材不足を抱えており、既存の従業員の生産性を向上させ、いかに業績につなげられるかが重要な課題となりました。
また、すでに多くの世界的企業でパフォーマンスマネジメントによる組織変革が開始されており、硬直的な評価体制から、従業員一人ひとりのパフォーマンスに注目した評価体制へと移行しつつあります。
そのために、積極的に新しい人材管理システムを導入する動きも広がっています。
本記事を参考に、ぜひ人材のパフォーマンスに注目した最新の管理手法について理解し、取り入れることを考えてみてください。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査