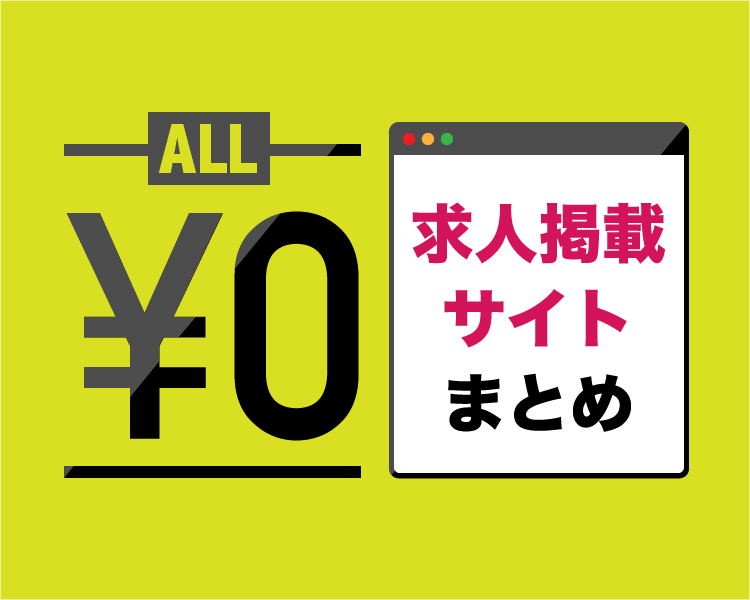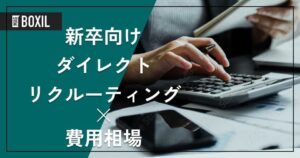採用サイトとは
採用サイトとは、新卒採用・中途採用のために作る求職者専用の自社サイトのことです。新卒・中途問わず、多くの求職者は、応募前にコーポレートサイトや採用ページを確認します。
しかし採用ページがなかったり、求人票程度の情報しか掲載していなかったりすれば、会社の魅力が求職者に十分に伝わらず、優秀な人材を逃してしまう可能性が高くなります。近年はインターネットで情報を収集するケースも多く、自社サイトで求職者のニーズに答えられなければ、多くの人材を離脱させる可能性があるでしょう。そのため求職者の疑問や不安を解消し、応募を促進する意味でも、自社で制作する採用サイトは重要度が増していると考えられます。
採用サイトを制作する目的採用サイトとは、新卒採用・中途採用のために作る求職者専用の自社サイトのことです。
リクナビやマイナビなどの求人サイトで情報の提供や応募の管理などを行っている企業も多いでしょう。近年は業種を絞った専用の求人サイトも多数存在します。とくに中小企業が求職者に知ってもらうためには、こういったサイトを活用することが欠かせません。
しかし、求人サイトでは掲載できる情報に限りがあり、充分に社風や差別化ポイントを伝えられません。画一化された情報だけでは求職者との間にギャップが生じやすく、ミスマッチにもつながる可能性があります。
この「ミスマッチ」を少しでも埋める目的で作られるのが、自社独自の採用サイトです。求人サイトに掲載し、興味をもってもらったうえで、自社採用サイトでより詳しく知ってもらうことで、より多くの人材に応募してもらえる確率が上がります。
求人サイトへの掲載も簡単に
一度採用サイトを作ってしまえば、他サイトに出稿する際も、採用サイトの内容をもとにまとめればいいため、作業も楽になります。1から採用サイトを作るのは大変かもしれませんが、大きな財産になるのも確かであるため、採用サイトをもっていない・作り込んでいない企業はこの機会に見直しましょう。
採用サイトの作り方
自社で採用サイトを作成する際には、次のような手順で行われます。
- 目的を明確化させる
- ターゲットを設定する
- 採用サイトのコンセプトを決める
- 掲載する情報を検討する
- サイトマップを作成する
- サイトのデザインを決める
- サイトの運用・改善を行う
各ポイントを紹介しますので、サイト構築の参考にしてください。
目的を明確化させる
冒頭でも簡単に紹介しているように、採用サイトの目的としては「ミスマッチの防止」が挙げられ、そのほかにも「応募者の増加・企業理解を深める」といった目的も考えられます。また、採用サイトを作る目的によって、掲載すべきコンテンツも変わってきます。
そのためまずは目的を明確化させることで、サイトや掲載すべきコンテンツの方向性をはっきりさせましょう。目的が複数ある場合でも、優先順位を決めることで方向性はわかりやすくなる効果があります。
ターゲットを設定する
次に「求める人物像」をより具体的にイメージしましょう。このときスキルや学歴といった情報はもちろん、より掘り下げて「ペルソナ」を設定するのが重要です。ペルソナとは、商品・サービスを利用する一般的な人物像のことで、趣味嗜好や性格、家族構成といった詳細な部分まで1人の人物を作り込みます。
これにより、ターゲットがどういった情報を求めているか考える際に、より具体的にコンテンツの内容をイメージしやすくなるでしょう。
採用サイトのコンセプトを決める
次に採用サイトのコンセプトを決めましょう。コンセプトを作ることで、採用サイトでターゲット層に対し何を伝えたいかが明確化でき、サイトのデザインをイメージしやすくなる効果があります。基本的には求める人物像や企業理念といった情報をベースとして、「〇〇な人物を求めています」や「会社の〇〇という理念を大切にしています」といった表現で作成します。
またこういったコンセプトを作れば、ターゲット層に対してもどういった企業でどういった人物を求めているかがわかりやすくなるでしょう。
掲載する情報を検討する
具体的にどのような情報・コンテンツをサイトへ掲載するか検討しましょう。自社で掲載したい情報と、ターゲット層が求めている情報と照らし合わせ、掲載すべき情報を整理します。コンテンツを検討する場合は、必ずターゲット層の目線に立って本当に必要な情報か考えるのが重要です。
コンテンツ例や具体的に記載する情報は、次の章でも紹介しているため、そちらも参考にしましょう。また自社らしさを見せ、差別化を図るためには競合他社の採用サイトを調査するのも効果的です。
サイトマップを作成する
掲載すべきコンテンツを洗い出したら、これをサイトマップにまとめましょう。サイトマップとは、サイト全体の構成をリスト化したもので、サイトのどこにどのコンテンツを掲載するかを定め、各コンテンツを見やすく配置します。
ただいきなり作成すると失敗しやすいため、まずは下書きを作成するのがおすすめです。またページ数を増やしすぎると閲覧者が情報を探しにくくなるため、構成はできる限りシンプルにして、ページごとの情報量は図やグラフにまとめるなど、うまく調整しましょう。
サイトのデザインを決める
最後に採用サイト全体のデザインを決定します。事前に設定したコンセプトに合わせ、どういったデザインにすればターゲットに刺さりやすくなるか考えましょう。ただし、ターゲットはあくまでも情報を求めているため、デザインは基本的にシンプルでわかりやすいものにするのがおすすめです。
アニメーションといった動きが多すぎると逆に情報を見にくくする可能性があるため、装飾は適度に抑えつつ、見やすさを重視したデザインにしましょう。
サイトの運用・改善を行う
採用サイトが完成したら、実際に公開して運用を行います。採用サイトは一度構築すれば長期的に情報を発信し続けられますが、公開後も効果測定を行い、サイトを改善するのが重要です。Googleが無料で提供するアクセス解析ツール「GA4」を活用することで、各コンテンツの閲覧数やユーザーの行動データを分析し、サイトの改善に役立てることができます。
GA4を使えば各コンテンツの閲覧数や回遊率、離脱されたページなどの分析を行えるため、掲載する情報のブラッシュアップや改善を行いましょう。また採用活動のトレンドやターゲットのニーズに合わせて、コンテンツの更新やサイトのリニューアルなどを行うと、より成果を出しやすくなります。
採用サイトのコンテンツの種類
採用ページでよく掲載されているコンテンツの例としては、次のようなものが挙げられます。
- 会社概要
- ミッション・ビジョン
- 代表メッセージ
- 募集要項
- 事業内容
- 1日の流れと仕事内容
- 福利厚生
- 社員インタビュー
- キャリアパス
- 研修制度
- 応募方法・選考の流れ
- よくある質問
- 他社と差別化したコンテンツ
それぞれ具体的な採用情報や、制作のポイントについて紹介します。
会社概要
企業の正式名称、主な事業内容、所在地など、企業の基本情報を掲載します。内容は自社のコーポレートサイトと同様で問題はありませんが、オフィスの中の写真を挿入することで、よりどういった企業かをイメージしやすくなるでしょう。
ミッション・ビジョン
求職者に対し自社のミッション・ビジョンを伝えるのは重要なことです。企業として目指すべき姿や志を見せることで、求職者に「自分もこの会社に入って同じ場所を目指したい」と思ってもらえます。
またミッションやビジョンは社風や企業の雰囲気にもつながるものであり、ミッションやビジョンに共感できる人材は、入社後のミスマッチも起こりにくくなるでしょう。
代表メッセージ
会社を経営する代表者からのメッセージは、ビジョンや採用に対する熱い思いをより具体的に伝えやすく、ビジョン・ミッションに納得してもらえ、応募意欲を高めてくれるでしょう。直筆メッセージとして掲載したり、インタビュー形式で掲載するケースがあり、ミッション・ビジョンとセットであることも多々あります。
募集要項
募集要項は新卒・中途に関係なく必ず掲載しましょう。掲載すべき主な情報は次のとおりです。
- 募集条件
- 募集する職種
- 給与・賞与
- 福利厚生
- 休日・休暇制度
- 勤務時間
またそのほか、必要に応じて採用人数といった情報も掲載します。もしすでに求人サイトで募集要項を掲載している場合は、これを流用しても問題ありません。
事業内容
企業が具体的にどういった事業や業務を行っているかも、求職者が注目する部分です。コーポレートサイトでは、ざっくりと紹介するケースも多く見られますが、求職者のニーズに答えられるようできる限り詳細に記載しましょう。
またとくに新卒採用者は事業をイメージしにくいため、事業の規模感や実際に取り組んでいる直近のプロジェクトといった、具体的な情報を提供するのがポイントです。
1日の流れと仕事内容
求職者が実際に自分がどういった仕事をするか理解できるよう、職種ごとに行っている仕事の内容や、1日の中でどのように動くのかを紹介します。インタビュー形式で業務の進め方や仕事のやりがい・難しさといった面も含めて紹介できると、より理解を深められるでしょう。また1日の流れは、表やグラフで表せると理解しやすくなります。
福利厚生
自社で行っている福利厚生はすべて掲載し、求職者へしっかりアピールしましょう。また福利厚生は健康保険や厚生年金といった「法定福利厚生」と、施設の利用割引や社員食堂といった「法定外福利厚生」の2種類があります。
法定福利厚生はどの企業も同じですが、法定外福利厚生は企業の個性が出やすいため、詳細を記載して他社との差別化を図りましょう。
社員インタビュー
実際に会社で働く社員の声を掲載することで、企業の雰囲気がイメージしやすく企業に対する親近感も高められます。募集要項にある職種ごとや性別ごとなど、求職者が自分に近い人物の声を聞けるよう、バランスよく社員のインタビューを掲載するのがポイントです。内容が類似するため、「1日の流れと仕事内容」とセットで掲載するケースもあります。
キャリアパス
求職者が入社後どのようにキャリアを重ねていけるかイメージできるよう、入社後のキャリアパスも紹介します。求職者が応募を判断する材料としては、求職者にとって、思い描くキャリアを実現できるかどうかも重要なポイントとなるため、職種ごとに具体的なキャリアのルートを示しましょう。
研修制度
募集要項とは別に、どのような研修制度があり、何が学べるのかを詳しく紹介することも大切です。思い描くキャリアを歩むためには、経験はもちろん学習も必要であり、ポイントポイントで必要な学習を行える制度があるかも確認されます。
研修といっても企業ごとに採用している制度や手段はさまざまであるため、できるだけ具体的にどのような教育や支援が受けられるかを掲載しましょう。
応募方法・選考の流れ
上記のコンテンツを提供して応募の意欲を高めたあとに、具体的に、応募から選考までの流れを紹介します。掲載する主な情報は次のとおりです。
- 書類選考はあるか
- 面接は何回あるか
- 内定が出るまでにどの程度の期間がかかるか
- 入社はいつ頃か
選考の流れに関しては、表やグラフを使って一目でわかりやすくするのがポイントです。
よくある質問
過去会社説明会や面接などでよく受ける質問があれば、それらをまとめてコンテンツ化するのも効果的です。求職者が疑問や不安に感じやすいポイントを事前に解消できるため、安心して応募に臨みやすくなります。都度質問を追加すれば、時間がたつほど充実したコンテンツになります。
もし採用活動の経験が少なく、よくある質問が思いつかない場合には、競合他社の「よくある質問」や、「就職白書」といったアンケート調査結果を参考にするといいでしょう。
他社と差別化したコンテンツ
上記で紹介しているのは、主に求職者の求めるコンテンツであり、その他にも他社と差別化できるコンテンツはあった方がいいでしょう。求職者は多くの企業の採用サイトをチェックして内容を比較し、応募先を決定します。
そのため、独自の情報を掲載できれば求職者の印象に残りやすく、好感を抱きやすくなるでしょう。競合他社のサイトをチェックして、前述した「法定福利厚生」のような、自社で掲載できるオリジナルの情報はないか確認しましょう。
採用サイト制作時のポイント
採用サイトは求職者に自社の魅力を伝えられる一方、内容が充実していなければ、せっかく興味を持ってくれた求職者を逃してしまう可能性もあります。そこで次に、採用サイトを制作する際のポイントについて詳しく紹介します。
入社後のイメージが伝わるコンテンツを
コンテンツを制作する際には、入社後のイメージを伝えることに重点を置きましょう。求職者が採用サイトで最も知りたい情報は、入社後のワークライフバランスや入社後実際に働く姿をイメージできる情報です。そのため、とくに次のようなコンテンツは人気があります。
- 福利厚生
- 社員インタビュー
- 1日の流れと仕事内容
- オフィスの様子
これらのコンテンツでは、求職者がより入社後の働く姿を想像できるか意識するのがポイントです。例として社員インタビューは入社後1~2年の若手をピックアップしたり、福利厚生では実際に育休を取ったあとの復帰の仕方や、後のキャリアアップなどについて紹介したりするといいでしょう。
企業イメージにあったデザイン
採用サイトでデザインを考える場合、「とにかくお洒落なデザインで目を引きたい!」と考えるケースは多くあります。しかし、サイトデザインが会社のイメージと大きくずれないよう注意が必要です。伝統的な製品を扱っている会社が、ポップすぎるデザインだと、企業全体のブランディングやイメージが崩れる可能性もあります。あくまで企業イメージを第一に、企業イメージに沿ってデザインを作ることが、見やすく伝わりやすいサイトには欠かせません。
レスポンシブデザインでスマホ対応に
サイトを作成する際には、「スマホからも見やすいか」を確認しましょう。とくに若い世代ほどスマートフォンで情報を検索します。せっかくいい内容が書いてあっても、スマートフォンに最適化されていない場合、読まれにくくなってしまいます。スマホに対応しているのはもちろん、スマホから見て見にくい部分がないかしっかりチェックしましょう。
採用サイトの成功事例
実際に求職者のニーズに合った採用サイトの構築・運用に成功している企業の事例を、参考としていくつか紹介します。
株式会社良品計画
株式会社良品計画は、大手雑貨店「無印良品」の企画から商品の調達・流通・販売までワンストップで行っている企業です。採用サイトでは、社員インタビューを主要コンテンツとして掲載し、入社後をイメージしやすくしています。
社員インタビューで、入社の決め手や仕事のやりがい、心がけていることにくわえ、自分自身を自社商品に例えて紹介している点がユニークです。また採用サイトでも自社ブランドと同様、白やナチュラルなカラーに差し色として濃い赤を使っており、一目でブランドがイメージできます。
※参考:良品計画「 新卒採用 」(2025年1月25日閲覧)
株式会社講談社
株式会社講談社は雑誌や本、漫画など幅広い出版物を手がける大手出版会社です。講談社の採用サイトでは「才能と働こう」のコンセプトとともに、イラストを使い、本や雑誌を作る人たちのイメージをポップでカラフルに表現しています。コンテンツには漫画の担当者による対談や、内定者が執筆したエッセイなどが掲載されており、出版社としての色を全面に出しているのが特徴です。
社内の様子はギャラリーとして紹介しており、入社後のイメージをよく理解できるよう作られています。また講談社の採用チームはSNSもよく利用しており、採用エントリーの方法やセミナー情報といった採用に関する情報を定期的に更新し、若い世代へアプローチを行っているのもポイントです。
※参考:講談社「 講談社2026年度定期採用[才能と、働こう。] 」(2025年1月25日閲覧)
株式会社星野リゾート
株式会社星野リゾートは「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的に合わせた宿泊施設や日帰り施設を運営する企業です。採用サイトでは、コンテンツ数を必要最小限に抑え、シンプルで分かりやすい構成にしています。
また開業から110年を記念して、社員インタビューを110人に対して行っているのも特徴です。社員インタビューでは職種や入社の年数といったさまざまな条件で絞り込めます。これにより求めている情報も見つけやすく、多種多様な職種を応募していても、入社後のイメージや後のキャリアアップについて理解を深めやすいでしょう。
※参考:星野リゾート「 星野リゾート 採用サイト【公式】 」(2025年1月25日閲覧)
採用管理システムを導入して効率化
採用業務をより効率化するために、「採用管理システム」を導入するのも一つの方法です。自社採用サイトの制作や応募者の情報確認、セミナー運営、選考の進捗状況などを一元管理できます。求人媒体も利用しつつ、自社のブランディングにもつながるでしょう。
おすすめの採用サイト作成ツール
最後に自社の採用サイトを作成するのに役立つツールを紹介します。
iRec
- 専門知識ゼロでも簡単に作成可能
- IndeedやGoogleしごと検索と自動連携
- 最短2週間で公開・スマホサイトも自動対応
iRec は、「採用のプロ」が開発した採用サイト制作ツールです。
人材紹介事業を手がけるプロコミットが開発したサービスで、キャリアコンサルタントが培ってきた視点を取り入れた採用サイトが、ブログ感覚で作成できます。手元に原稿や写真などの素材が揃っていれば最短2週間でリリースでき、スマートフォン用サイトにも対応可能です。自社サイトに求人を掲載すればIndeed、Googleしごと検索に自動連携するため、効率的に応募者数を増やせるでしょう。
採用係長
- 採用ページを短時間で作成可能
- 豊富な数の求人検索エンジンと自動連携
- 無料トライアルあり
採用係長 は導入実績が豊富で、採用を最適化するためのクラウド型採用マーケティングツールです。
ツールを簡単に操作できるため採用ページを短時間で作成可能です。IndeedやGoogleしごと検索など豊富な数の求人検索エンジンと自動連携できるため、工数をかけずに露出を増やし、制作した採用ページへの応募増加を見込めます。充実した内容のトライアルプランも用意されているので、安心して利用を始められるでしょう。
engage
- 無料で簡単に自社採用サイトを開設
- 求人ネットワークで広範囲に告知
- 豊富な機能で効率的な採用活動を支援
エンゲージ は、無料で簡単に採用サイトを作成できるサービスです。
作成した求人情報は、求人ネットワークであるエン株式会社が運営するエンゲージやエン転職などに掲載され、多くの求職者にリーチできます。さらに、「Map検索」機能により、近隣の求職者へもより強力にアプローチできます。豊富な情報量で自社の魅力を伝えられるだけでなく、社員クチコミサイトとの連携により、企業のリアルな情報を求職者に届け、応募意欲を高めることが期待できるでしょう。
bサーチの採用コンサルティング
- 専門チーム体制で手厚い採用支援
- Webマーケティングを駆使した戦略
- 多様な媒体、ツールをワンストップで提案
bサーチの採用コンサルティング は、戦略立案から実行、分析、改善までをワンストップで支援するサービスです。
ウェブマーケティングの専門知識と10年以上の求人広告ノウハウを活かし、効果的な求人運用を実現します。原則3名1チームの専門家体制でサポートをおこない、採用目標の達成に向けて、継続的なPDCAサイクルを実行できます。媒体選定から求人原稿作成、データ分析、さらには採用代行やWeb制作まで、採用に関する時間やお金、手間を大幅に削減し、ミスマッチを防ぐ効率的な採用活動のサポートが期待できます。
Airワーク 採用管理
- 幅広い求職者へIndeed PLUSで自動アプローチ
- 応募者管理を効率化し対応漏れを防ぐ
- クリック課金制で無駄なく予算管理
Airワーク 採用管理 は、採用ホームページ作成や応募者管理など採用業務を効率化できるツールです。
Indeed PLUSと連携し、幅広い求職者へ自動で求人掲載/アプローチが可能です。すべての応募情報を一元管理でき、煩雑な応募者対応や対応漏れを防ぎ業務を効率化します。また、クリック課金制で無駄なく費用を抑え、予算管理も安心して行えます。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査