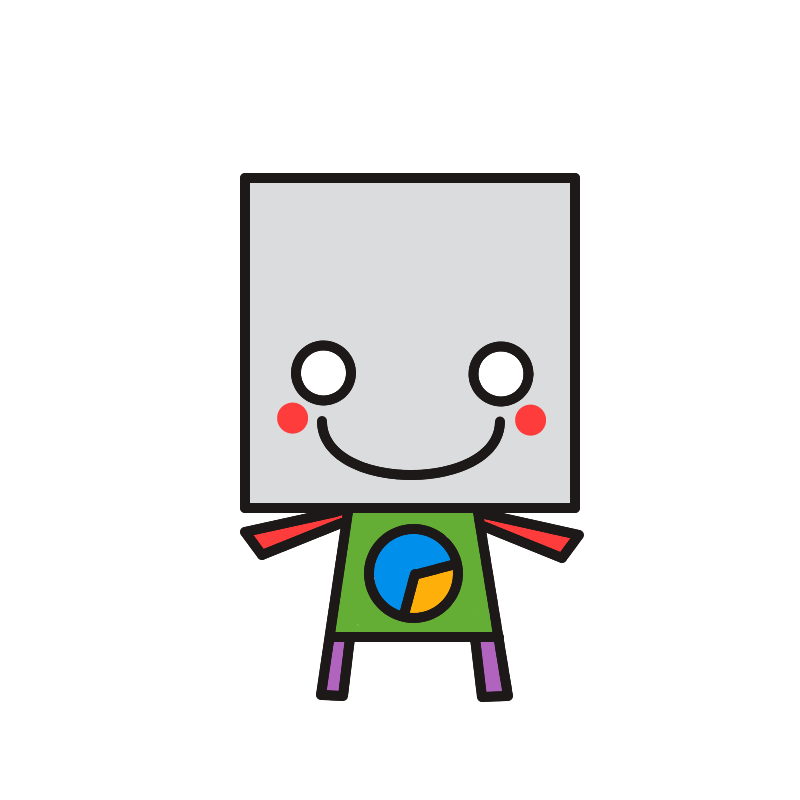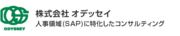RPAとは?意味やAIとの違い | メリット・導入手順をわかりやすく解説

目次を閉じる
RPAとは
RPAとは、ロボティックプロセスオートメーション(Robotic Process Automation)の略で、PC上で行う業務をソフトウェアロボットによる業務の自動化のことです。データの入力や転記、ファイルの複製といった単純作業の定型業務を自動化してくれるツール・端末のことを指します。
近年人件費の高騰や働き方改革などから定型業務の見直し、自動化に目が向けられるようになりました。RPA導入によって、従業員の工数削減や満足度向上、正確性の担保があるため、業務改善や働き方改革などの恩恵が受けられることから、導入の流れは世界的に広まりつつあります。
RPAの仕組み
最初にパソコン上で、ソフトウェアロボットに自動化させたい作業をRPAに記録します。フローチャート化された作業プロセスを、業務内容に応じてドラッグ&ドロップといった簡単な操作で編集し、ロボットを作成します。
あとは、ロボットを実行するタイミングをスケジュール指定すれば、ロボットがその時間に人が画面操作するのと同じように、複数のアプリケーションやツールを操作して定型業務を実行します。
RPAの活用例
RPAを活用した例には、次のようなものがあります。
- 問い合わせ内容をメールからExcelに転記
- 新入社員の情報を人事システムに自動で反映
- 営業実績のデータを月ごとにレポーティング
- 残業時間の多い従業員へメールで通知
単純作業や定型業務をRPAによって代替するのが主な活用方法です。
RPAと似た用語との違い
RPAとAIの違い
RPAとAIの違いは、判断を自動化するか否かです。RPAは、製作者によって決められたルールどおりに動くため、シンプルな業務を確実にこなしてくれます。一方AIは、大量のデータにもとづいてシステム自身で判断し定められた業務をこなします。
つまり、RPAの強みは単純作業を正確に実施する点に、AIの強みは人間の判断をある程度の精度で代替してくれる点にあるといえるでしょう。
| RPA | AI | |
|---|---|---|
| 特徴 | 決められたルールに基づいて処理 | ビッグデータに基づいて判断を自動化 |
| メリット | 定型業務を正確にこなす | 判断が必要な業務をこなせる |
| デメリット | 判断は人間が決めておく必要あり | 判断の正確性はAIによって異なる |
詳しくは次の記事を参考にしてください。

RPAとVBA(Excel マクロ)の違い
RPAとVBAの違いは、ExcelやWordといったOffice アプリケーション以外を自動化できるか、プログラミングの習得が必要かにあります。
RPAは、ツールにもよりますがアプリケーションを問わず幅広く自動化でき、プログラミングがわからずともある程度実装可能です。一方で、Excelでマクロと呼ばれるVBAは、Office アプリケーションを中心に自動化し、プログラミングを必要とします。そのため、現場の担当者が制作するのであればRPAの方が適しています。
| RPA | VBA | |
|---|---|---|
| Officeアプリケーション以外の自動化 | できる | あまりできない |
| プログラミングの必要性 | 基本的に不要 | 必要 |
ちなみに、Office アプリケーションを自動化するのであれば、VBAの代わりにPower AutomateというRPAツールを使うのがおすすめです。Power Automateはマイクロソフトが提供しているRPAツールで、プログラミングをせずともOffice製品を中心に業務を自動化できます。

RPAの3つのクラスとは
RPAは対応できる自動化レベルにより、次の3つのクラスに分類されます。
- クラス1:RPA(Robotic Process Automation)
- クラス2:EPA(Enhanced Process Automation)
- クラス3:CA(Cognitive Automation)
クラス1:RPA(Robotic Process Automation)
従来型のRPAのことで、定型業務のみの自動化に対応しています。主に入力作業や検証作業などに用いられます。
クラス2:EPA(Enhanced Process Automation)
EPAとは、AIと連携してデータを解析し、ある程度の非定型業務も自動化できるものことです。画像解析や音声解析などに用いられることもあります。
クラス3:CA(Cognitive Automation)
CAとは、高度なAIと連携してロボット自身が判断するため、ほとんどの業務プロセスを自動化できます。AIによるデータ分析を迅速に経営戦略に活かすことも可能です。
RPAを導入するメリット
RPAを導入するメリットは次のとおりです。
- 従業員満足度の向上
- 人的コストの削減
- 業務の精度を改善
従業員満足度の向上
RPAを導入すると、業務効率化により従業員の満足度が上がります。
RPAによって代替される業務は、テキストのコピー&ペーストやファイルの移動といった、判断を必要としない単純作業です。単純作業を自動化することで、クリエイティブな仕事に集中できるようになります。
人的コストの削減
定型業務の自動化による人的コストの削減も大きなメリットのひとつです。
RPAで従業員満足度が向上すれば、転職率が下がり、採用や教育にかかるコストの軽減できます。ちなみに人的リソースを削減できるRPAは、機械的な労働者という意味で「デジタルレイバー」と呼称されることもあります。
業務の精度を改善
単純作業の繰り返しにはRPAを導入するメリットが大きいといえるでしょう。
長時間労働では、どうしても集中力が切れてしまい、仕事の精度が下がってしまいます。一方で、RPAは24時間365日稼働でき、決められたルールに対して高い精度で業務をこなしてくれます。
RPAを導入するデメリット
RPAを導入した際のデメリットには次のようなものが考えられます。
- 導入コストが高い
- 経験者が少ない
- 修正する工数や体制が必要
導入コストが高い
RPAのデメリットとして、費用の高いツールの多い点があげられます。クラウドであれば数万円から利用できるものの、デスクトップ型であれば数十万円、サーバー型なら数百万円から1,000万円以上となるケースも珍しくありません。
小さな規模から導入をしたい企業はクラウド型、少なくともデスクトップ型の導入をおすすめします。
経験者が少ない
RPAのの経験者が少ない企業では、学習動画やマニュアル、書籍などを閲覧して習得したり、企業からサポートを受けられる体制を整える必要があります。RPAはプログラミングに比べてハードルが低いのは事実ですが、一朝一夕で使いこなせるようになるわけでもありません。
周知のためにどの程度時間が必要か見積もり、十分に時間をかけるようにしましょう。
修正する工数や体制が必要
RPAは、指示されたルールどおりには動けるものの、ルールに記載されていない想定外の事象が発生した際には稼働が停止します。その場合は担当者が原因の箇所を特定し、適宜修正する必要があります。
RPAの利用が広がってきた場合には、RPAに強い専門家を配置して修正にかかる工数を削減するのがおすすめです。
RPAツールの種類
RPAツールは大きく分けて、オンプレミスのデスクトップ型とサーバー型、クラウド型の3つに分類されます。これらの違いを比較してみましょう。
ちなみに、デスクトップ型のRPAをRDA(Robotic Desktop Automation)と呼びRPAと区別する場合もありますが、本記事ではRPAの1つとしてRDAを定義しています。
| デスクトップ型 | サーバー型 | クラウド型 | |
|---|---|---|---|
| インストール先 | 自社のパソコン | 自社のサーバーとパソコン | インストール不要 |
| 初期費用の目安 | 10万〜100万円 | 100万〜2,000万円 | 1万〜10万円 |
| 企業規模の目安 | 中小企業・大企業 | 大企業 | 中小企業 |
| おすすめ企業 | 主にオフラインでの作業を自動化したい新規導入の企業 | 他社のRPAを利用して勝手がわかっている企業 | 主にオンラインでの作業を自動化したい新規導入の企業 |
デスクトップ型(オンプレミス)
デスクトップ型のRPAツールは、パソコンそれぞれにインストールして使用するオンプレミスのシステムです。
RPAツールを利用したいパソコンにのみ導入するため費用が10万円程度と、導入しやすいのがメリットです。ただし、自動化する範囲を広げようとした際にサーバー型やクラウドに切り替える必要性があります。そのため、まずは小さな規模から自動化したい企業におすすめの形式です。
サーバー型(オンプレミス)
サーバー型のRPAツールは、サーバーおよびパソコンにインストールするオンプレミスのツールです。サーバーによって各パソコンのRPAツールを管理できるため、大規模でRPAツールを稼働させる場合に便利です。
デメリットは導入までに時間がかかること、購入にかかる費用が100万〜2,000万円と高額になりやすいことです。RPAツールをすでに使用していて大規模での運用に目処をつけられている企業におすすめです。
クラウド型
クラウド型のRPAツールは、提供先のサーバーにインストールされているシステムをオンラインにて利用するサービスです。
導入の工数およびコストがかからない点、リモートワークでも利用できる点が強みといえるでしょう。ただし大規模での導入を検討している場合は、サーバー型のほうが費用対効果が高くなるケースもあります。小規模から徐々に利用を拡大していく企業におすすめです。
RPAツールの導入手順・方法
RPAを導入する際は、次の手順に沿って進めるのがよいでしょう。
- RPAツールを最小限の規模で導入
- RPAツールを評価
- RPAツールを継続するか入れ替えるか判断
- (入れ替える場合は)RPAツールの要件詰め
- RPAツールの選定
- RPAツールの無料トライアル
- RPAツールの本格導入
重要なのは、RPAツールを最小の規模で試して効果を実感してから、拡大したり入れ替えたりすることです。RPAツールはデスクトップ型やサーバー型では、費用が何十万から何百万になることもあります。まずは稟議を通す必要がないくらいの小さな規模で試用して運用できるようになってから、あらためてRPAツールの本格導入を検討するとよいでしょう。
1. RPAツールを最小限の規模で導入
RPAツールを本格的に導入する前に小さな規模で試験的に導入します。まずは、1つのパソコンだけでトライアルするとよいでしょう。
従業員が、RPAツールによって単純作業から開放されて工数を削減できるだけでなく、本来の業務に時間をかけられる喜びを実感できるのも重要な点です。ゆえに、最初は低価格ですぐに利用できるクラウド型またはデスクトップ型の導入をおすすめします。
機能制限はありますが、無料で提供されているRPAツールもあるためチェックしてみましょう。

2. RPAツールを評価
RPAツールを導入したら使った担当者から効果や感想をヒアリングします。残業時間の減少以外の、費用対効果だけでは測れない従業員満足度の向上を実感できるはずです。もし、周囲でRPAツールの噂を聞きつけて「使ってみたい」という従業員がいれば体験してもらうとよいでしょう。
3. RPAツールを継続するか入れ替えるか判断
RPAツールの導入を小さな規模で成功させたあとは、同じツールを使い続けるかほかのツールに入れ替えるかを検討します。いままで利用してきたRPAツールのアカウント数を増やせばよいのか、ほかの使いやすいツールに乗り換える必要があるのかは、前述のヒアリングを踏まえれば判断できるでしょう。
4. (入れ替える場合は)RPAツールの要件詰め
もし、RPAツールを入れ替える場合は、RPAツールを導入したいと考えている部署の間で企画を進めます。RPAツールを試験的に導入したことでどのようなポイントに注目すればよいのか、どんな効果が得られるのかが明らかになっているはずです。
5. RPAツールの選定
要件にもとづいてRPAツールを選定します。RPAツールの仕様や料金は問い合わせないとわからない場合がほとんどなので、提供サービスの営業担当者にききましょう。

6. RPAツールの無料トライアル
RPAツールを1つまたは2つまで絞ったら無料トライアルにて、使用感を確かめましょう。RPAツールは、システムによってはテキストの多い表示だったり英語のみの対応だったりします。ツールを触る担当者に実際に触ってもらって使えそうかチェックしましょう。
7. RPAツールの本格導入
トライアルで問題がなければ本格導入します。RPAツールをはじめて利用する担当者は、使い勝手がわかるまでに時間がかかります。提供サービスが配信している学習用の動画やマニュアル、Q&Aなどを参考にしながら徐々に慣れていきましょう。
RPAツールの導入事例
RPAの導入事例を紹介します。各企業の導入前の課題や効果をまとめているので、RPAの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼RPAの導入例について、さらに詳しく知りたい方はこちら

西武ガス情報システム(IT・100〜500人)
西武ガス情報システムはエネルギー事業をはじめ、生活に関する多くの分野で事業を展開しています。
課題:人的ミスと残業時間の増加
経理がデータをExcelで管理していたものの、ヒューマンエラーが発生したり残業時間が増大したりする問題がありました。
効果:4時間の作業が5分に
会計システムへの仕分け入力と入力の確認をRPAで自動化させたところ、所要時間が4時間から5分へと短縮できました。入力や保存といった簡単な作業をRPAシステムに任せることで、残業時間の削減に一役買っています。
慈恵大学(学校法人・5,000人〜10,000人)
学校法人慈恵大学は東京慈恵会医科大学、慈恵第三看護専門学校、慈恵柏看護専門学校、その他附属病院を多く運営している学校法人です。医療現場での活躍を目指して多くの学生が勉学に励んでいます。
課題:医師の業務軽減
医師の事務作業をいかに減らすかが課題でした。事務的な仕事は医師以外の職員が担当していましたが、すでに手一杯の状況においては医師も事務作業をこなしていました。
効果:業務時間を90%カット
RPAを導入して事務職員の業務を削減。いままでは従業員が作業していた内容をRPAに任せたところ、所要時間を約1/10にまで短縮しました。節約した時間で、医師の業務を減らすことに成功しています。
RPAの導入で安定したクオリティと作業の効率化を
RPAを導入することで、従業員満足度の向上や作業の高速化、コスト削減など、さまざまなメリットを受けられます。しかし、RPAツールは選び方を間違えると導入に失敗するリスクもあります。そのため、RPAの導入を検討する際は、事前に社内の課題を洗い出し、目的に合ったサービスを選びましょう。
ボクシルでは、おすすめRPAツールの料金や機能、特徴がまとまった資料を無料でダウンロードできるので、ぜひサービス導入を検討する際は、事前の情報収集を念入りに行ってください。
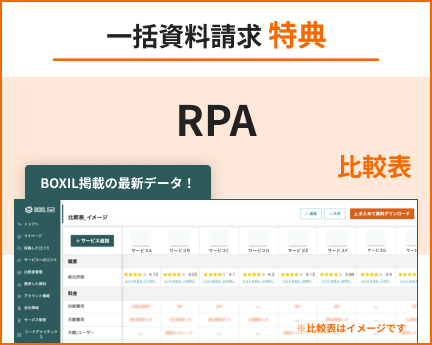
おすすめRPAの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なRPAを含むサービスを徹底比較しています。ぜひRPAを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
BOXIL CHANNELでは、RPAについて動画でも解説しています。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査