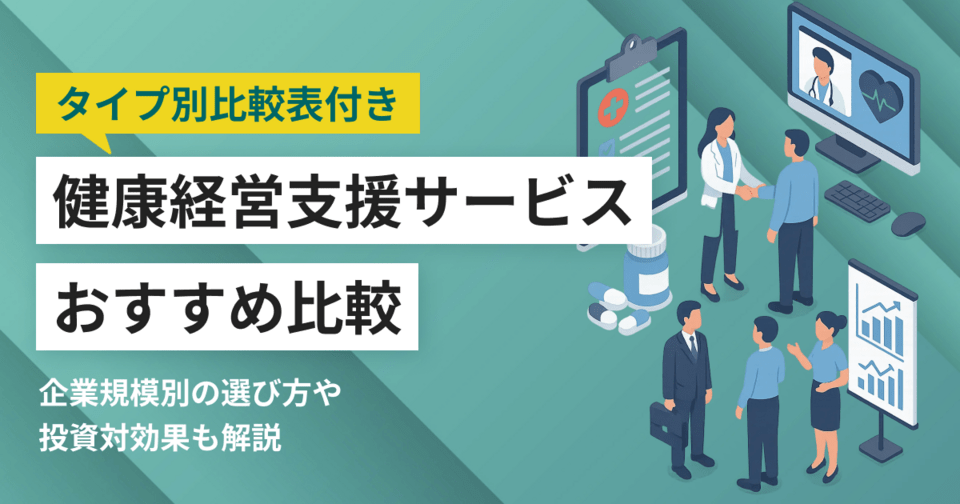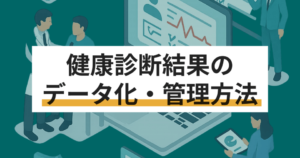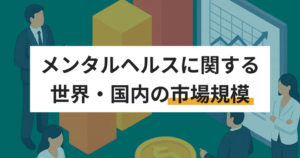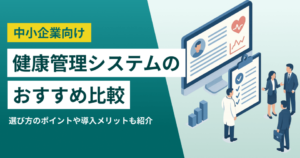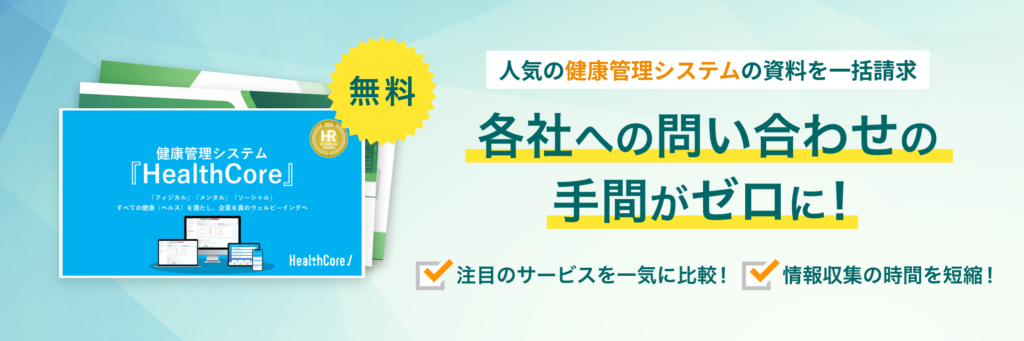健康経営とは
健康経営とは、従業員の健康管理を経営目線で考え、企業理念にもとづいて企業全体で戦略的に実践する経営方法のことです。企業が従業員の健康に投資を行うことで職場環境の改善を実現し、生産性や企業価値を向上させるのが目的です。
またメンタルヘルスやブラック企業といった社会問題を解決し、一人ひとりの生産性や創造性の向上を図るとともに、病気や体の不調による急な退職や休職のリスクを減らす狙いもあります。健康状態を単なる福利厚生ではなく、事業のような戦略的な活動と捉え、積極的に投資を行うことで、活力の向上やパフォーマンスの向上を目指す活動であるのが特徴です。
なお「健康経営」の言葉は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。ホームページやパンフレットに掲載する場合は、あらかじめ連絡し「健康経営®」とRマークをつけて、注釈を記載しましょう。
健康経営優良法人認定制度とは
多くの企業に健康経営を実践してもらうための施策として、健康経営優良法人認定制度が確立されています。
これは地域の健康課題や日本健康会議が進める健康増進の取り組みを基準として、とくに優良な健康経営の施策を実践している企業が顕彰される制度です。対象となる企業の規模は問われません。
企業による実践的な取り組みを見える化することにより、他社のロールモデルにすることや、求職者や関係企業が正しく企業を評価できるようにすることを目指しています。
なぜ健康経営が注目されるのか
そもそもなぜ健康経営が注目されるようになったのかでしょうか。そこで次に健康経営が注目される背景や、必要性について解説します。
注目されるキッカケ
健康経営の概念は、アメリカの心理学者であるロバート・ローゼンが1980年代に提唱した「ヘルシー・カンパニー」が発端とされています。
同氏は多くのアメリカ企業の事例を分析し、従業員の心身の健康が仕事に対する意欲を高め、生産性を向上させること、離職率や企業の医療負担費減少につながることを明らかにしました。
ほかにも、従業員の健康と企業の業績の関係性を科学的・統計学的に立証した研究は多くあります。そのためこういった考え方がアメリカ社会にも受け入れられるようになり、日本をはじめ先進諸国へ徐々に広がってきました。
社会情勢の変化
近年日本は急激に少子高齢化が進んでいるため、生産年齢人口(15~64歳)も減少傾向にあり、この流れはさらに加速すると予想されるでしょう。そのため人材不足の企業は多く、これをカバーするために、一人あたりの生産性向上が緊急の課題である企業も数多く存在します。
この生産年齢人口減少の対策として、企業における定年退職年齢の引き上げも決定していますが、代わりに職場の平均年齢が上がり、高齢化が進むと予想されます。高齢化が進めば体調を崩すことも増えるため、今後高齢の従業員でも快適に働ける職場環境の構築が重要になるでしょう。
こういった課題に対し、取り組みの一つとしてヘルシーカンパニーの考え方も強く推奨されるようになりました。一人ひとりの従業員が健康であれば、企業の負担は減り長い間企業に価値を提供し続けてくれるからです。これは今後も少子高齢化が加速するであろう日本の企業にとっては、非常に重要な経営問題といえるでしょう。
国全体の医療費や健康保険の問題と相まって、官民が協力して取り組むべき課題と認識されているわけです。
経営上のリスク回避
また、経営上のリスク回避といった観点からも、健康経営は必要性を訴えられています。景気が回復基調となった昨今、一部の企業は深刻な人材不足に陥っており、人手不足のまま倒産する企業も少なくないのが現状です。
このような状況のなか、過剰な労働によって身体を壊したり、病気になったりすれば、貴重な労働力を突如として失う危険性があります。経営者としては、何の前触れもなく貴重な戦力がいなくなるのは、何としても避けたいところでしょう。
そこで健康の増進に投資して、少しでも優秀な人材を確保し、少しでも長く健康に働いてもらうために、健康経営を実践する企業が増えています。
健康経営がもたらすメリット
健康経営は、単に健康管理面でのマネジメントが行えるだけではなく、長期的に見て経営面もよくなる可能性が高い方法です。
しかし具体的にはどのようなメリットがあるのかは、イメージしにくいかもしれません。次に健康経営がもたらすメリットを5つ紹介します。
(1)医療費の削減
企業で社員の健康づくりを促進することにより、社員が無理をして身体を壊さなくなるため、経費としての医療費が削減できます。また、身体を壊して社員がやめるリスクも軽減でき、一石二鳥です。
(2)生産性の向上
長時間労働は、疲弊するだけでなく生産性も向上しないため、メリットがありません。逆にしっかりと従業員に休息を取ってもらえば、決められた時間に集中して仕事をこなせるようになり、結果的に生産性が向上します。
ロバート・ローゼンが著書「ヘルシー・カンパニー」で述べたように、健康経営を実践すると、スタッフのモチベーションが向上し、これが生産性の向上へとつながります。また心身ともに健康になることで欠勤率も低下し、急な疾病や心身の不調で休職・退職するリスクを減らせるでしょう。
(3)離職率低下と人材の定着
健康経営を実践すれば、離職率の低下や人材の定着といった効果にも期待できます。従業員がメンタルや体調に不調を抱えている状況では、当然離職率は高まり、人材は企業に定着しません。離職率が高ければ、採用や教育にかかった手間やコストはすべて損失となり、残った従業員の負担が増えてさらに離職率が高まる悪循環に陥ります。
しかし健康経営を実現できれば、離職率が下がりこれらのコストや手間を最小限に抑えられます。少子高齢化の進む日本においては、今後さらに新たな人材の採用が難しくなると予想されるため、人材が定着することは、大きなメリットといえるでしょう。
(4)企業イメージの向上で採用力を強化
人材の確保には、企業イメージが重要です。過酷な労働環境を強いられる「ブラック企業」は、企業イメージが下がり、人が集まりにくくなります。一方で健康経営を実施しているとアピールできれば、求職者に対し従業員を大切にしているイメージが与えられるでしょう。このように健康経営を行うことは企業イメージの向上につながり、結果的に優秀な人材が集まりやすくなります。
(5)社内の風通しがよくなる
健康経営には、メンタルヘルス不調の予防策としてコミュニケーションの活性化も重要であり、結果として社内の風通しがよくなるのもメリットです。職場内でコミュニケーションが活発であれば、社員同士で信頼関係を構築しやすく、気軽に質問や相談が行えます。
またコミュニケーションが活発であれば、心理的安全性(自分の考えや気持ちを気兼ねなく表現できる状態)を確保できます。遠慮なく意見を交わせる環境があれば、よりよいアイディアが出やすく、生産性・クリエイティビティ向上にも期待できるでしょう。
健康経営の評価方法
健康経営を評価する指標としては、健康経営優良法人認定制度のほかにも、株価があります。従業員の健康を気づかうことで働きやすくなり、生産性の向上・業績アップにつながれば、結果的に株価の上昇に結びつくためです。
そのためには、経済産業省と東京証券取引所が選定する、健康経営銘柄を理解する必要があるでしょう。
健康経営銘柄とは
健康経営銘柄とは、国民における健康寿命延伸のための日本再興戦略の一つです。これは企業の健康経営を国が力を入れて促進する取り組みであり、上場企業から健康経営を実践している企業が投資家に紹介されます。
健康経営へ戦略的に取り組む企業を証券取引所で適切に評価してもらい、企業にインセンティブを与えることで、継続的に健康を維持するための施策を実践してもらうのが狙いです。実際の活動評価は、次の基準をもとに行われます。
(1)経営理念・方針
企業経営における健康への取り組みが、経営理念や方針にもとづいているのかを確認します。
健康経営の促進は、経営理念の一つとして行うものであり、企業戦略として取り組めているかどうかがポイントです。健康経営を、経営的視点をもって実践するのが非常に重要です。
(2)組織体制
健康経営の促進は、社員ではなくトップの仕事です。
そのため、経営者が積極的に健康経営に対して関心をもち、どれだけの金銭投資ができるかも重要です。またそれを外部ではなく、企業内で管理できるよう、責任者が設置されているかもチェックされます。
(3)制度・施策実行
どのような取り組みがされているのか、といった具体策も重要です。企業に健康経営に取り組むための制度ができており、施策がどのように実行されているかがポイントです。具体的な認定基準としては、次のような項目が設けられています。
- 従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討
- 健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント
- 従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」では、定期健診受診率やストレスチェックの実施、有給休暇の消化率といった点をチェックし、自社における健康課題を確認します。またこの課題に対し、健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標・計画の立案が必要です。
次の2つの項目に関しては、実際に過重労働の防止やメンタルヘルス不調の防止、健康促進に向けた具体的な施策の実施が求められます。具体的に何をするか、詳しい取り組みの例については次の見出しで紹介しているため、こちらも参考にしてください。
(4)評価・改善
実際に行っている施策に対して効果検証を行い、改善を行っているかを確認します。PDCAサイクルを循環させ、よりよい健康経営を目指すために、結果に対しての課題点を抽出し、それをどう改善するか考え実行に移しましょう。
(5)法令遵守・リスクマネジメント
企業は、労働関連の法令遵守が義務づけられています。
健康診断の実施、長時間労働の抑制など、企業としてやるべきことに取り組めているかを確認しまましょう。企業としてはできていることが当然であるため、法令遵守・リスクマネジメントの健康経営の前提条件とされています。
健康経営の具体的な施策例
健康経営を実現するため、実践すべき施策について詳しく紹介します。健康経営銘柄や健康経営優良法人の認定基準をもとに、カテゴリー別で紹介するため、これらの認定を目指している場合も参考にしてください。
定期健診受診率や保健指導の実施率アップ
定期健診受診率が100%に達していない企業は100%を達成させ、あわせて保健指導の実施率向上も目指しましょう。定期健診は労働安全衛生法に定められた義務ですが、受診率が100%に達していない企業も多く存在します。
厚生労働省が行った「労働者健康状況調査」※によれば、定期健康診断の実施率は500人以上の規模の企業では100%になるものの、それ以下の規模では89.4~96.8%に留まっています。また実施した企業においても、受診率は平均でも81.5%と、100%には遠くおよばないのが現状です。そのため、定期健診受診率が低い企業は次のような対策を行い、受診率・実施率アップを目指しましょう。
- 職場で一斉検診を実施
- 受診していない事業者へ、メールやチャット・声かけで連絡し受診を促す
- 受診が終わった後の報告を義務づける
- 受診を特別休暇扱いにするか、残業時間として認定する
※出典:厚生労働省「 平成24年 労働者健康状況調査|結果の概要 」(2024年5月25日閲覧)
ワーク・ライフ・バランスの支援
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活のバランスがとれた状態のことで、どちらも充実させた働き方・生き方を目指します。残業や休日出勤などが多い状態では、プライベートが充実せず仕事にも悪影響が出ます。
そのため、有給休暇の取得促進や残業時間の削減、育児・介護の支援などを行うことで、仕事とプライベートの両立を支援しましょう。具体的な施策は次のとおりです。
- テレワークやフレックスタイム、時短勤務の導入
- 時間単位での有給休暇導入
- 病気休暇・リフレッシュ休暇といった特別休暇の導入
- パソコンのログイン・ログアウト時間の記録(残業時間の改ざん防止)
- 残業時間の事前申告制度導入
職場でのコミュニケーション促進
職場でのコミュニケーション促進も、健康経営につながります。メンタルヘルス不調は、職場における人間関係を原因とするケースが多くあります。しかし職場でのコミュニケーションを促進できれば社員同士で信頼関係が構築でき、気軽に質問・相談がしやすくなり不調の原因解消につなげられるでしょう。
また前述したよう職場内のコミュニケーションが活発であれば、心理的安全性を確保できるため、風通しがよくなり生産性向上にも期待できます。具体的な施策例は次のとおりです。
- 社内SNSやチャットツールといったコミュニケーションツールの導入
- サンクスカードといった社員の交流を促進する制度の導入
- 社内部活やサークルへの参加を促し、金銭支援や備品・場所などを提供
- 社員旅行や、家族交流会といった交流イベントの企画・開催
食生活の改善や運動機会の増進
運動不足や食事の偏りは体の不調につながるため、これらを改善するための施策もおすすめです。食事や運動はこれまで従業員の自己責任・自己管理とされていましたが、職場の高齢化や人手不足を考えれば、企業からの関与も重要になると考えられます。
具体的な施策例は次のとおりです。
- 社員食堂や仕出し弁当といった、現物支給で栄養バランスを管理
- 社内自販機で、健康に考慮した食事や飲料を販売
- 腹八分目運動や、料理イベントといった健康促進イベントの企画・開催
- ジム・スポーツクラブの優待券といった金銭的支援
- 社内運動会といったスポーツイベントの企画・開催
- 徒歩通勤・自転車通勤の促進・支援
過重労働やメンタルヘルス対策
万が一過重労働やメンタルヘルスの不調が発生した場合に、即座に対応できる体制の構築も重要です。これらのトラブルを早期発見し、従業員の負担軽減や復帰支援ができるよう対策を講じましょう。具体的な施策例は次のとおりです。
- メンタルヘルスやハラスメントが気軽に相談できる(外部)窓口の設置
- 医師やカウンセラーによる面談・指導の実施
- 不調をきたした従業員に対する復帰プログラムの作成
- 指導にあたっていた上司への面談や指導の実施
受動喫煙対策
喫煙は肺がんをはじめ数多くの病気を引き起こすものであり、職場での副流煙による受動喫煙も大きな健康被害につながるため、対策を行いましょう。この時、喫煙者に対して禁煙を促すための取り組みを行うのもおすすめです。具体的な施策例は次のとおりです。
- 室内(禁煙室以外)や職場の敷地内での禁煙(分煙の徹底)
- 禁煙治療の費用補助
- 喫煙者に対して健康セミナーや保険指導の実施
- 非喫煙者や禁煙達成者に対し手当を支給
感染症予防対策
感染症は、社内に広がると事業の継続自体危うくなる危険性があり、従業員の命にも関わるため、しっかり対策しましょう。
- 従業員や家族が感染、もしくは濃厚接触者となった場合のルール策定
- 自宅待機や療養期間中は、特別休暇として対応
- テレワークの導入
- 出勤時の体温測定といった健康管理の実施
- 海外出張・勤務時に予防接種を実施し、予防内服を用意
健康経営の取り組み成功事例
実際に問題を明確化し、戦略をもって健康経営に取り組んだ企業は、社員の離脱やコスト削減などに成功しています。次にこれら3つの事例の内容を紹介します。
事例1. 会社全体の医療費削減
A社では、代表取締役社長がみずから健康管理のトップも兼任することにより、社内全体への意識づけに成功しました。
肥満や血圧などの項目をピックアップしたことで健康経営が明確化し、企業トップがみずから実践ことで、管理職であるメンバーも積極的に取り組み、会社全体の医療費削減が実現しました。
事例2. 長時間労働の改善
B社では、社内アンケートを実施し、残業による食生活の乱れから、体調不良や肥満を引き起こしている社員が多数いることを知りました。
そこでまずは長時間労働削減にコミットし、「残業削減委員会」を設置。結果残業の多い部署や少ない部署が可視化され、少ない部署の働き方例を参考にすることで、少しずつ長時間労働が改善されました。
事例3. 有給休暇の取得率アップ
C社では、健康維持には余暇の過ごし方が重要であるとし、休暇取得推進を行いました。
日本では上司が有給を取得しないから取得しにくい、といったケースが少なくありません。それを改善するために、社内で決めた取得条件を満たせない場合にはボーナスを減少し、全体の有給休暇取得率のアップに成功しました。
健康経営に取り組む際のポイント
健康経営による成果を最大化するには、ここまで紹介したように自社の問題を明確にする必要があります。次に健康経営に取り組む際のポイントを解説します。
1. 経営トップが主導する
企業が健康経営に取り組む姿勢として、社員に任せきりにするのではなく、管理職であるメンバーが中心になる必要があります。企業の方針を進めていくのは社員ではなく、リーダーだからです。
2. 社員の能力を最大化する環境づくり
前述したよう健康的に働くためには、仕事とプライベートのバランスが非常に重要です。結果を最大化するため、社員がやる気をもって取り組める環境や制度を構築しましょう。
3. 長期的な視点をもち継続して取り組む
健康管理は一朝一夕でできるものではありません。大切なのは継続することで、すぐに結果が出ないからといって活動をやめてはいけません。成果を最大限に発揮するためには、長期的な視点をもって活動するのが重要です。
健康経営の始め方
健康経営を実践するためには、まず概念を組織マネジメントの一環として体系的に理解し、実践する方法を検討する必要があります。とくに次の点に配慮しながら、一つひとつ計画的に進めましょう。
明確なビジョンの提示
まず、経営理念に沿って健康に関する基本方針を決定し、企業のトップが大々的に通知しましょう。
従業員一人ひとりがみずからの健康問題に向き合い、企業の掲げる健康経営に取り組むためには、経営のトップが意義や重要性を認識し、組織の内外に広くアピールするのが重要です。
できれば健康経営の概念を理念に取り入れ、何をどのように実践していくのか具体的なプランを立てましょう。また従業員のみならず、他のステークホルダーにもメッセージとして発信するのもおすすめです。
組織の体制の配備
健康経営を実践するための体制づくりも欠かせません。各部署に健康経営の専任・兼任職員を設けるといった対応や、健康経営推進のための専門部署を設置します。
健康についての専門資格があるスタッフを配置するのもおすすめです。権限を与えて自発的に取り組んでもらえるよう、体制づくりを模索しましょう。
目標を定め、施策を実行
組織づくりを行ったら、まず従業員の健康状態を把握し、そこで浮かび上がった課題を解決するための施策を検討してください。しっかりと目標を定め、計画的に実行する必要があります。
また定期的にどのような効果を上げられたかを検証、設定した数値目標の達成度について計測し、次の課題の設定を行います。このように絶え間なくPDCAを回し、よりよい健康経営を目指しましょう。
関連おすすめ記事
次の記事では、健康経営と働き方改革の関連性を詳しく解説しています。
次の記事では、健康経営で欠かせないストレスチェックや、従業員満足度の向上について詳しく解説しています。ぜひこちらも参考にしてください。
健康経営をするために欠かせないサービスの紹介は、次の記事で行っています。健康経営の導入を考えている方はぜひ参考にしてください。
健康経営は今後の発展に必要不可欠
企業運営におけるシステムの関与がいかに大きくなろうとも、重要な判断や方向性を決めるのは人間です。優秀な人材がいかんなく能力を発揮できる環境があってこそ、企業の繁栄が保証されます。株価にも影響を与える、健康企業銘柄が存在するのも、この事実が広く認知されているからにほかなりません。
確実に訪れる生産年齢人口の減少といったリスクがあるなか、優秀人材を確保し、企業繁栄の継続を実現するには、今後ポイントを押さえた健康経営への取り組みが欠かせなくなるでしょう。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査