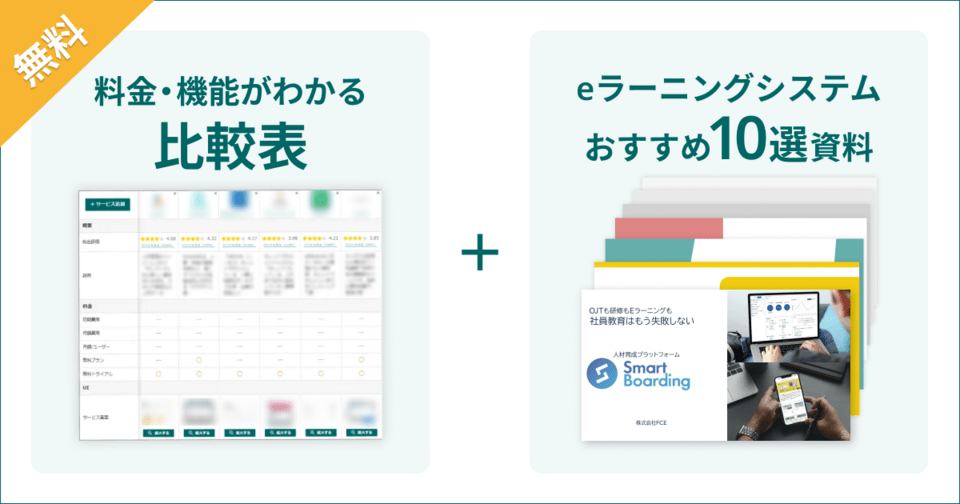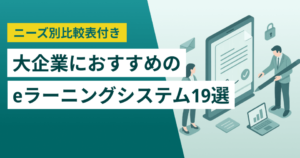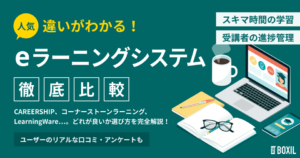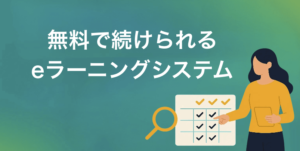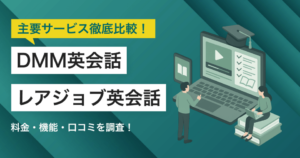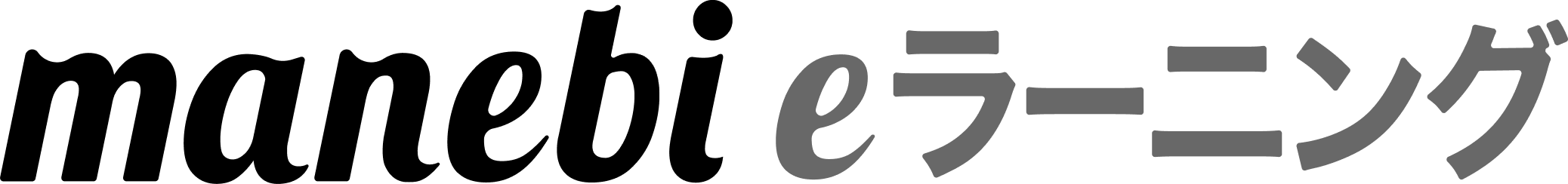アクティブラーニングとは
アクティブラーニングとは、講義や授業を受けるだけの受動的な学習ではなく、学習者自身が主体的に課題を見つけ、解決に向けて能動的に学ぶ学習方法です。
アクティブラーニングの「アクティブ」は「能動的な」という意味の「active」であり、その対義語は「受動的な」を意味する「passive(パッシブ)」です。
このことから、アクティブラーニング(active learning)は、みずから主体的に考え、問題解決能力を養うことを目的とした学習法であることがわかります。
文部科学省におけるアクティブラーニングの定義
文部科学省が大学教育において示したアクティブラーニングの定義は、次のとおりです。
【アクティブ・ラーニング】
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。
※出典:文部科学省「 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(答申) 用語集 」(2025年9月17日閲覧)
新学習指導要領(小中高校教育)におけるアクティブラーニングの定義は、次のとおりです。
アクティブラーニングとは、「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び」※1のこと、もしくは「主体的・対話的で深い学び」※2のこと。
※1 出典:文部科学省「
教育課程企画特別部会 論点整理
」(2025年9月17日閲覧)
※2 出典:文部科学省中央教育審議会「
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)
」(2025年9月17日閲覧)
体験学習との違い
体験学習とは、実際の活動を通じて学ぶ学習形態です。学習者自身が集団との相互作用を体験しながら、自己理解や他者理解を深めていく学習方法です。
体験学習は、アクティブラーニングの一環としてプログラムに組み込まれることもあります。
PBL(課題解決型学習)とは
PBL(Problem Based Learning)は、日本語では「問題解決型学習」と呼ばれています。みずから発見した課題の解決方法を考え、その過程で知識や経験を深めていくアクティブラーニング手法です。参加者が具体的なプロジェクトに落とし込む「Project Based Learning」(プロジェクト型学習)の略称とする場合もあります。
PBLは、医療分野の現場での問題解決能力が重視される教育過程で実施されていたものが、アクティブラーニングの方法として採用されたものです。PBLでは、チームで問題を発見し、仮説を立てて解決策を考え、検証を行います。
アクティブラーニングが広まる背景
アクティブラーニングは大学教育への導入に始まり、新しい学習指導要領にも記載されるようになりました。
2012年8月に中央教育審議会が、「大学教育において、学生の受動的受講から能動的学修への転換が必要」という「質的転換答申」を行ったことにより、大学でのアクティブラーニング導入が開始。
さらに2014年11月には、文部科学大臣が「初等中等教育における教育課程の基準などの在り方について」について、中央教育審議会に意見を求めました。そして、小・中・高校におけるアクティブラーニング導入が検討されました。これが、新学習指導要領の導入や英語教育改革、大学入学共通テストといった、2020年の教育改革へとつながっていきます。
ビジネスの分野では、企業が競争力強化のために、人材育成の手段としてアクティブラーニングに注目しました。社会や顧客ニーズの目まぐるしい変化にいち早く気づき、能動的・自主的に課題を解決できる人材が求められるようになったためです。
企業は近年、人材こそが成長の原動力と捉え、人的資本の価値を高める戦略の一環として、アクティブラーニングの導入を進めています。
アクティブラーニングのメリット
企業がアクティブラーニングを導入するメリットについて、紹介します。
人材の主体性を養う
アクティブラーニングでは、学習者自身が能動的に学ぶことが求められるため、主体性を育めます。
チームワークの強化
アクティブラーニングでは、グループで対話して他者の意見に耳を傾けながら、問題解決を探っていきます。そのため、コミュニケーションやコラボレーション能力が育まれ、組織のチームワーク強化につながります。
プレゼンテーションスキルの向上
アクティブラーニングのグループディスカッションやディベートを通じて、説得力のあるプレゼンテーションスキルを身につけられます。
問題発見・課題解決能力の向上
アクティブラーニングの能動的な学びの姿勢と、他者との対話による新たな視点は、人材のロジカルシンキングスキルを育み、問題発見・課題解決能力の向上に寄与します。
アクティブラーニングの手法
アクティブラーニングは、問題発見・課題解決やグループディスカッションといった、他者と一緒に考える過程を設けているのが特徴です。代表的なアクティブラーニングの手法について紹介します。
ジグソー法
ジグソー法は、学習に参加する者同士で協力し、互いに教え合うことで理解を促進するアクティブラーニング手法です。
教師が全員に対して、異なる学習内容を共有します。グループを作り、各メンバーがそれぞれ学習する内容を決めます。新しく学習内容別のグループを作って集まり、グループ内で学習。それから、最初のグループに戻って、互いに学習した内容を伝え合います。
ジグソー法は、他者に学習内容をうまく伝えるために、自己の学びが深くなり、コミュニケーション能力とコラボレーション能力が養えます。
ラウンドロビン
ラウンドロビンは、グループを作り、1つの課題に対して順番にアイデアや意見を出し合っていくアクティブラーニング手法です。
途中で質問や議論をせずに、決めておいた順番に従って新しい考えを次々に発言することがポイントです。参加者全員に順番が回ってくるため、他者の考えを平等に聞けます。グループで行う「壁打ち」のような効果が期待できます。
ケースメソッド
ケースメソッドは、実際の事例をもとに、複数名で討論して最善策を探っていくアクティブラーニング手法です。
参加者は、具体的な事例を疑似体験して、実践的な解決方法を生みだす能力が高まっていきます。
ケースメソッドは、1920年代に、リーダーシップや経営手法を身につける手法として、アメリカのハーバードビジネススクールで始まりました。アクティブラーニングを導入する多くの企業では、このケースメソッドが採用されています。
フィールドリサーチ
フィールドリサーチは、発見・体験型のアクティブラーニング方法です。フィールドメソッドとも呼ばれています。
フィールドリサーチでは、実際の現場を訪れて観察や調査を行い、課題解決方法を探ります。これにより、課題発見力や課題解決能力が高まり、新人研修からリーダーシップ研修まで、幅広い人材教育に活用できます。
KP法
KP(紙芝居プレゼンテーション)法とは、あらかじめ紙に授業の要点をまとめておき、進行に合わせて黒板やホワイトボードに貼り付けながら説明していく手法です。
従来のプレゼンと違って要点が残り続けること、講義全体のまとまりを意識できることで理解力を高める効果があります。
アクティブラーニング実践のポイント
アクティブラーニングの目的は、参加者の「主体的な対話と学び」を促進することです。
アクティブラーニングにおいては、教師は講師というよりファシリテーターとなり、議論の進行や参加者の主体的なアウトプットを促す役割を担います。
対話によって導きだしたアウトプットは、次回の議論へのヒントとするためにも、検証とフィードバックを行うこともポイントといえます。
アクティブラーニングの導入事例
アクティブラーニングを導入している企業や大学、高校の事例を紹介します。
ソニー銀行
ソニー銀行株式会社では、入社後2か月の間に行われる新入社員研修に、アクティブラーニングを導入しています。5日間の「データサイエンスブートキャンプ」で、実際にデータ分析を行い問題解決のアプローチを新入社員に修得してもらいます。
また、講義にもアクティブラーニングを導入し、ペアを組んで講義の最後に学んだことを検証する工夫がされていることも特徴です。
ソニー銀行が、アクティブラーニングを新入社員研修に取り入れた目的は、データドリブンな企業カルチャーを築いていくことです。新入社員が配属後に、周囲のデータドリブンな考え方の社員と、コミュニケーションの取りやすい環境の構築を支援しています。
産業能率大学
産業能率大学経営学部では、組織で意思決定を行う社会人に学生を適応させるため、アクティブラーニングによるグループ活動を重視したカリキュラムが採用されています。
実践方法として、授業の各科目にアクティブラーニングを取り入れた「基本プログラム」と、講義形式で知識や理論を学ぶ「バックアッププログラム」を同じ位置付けで配置しています。それぞれが相互に補完し合う形となっているのが特徴です。
たとえば、マーケティング情報コースでは、「マーケティング実践」がバックアップとしての講義科目、「マーケティング情報演習」が基本のアクティブラーニング科目となります。学生は、ビジネスゲームによる定量的評価の実践を行っています。
埼玉県立越ヶ谷高等学校
埼玉県立越ヶ谷高等学校では、小林先生の担当する「物理I」「物理II」で、グループワークを中心にしたアクティブラーニングの授業が年間を通して行われています。授業構成は、次のようなものです。
- 学習内容の説明(15分)
- 問題演習(35分)
- 振り返り(15分)
座席もグループも自由な中で、生徒同士の学び合い・教え合いを重視した問題演習が行われます。さらに、振り返りでは問題演習と同じ「確認テスト」を実行します。
「なぜ解答までいたったか」の学び合い・教え合いを通じて、解答の導き方を定着させる取り組みが行われていることも特徴です。
関西学院千里国際中等部・高等部
関西学院千里国際中等部・高等部と大阪インターナショナルスクールは、開校時より国際教育とアクティブラーニングを実践してきた国内でも先駆的な教育機関です。同校では、2012年からiPadを高校生全員に貸与して授業などに活用しています。2017年からは、BYOD(Bring Your Own Device)に移行して、高校生が自分のデバイスを学校に持ってくる体制にしています。
2022年夏には、教室の大改修を行い、教室の「前」「後」という概念を取り払い、教室壁面にホワイトボードを設置、大きな教卓を取り払い、アクティブラーニングを推進できる教室仕様に改めました。
また、教室の壁を全面ガラス張りとし、開放感あふれる空間へとリニューアルしました。さらに、ロッカーの高さを低くすることで、生徒が自由にコラボレーションできる学習スペースを実現しています。機能的であるだけでなく、生徒の主体的なアクティブラーニングが生まれる美しいデザインとなっています。
アクティブラーニングが人材の新しい価値を生み出す
アクティブラーニングとは、学習者が主体的に課題を発見し、解決に向けて能動的に学ぶことです。企業は、社会や顧客ニーズの目まぐるしい変化にいち早く気づき、能動的・自主的に課題を解決できる人材育成の手段として、アクティブラーニングの導入を進めています。
アクティブラーニングを活用することで、人材の新しい価値を生み出し、競争力を高めるための人的資本戦略が実現できるようになります。
\ 稟議や社内提案にも使える!/
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査




-e1767593455313.jpeg)