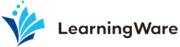eラーニングとは - メリット・デメリット | 目的・費用・トレンドまで紹介

目次を閉じる
- eラーニングとは
- LMS(学習管理システム)とは
- eラーニングの目的
- eラーニングのメリット
- eラーニングのメリット【管理者】
- eラーニングのメリット【受講者】
- eラーニングのデメリット・課題
- eラーニングのデメリット【管理者】
- eラーニングのデメリット【受講者】
- eラーニングの市場規模
- eラーニングの歴史
- eラーニングの誕生以前
- CD-ROMによる学習
- オンラインシステムの導入
- これからのeラーニング
- eラーニングの使い方
- 受講者側
- 管理者側
- eラーニングのトレンド・活用例
- ブレンディッドラーニング
- ゲーミフィケーション
- eラーニングの費用比較
- eラーニングシステム導入で利用できる補助金
- オンラインスキルアップ助成金
- IT導入補助金
- eラーニングで人材育成を効率化しよう
- BOXILとは
eラーニングとは
eラーニング(e-Learning)とは、パソコンやスマートフォン、タブレットを使ってインターネットを通して学ぶ学習形態のことです。eラーニングの「e」とは、「電子の」「インターネットの」を意味する英語「electronic」の略です。
教育機関で用いられる「オンライン学習」や「オンライン教育」と同じ意味の言葉ですが、eラーニングは企業の社員教育や人材育成において多く使われる傾向があります。
eラーニングを支えるシステムは、LMSと呼ばれています。
LMS(学習管理システム)とは
LMSとは「Learning Management System」の略で、「学習管理システム」と訳されています。
LMS(学習管理システム)は、eラーニングの受講者と教材・学習履歴・成績の管理を一元的に行うeラーニングシステムです。受講者がログインして学習コンテンツを閲覧したり、管理者が受講メンバーの受講状況や成績を管理したりできるのが特徴です。
LMSとeラーニングの違いやLMSの機能については、次の記事で詳しく解説しています。
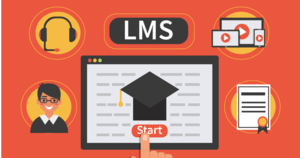
eラーニングの目的
企業がeラーニングを行う目的としては、学習機会を拡大し人材育成やキャリアアップを支援することが挙げられます。とくにキャリアチェンジをされた方や新入社員などは、知識が不足していることも多いため、これをフォローする研修として利用されます。
また、従業員が業務を行いながら学習の機会をつくるのは難しいですが、eラーニングを利用すればすきま時間を活用した学習が可能です。従業員としても業務に役立つ知識が得られるため、手軽にスキルアップやキャリアアップが目指せるでしょう。
eラーニングのメリット
eラーニングのメリット【管理者】
eラーニングの管理者のメリットは、社員教育や研修の時間と場所の制約がなくなることと、教材の再利用ができることです。工数の限られている研修において、担当者が教材の改善に時間を割けるようになるのは大きなメリットといえるでしょう。集合研修と比べた際の特徴は次のとおりです。
| オフラインでの集合研修 | eラーニングでの研修 | |
|---|---|---|
| スケジュール調整 | 必要。 該当社員全員のスケジュール確保が必須 |
不要。 好きなタイミングで受講 |
| 教材の配布と更新 | 現地での配布。 修正内容はメールにて連絡 |
公開のみで配布。 修正や更新も教材を編集して通知するのみ |
| 教材の再利用 | 不可能。 必要に応じて都度講義をする |
可能。 教材の共有のみで完了 |
| コスト | 講義のたびにさまざまな費用がかかる | 費用を抑えて質の高いコンテンツを提供 |
スケジュール調整が不要
eラーニングのメリットの1つは、スケジュール調整が不要となる点です。
集合研修では、受講者全員のスケジュールと収容するための会場をおさえる必要がありました。それに対しeラーニングは、教材を作成して配布することに集中できるのがメリットです。
教材の配布と更新が容易
eラーニングの利点には、教材を配布しやすく更新しやすい点があります。集合研修では、都度講師が印刷や配布をしなくてはなりません。
eラーニングでは、Web上で教材を作成し配信まで完結できます。さらに更新もオンラインで行い、即座に反映されるためスピーディーに情報共有ができ、情報の周知徹底も簡単です。
教材の再利用が可能
eラーニングの便利なメリットとして、教材を再利用できる点があげられます。
集合研修では定期的に時間を割いて講師が直接教えます。しかし、eラーニングでは一度作成したドキュメントや動画を編集して公開するだけで、何度でも再利用が可能です。
受講者の管理を効率化できる
eラーニングは、受講者の学習進捗状況やテスト結果、出席状況などをすべてオンラインで把握できるため、学習管理を効率化できます。たとえば、進捗が進んでいない受講者の情報を抽出し、メールを送って学習を促すといったように、従来の方法よりも工数を削減して管理が行えます。
また情報を一元管理できるため、データ分析も容易です。受講者を適正に評価し、教材や社員教育の課題も把握可能です。
コスト削減
どのようなeラーニングシステムを利用するかにもよりますが、eラーニングは集合研修よりもコストを抑えられる可能性が高いです。集合研修では会場代や講師への依頼料、交通費、宿泊費などが毎回かかります。
一方eラーニングは、これらの費用を抑えたうえで質の高い学習コンテンツが提供可能です。eラーニングシステムの費用相場に関しては、あとで詳しく紹介します。
eラーニングのメリット【受講者】
eラーニングの受講者のメリットは、スマートフォンでの受講が可能な点や自由に講座を選べる点にあります。集合研修と違い、画一的な方法での研修から開放された点はかなり大きいメリットといえるでしょう。集合研修と比べた際の特徴は次のとおりです。
| オフラインでの集合研修 | eラーニングでの研修 | |
|---|---|---|
| 時間と場所 | 参加者全員で一致させる | 各人が好きな場所と時間でOK |
| 学習内容 | 全員一律。ないし個別指導 | 習熟度に応じて選択 |
| 受講方法 | 指定の会場へ集合 | パソコンやスマートフォンから受講 |
| 教育の質 | 講師によってバラつきあり | 共通の教材で均一化 |
| 反復性 | 講師の話は一度きり | 繰り返し復習OK |
時間と場所の制約なし
特定の時間と場所に向けて調整しなくてよい点がeラーニングメリットの一つです。集合研修では、指定された会場へ決められた時刻に集まる義務が発生します。対してeラーニングでは、都合のつくタイミングでWebサイトにログインし、自由に学習を進められます。
習熟度に合わせて受講可能
eラーニングでは、習熟度に合わせ個人のペースで学習ができます。集合研修では、ひとまとめに進められるため、習熟度にかかわらず一律の内容を受講します。
eラーニングであれば知っている内容は飛ばしたり、講座自体をスキップしたりできるため、個人にとって必要な学習に注力できるでしょう。
スマートフォンでの受講が可能
eラーニングを受講するにあたって、スマートフォンやアプリだけで受講が可能となった点はメリットです。以前のパソコンを使用していた講習では、受講できる人に限りがありました。それに対しスマートフォンやアプリで受講できるeラーニングなら、社員でなくとも気軽にアクセスでき習得も容易です。
教育の質を均一化できる
eラーニングの場合、利用される教材は基本的に統一されているため教育の質の均一化が可能です。集合研修のような対面型学習の場合、担当する講師はそれぞれ考え方が異なるため、どうしても講義の質に差が生まれます。
一方でeラーニングは教材や学習コンテンツは全員同じであるため、同じ教材を使う限り、均一な教育を受けられます。
何度も繰り返し学習できる
eラーニングは、過去に受講した講座でも再度学習が可能です。集合研修の場合、研修後も教材は残りますが、講師の話を聞けるのは一度きりで、再度受講するには追加費用がかかります。
一方でeラーニングは気軽に復習ができるため、習熟度を高めてたしかな知識を身につけられるできるでしょう。
eラーニングのデメリット・課題
eラーニングのデメリット【管理者】
eラーニングの管理者側の問題点としては、「eラーニングシステムの導入や体制を整えるための負担が大きい」点が挙げられます。
ある程度のIT知識は必要
eラーニングには学習管理システム(LMS)が不可欠であるため、これを扱うための知識が必要です。操作やエラーに対応できる人材がいれば問題ありませんが、人的リソースが不足している場合は苦手な従業員でも扱えるよう、ITリテラシーの底上げが必要になるでしょう。
また、eラーニングは受講者からシステムに関する質問が来ることも考えられるため、事前に対応を考えなければなりません。ベンダーのサポートが受けられる場合もあるため、こちらも事前に確認してください。
学習コンテンツの作成に時間がかかる
eラーニングには教材となる学習コンテンツが不可欠で、これを内製すると手間や時間がかかります。もちろん市販の教材を購入しても問題ありません。システムに教材が付属していることや、ライブラリを定額で利用できるサービスもあります。しかし内容によっては独自の教材が必要な場合もあり、作成を迫られる場合もあるでしょう。
一方でeラーニングシステムには、コンテンツ制作ができるツール機能を搭載したものもあります。オリジナル教材が必要な場合は、このツール機能があるシステムを選び、なるべく効率的に学習コンテンツを制作しましょう。
eラーニングのデメリット【受講者】
eラーニングの受講者の問題点には、オンラインであるがゆえに実際に習得できているのか把握しにくい側面があげられます。ただし、日々のテクノロジーの進化により改善されている部分もあります。
モチベーションの維持が難しい
eラーニングのデメリットには、受講者のやる気がわかりにくく、モチベーション維持の難しい点があげられます。
eラーニングでは、それぞれの受講者の様子を伺いづらく、個人のモチベーションをつかむのがどうしても難しくなります。こうした欠点を補うために、チャット機能やランキング機能などが導入されているeラーニングシステムもあるため、受講者のモチベーション維持のためにも検討してみましょう。
実技の研修をしにくい
eラーニングを運用するうえで、実技の研修がしにくいのも大きな欠点といえるでしょう。
対面の研修では、人数によっては実技の研修を実施でき、フィードバックもしやすい環境でした。一方eラーニングでは、Web会議にて類似の動作をしてもらったり、逆に現場でスマートフォンを使って受講し、すぐに実践したりといった工夫がなされています。
インターネット環境が必要
eラーニングの受講には、安定したインターネット環境が必要です。
インターネット環境がない方は、eラーニングシステムにアクセスできず受講が不可能です。しかし、近年はモバイルWi-Fiやスマートフォンの普及によって、インターネットがインフラとして定着してきたため、そこまで障害とはなりえないでしょう。
コミュニケーションが不足する
eラーニングは、自己学習が基本でコミュニケーションが手薄となるため、学習中に疑問が生まれてもすぐにそれを解決できません。そのため、教材の内容がeラーニングだけで完結できるかどうかは、事前にチェックが必要です。
また受講者同士のコミュニケーションが不足することも懸念点です。集合研修の魅力の1つとして、社外の方との交流や情報交換が挙げられます。しかし、チャット機能やライブ授業機能などがない場合、eラーニングでこれを行うのは難しいでしょう。交流の場は、また別に機会を設ける必要があります。
eラーニングの市場規模
矢野経済研究所の調査※によれば、2021年度の国内eラーニング市場規模は、前年度比13.4%の約3,309億円を見込んでいます。法人向け(BtoB)、個人向け(BtoC)共に規模は拡大傾向です。
法人向けeラーニング市場は、コロナ禍以降集合研修や対面教育などがオンラインに切り替わった影響で需要が高まっており、2021年度も同様の状況です。また需要の高まりに伴いサービスの価格下落が起こっているため、コンテンツ制作の依頼やシステム導入はしやすい環境になっていると言えるでしょう。
※出典:矢野経済研究所「eラーニング市場に関する調査を実施(2022年)」(2023年9月1日閲覧)

eラーニングの歴史
eラーニングはIT技術の進化とともに誕生し、形を変えています。そこで次に、eラーニングが歩んできた歴史について簡単に紹介します。
eラーニングの誕生以前
eラーニングが誕生する以前は、オフラインでの集合研修や、テレビ・ビデオを教材とした学習が行われていました。しかし集合研修は時間や場所に制限があり、ひとまとめに進行が行われるため習得に差が出ます。
またビデオ教材は好きな時間に、映像でわかりやすく学習できますが、一方的に情報が送られるため、受講者からアクションを起こせないことが課題でした。そこでコンピューターを使って学習する方法が模索されました。
CD-ROMによる学習
1990年代の後半には家庭にパソコンが普及しはじめ、CD-ROMが標準装備されていたことから、CD-ROMを使った学習方法が生まれます。CD-ROMを使うことで、マルチメディアを活用した対話型の学習が可能となりました。
しかしCD-ROMはコストがかかるため一部の大企業しか導入できず、一度配布すると修正できない点が課題でした。
オンラインシステムの導入
2000年代になると、一般家庭・企業でも手軽に高速・大容量のインターネットサービスが利用できるようになり、システムによるWeb配信型の学習が普及しました。
企業はコンテンツの配布にかかるコストを大幅に減らし、教材の修正も手軽にできるようになります。またスマートフォン・タブレットが普及したことで、さらに利便性が向上しました。受講者はいつでもどこでも、インターネットを使って学習ができるようになりました。
これからのeラーニング
今後のeラーニングとしては、AI(人工知能)やVR・AR・メタバースなどの活用が考えられます。AIに関しては、個人それぞれの最適な学習プランの作成や、学習方法の提案といった可能性が考えられるでしょう。
また顔認証によるセキュリティの向上や、AIによる語学やコーディングのトレーニングなどはすでに実用化されており、今後さらなる進化が期待できます。
eラーニングの使い方
eラーニングはどのような使い方ができるのか、受講者と管理者別に解説します。
受講者側
eラーニングは、受講者側では次のような使い方が可能です。
- インプット学習(動画教材やテキスト教材、ライブ配信講義などでの学習)
- アウトプット学習(テストやレポートの提出)
- コミュニケーション(わからないことを質問したりアンケートに回答したりできる)
eラーニングでは、インプット学習に加え、テスト・レポートの提出などアウトプット型の学習が可能です。また、チャット機能を活用して、質問や受講者同士のコミュニケーションが可能なライブ配信機能を搭載したシステムも登場しており、多様な受講者のニーズに合った最適な学習環境を提供する仕組みが用意されています。
講師への質問をしたりフィードバックを受けたり受講者同士で情報交換をしたりできれば、eラーニングでの学習を深められ、効果の向上が期待できるでしょう。
管理者側
管理者側では、次のような使い方が可能です。
- 受講者登録
- 履修登録
- 教材・コース作成(教材の作成・登録)
- 受講管理(受講者の進捗管理や成績管理)
- メンタリング・フォローアップ(質問への対応や受講者への個別対応)
受講者の登録や教材・コース作成のほか、受講者の進捗状況や成績を一元管理したり、受講者の個別対応をしたりできるため、効率的にメンタリングやフォローを行えます。eラーニングシステムで受講者一人ひとりの達成度合いを把握し、受講生のモチベーションも維持しながら効果的な運用が可能です。
eラーニングのトレンド・活用例
eラーニングは時代とともに変化しています。本章では、現在のトレンドや新しい使い方を紹介します。
ブレンディッドラーニング
近年は、eラーニングと集合研修、2つの手法を組み合わせた「ブレンディッドラーニング(ブレンド型学習)」が話題になりつつあります。eラーニングでは基本的な知識の習得を行い、ディスカッションや質疑応答は集合研修で行うといった研修スタイルがブレンディッドラーニングです。
チャット機能やライブ授業機能が搭載されていないeラーニング単体での学習では、受講者にとって「受講者同士の交流ができない」「直接質疑応答ができない」といったデメリットがあります。しかし、ブレンディッドラーニングを活用すれば、自身のペースで学習できるeラーニングのメリットを維持したまま、デメリットとなる点を解消して学習効果を高められます。
ゲーミフィケーション
ポイント加算によるレベルアップやスコア競争といった、ゲームの要素や手法をコンテンツに取り入れ、より学習を楽しめるようにする「ゲーミフィケーション」が普及しています。
ゲーミフィケーションは、ゲーム感覚で受講者が目標達成へと向かうモチベーションを高め、意欲的に学習に取り組むことを目的としたものです。
ゲーミフィケーションは、強制ではなく自発的に学習に取り組むことをサポートできるため、ビジネスでの成果や実践力を高めることにつながります。
eラーニングの費用比較
企業がeラーニングを行うには、LMS(学習管理システム)と呼ばれるeラーニングシステムが不可欠です。システムはサーバー上に構築され、ここから教材を配信し、受講者の学習履歴や活動の情報が記録され、効率的に管理が行えます。
LMSは主に「オンプレミス型」「クラウド型」の2種類にわかれます。オンプレミス型は自社サーバーにシステムを導入し、社内ネットワークを通してアクセスするため、セキュリティレベルの高さが特徴です。
クラウド型は、システムをサブスク利用する形態のことで、インターネットを介してシステムを利用します。初期費用が安く、導入しやすいのが特徴です。
eラーニングシステムの費用は、オンプレミス型かクラウド型によって大きく異なります。それぞれ初期費用と月額費用にわけて紹介するため、参考にしてください。なお、システムに教材が付属している場合は料金内に含まれているか、作成ツールがオプションでないかも確認しましょう。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| クラウド型 | 5~20万円 | 従量課金タイプ:1ユーザー500~2,000円程度 月額固定タイプ:5~20万円程度 |
| オンプレミス型 | 100~500万円程度 | 3~10万円程度 |
eラーニングシステムのなかには無料で利用できるものもありますが、基本的には人数・利用期間・コンテンツに制限がかけられています。セキュリティ面でもリスクがあるので、有料のシステムがおすすめです。
eラーニングシステム導入で利用できる補助金
eラーニングに関連したシステムやサービスの導入は、補助金・助成金の対象です。システムは導入したいものの、資金面で不安を感じる方はぜひ利用を検討してください。
オンラインスキルアップ助成金
まず東京都の中小企業であれば、「オンラインスキルアップ助成金」が利用できます。これはeラーニングに特化した助成金で、コロナ禍にある企業を支援するためにつくられたものです。
受講料やeラーニングの運営にかかる費用が対象であるため、サービスによっては教材にかかる費用も対象にできます。助成額は2分の1~3分の2、上限額は20~27万円です。詳しくは公式サイトを確認してください。
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、全国の中小企業が新規のITツールを導入した場合に受けられる補助金です。eラーニングシステムももちろん対象ですが、認定事業者の商品やサービスから選ぶ必要があります。
通常枠から申請する場合、補助率は2分の1、上限額は150万~450万円です。詳しくは公式サイトを確認してください。
eラーニングで人材育成を効率化しよう
eラーニングによる社員教育や研修にはいくつものメリットがあるので、ぜひとも活用して効率化を図りましょう。反対にいくつかのデメリットは、eラーニングの運用方法によって対応するのが好ましいです。うまく工夫して、管理者・受講者ともに満足したeラーニングができるよう調整しましょう。
eラーニングシステムの選び方がわからない、おすすめのサービスを知りたい方は次の記事をチェックしてください。はじめてシステム選定をする方や入れ替えを検討している方が便利なよう、比較表を掲載しながらおすすめサービスを紹介しています。

本記事の内容は動画でも触れて解説しているので、視覚的に理解したい方は動画での視聴がおすすめです。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査





















 目次
目次