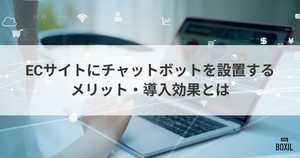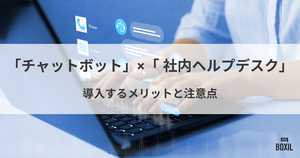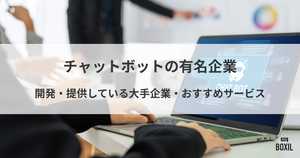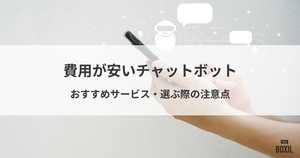チャットボット運用における改善ポイント・よくある課題


おすすめチャットボットの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なチャットボットを含むサービスを徹底比較しています。ぜひチャットボットを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
目次を閉じる
- チャットボットとは?
- チャットボットの重要性
- チャットボットにおける正答率や利用率、解決率とは
- 正答率
- 利用率
- 解決率
- チャットボット運用におけるよくある課題
- ユーザーの利用率が低い
- ユーザーの離脱率が高い
- 成果が出ているのか見えない
- メンテナンスが滞っている
- チャットボット運用の課題に対する改善策
- ユーザーからの認知を広げる
- 前後の数値を把握する
- FAQを拡充させて解決率の向上を図る
- FAQアップデート後の周知も忘れずに行う
- ユーザーの離脱ポイントを突き止める
- チャットボットの運用担当を増員する
- チャットボットにキャラクター性をもたせる
- 有人対応に切り替えられるようにする
- チャットボットの利用率や解決率が高まることで得られるメリット
- 顧客満足度が向上する
- 人件費の削減やコア業務への集中につながる
- 対応品質の均一化を図れる
- データをマーケティング活動に活用できる
- チャットボットを改善して顧客満足度向上を図ろう
チャットボットとは?
チャットボットとは、リアルタイムでメッセージのやり取りができる「チャット」と、コンピューターが自動で業務を実行する「ボット」を組み合わせた用語です。端的にいうと、ユーザーからの問い合わせに自動で返答するプログラムを指します。
データベースに蓄積された情報からロボットが最適な回答を探し出し、ユーザーに提示する、これがチャットボットの簡単な仕組みです。チャットボットには「シナリオ型」や「AI型」などの種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
チャットボットの概要や仕組み、メリットなどについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

チャットボットの重要性
チャットボットは、顧客満足度向上のために重要といえます。一般的には、コーポレートサイトやECサイトに「質問を受け付ける窓口」としてチャットボットを設置します。
チャットボットをWebサイト上に設置しておけば、ユーザーは24時間365日質問できるため、電話のような待ち時間が発生しません。
また、電話やメールと比べて気軽に問い合わせができます。ユーザーが質問しやすいことに加えて、正確な回答を提示できれば、顧客満足度の向上につながります。
チャットボットにおける正答率や利用率、解決率とは
チャットボットの改善にあたって理解しておきたいのが「正答率」や「利用率」、「解決率」などの指標です。それぞれの意味を解説します。
正答率
チャットボットにおける「正答率」とは、「質問に対してチャットボットが正しく回答できた割合」を指します。正答率はチャットボットの「回答精度」に直結します。
利用率
チャットボットにおける「利用率」とは、「どのくらいのユーザーが利用しているか」を示した指標です。具体的には、Webサイトを訪問したユーザーのうち何人がチャットボットにアクセスしたか、をもとに算出します。
解決率
チャットボットにおける「解決率」とは、「チャットボットによってユーザーの悩みが解決された割合」を指します。たとえば、100件の問い合わせに対して、50件を解決した場合、解決率は50%です。
チャットボット運用におけるよくある課題
チャットボットは顧客満足度の向上に寄与しますが、課題を抱える企業も少なくありません。チャットボット運用におけるよくある課題として、次のものがあげられます。
- ユーザーの利用率が低い
- ユーザーの離脱率が高い
- 成果が出ているのか見えない
- メンテナンスが滞っている
ユーザーの利用率が低い
チャットボット利用率が低く、導入が失敗に終わってしまうケースです。時間とコストをかけてチャットボットを設置しても、ユーザーに利用してもらえなければ意味がありません。そもそもチャットボットが認知されていない、使い方がわからないといった原因が考えられます。
ユーザーの離脱率が高い
チャットボットは利用されるものの、多くのユーザーが離脱してしまうケースです。チャットボットにおける「離脱率」とは、企業側が用意した回答にたどり着く前に、ユーザーが質問を辞めてしまうことを指します。
チャットボットでは、何度かやり取りを繰り返すことで回答を提示するのが一般的です。しかし、ユーザーがやり取りにストレスを感じたり、目的の回答を得られないと判断したりした場合、離脱につながります。
成果が出ているのか見えない
チャットボットは利用されているものの、成果が出ているのが見えないケースです。具体的なKPIや効果を設定していなければ、成果は感じにくくなります。
たとえば、チャットボットの導入目的が「有人オペレーターによる電話応対の負担軽減」だったとします。この場合、電話の件数がどのくらい減ったのか、オペレーターの働きやすさがどのように変化したかなど、数字の変化を見なければなりません。
メンテナンスが滞っている
チャットボットを中長期的に利用してもらうには、導入後のメンテナンスが重要です。何度もアップデートすることで回答精度が高まり、ユーザーの利用率や定着率も上がります。
しかし、チャットボットの運用や更新に詳しい人材がいない、時間がないといった理由でメンテナンスができていない企業も少なくありません。
チャットボット運用の課題に対する改善策
チャットボット運用の課題に対する改善策として、次のものがあげられます。
- ユーザーからの認知を広げる
- 前後の数値を把握する
- FAQを拡充させて解決率の向上を図る
- FAQアップデート後の周知も忘れずに行う
- ユーザーの離脱ポイントを突き止める
- チャットボットの運用担当を増員する
- チャットボットにキャラクター性をもたせる
- 有人対応に切り替えられるようにする
ユーザーからの認知を広げる
利用率を上げるためには、ユーザーに「チャットボット」の存在を知ってもらう必要があります。ユーザー認知を広げる方法は次のとおりです。
- プロモーションや情報発信を行う
- ページ訪問からチャットボットまでの導線設計を見直す
- 目に付きやすい場所にチャットボットを配置する
- 目に付きやすいデザインや配色にする
- バナーやテキストリンクでチャットボットに誘導する
Webサイトにおける配置場所やデザイン、導線を工夫することで認知拡大が可能です。必要に応じて、プロモーションや広告なども活用しましょう。
前後の数値を把握する
チャットボットの適切な効果測定を行うためにも、改善策の実行前後の数値を把握しましょう。たとえば、電話での問い合わせ削減を目的とした場合、「着信数(問い合わせでの)」を記録します。施策実行前の着信数と、実行後の着信数を比較することで、本当に成果が出ているのかを評価可能です。
ほかにも、チャットボットの起動数や解決率、遷移数(チャットボットから狙ったサイトに誘導できた数)など、さまざまな数値があげられます。ユーザー自身の「満足度」も重要な指標です。アンケートを行うことで、チャットボットに対する満足度を図れます。
FAQを拡充させて解決率の向上を図る
FAQを拡充することも、チャットボットの課題改善につながります。FAQとは、Webページに設置された「よくある質問」のことです。FAQをもとにルールベースで構築されたチャットボットでは、よくある質問に定型文で回答するシステムが一般的です。
FAQを拡充させる、つまり、より多くの質問を想定し、その回答を用意することを意味します。FAQが充実すれば、ユーザーが回答にたどり着くまでの時間を短縮可能です。精度の高い回答を用意できれば、ユーザーの満足度向上にもつながります。
FAQアップデート後の周知も忘れずに行う
FAQを拡張、アップデートしたら、必ずユーザーに対して告知しましょう。FAQを追加しても、それがユーザーに認知されなければ利用率は上がりません。次のような方法でアップデートの旨を伝えましょう。
- チャットボットの最初の会話でアップデートの旨を伝える
- アップデートするごとにチャットボットやキャラクターのデザインを変更する
アップデートによってチャットボットの回答精度が上がったことが伝われば、ユーザーの利用率も上がるでしょう。
ユーザーの離脱ポイントを突き止める
ユーザーとチャットボットのやり取りにおける「離脱ポイント」を突き止めることも重要です。離脱ポイントの例として、次のものがあげられます。
- 専門用語が増えるタイミングでユーザーの離脱が増えた
- 入力が自由記述式に切り替わった途端、ユーザーが離脱してしまった
専門用語や自由記述形式は、ユーザーに負担をかける要因になります。「わざわざ難しい用語を調べたり、入力の手間がかかったりするくらいなら、質問するのをやめよう」と考えるユーザーも少なくありません。離脱率が高い場合、離脱ポイントはどこか、なぜユーザーが離脱しているのかを熟考してみてください。
チャットボットの運用担当を増員する
現在1〜2名の少人数でチャットボットを運用している場合、運用担当者を増員しましょう。少人数でも運用できますが、「負担が偏りやすい」「業務が属人化しやすい」といった問題が起こりやすいです。
知識やノウハウが1人に集中すると、管理負担が大きくなるうえ、情報共有や引継ぎに支障が出る恐れがあります。担当者を増員することで負担が分散され、スムーズな情報共有が可能です。管理が行き届くようになれば、リソースにも余裕が生まれ、チャットボットの品質向上のために労力を使えるでしょう。
チャットボットにキャラクター性をもたせる
利用率を上げるためには、チャットボットにキャラクター性をもたせるのも効果的です。たとえば、チャットボットの回答者を、動物のマスコットキャラクターに設定します。動物のキャラクターが質問に対してかわいらしく返答すれば、ユーザーも親近感をもちます。会話の流れも自然になるでしょう。
ユーザーに「話しやすい」「面白い」と思ってもらえれば、チャットボット自体の利用率向上につながります。
有人対応に切り替えられるようにする
チャットボットから有人対応に切り替えることで、カスタマーサービス全体の品質向上につながります。「専門性が高すぎる」「文脈の難易度が高い」などの理由で、チャットボットでは正確な回答が難しい場合もあるでしょう。
その際、人間によるチャット(あるいは電話)にすぐ切り替えられると、顧客満足度の低下を防げます。チャット対応をロボットに依存するのでなく、ある程度「有人対応」のリソースを設けておくことが、全体の品質向上において重要です。
チャットボットの利用率や解決率が高まることで得られるメリット
チャットボットの利用率や解決率が高まることで、次のようなメリットを得られます。
- 顧客満足度が向上する
- 人件費の削減やコア業務への集中につながる
- 対応品質の均一化を図れる
- データをマーケティング活動に活用できる
顧客満足度が向上する
チャットボットの正答率を高めることで、顧客満足度の向上を図れます。加えて、チャットボットは24時間365日稼働できるため、有人オペレーターと比べてスピーディーな対応が可能です。クオリティの高い回答を迅速に届けることで、顧客満足度の向上につながります。
人件費の削減やコア業務への集中につながる
定型質問への回答をチャットボットに任せることで、人件費を削減が可能です。チャットボットの回答精度が高まれば、複雑な質問も「無人」で対応できるようになり、オペレーターの稼働時間を削減できます。これにより、オペレーターは本来やるべきコア業務に時間を割けるようになります。
対応品質の均一化を図れる
問い合わせに対する対応品質の均一化を図れるのも、チャットボットの強みといえます。とくに電話対応では、オペレーターの知識や経験によって個々に品質のバラつきが出やすいです。その点、チャットボットを導入すれば、対応に差が出ることはなく、統一された回答内容や品質を提供できます。
データをマーケティング活動に活用できる
チャットボットでは、ユーザーからの質問や返答データが蓄積され、それらをマーケティングに活用可能です。蓄積された会話データを分析することで、顧客の傾向やニーズを掴めます。新商品の開発や既存サービスの改善などに役立てられるでしょう。
チャットボットを改善して顧客満足度向上を図ろう
チャットボットを改善するためには、正答率や利用率、解決率などの数字を測定し、それらを高めるための策を講じることが大切です。具体的な対策として、認知の拡大やFAQの拡充、有人対応への切り替えなどがあげられます。
適切な改善策を講じることで、業務効率化やオペレーターの負担軽減が可能です。最終的には「顧客満足度の向上」につながります。
ただし、チャットボットには種類が豊富にあるため、自社の課題やシステムの特徴、導入形態に合わせたものを比較検討して選ぶことをおすすめします。