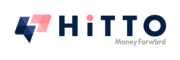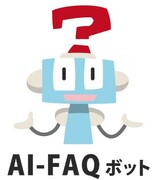チャットボットとは?仕組みやメリット


おすすめチャットボットの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なチャットボットを含むサービスを徹底比較しています。ぜひチャットボットを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
AI技術の発達によって、人同士の会話に近付きつつあるチャットボット。
幅広い対応ができるようになり、LINE・Facebook Messenger・Slackをはじめ多くのSNSやツール、そしてウェブサイトや公式アカウントなど、さまざまなシーンで活用の場が広がっています。
目次を開く
チャットボットとは
チャットボット(Chatbot)とは、「リアルタイムで短文のやり取りを行うこと」を意味する「チャット」と、「一定の作業を自動化するロボット」を意味する「ボット」を合わせた名称です。簡単にいうと、チャットでの質問に自動で返答するプログラムや、アプリケーションのことです。
また、AIチャットボットとは「AI(人工知能)を活用した自動会話プログラム」を意味します。人同士のような感覚でAIと会話を行い、情報収集や自動応答を行うのが特徴です。
AIとチャットボットの違い
簡単に言えば、AIは「学習・推論」、チャットボットは「会話」に重点を置いているのが特徴です。混同されがちな理由は、AIを搭載したチャットボットが数多く存在するからでしょう。
この二つの技術の主な違いは、応用の範囲と技術の複雑さにあります。AIはより広範なタスクと高度な問題解決に利用され、深層学習(ディープラーニング)や自然言語処理(NLP)など複雑な技術を含んでいることも多いです。一方、チャットボットは比較的単純なロジックで構成され、対話に関連するタスクに特化しています。
このように、AIとチャットボットは似ているようでいて、役割と機能が大きく異なります。
AIの特徴
AIは、人間のような知的能力を模倣し、学習や推論、自己修正などの複雑なタスクを実行するシステムです。これは、データ分析や機械学習、パターン認識など幅広い分野での応用が可能で、医療、金融、製造業などさまざまな業界に影響を及ぼしています。AIの最大の特徴は、データをもとに学習し、経験から判断や予測を改善していく点にあります。
チャットボットの特徴
チャットボットは、主にテキストや音声にもとづく人間との対話を自動化するプログラムです。すべてのチャットボットがAIを使用しているわけではなく、多くは固定されたシナリオにもとづいて対話を行います。チャットボットはとくに顧客サービス、FAQ応答、予約システムなどの分野で利用され、ユーザーの質問に対して迅速に回答を提供することが目的です。
チャットボットの起源と歴史
チャットボット(Chatbot)の起源は、1960年代にアメリカで開発された「ELIZA(イライザ) 」といわれています。当時は人間が事前に設定したパターンにしか対応できず、柔軟性に欠けていたため、ビジネス利用に至るほど広まりませんでした。
しかし2010年代人工知能(AI)が急速に発展し、自然言語処理技術が実用レベルになったことで状況は大きく変わります。チャットボットにAIを導入することで、人間が回答するような柔軟性のある回答ができるようになりました。
2011年には、Appleから「Siri」が登場し、日本でもチャットボットやAIが身近な存在となります。それからもチャットボットやAIは進化を続けてビジネスにも導入されるようになり、徐々に社会に浸透していきました。
チャットボットの現状
現在チャットボットはさまざまなサービスが登場しており、新型コロナウイルスの流行でビジネスのオンライン化を進める流れもあって、導入を検討する企業は増加しています。AIに関しては、ビッグデータの活用やディープラーニングによる自己学習などもあり、今も急激な速度で進化を続けています。
現在のチャットボットは、人間の言葉の意味を深く理解し回答するレベルには至っておらず、人間による細かなサポートも必要です。しかし2022年にChatGPTといった生成AIも登場しており、今後はさらなる技術の進化が予想されるため、今後もチャットボットを導入する企業は増えていくでしょう。
チャットボットの進化と未来
ChatGPTをはじめとする生成AIの出現は、チャットボットの機能と可能性を大きく拡張しています。これまで主にテキストベースの対話に限定されていたチャットボットですが、今後は画像認識や音声認識といったマルチモーダルな機能を統合する方向への進化が予想されるでしょう。
画像と音声の統合
チャットボットが単にテキストを解析するだけでなく、ユーザーがアップロードする画像や音声を理解し反応できるようになることで、よりリッチで直感的なユーザー体験が提供されるようになります。たとえば、ユーザーが写真を送信することで製品に関する情報を得たり、音声コマンドで簡単に情報をリクエストしたりできるようになるでしょう。
高度なインタラクション
マルチモーダルなチャットボットは、単なる質問応答を超え、より複雑で対話的なインタラクションを可能にします。たとえば、ユーザーの感情や意図を音声トーンや表情から読み取り、より適切な応答を行えるようになるかもしれません。これによって、顧客サポートや教育、エンターテイメントなど、さまざまな分野での応用が期待されるでしょう。
新たな応用分野の開拓
画像認識や音声認識を統合したマルチモーダルなチャットボットは、ヘルスケア、リテール、セキュリティなど、新たな分野での応用も期待されています。たとえば、医療分野では症状の画像を分析して初期診断をサポートしたり、小売業界では顧客の要望を音声で受け付けて商品を推薦したりするなど、多様な用途で利用されるようになるでしょう。
チャットボットのタイプ
チャットボットには、大きくわけて「AI型」と「シナリオ型」の2タイプがあり、この二つを組み合わせた「ハイブリッド」も存在します。よく導入される「AI型」と「シナリオ型」について詳しく解説します。導入する前に違いを確認しましょう。
AI型(ログ型)チャットボットの特徴
「AI型」はログ型とも呼ばれ、機械学習により会話のログデータを蓄積して最適な答えを返す方式です。
AI型は学習により、人間と会話しているような自然な応答が可能です。しかし、データの蓄積が少ない期間は、精度が上がっていないため、最適とはいえない答えを返すことがあります。初期段階では、チャットボットの訓練をして精度を上げなければいけません。サービスによっては初期段階から、ある程度の回答を学習している場合もあります。

しかし、最近ではChatGPTをはじめとした生成AIを用いたチャットボットも出現し、従来のAI型チャットボットが抱えていたデータの蓄積や精度といった課題点も、問題なく解決できるようになってきました。
こうした生成AIを導入したチャットボットは、卓越した会話能力や学習能力をもち、単なるチャットに留まらず幅広い分野で活躍しています。
シナリオ型(ルールベース型)チャットボットの特徴
「シナリオ型」はルールベース型とも呼ばれ、入力された文言によって、あらかじめ設定しておいた回答を返す方式です。
シナリオ型は事前に、シナリオを設定するため初期段階から顧客への対応が可能です。ただし、データの蓄積や回答精度が向上することはありません。期間が限定されているサービスや、質疑応答が複雑化しないサービスに導入すると効果的です。
チャットボットの仕組み
チャットボットは基本的に、「アプリケーション」と「bot」といわれるシステムをAPIで連携して作られます。botシステム内で問いかけの解釈・返答生成を行い、API経由でアプリケーションに戻される仕組みです。
 チャットボットの仕組み
チャットボットの仕組み
主にデータベースに蓄積された情報から、ロジックにしたがって回答を探して解析します。たとえば「〜の料金は?」といった問いに対し、名称や料金などのフレーズを分析して回答するイメージです。
音声解析やロジックのエンジンにAIを活用するものは、AIチャットボットとも呼ばれます。

チャットボットの種類
外部サービスや基幹システムなどと連携するチャットボットもありますが、一般的にはアルゴリズムによって次の4種類にわけられます。
選択肢タイプ
選択肢タイプのチャットボットは、データベースに蓄積されたシナリオや、設定された回答を選択して会話するタイプです。設定されていない受け答えはできません。
たとえば、カスタマーサポートボットが「製品に関する問い合わせですか?それともアカウントに関する問い合わせですか?」と質問し、ユーザーが選択肢のなかから回答を選ぶといった形式です。
このタイプは、単純な問い合わせやナビゲーションに適しており、とくにWebサイトでよく利用されてます。
ログタイプ
ログタイプのチャットボットは、行った会話の記録をログとして蓄積し、これを利用して人間に近づけた会話を行うタイプです。ログが蓄積されることによって、より自然な会話ができるようになるため、ログが少ない場合は会話が続かなくなります。
たとえば、カスタマーサービスで用いるチャットボットが過去の顧客とのやり取りを分析して、よくある質問に対する回答を学習するといったことが考えられます。
この方式は時間とともにボットの応答品質が向上し、より人間らしい対話が可能になるのが特徴です。反面、ログが少ない場合は会話が続かなくなってしまいます。
近年このタイプのボットはAI技術が進化してきたため、より複雑な対話を処理できるようになっています。
ハッシュタイプ
辞書に登録されたテンプレートをもとに、会話を行うタイプです。辞書タイプと呼ばれることもありますが、範囲の限定された利用方法であれば、受け答えには問題ありません。
たとえば、レストランの予約ボットが「予約」といった言葉に反応して、予約手続きを案内するといった形です。
このタイプのボットは、特定の状況や用途に特化しており、限定された範囲内では効果的に機能するでしょう。
ELIZAタイプ
「Yes」「No」や相づちで返答しつつ、相手の言葉を要約したり聞き返したりすることで会話するタイプです。前述したチャットボットの原型ともいわれるELIZAから名付けられており、基本的には聞き役に徹するチャットボットといえます。
このタイプは顧客の課題を解決するよりは、カウンセリングや聞き役に適しています。シンプルながらも相手が話しやすい環境を作るため、ユーザーに共感や理解を感じさせられるでしょう。
チャットボットの分類
チャットボットといっても分類はいくつかあります。
- 一つの質問に対して一つの回答をする一問一答形式
- 回答が複数用意されていて選んだ回答によって内容が分岐していくシナリオ型
また、これらはさらにいくつかの分類にわけられています。
チャットボットAPI
チャットボットAPIとは、言葉や回答のデータを登録しておくと、会話の組み立てをできるチャットボットの本体のことです。
チャットボットAPIには、Alexaと同じ会話エンジンを使用しているAmazon Lexや、SiriをカスタマイズできるApple SiriKitがあります。ほかにも、LUISと呼ばれる言語解析プログラムを使った、Microsoft Azure bot serviceといったサービスがあります。
メッセージングAPI
メッセージングAPIとは、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSが提供している、チャットボットとSNSをつなげられるAPIのことです。
たとえば、自然な会話のやりとりができるLINE ビジネスコネクトや、ダイレクトメッセージに対応したダイレクトメッセージチャットボットがあります。また、商品や領収書を表示する機能があるFacebookメッセンジャーbotといったサービスがあります。
Webチャット
Webチャットは、Webサイトに設置するチャットの入力と出力のツールです。Webサイトの右下に設置されているのを見かけたことがある人も多いかと思います。
WebチャットではSNSのような専用のアプリは必要とせず、Webサイトに簡単に設置できることが特徴です。
Webサイトに設置するためログインの手間がいらず、サイトからすぐに質問できるメリットもあります。チャットボットの対応範囲外の解決できない問題は、有人チャットや電話といった有人対応に切り替える設定も可能です。
チャットボットの機能
チャットボットに搭載されている機能は大きくわけると5つあります。
- 問い合わせ自動応答
- 回答精度の向上
- FAQ連携
- 有人対応連携
- 外部システム連携
それぞれを詳しく解説していきます。
問い合わせへの自動応答
上記で紹介した種類ごとに応答の判断方法は異なりますが、ユーザーからの問い合わせに自動応答可能です。
サイトやサービスごとで適切な形式を選ぶ必要はあるものの、自動で応答できる点に関してはどのチャットボットの種類でも共通しています。
AIによる回答精度の向上
チャットボットによっては、AIの深層学習や強化学習などの機能があり、会話を繰り返すことで学習します。AIによる回答精度はデータが多いほどAIの学習が進み、より自然な回答や適切な応答をできるようになるため、会話のやりとりをするほど回答精度が高められるでしょう。
FAQ連携
チャットボットはFAQと連携させることで、FAQのデータを有効活用できます。コールセンターやヘルプデスクに似たような内容の問い合わせが寄せられるのは、よくある悩みです。「サイトのQ&Aのページに載せているのに問い合わせが来てしまう。」、「過去対応した内容に再び対応しなければいけない。」などの事象は多々あります。
しかしチャットボットとFAQシステム、Q&Aを連携させれば、問い合わせの内容から適切な記事・ページを提示して解決できます。

有人対応連携
簡単な問い合わせには強いチャットボットですが、細かい対応はできないこともあり、人が対応しなければならないこともあります。
しかしチャットボットを問い合わせの窓口にすれば、詳細内容を記録したうえで担当者や担当部署に直接つなげられるため、直接人が対応するよりも効率のいい対応が可能です。サービスによっては、有人チャットに切り替えられる機能が付いている場合もあります。
外部システム連携
社内の在庫管理システムや人事管理システムなどと連携させれば、チャットボットを通して在庫数を確認したり、勤怠入力を行ったりもできます。
近年ではChatGPTと連携できるチャットボットも増えてきています。


チャットボットの導入形態
チャットボットの導入形態には、主に「クラウド型」と「オンプレミス型」の二つがあります。それぞれの特徴やメリット、デメリットを紹介するので、ニーズに適した導入形態を選択しましょう。
クラウド型
クラウド型は、インターネットを通じてサービスプロバイダーのサーバー上で稼働するチャットボットです。たとえば、Amazon LexやGoogle Dialogflowなどは、このタイプに属します。
クラウド型のメリット
クラウド型は初期費用が安く、導入や運用もしやすい点がメリットとして考えられます。物理的なサーバーを設置する必要がないため、迅速な導入が可能です。また、サービスプロバイダーがサーバーの保守やアップデートを行うため、運用にかかる手間も少なくて済むでしょう。柔軟性が高く、需要の変動に応じてリソースを調整することも簡単です。
また、インターネットに接続できる場所ならアクセスできるため、近年のテレワーク需要にも対応しやすいといった特徴があります。
クラウド型のデメリット
一方で、クラウド型チャットボットにはいくつかの欠点もあります。データが外部のサーバーに保存されるため、セキュリティとプライバシーに対する懸念が考えられるでしょう。また、サービスプロバイダーの提供する機能に依存するため、カスタマイズの範囲が限られる場合もあります。
さらに、初期費用が安いものの、チャットボットの運用規模によってはランニングコストが高額になりがちです。
オンプレミス型
オンプレミス型、企業の内部サーバー上で運用されるチャットボットです。このタイプは、とくにデータのセキュリティやカスタマイズ性が重要視される場合に適しています。自社で完全なコントロールと管理が可能であり、特定のニーズに合わせた高度なカスタマイズが行えます。
オンプレミス型のメリット
オンプレミス型における最大のメリットは、データセキュリティとプライバシーが強固な点です。すべてのデータが社内サーバーに保存されるため、外部のサービスプロバイダーに依存するリスクがありません。また、企業独自のセキュリティ基準に合わせた運用が可能であり、業務の特性に合わせた細かなカスタマイズが行えます。
さらに、クラウド型では懸念点になりがちなランニングコストも、自社で管理できる人材がいれば抑えられる点もメリットの一つです。
オンプレミス型のデメリット
しかし、オンプレミス型の導入には高い初期投資が必要であり、サーバーの維持・管理にかかるコストも大きいです。また、システムの運用とメンテナンスに専門的な知識が必要であり、それに伴う手間が増えることも考慮する必要があります。
そして、外部からのアクセスが制限されてしまうのもデメリットでしょう。VPN接続によって社内LANにつなげないとチャットボットを使えないため、使用感が低下するかもしれません。
チャットボットの導入効果・メリット
企業がチャットボットを導入するメリットや得られる効果は次のとおりです。
- 顧客との接点の増加
- データ蓄積によるマーケティングへの活用
- ユーザーニーズとのマッチ
- 問い合わせ対応を効率化
- 顧客満足度向上につながる
- 売り上げ向上につながる
- 属人化の解消し回答を標準化できる
それぞれの導入効果やメリットについて説明します。
顧客との接点の増加
Web上での企業とユーザーの接点として、Webサイト、アプリに次ぐ第三の接点がチャットボットになります。
チャットボットのボット(bot)を作成し、LINEやFacebook Messengerなどのプラットフォームに公開すれば、プラットフォーム上にもユーザーとの接点を作れます。
一度チャットボットを利用してくれたユーザーには、再度企業側からメッセージを送れるため、再訪率もウェブページに比べると断然高い点が大きなメリットです。
データ蓄積によるマーケティングへの活用
チャットボットには、顧客との会話のログを蓄積させて内容を分析し、レポートを作成してくれる機能があり、マーケティングに役立てられます。このデータをもとに、一人ひとりの顧客のニーズに合わせたマーケティングを実現できれば、大きな収益向上につながるでしょう。
チャットボットでの会話履歴にくわえ、商品の購入履歴やメッセージの開封履歴、顧客のプロフィールを組み合わせれば、さまざまなインサイトが発見できるかもしれません。
また今まで顧客のニーズに応えるために割いていた、コストの削減にもつながります。
ユーザーニーズとのマッチ
若者を中心に、コミュニケーションツールは電話やメールからLINEをはじめとするSNSへと移行しています。10代、20代のコミュニケーションの7、8割はチャットベースです。場所を選ばない気軽さや敷居の低さが一つの理由であり、これまで中心だった電話のようなコミュニケーションが受け入れられづらくなっているのです。
しかしチャットボットを活用すれば、質問に対するハードルを下げ、よりユーザーのニーズにマッチした顧客対応を実現できるでしょう。
問い合わせ対応を効率化
問い合わせの対応をしていると、毎回同じような内容やすぐに解決できるようなものが多く寄せられます。
簡単に対応ができる問い合わせに対しては、あらかじめ回答を用意してチャットボットに対応させることで、対応者の負担軽減が可能です。
これはとくにコールセンター業務の多い業種・業界で効果を発揮します。簡単な質問はボット、難しい質問はオペレーターの二重フォロー体制にすれば、コールセンターのコストを削減できるでしょう。
また、外部だけでなく、社内問い合わせにチャットボットを活用すれば、ヘルプデスクや総務経理などの業務を削減できる点もメリットです。
いずれにしても、社内外からの定型的な質問に対応しなければならない企業は、問い合わせ対応を効率化して、コストを削減できる可能性があります。
顧客満足度向上につながる
顧客が問い合わせを行った時間が営業時間外だと、すぐに問題を解決できず顧客満足度が低下しかねません。しかしチャットボットを導入すれば、24時間いつでも問い合わせに対応できます。営業時間外でもスピーディーに回答が得られるようになるため、顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
またよくある質問や簡単な質問をチャットボットで対応できるようになると、コールセンターへの問い合わせ数が減少し、電話がつながるまでの待ち時間も短くなります。電話をするっとすぐにつながり、スピーディーに問題が解決できれば、やはり顧客満足度の向上が期待できます。
売り上げ向上につながる
顧客満足度の向上も売り上げにつながりますが、チャットボットではさらに、新たな売り上げの創出も可能です。WebサイトやECサイトにチャットボットを設置すると、商品に気になる点があれば画面上にあるチャットボットへ即座に質問し解決できるため、サイト訪問者の離脱を防ぎやすくなります。
また、サービスによっては顧客の動向や行動履歴を収集・分析しておすすめの商品や、最適な情報をホップアップで表示するといった動きができます。つまり、店舗にいる店員のような対応ができるため、チャットボットのないサイトよりも機会損失を防ぎ、売り上げ向上が図れるのです。
属人化の解消し回答を標準化できる
属人的な対応を解消し、オペレーターの回答を標準化できることもメリットです。
コールセンターのオペレーターは、あらかじめ用意されたマニュアルに沿って対応しますが、オペレーターごとに知識のばらつきが見られることも多々あります。また、コミュニケーション能力や電話応対のマナーについても、新人とベテランオペレーターでは、レベルに差が出ることもあるでしょう。
しかしチャットボットを導入すると、回答内容を標準化でき、オペレーターのスキルに依存せず、一定した回答品質を確保できます。そのため、オペレーターのスキル不足によるクレームや満足度の低下防止につながります。

チャットボット導入のデメリット
チャットボットの導入には、次のようなデメリットも存在します。
- 導入までに手間と時間がかかる
- 一度に複数の質問に対応できない
- 逆にユーザー体験が悪くなることもある
- 費用対効果に見合わないことがある
デメリットをあらかじめ把握しておけば、自社サービスへの不利益を避けられます。それぞれのデメリットについて詳しく説明します。
導入までに手間と時間がかかる
チャットボットの運用体制を整えるため、初期設定に手間と時間を要する点がデメリットです。チャットボットは、導入当初から最適化したサービスを提供できるわけではありません。AI型のチャットボットは精度を上げるために、人手によるデータ収集やラベル付けなどを行う必要があります。
またシナリオ型のチャットボットでも、予想できるシナリオを用意して自社のサイトに最適化させる必要があります。
サービスによっては、AIの機械学習やシナリオ作成のサポートなど、手厚い導入支援を行っているので、不安な方はサポート体制が整っているツールを選ぶとよいでしょう。
一度に複数の質問に対応できない
一度に複数の質問に対応できない点もデメリットです。人間同士の自然な会話では、一つの文章で複数の質問が可能です。しかし、チャットボットは人間の質問の意図を理解して回答できません。
ユーザーが自身の意図に沿った回答を得るためには、質問を一つずつ行う必要があります。
逆にユーザー体験が悪くなることもある
チャットボットは自動化された対話システムであるため、ユーザーの質問やニーズに完全にマッチする回答を提供するのが難しい場合もあります。とくに複雑な質問や個別の事情に関連する問い合わせでは、ユーザーが満足する回答を得ることが困難になるでしょう。
シナリオ型(ルールベース型)チャットボットでは用意しておいた回答が少ない場合、AI型(ログ型)チャットボットでは蓄積データが少ない場合などに、この傾向が見られがちです。
この結果、顧客満足度の低下や、ブランドイメージの損傷につながる可能性があります。
費用対効果が見合わないこともある
チャットボットを導入するには費用が発生するため、チャットボットの利用者数が増えない場合は、導入費用や運営費用の負担だけがかかります。
問い合わせが増加しなければ、チャットボット導入による効率化や収益化に至りません。導入前に、人間のオペレーターだけでは対応できないほどのユーザー数がいないと、損をする可能性が高いでしょう。
チャットボットの費用相場
チャットボットの費用は、初期費用+月額費用です。初期費用は数十万円かかることもありますが、近年はクラウド型チャットボットの増加により、初期費用は無料の場合も多くあります。
月額費用は数千円から数十万円までとさまざまで、チャットボットの種類や利用できる機能によって異なります。シナリオ型の方が安い傾向にあり、費用相場は3万円~15万円程度、AI型は10~60万円以上です。
また、APIを利用した外部連携タイプのチャットボットの場合、やり取りした会話数や文章量に応じて料金が変わる、従量課金制を採用していることが多いです。
高額なチャットボットを導入しても、使いこなせなければ大きな損害となるため、適したサービスを見極めましょう。
チャットボットを導入した企業の活用事例
チャットボット(Chatbot)が実際にどのようなシーンで活用されているのか、利用シーンをチェックしましょう。紹介するのは、次の4つのチャットボット利用例です。
- ECサイトでWeb接客
- 飲食店予約代行の連絡に
- カスタマーサポートでの活用
- マーケティングに活用
(1)ECサイトでWeb接客 --H&Mの事例
アパレルブランドのH&Mは、メッセンジャーアプリ内に、チャットボットが「接客」してくれるオンラインストアを設置しています。サイズや欲しいアイテムなどを入力すると、おすすめの商品を提案してくれます。
ユーザーは、チャットボットシステムとの対話を通じて、求める商品により効率的にたどり着けるため、店舗で購入するのと同じように購入が可能です。チャットボットの高い有効性を示した事例です。
(2)飲食店予約受付代行の連絡に --ペコッターの事例
「ペコッター」はチャットボットを活用した電話予約受付の代行アプリです。
希望の飲食店と予約したい日時を入力すると、ユーザーに代わって飲食店へ電話し、結果をチャットで知らせてくれます。予約受付内容の変更といった要望も、すべてチャットボットでやり取りできます。情報提供だけでなく複数システムを連携させることで、予約受付業務を可能にした活用事例です。
(3)カスタマーサポートでの活用 --LOHACOの事例
通販サイトLOHACOは、Webサイト上でのカスタマーサポートに、AI型チャットボット「マナミさん」を導入しています。導入は2014年9月と早く、24時間365日稼働しスピーディーな対応を実現するとともに、6.5人分の人件費削減を実現(2016年7月発表)しました。
2016年11月からは、LINEアカウントにもマナミさんを実装。自動対応では適切な回答が難しい場合は、スタッフによる有人チャットへシームレスに引き継ぐサポートシステムも導入しました。
(4)社内の問い合わせに活用する --サッポロホールディングスの事例
お酒や飲料のメーカーであるサッポロホールディングスでは、社内の問い合わせ対応(ヘルプデスク)にチャットボットを使用しています。導入前にはナレッジが属人化していたり、社内FAQの所在がわからなかったり、そもそも情報が更新されていなかったりする問題がありました。
サッポロホールディングスはこの問題に対応するために、チャットボットAIを導入します。結果として社員が自身でチャットボットを利用し、探している答えにたどり着けるようになりました。またこれにより、社内ヘルプデスクは対応時間を削減でき、よりクリエイティブな作業に時間をさけるようになりました。
チャットボットの導入事例について、詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。
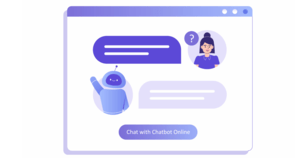


チャットボットの具体的な使い方
活用事例で紹介した以外にもチャットボットは多くの業界や分野で有効に活用されており、使い方もさまざまです。次に、いくつかの主要な業界や分野に焦点を当て、具体的な使い方を探ってみましょう。
顧客サポート向け
オンラインサポートとFAQ
顧客がオンラインで遭遇する一般的な問題やFAQに対して、チャットボットが即時に回答を提供します。これにより、顧客の問題解決を促し、サポートチームの負担を軽減できるでしょう。
製品・サービス案内
チャットボットが製品やサービスの情報を提供し、顧客の購入決定をサポートします。たとえば、製品の特徴や使用方法、価格に関する問い合わせへの対応を、チャットボットが行う使い方です。
ヘルスケア向け
予約管理と問診対応
医療機関やクリニックでの予約管理や問診にチャットボットを使用します。患者の基本情報の収集や、診察の予約手続きにおける効率化が可能です。
健康情報の提供
患者へ向けた健康関連情報の提供や、健康に関する一般的な質問にチャットボットが回答します。
教育機関向け
学生サポート
学生向けに授業のスケジュール、試験の日程、キャンパス情報などを提供します。また、入学手続きや奨学金に関する問い合わせにも対応可能です。
受験生・保護者向け案内
大学や学校の入試情報、キャンパスライフに関する情報を受験生や保護者に提供します。
金融機関向け
取引情報の提供
顧客が口座情報や取引履歴、金融商品に関する情報を簡単に取得できるようサポートします。
投資アドバイス
投資に関する基本的な情報やアドバイスを提供し、顧客の投資決定をサポートする使い方です。
レストラン・ホスピタリティ向け
予約受付
レストランの予約受付や確認を自動化し、顧客の利便性を高めます。
施設案内
ホテルやリゾート施設の予約管理、客室の案内、施設内サービスに関する情報を提供する使い方です。
不動産業界向け
物件案内
チャットボットが利用者のニーズに応じて、適切な物件を案内します。賃貸や購入に関する質問にも対応し、物件探しのプロセスを効率化します。
問い合わせ対応
物件の詳細情報や見学予約、契約手続きに関する問い合わせに対応させる使い方です。
小売業界向け
製品案内と在庫確認
顧客が求める製品の情報や在庫状況を提供します。オンラインショッピングのサポートにも活用可能です。
販売促進
製品の特別オファーやプロモーション情報を顧客に提供します。
エンターテイメント業界向け
イベント情報提供
コンサートや映画、展示会などのイベント情報を案内します。
チケット予約サポート
イベントのチケット予約や購入手続きをサポートする使い方です。
交通・旅行業界向け
交通情報案内
電車やバス、飛行機などの交通機関の時刻表や運行状況を提供します。
旅行計画サポート
旅行計画の提案や予約手続きをサポートする使い方です。
公共サービス・自治体向け
行政手続きの案内
市役所や区役所の手続き方法、必要書類、窓口の情報を提供します。
地域情報提供
地域のイベントや施設、緊急情報などを住民に提供する使い方です。
チャットボットの作り方
チャットボットの作成には自社で開発する方法と、チャットボット作成ツールを使用する方法があります。
それぞれの作成方法について説明します。
自社でチャットボットを開発する
自社でチャットボットを開発する場合でも次のようにいくつか手段があるため、ニーズや要件にあった開発方法を選びましょう。
なお、自社でチャットボットを開発する方法には、どれも技術力の高いプログラマーやエンジニアが必要です。社内にチャットボットの知識をもつプログラマーがいない場合は、新しく社員を採用するか、外部委託する必要があり、コストがかかります。
チャットボットを運用するうえで、カスタマイズしたいといった強いこだわりがないのであれば、チャットボット作成ツールを使用するとよいでしょう。
APIを活用する
API(Application Programming Interface)を活用することで、既存のチャットボットサービスやプラットフォームの機能を自社のシステムに組み込めます。
たとえば、Googleの「Dialogflow」やMicrosoftの「Azure Bot Service」、OpenAIの「ChatGPT API」などが提供するAPIを利用することで、高度な会話能力をもつチャットボットが開発可能です。
APIを活用する方法は、カスタマイズ性と効率性のバランスを求める場合に適しています。
ただし、チャットボットAPIは利用できるプラットフォームが限定されている場合も多く、運用方法を考える必要があるでしょう。

開発フレームワークを活用する
開発フレームワークを利用する方法では、より柔軟なカスタマイズが可能です。フレームワークは、チャットボットの基本的な構造を提供し、開発者が独自の機能やロジックを追加できるようにしています。
たとえば、Node.jsやPythonを使用してチャットボットを開発するためのライブラリやツールキットが多数存在し、これらを利用することで特定のビジネスニーズに合わせたチャットボットを開発できるでしょう。
オープンソース(OSS)のプラットフォームを活用する
オープンソース(OSS)のチャットボットプラットフォームを利用することで、コストを抑えながらカスタマイズ可能なチャットボットを開発できます。
オープンソースのプラットフォームには大規模な開発者コミュニティが存在し、マニュアルやフォーラムも豊富に用意されているため、技術力さえあれば開発も進めやすいでしょう。
たとえば、RasaやBotpressはオープンソースのチャットボットプラットフォームとして広く知られています。
ただし、あくまでもオープンソースであるため、セキュリティやプライバシーに関する対策も自身で管理する必要があります。

チャットボット作成ツールを活用する
チャットボット作成ツールを活用すれば、専門的な知識がなくても簡単にチャットボットを作成できます。
ツールを使用したチャットボットの作り方は次のとおりです。
- 課題とユーザーニーズを明確にする
- チャットボット作成ツールを選ぶ
- チャットのシナリオ作成・設定をする
- チャットボットの動作確認・アップデートをする
ツールの利用に費用はかかりますが、機能やサービスの充実したツールが多いため、手間をかけずにチャットボットを導入できます。
また、数は少ないながらも無料で使えるチャットボットツールがいくつか存在するため、まずはチャットボットを導入してみたいといった場合もツールの利用がおすすめです。

チャットボットの比較表【料金・機能・口コミ評価】
チャットボットを導入したい企業におすすめのサービスを比較表にしてまとめました。値段や無料トライアルの有無、連携できるサービス、設置できる場所などが一目で比較できます。
まずは問い合わせ対応の効率化かマーケティング支援かといった、導入する目的を明確にして、この比較表を参考に、サービスを絞り込むとよいでしょう。
【特典比較表つき】『チャットボットの資料11選』 はこちら⇒無料ダウンロード
一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。
【特典比較表つき】『チャットボットの資料11選』 はこちら⇒無料ダウンロード
※ダウンロード可能な資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。
チャットボットサービスについて詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

AIチャットボットを見たい方はこちら

社内向けのチャットボットを見たい方はこちら

無料で利用できるチャットボットを見たい方はこちら

チャットボットでマーケティングを成功させる
LINEといったツールで当たり前のように導入されるようになったチャットボットは、マーケティング戦略や顧客対応の要として、成長し続けているツールです。
またAIの活用が進むなかで、より自然で人間との会話に近い対話が実現できるようになりました。従来マンパワーで担っていた業務を削減でき、かつデータも蓄積できるためマーケティングにも有用です。
機能も充実し、ほかのSNSに埋め込めたり、既存のCRMツールと連携できたりと、トータルでデータを活用できるものも増えています。自社で実現したいことは何かを見極めながら、導入に失敗しないよう注意して適切なチャットボットサービスを選びましょう。
チャットボットとは?動画でわかりやすく解説
【チャットボットとは?効果や種類をわかりやすく解説】
【おすすめチャットボット3サービス・導入事例の紹介】
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査