電子契約の主な2つの保管方法
電子契約の主な保管方法は次の2つです。
- 電子データのまま保管する
- 紙の契約書をスキャナで読み込んで保管する
電子データのまま保管する
電子契約は電子データで契約書が作成されるため、電子データのまま契約書を保管できます。電子データで契約書を取り扱う方法には次のようなものがあります。
- 契約書を電子メールで授受する
- 電子契約システム で契約を行う
- 契約先が用意したサイトからダウンロードする
それぞれ作成・締結・送付・保管を電子データのみで行っていることが特徴です。作成から保管まで一貫して電子データでやり取りした契約関係の書類は、 電子帳簿保存法 の原則上、印刷した紙を原本として管理・利用ができません。やり取りした電子データのまま保管することが義務付けられているため、保管の方法に注意しましょう。
紙の契約書をスキャナで読み込んで保管する
紙の契約書をスキャナで読み込み、電子データ化して保管もできます。普段は電子契約を電子データのみで行っている事業者でも、従業員が受領する領収書や契約書が紙媒体であることは珍しくありません。このような場合は、紙の書類をスキャナで読み込み電子データにして保管可能です。
スキャナで読み込んでデータ化する場合、見やすい解像度であることやカラー画像にすること、タイムスタンプを速やかに付与することなどが条件とされています。条件を満たせば、スキャナで読み込んだ画像のほかにも、スマートフォンやタブレットで読み込んだ画像も保存が可能です。
電子帳簿保存法の改正された要件
電子帳簿保存法は2022年1月に大きな改正が行われ、2024年1月からは宥恕期間が終了し本格的に施行されています。改正された次の要件について、それぞれどのような点で改正が行われたのか確認します。
- タイムスタンプの日数が緩和
- 検索要件の緩和
- 税務署への事前承認の不要化
- 電子取引を電子データまま保存することの義務化
タイムスタンプの日数が緩和
改正電帳法ではタイムスタンプの付与日数要件が大幅に緩和されました。これにより電帳法対応の電子データ保存はかなり利用しやすくなり、一般に電子電子データ保存が普及しました。
具体的な日数としては、改正前はタイムスタンプの付与は3営業日以内とされていたものが、改正後は最長2か月とおおむね7営業日以内へ変更されています。
「3営業日以内では期間がシビアで受領した紙の領収書の電子化が間に合わない」との判断から、多くの事業者では紙で受領した書類の電子保存が行えませんでした。しかし、改正された電帳法で付与日数要件が緩和されて電子保存が行いやすくなったため、多くの事業者で電子保存の利用が推進される要因となりました。
検索要件の緩和
タイムスタンプの日数緩和に加えて、必要な検索要件も大きく緩和されています。改正前の検索要件と改正後の検索要件を比較したものが次の表です。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 取引年月日・勘定科目・取引金額やその他帳簿に応じた主要な記載項目で検索できること | 取引年月日・取引金額・取引先で検索できること |
| 日付、または金額の範囲指定で検索できること | 日付、または金額の範囲指定で検索できること※ |
| 2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索ができること | 2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索ができること※ |
※改正後は書類を保管する人が税務署職員のダウンロードの求めに応じられる場合、不要となる
このように大幅に検索要件が改正されたため、電子保存導入のハードルはさらに下がったといえます。
税務署への事前承認の不要化
改正後の電帳法では税務署への事前承認が不要とされています。電帳法が改正される以前は、電子帳簿やスキャナ保存を行いたい事業者は事前に税務署に申告を行い承認を受ける必要がありました。しかし、事業者の負担を軽減するため改正電帳法では税務署への事前負担が不要となり、申請の負担が減ることで、多くの事業者が電子保存に取り組みやすくなりました。
電子取引については改正前の電帳法から事前承認は不要で、改正後も変わらず申請なしで電子保存が可能です。
電子取引を電子データまま保存することの義務化
改正電帳法ではメールやシステムを利用した電子取引について、印刷して紙で保管することが原則的に禁止され、電子データのまま保管することが義務付けられています。データ保管に対応しなければならず、システムの導入や業務フローの改善を余儀なくされた事業者は負担が増えたと感じることもあるでしょう。
なお、一定の条件を満たすと電子取引を印刷し、紙での保管も可能です。ただし、税務署から電子データのダウンロードを求められたらその求めに応じるために、紙と電子データの契約書を両方保管しなければならず、書類管理により多くの手間がかかってしまう点に注意が必要です。
電子帳簿保存法の詳しい改正内容については、次の記事をご覧ください。
電子帳簿保存法の要件に対応する電子契約の保管方法
電子契約の具体的な保管方法としては、次の4つの要件を満たすことが必要です。この4つの要件は電帳法における真実性と見読性(可視性)を確保するために定められています。
- 真実性確保のため電子署名やタイムスタンプを付与する
- 見読性確保のため閲覧機能があるシステムに保管する
- 見読性確保のため検索機能があるシステムに保管する
- マニュアルをシステム利用者が見られるようにする
真実性確保のため電子署名やタイムスタンプを付与する
真実性を確保するために、電子署名やタイムスタンプを電子データに付与することが必要です。真実性を確保すると、契約内容が記載されたデータが真実のものであり、不正に作成されたり改ざんされたりしていないことを証明できます。その証明方法の1つが電子署名やタイムスタンプです。
電子署名やタイムスタンプがあることで、その署名がタイムスタンプが付与された時点では書類はたしかに存在し、契約者双方がそれぞれ本人の意思で契約に同意したことの証明になります。
また、電子署名やタイムスタンプの付与ではなく訂正や削除の履歴が残るシステムの利用や、そもそも訂正や削除ができないシステムの利用によっても電帳法の真実性確保の要件を満たします。現在の業務にマッチする方法で要件を満たせるように利用するシステムを選定しましょう。
見読性確保のため閲覧機能があるシステムに保管する
見読性(可視性)を確保するため、電子契約は閲覧機能があるシステムに保管しなければなりません。見読性(可視性)を確保することで、従業員が滞りなく業務を進行し、必要に応じて税務署職員の求めに応じて契約データを提供できます。電子契約データをデータのまま保存すればよいと考え、サーバーに契約情報を蓄積しているだけの状態ではこの見読性要件を満たしているとはいえません。契約情報を適切に保管したうえで、必要に応じていつでもすぐに電子契約書を見られる環境を整えておくことで見読性の要件を満たせます。
見読性が確保された環境を具体的に説明すると、データを表示するためのディスプレイや印刷のためのプリンタ、必要に応じてパソコンやディスプレイを操作するマウスやキーボードなどがあればよいとされています。設置機器の台数は要件には含まれず、一般的に業務で利用するものがあれば閲覧機能の要件は自然に満たせることが多いでしょう。
見読性確保のため検索機能があるシステムに保管する
一定の条件で文書を検索し、必要な書類をすぐに取り出し表示できる検索機能を備えたシステムに保管することも見読性の確保に必要です。データを適切に保管し閲覧できる環境を整えても、データ自体がどこにあるのかわからずすぐに参照できない状態では、見読性確保の要件を満たせません。
電帳法の改正後は検索機能の要件も大幅に緩和されているため、要件を満たす難易度も高くはありません。改正後の検索要件を満たしてデータを保管するか、税務署のダウンロードの求めに応じられる状態でデータを保管しましょう。
マニュアルをシステム利用者が見られるようにする
契約データ保管するシステムのマニュアルを用意し、マニュアルを参照しながらシステム利用者が契約データを問題なく見られるようにすることも、見読性確保の要件とされています。
用意されたマニュアルさえあれば、機器操作に慣れていない新入社員や中途採用の社員、税務署職員でも必要に応じて保管された電子契約のデータを閲覧できることで、見読性が確保されていると判断されます。保存要件を正しく満たして電子契約データを保管し、特定の人にしか閲覧できない属人化した状態を解消することで、電帳法の見読性要件を満たしましょう。
電子契約を保管する際の注意点
電子契約を保管する際は、次のような注意点があります。
- 契約書を長期保存できるシステムを利用する
- 規定やフローの見直しが必要な場合もある
契約書を7年以上長期保管できるシステムを利用する
電子契約は一定期間保存することが義務付けられているため、長期保存が可能なシステムの利用が必要です。具体的な保管の期間としては、法人税法に対応できる7年間、繰越欠損控除を利用する際は10年間を目処にしましょう。とくに、契約書に電子証明書を付与した電子署名を利用する場合は、電子証明書自体にも有効期限があるため、有効期限を伸ばせる 長期署名 に対応したシステムを利用することが重要です。
電子証明書は有効期限が切れてしまうと真実性の確保に役立たなくなってしまうため、適切に有効期限を更新しながら契約書の法的効力を確保して保管できるシステムを利用しましょう。
規定やフローの見直しが必要な場合もある
電子契約をデータとして保管するにあたり、従来の規定やフローでは対応できない場合は、規定やフローの見直しが必要な場合もあるため注意しましょう。
電子契約であれば作成から送付、保管までが電子化できるため、作成から社内申請・承認、さらには保管する方法が従来と変わってくるでしょう。
社内で申請や保管を行うことについて定めていた規定も、紙と電子データでは扱いが異なるため改定が必要になります。このように、電子契約を行い最終的に電子データで保管する場合は、紙の契約書と異なる点が多いため規定やフローの見直しが必要になる点に注意しましょう。
電子契約は適切に法対応して保管しよう
電子契約は適切に法対応して保管することが必要です。電子契約を電子データのまま保管する場合も、紙媒体の書類を電子化して保管する場合も、電帳法の保存要件を満たさなければならず、適切な対応ができていない場合は罰則もあるため注意しましょう。
電帳法における電子保存の要件は真実性と見読性が確保できるように定められたものです。真実性の確保のためにタイムスタンプや訂正・削除の履歴が残ることが必要で、見読性の確保のためには閲覧機能・検索機能・マニュアルをシステムが備えていることが必要です。
それぞれの要件を満たしたうえで、電子データを最低でも7年は保存できるシステムを利用し、電子契約を適切に保管しましょう。
\ 稟議や社内提案にも使える!/




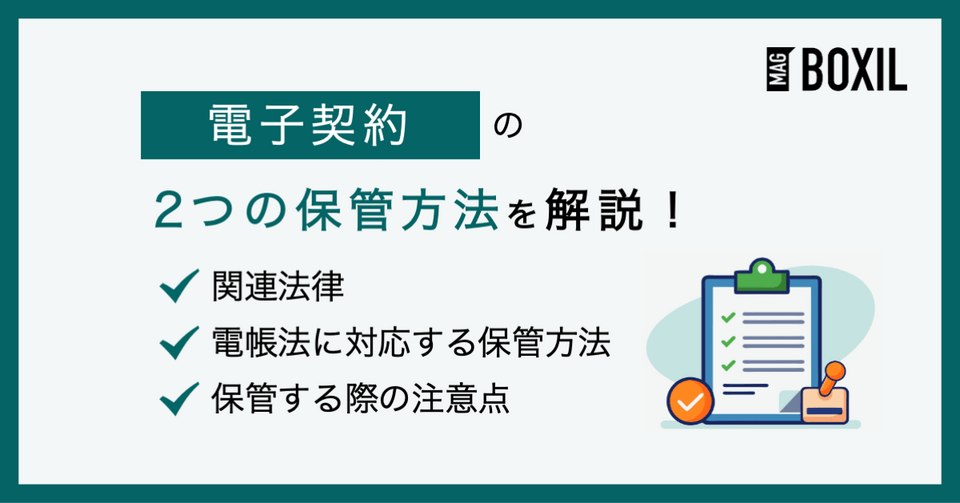

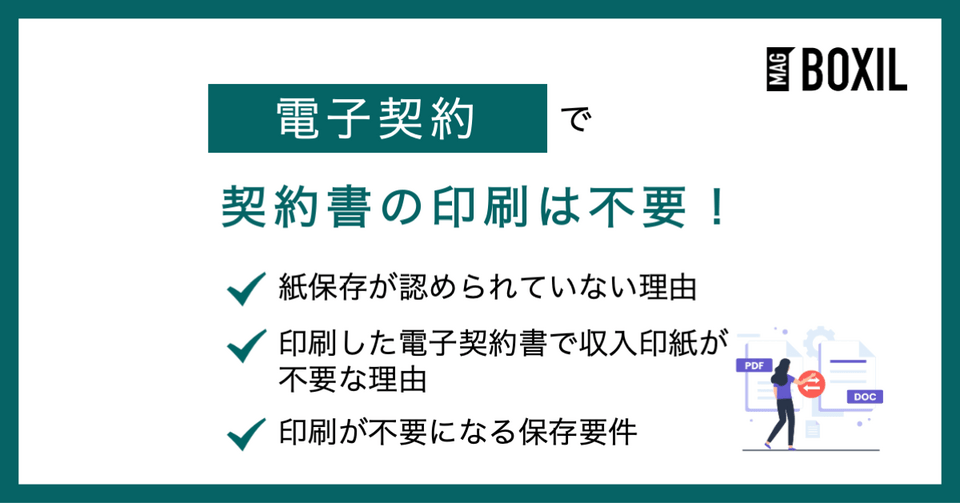
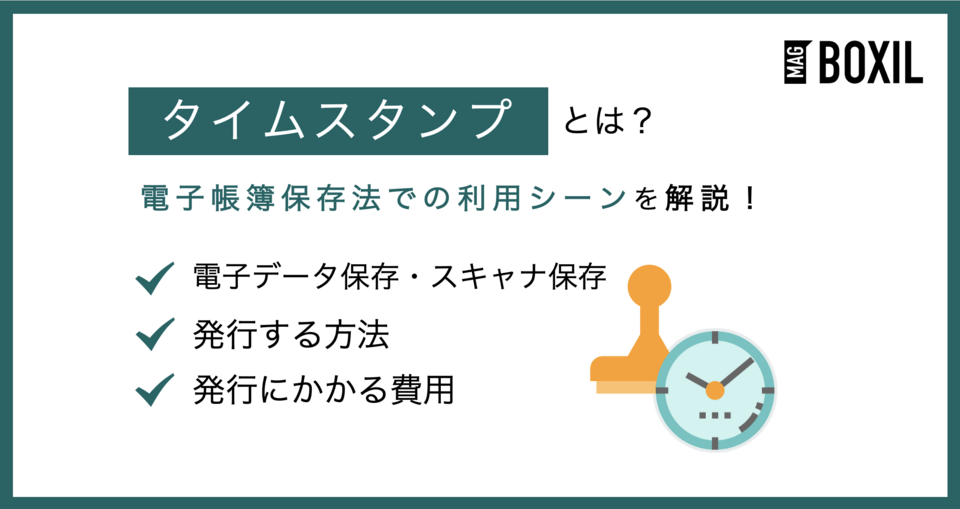
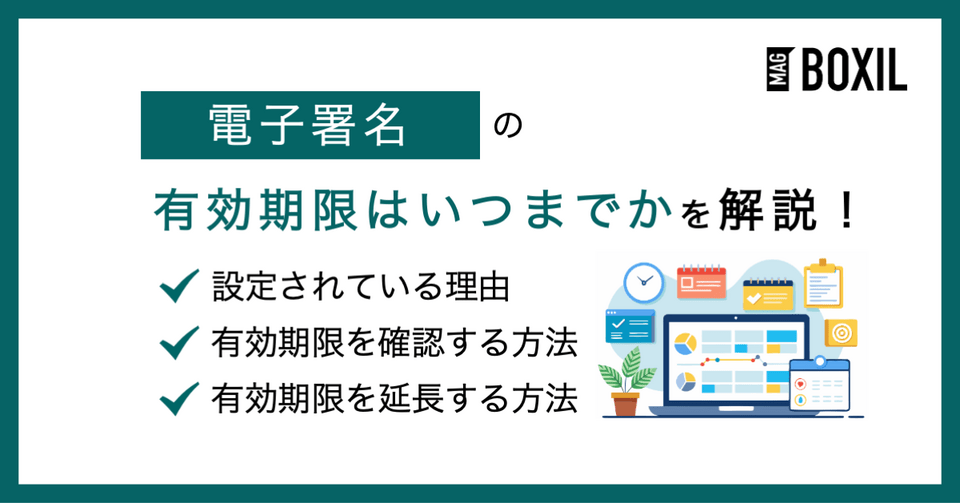
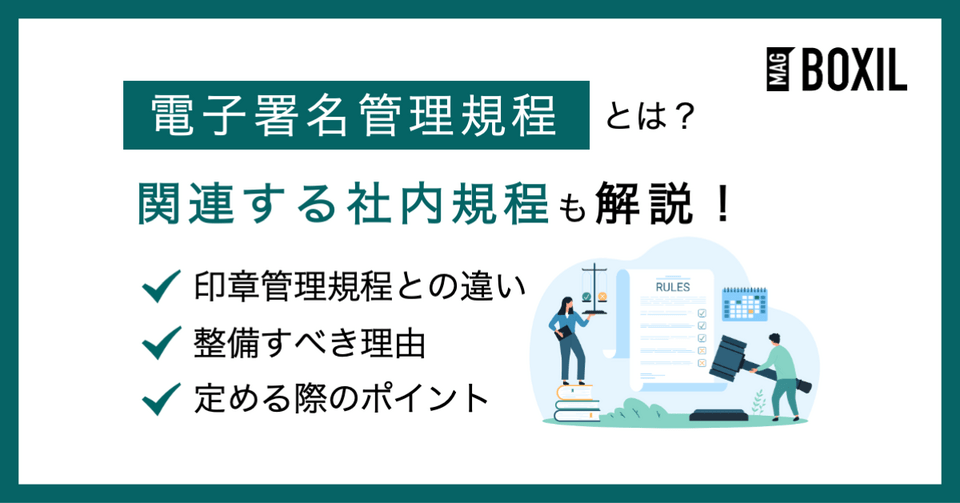
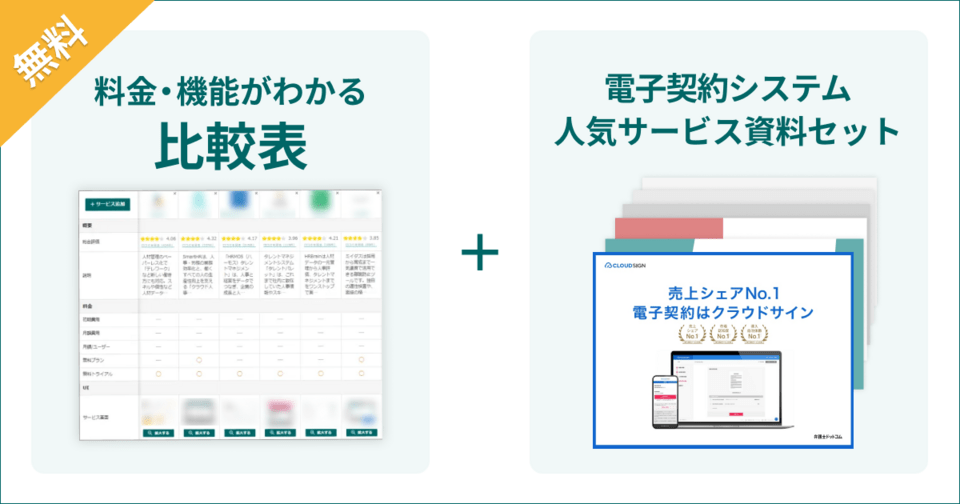


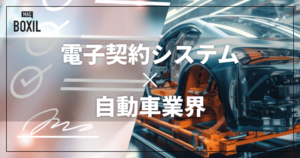
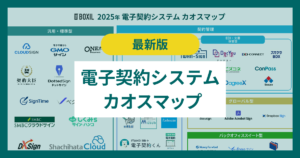
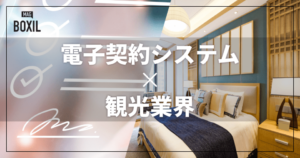
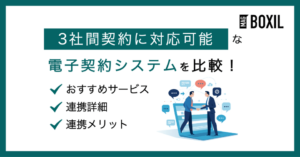
-e1767660072782-300x165.jpeg)












