電子契約では締結した契約の一方的な解除・破棄はできない
電子契約では、締結した契約の一方的な解除・破棄はできません。電子契約に限らず契約は、原則として一方の都合で解除や破棄ができないため、 電子契約システム でも解除・破棄の機能を提供していません。
また、電子契約では契約の際に 電子証明書 と タイムスタンプ といった仕組みを活用して電子署名を施すことで、契約の法的な効力を担保しています。そのため、一度契約した契約書に変更を加えると、電子署名との整合性が取れなくなってしまい法的な効力を担保できなくなるため、締結済みの電子契約に対して変更や修正ができません。
電子契約サービスの利用を終了しても契約や法令への対応は必要
電子契約サービスの利用を終了しても契約自体の効力は維持されるため、契約の履行は必要です。また、 電子帳簿保存法(電帳法) や法人税法といった法令への対応も継続しなければなりません。
電子契約サービスの利用を終了する際は、契約や法令への対応を継続するためにほかの電子契約サービスを契約するか、自社内で法令の要件に従った保存方法で契約書をデータのまま保管するといった対応を取りましょう。
このとき、電子データを書面化して保存することを検討する事業者もあるかもしれませんが、その対応では法令に違反してしまいます。電帳法では、データで取り交わした契約はデータのまま保存することが原則であるためです。よって、データによって締結したデータはデータのまま保存できる環境を整えましょう。
【関連記事】
電子契約サービスを乗り換える方法は?注意点や確認すべきポイント
電子契約は契約書の印刷は不要!理由や印紙の扱いについても紹介
電子契約の2つの保管方法とは?電子帳簿保存法の改正もあわせて解説
電子契約で契約を解除・破棄する方法
電子契約で契約を解除・破棄する場合には、次に紹介するような方法を取りましょう。
- 相手の同意のもと解除・破棄のための契約を結ぶ
- 債務不履行の場合は法定解除もできる
- 解除要件に同意があれば約定解除もできる
相手の同意のもと解除・破棄のための契約を結ぶ
相手の同意のもと解除・破棄のための契約を新規に結ぶことで、電子契約は解除・破棄できます。
締結した契約は一方的な解除は基本的にできないため、相手の同意を取り付けてから契約の解除を行うことが原則です。電子契約であれば解除のための契約を新規締結することで、双方の解除に対する同意を示せます。
契約解除のための契約を新たに締結することを手間と感じる場合もあるでしょう。しかし、契約を一方的に解除できるような状態では、いつ契約相手が解除を求めるかわからないため、安心して契約ができません。そのため、契約においては一方的に解除ができないことを原則として、双方が安心して契約ができる仕組みになっています。
債務不履行の場合は法定解除もできる
債務不履行の場合は例外的に法定解除もできます。法定解除とは、定められた法律の要件に従って契約を解除することです。改正民法の541条と542条には契約の解除について定められており、次のような場合に法定解除ができます。
- 契約相手に契約履行を催告しても相当期間履行されないとき
- 契約相手が契約の履行ができないとき
- 契約相手が「履行をしないと」明確に意思表示をしたとき
- 契約の一部について履行できなかったり履行しない意思を示したりした場合において、履行できる部分では契約の目的を達成できないとき
このように、法律の定めに従って契約を法定解除する場合は、相手方の同意がなくとも契約を解除できます。
解除要件に同意があれば約定解除もできる
あらかじめ契約で解除要件を定め、解除要件に契約者双方が同意している場合には約定解除も可能です。約定解除のための契約解除条項として一般的に利用されているものとしては、次のようなものがあります。
- 一方が契約に違反したときは催告なしにただちに契約を解除できる
- 契約期間中でも契約者のどちらかが定めた期間をもって相手方に通知して解除できる
- 契約者の一方が解約金を支払うことで希望した期間でいつでも解除できる
このように、「双方が解除可能な条件にするのか」「一方が解除可能な条件にするのか」「解除のための解約金や違約金などのペナルティをどのようにするか」などを解除要件に盛り込みます。この解除要件で定めているものであれば、約定解除として契約は一方的に解除可能です。
BtoC契約における契約の解除
BtoC契約における契約解除は、次のようなやや特殊な例もあります。消費者を保護する目的で定められた法律による制度も多く、事業者は消費者に対して適切な対応をしなければ、一方的な契約解除が行われる可能性があるため注意しましょう。
- 事業者の対応が不適切な場合は消費者は契約を取消できる
- 一部契約ではクーリングオフ制度による契約解除もできる
事業者の対応が不適切な場合は消費者は契約を取消できる
事業者の対応が不適切な場合は、消費者は契約を取り消せます。これは、電子契約法において定められたもので、錯誤による意図せぬ契約を取り消せるようにするための措置です。
たとえば、商品を100個購入しようとしている人が、桁を誤って1,000個購入してしまったとします。この場合、意図せぬ購入になるため、消費者側から契約の取消を求められます。
ただし、事業者側が消費者に対して本当に1,000個でよいか確認画面を示した場合や、消費者側からそのような確認画面は不要と意思表示している場合には、この措置は適用されません。あくまでも、事業者側に不備があり、そのうえで錯誤による契約が行われた場合に適用される措置です。
よって、消費者側は確認画面で契約に問題がないことを、事業者側は電子契約法にのっとって正しい画面表示ができていることを確認しながら契約を行いましょう。
一部契約ではクーリングオフ制度による契約解除もできる
一部契約ではクーリングオフ制度による契約解除も可能です。割賦販売法や特定商取引法(特商法)に定められているクーリングオフの条件に該当すれば、消費者は契約を無効にできます。
クーリングオフとは、契約金額が高額で契約期間が長くなりがちな特定の取引において、契約後も一定期間までは無条件で契約解除ができる仕組みです。エステや語学教室、訪問販売といったものがクーリングオフの対象取引です。
一度契約したものの、あとから冷静になって契約を取り消したいと考える消費者を保護する目的で定められたもので、この制度があることで消費者が安心して契約を締結できます。
事業者側は、契約の際は消費者が十分に納得してから契約を行うことで、クーリングオフを適用されることを防止できます。いずれにせよ、意図せぬ契約を行わずに済むため、消費者にとっては非常に便利な制度だといえるでしょう。
電子契約は一方的な解除はできないため慎重に契約しよう
電子契約を含む契約は、基本的に一方的な解除はできないため契約を締結する際は慎重な検討が必要です。ただし、契約不履行の場合や、あらかじめ契約で定めた解除要件を満たす場合は、法定解除や約定解除によって一方的な解除ができる場合もあります。
とくに契約において立場の弱い消費者は電子契約法や特商法で手厚く守られているため、条件を満たせば錯誤による契約解除や、クーリングオフ制度による契約解除ができることを覚えておくと便利です。
契約は一度締結すると、基本的に一方的な解除も修正もできません。解除や修正について相手方の同意を取得することも大きな手間となるため、契約前には内容をよく検討して慎重に契約を締結しましょう。
\ 稟議や社内提案にも使える!/




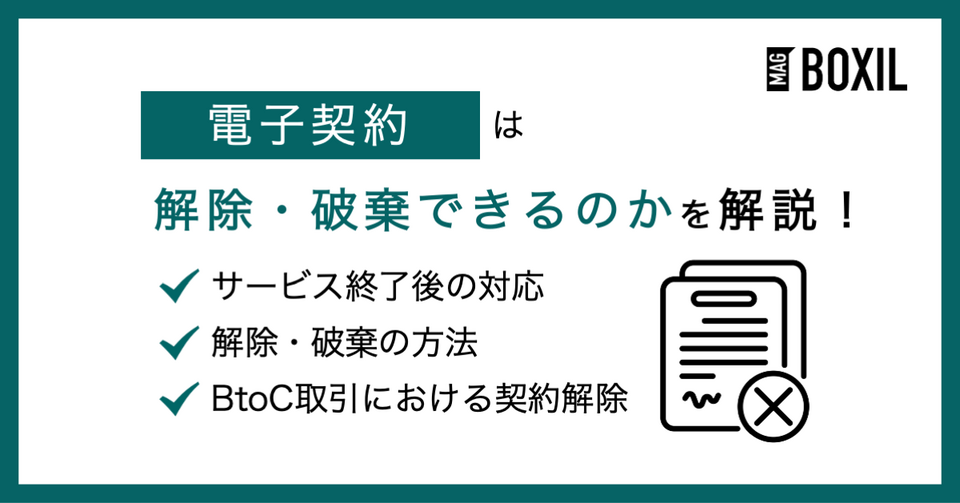


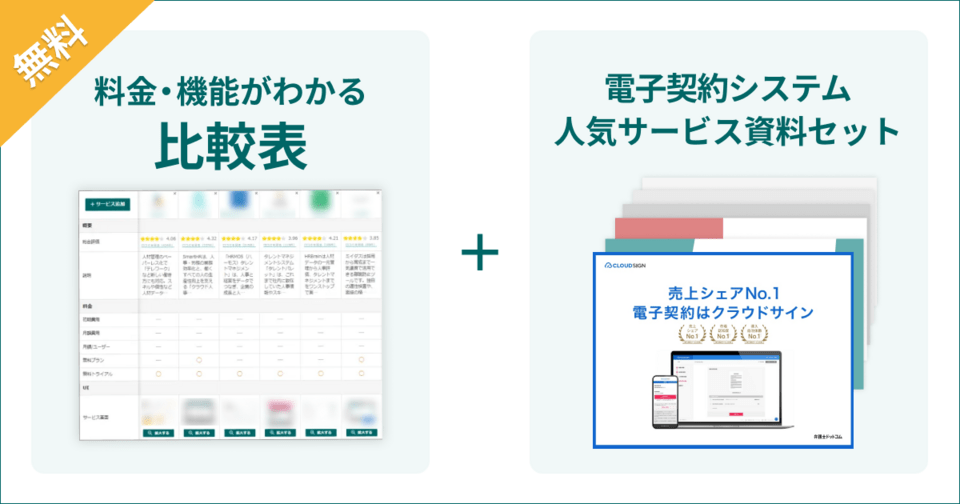


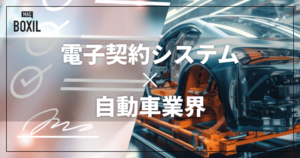
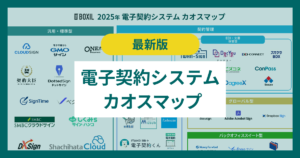
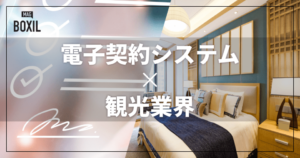
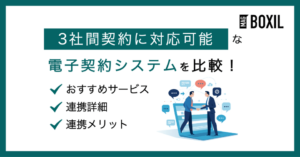
-e1767660072782-300x165.jpeg)












