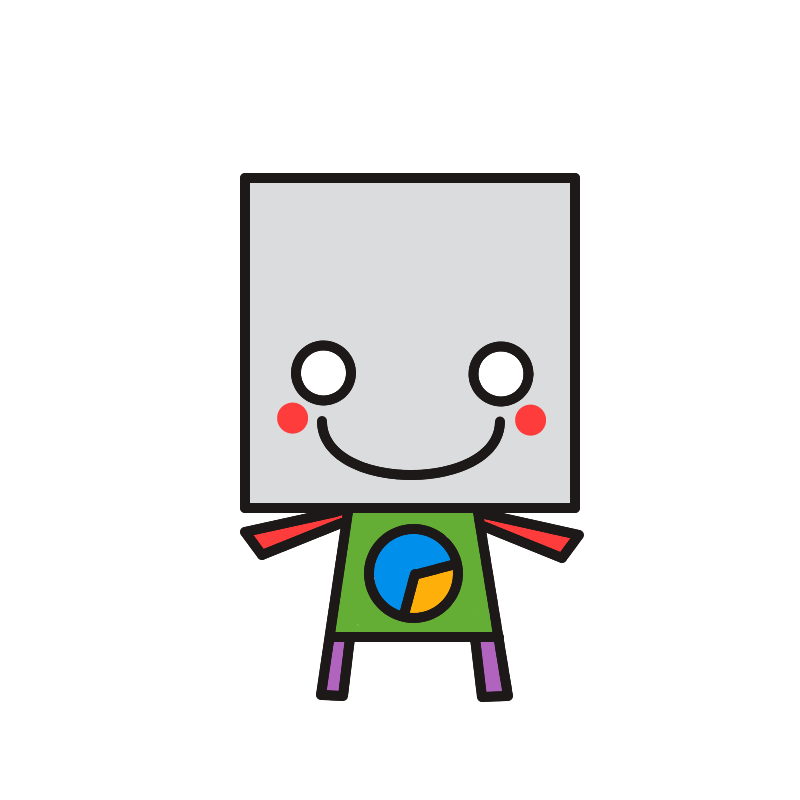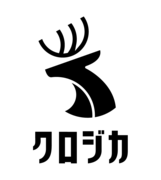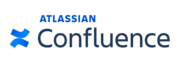グループウェアの導入事例|抱えていた課題と導入後の効果まとめ


おすすめグループウェアの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なグループウェアを含むサービスを徹底比較しています。ぜひグループウェアを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
目次を閉じる
- グループウェアとは
- マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメントの導入事例
- マスコミ・広告業界F社の場合
- 抱えていた課題
- Google Workspace
- 導入後の効果・メリット
- 資料をDLしてサービスを比較しましょう
- 協同組合/教育/公務員の導入事例
- 教育業界L社の場合
- 抱えていた課題
- 導入後の効果・メリット
- 資料をDLしてサービスを比較しましょう
- IT/通信/インターネットの導入事例
- IT業界A社の場合
- 抱えていた課題
- POWER EGG
- 導入後の効果・メリット
- 資料をDLしてサービスを比較しましょう
- 小売/流通/商社の導入事例
- アパレル業界S社の場合
- 抱えていた課題
- J-MOTTOグループウェア
- 導入後の効果・メリット
- 資料をDLしてサービスを比較しましょう
- 導入前に知っておきたいグループウェア導入の失敗例
- 失敗例1:トライアル時に実際に使用する従業員を含めなかった
- 失敗例2:必要な機能を洗い出していなかった
- おすすめグループウェアの比較表
- グループウェアの主な機能
- コミュニケーション
- 情報共有
- 申請・そのほか
- 失敗しないために押さえておくべき手順とポイント
- 導入の目的を明確化する
- 提供形態を確認する
- 使いやすいツールを選択する
- トライアルを最大限に活用する
- BOXILとは
グループウェアとは
グループウェアとは、企業内でのコミュニケーションや情報共有を円滑化するツールのことです。グループウェアの導入目的は、業務効率の向上です。社員同士のやり取りや情報共有がスムーズに行われれば、業務フローも滞りなく進みやすくなります。
テレワークが増えた現在、グループウェアを活用すれば、拠点が離れた社員同士も連携が容易になり、業務を行いやすくなるところも導入のメリットだといえるでしょう。
ではさっそくグループウェアの導入後のイメージがつかめるように、いくつかの導入・活用事例について紹介します。
マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメントの導入事例
マスコミ・広告業界F社の場合
F社は新聞・メディアの販売を行っています。
| 会社情報 | 内容 |
|---|---|
| 従業員人数 | 31~50人 |
| 所在地 | 東京都 |
| 設立年数 | 31~50年 |
※2022年5月時点の数値
抱えていた課題
課題1.データ共有に時間がかかりすぎる
F社の抱えている課題には、データ共有に時間がかかりすぎていた点が挙げられます。データ共有する際は、メールにて添付する形が基本でした。
それに加え社外秘のデータは、一旦独自のセキュリティソフトを通す必要がありました。
課題2.人の入れ替わりが激しくシステム対応が追いつかない
F社は人材の定着がうまくいかず、人の入れ替わりが激しい状態でした。そのためすでに退職した社員へデータが共有され、逆に新しく入った社員へは情報共有がもれる状況が起こっていました。
これらの課題を解決するために、F社は次のサービスを導入します。
Google Workspace - グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
導入後の効果・メリット
効果1.データ共有が瞬間的に行えて効率性アップ
Google Workspaceを導入したことで、今まで半日はかかっていた社外秘のデータ共有が、信頼できるセキュリティのもとで瞬時に共有可能となりました。
効果2.チームのメンバーをリアルタイムで確認
Google Workspaceを導入するまでは、スタッフ各自で入社や退職の社内メールを確認し、手動でチームやメールアドレスリストから情報の追加や削除を行っていました。しかし、サービスの導入後はこの作業が自動化され、1回あたり6個の登録で完結できるようになりました。
資料をDLしてサービスを比較しましょう
自社に合うサービスを選ぶには、各サービスの内容を比較することが重要です。気になるサービスの資料をダウンロードして検討しましょう。
協同組合/教育/公務員の導入事例
教育業界L社の場合
L社はスポーツ教室をメインにした教育事業を行っています。
| 会社情報 | 内容 |
|---|---|
| 従業員人数 | 2~10人 |
| 所在地 | 東京都 |
| 設立年数 | 11~20年 |
※2022年5月時点の数値
抱えていた課題
課題1.会費の徴収に手間取っていた
グループウェアの導入に至った理由は、会費の徴収が非効率だったためです。毎月の会費の徴収は現金で行っており、手作業でExcelに一人ひとり金額を記入し、計算していました。そのためミスもかなり多かったといいます。
課題2.会員との連絡が取り難い
レッスンのスケジュール、その他のやり取りは電話かGmailで行っていました。しかし、会員数が増えるにつれ、連絡のもれが増えてきました。
課題3.会員情報の一元化が難しい
会費や連絡と同様、会員の入会や退会の管理もExcelにて実施していました。そのため、作業に時間がかかり、何か別の形で対応できないかと考えていました。結果、L社ではグループウェアの「PiCRO」を導入します。
導入後の効果・メリット
効果1.会費の口座振替とデータベース化を実現
PiCROを導入した後は、会費の支払いは口座振替へ移行し、データベースでの管理が可能になりました。おかげでスムーズに会費が回収できるようになり、未収金や計上もれなどが減少しました。
効果2.会員とのスムーズな連絡システムを構築
グループウェアのコミュニケーション機能で、PiCROに登録した会員とスムーズに連絡が取れるようになりました。またクラスごとにグループわけができ、入会時に自動でクラス設定もされるので、連絡もれが減りました。
効果3.会員情報のデータベース化で見やすく
今まで会員情報をExcelで管理していましたが、PiCROを導入したことで一元化ができるようになりました。入会や退会のデータを見やすくなり、数字の流れを視覚化することに役立っています。
資料をDLしてサービスを比較しましょう
自社に合うサービスを選ぶには、各サービスの内容を比較することが重要です。気になるサービスの資料をダウンロードして検討してみましょう。
IT/通信/インターネットの導入事例
IT業界A社の場合
A社は文具・事務用品・OA機器の販売を行っています。
| 会社情報 | 内容 |
|---|---|
| 従業員人数 | 101~200人 |
| 所在地 | 東京都 |
| 設立年数 | 31~50年 |
※2022年5月時点の数値
抱えていた課題
課題1.運用コストを見直したい
グループウェアの導入に際し、自社に適した製品であることはもちろん、運用コストをなるべく抑えたサービスを探していました。
課題2.動作環境・運用を考慮
業務上の守秘義務が多く、オンプレミス環境でのシステム構築を検討していました。しかし、ベンダーがクラウドの知識しか持ち合わせておらず、オンプレミス環境の保守に懸念がありました。
課題3.情報共有に懸念
グループウェアを導入する前はメールを全社に配信していました。しかし、メールの量があまりに多く、共有された情報を見落とすことも。そのため、大切な情報共有がもれなく行える方法を探していました。
A社ではこれらの課題を解決するために、次のサービスを導入しました。
導入後の効果・メリット
効果1.動作環境・運用が最適
POWER EGGを提案した企業は、オンプレミス環境での構築を多数行っていました。保守も外注せずにワンストップで完結していたため、最適と判断し導入へ至りました。
効果2.情報共有の円滑化に貢献
POWER EGG導入後は、顧客と社内の情報をわけられるようになりました。顧客の情報はメール中心、社内の情報はグループウェア中心となり、情報の確認もれが軽減されています。
その他にも必要な情報への検索性が向上し、社内と社外の情報をわけられたことで、セキュリティレベルを高められています。
資料をDLしてサービスを比較しましょう
自社に合うサービスを選ぶには、各サービスの内容を比較することが重要です。気になるサービスの資料をダウンロードして検討してみましょう。
小売/流通/商社の導入事例
アパレル業界S社の場合
S社はアパレルの販売業を行っています。
| 会社情報 | 内容 |
|---|---|
| 従業員人数 | 1,001人以上 |
| 所在地 | 福岡県 |
| 設立年数 | 51年以上 |
※2022年5月時点の数値
抱えていた課題
課題1.店舗が多く各店バラバラな対応
グループウェア導入前は、店舗があまりに多く、各店舗でバラバラに販売を行っていました。そのため、他店舗の在庫の有無が把握できず、店舗間で在庫を融通し合えない状態でした。
課題2.情報の共有が困難
S社は情報をまとめ、店舗間で共有できるような運用を構築できていませんでした。店舗間でのやりとりをするには、まずは情報を共有する必要があるので、正確に共有できるシステムが求められていました。
S社はこれらの課題を解決するために、次のサービスを導入しました。
J-MOTTOグループウェア - リスモン・ビジネス・ポータル株式会社
導入後の効果・メリット
効果1.店舗間の共有を達成
J-MOTTOグループウェアを導入し、店舗間での共有ができるようになりました。店舗が多くても情報を共有しやすいサービスであるため、使いやすく容易に共有ができます。
効果2.店舗間での効率的なやり取りが可能
店舗間でのやり取りが活発化し、在庫の情報や新作情報などを効率的に把握できるようになりました。情報共有が容易になったことで、緊急時でも店舗間で互いに在庫が融通でき、利便性が向上しています。
資料をDLしてサービスを比較しましょう
自社に合うサービスを選ぶには、各サービスの内容を比較することが重要です。気になるサービスの資料をダウンロードして検討してみましょう。
導入前に知っておきたいグループウェア導入の失敗例
サービス選定で重要なのは自社にあったサービスを導入することです。たとえシェア率が高かったとしても、自社に合うとは限りません。サービスの導入でよくある失敗例をまとめたので、導入時の参考にしてください。
失敗例1:トライアル時に実際に使用する従業員を含めなかった
実際にシステムを使用する従業員が、トライアルで画面の操作感や機能を確認しないと導入に失敗しやすいでしょう。
なぜなら、従業員がカレンダーやファイル共有、ワークフロー機能などを確認していないと、操作に慣れるのに時間がかかって導入がスムーズに進まないからです。現場の従業員が業務で使いやすいツールか確認することで導入後、ツールが扱いにくいため現場で使われず、放置されるリスクを未然に防げます。
サービスを選ぶ際は、システムを使用する従業員がトライアルを行い、画面の操作感や機能に問題がないかを確認しましょう。
導入ユーザーの体験談
運用する前に、システムを利用する従業員とトライアル期間でコミュニケーションを深める必要がありました。
従業員から希望や不満、疑問についてさまざまな意見を汲み取って導入すれば良かったと強く思います。
失敗例2:必要な機能を洗い出していなかった
トライアルの前に必要な機能の洗い出しを行わなければ、導入に失敗しやすいでしょう。
たとえば、あとから機能が足りないと気づいて他サービスを追加導入すると、グループウェア1つを導入するよりも、かなり費用は高くなります。また逆に機能が豊富な高額なプランを契約しても、使用しない機能が生まれると、余分に費用を支払うことになります。
サービスを選ぶ際は、機能の想定もれや他のサービスとの連携を考慮して、トライアルの前に必要な機能を洗い出しましょう。
導入ユーザーの体験談
参加する従業員の数を把握せずに導入し費用が余計にかかってしまったので、要員計画を確認しておくべきだったと反省しています。
トライアルで実際に機能を使ってみるほか、項目を厳密に洗い出して機能が十分か確認しておけばよかったです。
おすすめグループウェアの比較表
【特典比較表つき】『グループウェアの資料10選』 はこちら⇒無料ダウンロード
一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。
【特典比較表つき】『グループウェアの資料10選』 はこちら⇒無料ダウンロード
※ダウンロード可能な資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。
グループウェアの主な機能
グループウェアにはさまざまな機能があり、目的によって次の3つの種類にわけられます。
- コミュニケーション
- 情報共有
- 申請・そのほか
次にそれぞれ機能を詳しく紹介するため、必要な機能を洗い出す際の参考にしてください。
コミュニケーション
- ビジネスチャット
- Web会議
- メール配信
- 社内掲示板
- スケジュール管理 など
上記のように、グループウェアには社内のコミュニケーションを強化する機能が豊富です。Web会議では、離れた場所からビデオ通話で会議ができ、録画や画面共有などができます。メール配信では、一斉送信やメールマーケティングができ、社内掲示板は、社内全体へのお知らせ・告知や緊急時・災害時の連絡ツールとして利用可能です。
またスケジュール管理では、複数の予定を共有しカレンダー形式で可視化します。ほかの従業員の予定を把握しやすく、打ち合わせといった業務の日程調整が行いやすくなるでしょう。
情報共有
- オンラインストレージ
- 日報管理
- プロジェクト管理
- アンケート作成 など
グループウェアではさまざまなデータが共有・管理できるため、業務効率を向上できます。オンラインストレージはインターネット上のファイル保管場所であり、ファイルの共有やアクセス制限、容量拡張が可能です。
日報管理は、テンプレートを活用して日報作成を省力化でき、アプリを利用すれば社外からでも投稿できるため、すきま時間を有効活用できます。プロジェクト管理では、チーム内でタスク管理やスケジュールの把握ができ、プロジェクトの進捗状況を可視化できます。また、アンケートを作成し、集計までできるため、社内で意見を募りたい場合やテストを実施したい場合に便利です。
申請・そのほか
- ワークフロー
- 会議室予約
- 社内ポータル
- 従業員の安否確認 など
グループウェアにはそのほかにもさまざまな機能があり、省力化や自動化で業務をサポートしてくれます。ワークフローは稟議や書類チェックの工程を自動化する機能で、通知機能やアプリによる申請・承認で業務を効率化できます。
会議室予約では、施設や備品の予約管理ができ、災害時・緊急時はメールの一斉送信やアプリへのデータ登録などで従業員の安否確認が可能です。またよく利用する機能は、社内ポータルとして1つの画面に集約し、一目で業務の状況が把握できます。
失敗しないために押さえておくべき手順とポイント
失敗例のようにならないために、グループウェアの導入手順や、押さえておくべきポイントを紹介します。主な手順は次のとおりです。
- 導入の目的を明確化する
- 提供形態を確認する
- 使いやすいツールを選択する
- トライアルを最大限に活用する
導入の目的を明確化する
グループウェアの導入目的を明確にしましょう。グループウェアで何を解決したいのか、現状の課題や問題点をふまえて文章に起こすのが重要です。目的が決まれば必要な機能もわかりやすくなります。
グループウェアは、どの製品でも基本機能はおおよそ同じです。しかし、オプションやメイン機能は製品によって違います。そのため、目的が定まっているのであれば設計思想の観点からグループウェアを選択でき、「思っていたのと違った」と後悔する可能性が低くなるでしょう。
提供形態を確認する
グループウェアの提供形態はおおきく、「クラウド型」と「オンプレミス型」にわかれています。クラウド型は、インターネット環境があれば外部からもアクセスできる利便性が特徴です。オンプレミス型は、社内サーバーへインストールするためカスタマイズしやすいのが強みです。
初期費用が高いオンプレミス型ですが、導入後のコストはあまりかかりません。一方、クラウド型は導入時のコストは比較的安いものの、毎月利用料がかかります。利用人数や期間によってトータルコストが変わるので、どちらの提供型でも試算して、どちらの費用対効果が高いかをしっかり確認しておきましょう。
使いやすいツールを選択する
グループウェアは社内全体で利用するものであるため、誰でも簡単に使えることが大前提です。優秀なツールを探し出せたとしても、複雑で特定の社員しか使いこなせないようでは意味がありません。
そのため、ITに詳しくない社員でも使いこなせるかどうかを考えて、ツールの絞り込みを行いましょう。使いやすいツールであれば、社員が操作に困ることも少なく、導入や現場への浸透がスムーズに進められます。
トライアルを最大限に活用する
使いやすいツールが選択できたとしても、ツールが自社の体制や業務に合っているか、実際に簡単に使えるかどうかは、直接ツールを使ってみなければわからない部分も多くあります。
そのため、無料トライアルを実施しているサービスの場合は、実際に試しましょう。これにより、導入が成功するかどうかをイメージできます。またこのときに、できれば対象者全員へテストを依頼し、アンケートで使用感をきくのがおすすめです。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査