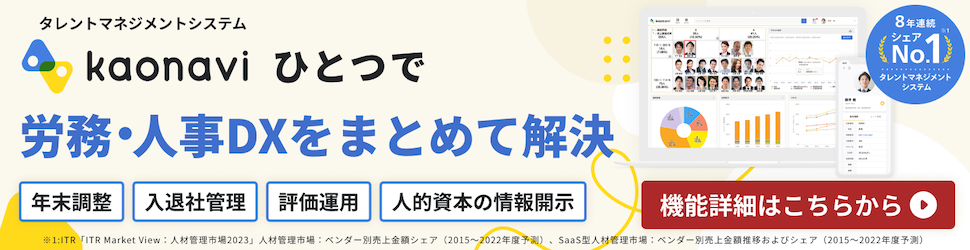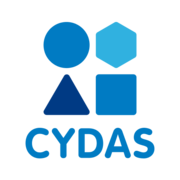組織の「全体最適」とは?実施する意味や部分最適との使い分け・注意点

全体最適とは
全体最適とは、英語で「Total Optimization」といい、「組織全体として最適な状態」のことを指します。経営状況について説明する際によく使われる用語です。
経営の世界では、個々の社員が成果を発揮しても組織として利益が最大化しない場合があります。これは、個人が頑張っても全体として最適な状態にはならないからです。
組織として収益を最大化するために、経営者は「全体最適とはどのような状態なのか?」を考える必要があります。
全体最適と部分最適の違い
全体最適が組織全体が最適化されていることを指すのに対し、部分最適は全体ではなく「組織の一部や個人が最適な状態」のことを指します。
しかし、各自が部分最適を追求することが、必ずしも全体最適になるわけではありません。
部分最適は特定の部門で課題を抱えている場合には効果的と言えますが、他部門で問題が生じることもあります。そのため、根本的な課題解決にはつながらないケースが多いです。
全社最適の重要性
全社最適が重要な理由としては、経営課題を解決に活用できる考え方だからです。
近年は人口減少や高齢化により人手不足が進み、少ない人材で高いパフォーマンスを出す必要がありますます。そのためには組織全体の効率化を図り、パフォーマンスを最大化することが不可欠です。
しかし、人材不足であっても個々の能力が発揮できるように、現状のリソースを最適化することで生産性を上げ、利益につなげることもできるでしょう。そのため、経営層は全社最適でどのような効果が得られるのかを理解して、俯瞰的な視点で取り組みを進めることが重要です。
全体最適と部分最適の使い分け
組織を動かすためには全体最適と部分最適をきちんと使い分ける必要があります。
全体最適すべきケース
全体最適を意識するべきなのは、企業の中でも経営層や部門長クラスなどの経営全体を意識して行動しなければならないメンバーです。
個々の部署や従業員が部分最適を目指して、組織としての連携がとれなくなってしまう課題が起こりがちです。
組織全体の活動を意識しながら、個々の部署や従業員に求められる役割をコントロールする必要があります。
部分最適すべきケース
管理職以上は全体最適を意識するべきですが、個々の部署や従業員が全体最適を意識することは困難です。
個々の部署や従業員がそれぞれに全体最適を考えると、部署や従業員の数だけ組織のあるべき姿像ができてしまい、かえってパフォーマンスを発揮できなくなってしまうからです。
管理職層がうまく役割を与えることによって、現場職にはその役割における部分最適を目指して行動してもらう方が全体のパフォーマンスは良くなります。
全体最適のメリット、問題点
では、全体最適にはどのようなメリットや問題点があるのかを説明します。
全体最適のメリット
役割の明確化
組織のありかたを全体最適化することによって個々の役割が明確になります。
たとえば、営業部門1つにとっても、何のエリア担当かや何の商材担当、何の企業担当とそれぞれに求められる役割は違うはずです。
誰かが全体最適を考えて、個々のチームや部門の役割を明確にすることによって個々が部分最適を目指しても、全体最適につながりやすくなります。
ミスの減少
また、誰かが全体最適な状態になるように、現場をコントロールすることによって社内のミスが減少します。
たとえば、営業と商品管理部門がうまく連携できずに発注する、過剰在庫や発注ミスなどは、誰かが営業の現場と商品管理の現場の両方をチェックすることで減少することが期待できます。
生産性の向上
全体最適をコントロールすることによって、生産性を向上することが期待できます。
たとえば、部署ごとに活動していると実は重複した事務作業をしていて、全体の手続きを誰かが知っていれば、削減できた事務作業というのはよくあるでしょう。
このように部署ごとに活動しているからこそ発生している、重複している事務作業を削減することによって、無駄な業務が少なくなり組織としての生産性は向上します。
全体最適の問題点
つづいて、全体最適が持っている問題点について説明します。
会社内の対立
まず、問題点として挙げられるのが組織としての対立が起こりやすくなることです。
たとえば、営業にインセンティブで給料が支払われている場合、工場の生産量の都合で受注を抑えてほしいという指示は、組織の全体最適を考えるうえでは正しくても営業から反発がくるはずです。
このように全体最適を追求することによって、部門間の対立が発生する場合もあるので、経営者やリーダーはリーダーシップをさらに全体最適化のために必要な指示を出す必要があります。
変化に対応できない
また、管理職層は全体最適を意識して意思決定しても、現場がついていけない場合があります。
たとえば、全体最適のために在庫の量や工場の生産量をコントロールしようとしても、メーカーや商社との契約や労働シフトや原材料の量などによって、指示どおりに活動できないことはよくあります。
組織を全体最適させるポイントは
では、組織を全体最適化させるために経営者やリーダーは何に気をつけるべきでしょうか。
社員の意識の統一
まず必要なのが社員の意識の統一です。現場職はそれぞれの与えられた役割をもとに行動します。しかし、そもそも全体最適化が「どのような状態でなぜ自分にその役割を与えられているか」「自分の業務を全体に合わせなければならないのか」の納得感をもって行動できません。
全体最適とはどのような状態であるのか、社員の意識の統一が必要です。
社内コミュニケーションの活性化
社内のコミュニケーションの活性化も同時に必要です。
問題点の所でも説明したとおり、全体最適を推進する過程で社内の対立を発生させる可能性があります。カリスマ的なリーダーが存在すればその人の鶴の一声で決まることもありますが、たいていの場合においてそのようなことは期待できません。
前提として、自部署の最適化だけを推進するのではなく、利益の対立する部署についてもいざというときに配慮できるように、部署間・従業員間のコミュニケーションを活発にする必要があります。
ITシステムの導入
ITシステムの導入も全体最適のために有効です。重複する事務コストの削減はコミュニケーションコストに由来することが多いためです。すなわち、それぞれが互いにやっていることを知らないので重複する作業が発生しがちになります。
ITシステムを導入することによって、コミュニケーションコストを下げられれば、全体最適による労働生産性の向上が加速するでしょう。
コミュニケーションコスト削減に寄与するシステムとしては、ビジネスチャットツールや社内SNS、人事労務関連システムなどが考えられます。中でもタレントマネジメントシステムは、従業員一人ひとりの個性(タレント)を可視化し、最適な人員配置を支援します。「ジョブ型雇用」制をとりいれて全体最適を実現するなら検討したいシステムです。

全体最適と部分最適の使い分けが組織を成長させる
経営層やリーダーがとくに意識するべきなのは全体最適の方です。個々の部署や従業員が最もパフォーマンスを発揮できるように、組織は部分最適に走りがちです。
経営層やリーダーは組織としての全体最適を目指すように、現場職は社内で共有されている全体最適化された組織像にしたがって、自分に求められた役割の中で部分最適を目指すというように使い分けが必要になります。
経営層やリーダーは、部分最適に走りがちな組織をコントロールして全体最適な状態に持っていくことが必要です。
組織が全体最適化することによってムダな業務がなくなり、絶え間なく変化するビジネス環境に対応できる柔軟性の高い企業になれます。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査