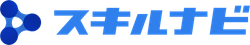採用通知書とは
採用通知書とは、企業が求職者に対して採用する旨を連絡するための書類です。企業に発行する義務はなく、法的効力もありません。しかし採用通知書を送ることで、求職者へ採用をアピールでき入社の許諾が取れないケースを減らせます。
また内定通知書を送ったあとに、雇用契約が結ばれた証として採用通知書を出すケースもあります。
内定通知書との違い
内定通知書とは、企業が求職者へ内定を知らせるための書類です。採用通知書同様発行する義務はないものの、発行したら法的効力をもつのが採用通知書との違いです。内定承諾書に署名・捺印をしてもらい、書類が企業側に送付されれば双方の合意が成立します。
基本的には内定が出てから入社までの期間が長い新卒採用で利用されるものですが、中途採用でも発行するかは企業ごとに判断がわかれます。内定通知書は、採用通知書とまとめて「採用内定通知書」として送付するケースもあるようです。
不採用通知書とは
不採用通知書は、求職者へ不採用となった連絡をするための書類で、書面にて発行する必要はなくメールで連絡しても差し支えありません。履歴書をはじめ面接時に受け取った書類を返却する企業もあります。いずれにしても忘れずに連絡をいれることで、失礼にあたらないよう注意しましょう。
労働条件通知書との違い
採用・内定が決まった人に渡す書面として、「労働条件通知書」も存在します。こちらは、採用ではなく労働条件を連絡するための書類です。労働条件通知書は 労働基準法の第十五条 にて労働者への明示が義務づけられています。
企業によっては採用通知書・内定通知書と労働条件通知書をまとめて交付する場合もあります。採用通知書・内定通知書は法定書面ではないため、どちらも兼ねた書類を作っても法的には問題ありません。しかし2つの書類は目的が異なるため、別途作成するのが妥当でしょう。
内定通知書の法的効力
前述したように内定通知書には法的効力がありますが、正確には「内定」に法的効力が存在します。採用活動における内定は、労働契約は成立し契約を開始する時期も決定しているものの、この時期までに特定の理由があれば契約を解約する権利が企業側にある状態のことです。
しかし内定は極端にいえば口約束でもできるものの、それではあとから「いった、いわない」といったトラブルが発生する可能性はあります。こういったトラブルを避けるため採用予定者から承諾をもらい、内定を明確なものにする証明書として企業側が「内定通知書」を発行します。
また法的効力があることから、採用予定者が内定を辞退する際や企業側が内定取り消しを行う際にも注意が必要です。
内定を辞退する場合
採用予定者が内定辞退を希望する場合、内定辞退について明確な法的ルールはありませんが、入社日直前の辞退は企業側に迷惑をかけるため、できるだけ早めに申し出ることが望ましいでしょう。
内定辞退は法律で守られている権利であり、企業も守らなければなりません。そのため内定を出す場合には、内定辞退が発生することを考え人員計画や人材配置に問題がないよう調整しましょう。
内定を取り消しする場合
企業側が内定の取り消しを行う場合は、 労働契約法第16条 によって厳しい制限をかけられているため注意が必要です。主に次のような「社会通念上相当」とされる事由がなければ、内定取り消しを行っても無効とされる可能性は高いと言えるでしょう。
- 重大な経歴詐称
- 重大な犯罪行為
- 業務ができないほどの健康上の問題
もし上記に該当したとしても、重大な問題でなければ内定取り消しは難しいと考えましょう。内定取り消しを行うと損害賠償にまで発展する危険性もあるため、十分慎重に考えるのが重要です。
また業績の悪化といった理由で内定取り消しを行う場合には、次の4つの要件を満たす必要があるため、こちらもチェックしましょう。厚生労働省の「 労働契約の終了に関するルール 」にある、「整理解雇の4要件」を参考にするのもおすすめです。
- 人員の削減(整理)が必要なこと
- 内定取り消しを回避するため最大限努力すること
- 内定者を解雇の対象者として選ぶ理由が合理的であること
- 対象者への説明方法や手続きが妥当であること
採用通知書・内定通知書の必須項目
採用通知書・内定通知書を作成する際、内容に必須の記載事項としては次のものが挙げられるでしょう。
- 日付
- 社名・代表取締役の氏名
- 採用試験への応募のお礼
- 採用が内定した知らせ
- 同封書類の案内
- 入社までに必要な書類の案内
- 入社日
- 内定取り消し事由
- 人事担当者の連絡先
採用通知書・内定通知書は企業としての正式な決定を表す書類であるあるため、作成する際には会社印を押印するのが望ましいでしょう。またそのほか入社までのスケジュール(研修や出社日など)を記載するケースもあります。
各項目についてそれぞれ詳しく紹介します。
日付
通知書の右上に書類を作成した日付、もしくは内定が決定した日付を記載します。どちらにすべきかはとくに決まりがないため、企業のルールとして定めておくといいでしょう。
社名・代表取締役の氏名
会社の代表者による通知であることを示すため、企業の名前と代表取締役の氏名を役職名とともにフルネームで記載します。社名と氏名の間に本社の住所を記載するのもいいでしょう。ただ必ずしも代表取締役である必要はなく、代表となる社員として人事部長の名前を記載するケースもあります。
採用試験への応募のお礼
採用予定者が自社へ応募してくれたことに対し、感謝の気持ちを伝えるためにお礼の言葉を記載しましょう。文面にルールは存在せず表現も自由で、時候の挨拶からはじめることもあります。時候の挨拶に関してはWordといった文章作成ソフトにテンプレートがあるため、そちらも参考にしましょう。
採用が内定した知らせ
お礼に続けて選考の結果採用内定が決定したことを知らせます。とくに文面の決まりはないものの基本的には「厳正な選考の結果、貴殿の採用が決定いたしましたのでご連絡します。」といった文言が使われます。ただ、採用予定者に内定が伝われば問題ないため、自社でアレンジを加えてもいいでしょう。
同封書類の案内
採用通知書・内定通知書と共に同封した書類を一覧で表記します。採用予定者にはこれらの書類が同封されているか確認してもらい、もし書類の抜けがあった場合どこに問い合わせを行えばいいかも明記します。同封すべき書類の内容に関しては、記事の後半で詳しく紹介しているため、そちらも参考にしましょう。
入社までに必要な書類の案内
入社までに提出してもらう書類を一覧で表記します。提出の期限がある場合は、それぞれ提出期限や返送期限についても明記するといいでしょう。例としては次のようなものが挙げられます。
- 入社(内定)承諾書
- 入社誓約書
- 身分保証書
入社日
採用予定者の入社日を、具体的に年月日で記載します。もし内定を出した時点で入社日が未定だった場合は、決定次第別途連絡する旨を知らせましょう。
内定取り消し事由
内定通知書を発行すると、採用予定者との間に労働契約が成立するため、万が一採用予定者にトラブルが発生し内定の取り消しが必要になった場合に備え、内定取り消し事由も明記しましょう。一般的に記載される内定取り消し事由としては、次のようなものが挙げられます。
- 入社日までに在籍する学校を卒業できない場合
- 入社(内定)承諾書が期限までに返送されなかった場合
- 健康上の理由で入社日以降出社が不可能になった場合
- 企業や社会の信用を損なう犯罪や反社会的な行為があった場合
- 暴力団および関係者といった反社会的勢力との関わりが発覚した場合
- その他社会的・道義的にやむを得ないと判断された場合
人事担当者の連絡先
最後に採用予定者がスムーズに問い合わせや内定辞退の連絡を行えるよう、担当者の名前と連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載します。また社内でも誰が担当者かをしっかり共有し、すぐに取り次ぎできるようにしておくと安心です。
採用通知書・内定通知書のテンプレート
内定通知書のテンプレートを次のページで紹介しています。内定通知書用の雛形ではあるものの、内容が4種類あり、表題を変更すれば採用通知書へも応用可能です。例文や書き方の詳細もテンプレートで確認できるので、採用通知書や内定通知書を用意する際には参考にしましょう。
採用通知書・内定通知書に同封する書類
採用通知書・内定通知書は、採用活動が終了し内定を言い渡したらできる限り早く送付します。内定の電話連絡→通知書の送付がスムーズに行くように、あらかじめ準備します。また返信用封筒も忘れずに同封しましょう。
採用通知書・内定通知書
採用通知書・内定通知書を送ることで求職者に採用内定を知らせます。前述した内容にそって書類を作成し、同封の入社(内定)承諾書・入社誓約書の締め切り、担当者の連絡先などを忘れずに記入しましょう。
入社承諾書(内定承諾書)・入社誓約書
採用通知書・内定通知書と同じ封筒に、入社承諾書(内定承諾書)、入社誓約書を同封します。採用内定通知を渡すだけでは企業が一方的に入社を受け入れただけで、求職者の意思を確認できないためです。特別な理由がない限り内定を辞退しないこと、会社の機密情報を漏えいさせないことなどを書類にてとりまとめます。
入社承諾書(内定承諾書)・入社誓約書に記載する項目は次のとおりです。入社承諾書(内定承諾書)と入社誓約書をわけて発行する場合は、入社するまでの期間にかかる内容を入社(内定)承諾書へ、入社後の契約内容を入社誓約書へ記載するよう文面を作ります。
- 日付
- 社名、代表取締役の氏名
- 入社承諾の旨
- 入社日
- 宣誓事項
- そのほか労働条件(必要があれば)
- 求職者の氏名記入欄
- 捺印の欄
- 保証人氏名と捺印(必要があれば)
送付した書面に、求職者が署名・捺印をして返却されれば書類が成立します。
労働条件通知書
前述したように、内定は労働契約の成立を意味するため労働基準法によって労働条件の明示が義務づけられています。そのため採用通知書・内定通知書とは内容をわけて労働条件通知書を作成し、同封しましょう。
主に記載すべき内容としては、次のものが挙げられます。
- 労働契約の期間
- 就業場所・従事業務
- 始業・終業の時刻
- 賃金の決定・計算・支払い方法
- 退職・解雇に関する事項 など
必須項目は合計で14つあるため、詳細は 厚生労働省のホームページ をチェックしましょう。また厚生労働省が提供する 労働条件通知書のテンプレート も存在するため、こちらの利用もおすすめです。
労働条件通知書は制度に合わせて昇給や退職手当、職業訓練、災害補償、表彰・制裁などの併記も必要です。自社の状況と照らし合わせて文面を調整しましょう。
採用通知書・内定通知書の送付方法
採用通知書・内定通知書の送付方法としては、メールと郵送の2パターンが考えられます。それぞれの特徴やメリット・デメリットをチェックしましょう。
メールで送る場合
近年は採用活動のオンライン化が進んでいることもあり、通知書をPDF化してメールで送付するケースも増えています。メールによる送付は、郵送に比べてスピーディーに内定を知らせられることがメリットです。
しかし入社(内定)承諾書といった返送が必要な書類に関しては、相手がプリントし返送用封筒や切手などの用意もお願いしなければならず、双方で手間がかかります。またメールだと相手が通知に気づかない可能性があるため、メール通知を事前に伝えたり送付後に開封確認機能や電話で確認したりする必要があるでしょう。
郵送する場合
従来どおり郵送する場合は、労働条件通知書や承諾書といった書類を同封できるのが大きなメリットです。また郵送にかかる時間も、速達や簡易書留を利用すればある程度短縮も可能です。書留であれば送付した客観的な証拠になるため、「受け取った受け取っていない」のトラブルも回避できます。
ただしメールに比べれば速度は遅く、書類の準備や郵送にかかる料金などコストもある程度は必要です。内定者の数が多ければコストの負担は無視できないものになるでしょう。
採用通知書・内定通知書はいつまで – 10日以内に送付
採用通知書・内定通知書は、採用を決定してから10日以内を目安に送付しましょう。可能であれば10日といわずすぐに送るのが理想です。求職者は入社する企業を決めるまで就職活動を続けるため、早期に連絡することで企業への熱意が冷める前に承諾を受け取れます。確実に採用するためにもなるべく早く送付するよう心がけましょう。
次の記事では比較的導入しやすい人材管理・採用管理システムを紹介しています。クラウド型のサービスは導入のコストや手間が少ないため、導入を検討してはいかがでしょうか。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査











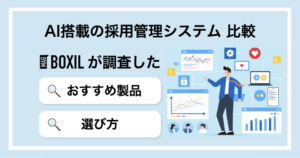

-e1767753139399-300x187.jpeg)
![[PR] SaaS企業の人材採用プロフェッショナルに聞く!キーパーソン採用で力を入れるべきところは? – SCTX2019特集](https://boxil.jp/mag/wp-content/uploads/2025/12/1c47ec52-6c61-4cef-aee1-09dbd91708f5.large_-300x158.jpg)