\ 稟議や社内提案にも使える!/
離職防止とはどのような取り組みなのか
離職防止とは、従業員の離職を防ぐために何らかの施策を講じることです。
従業員の離職は企業における大きな損失となるほか、離職率が高い企業は求職者から敬遠される恐れがあります。
そのため、企業には従業員が退職しないための対策が必要です。ただし、従業員が退職する理由は人によって異なるため、それぞれの原因を見極めたうえで離職を防ぐための取り組みが必要になります。
離職理由の分析と対策の策定
従業員の離職を効果的に防止するためには、まず離職の原因を正確に把握することが重要です。退職者へのヒアリングや在職者への定期的なアンケート調査を実施し、職場環境や業務内容、評価制度などに関する不満や課題を明らかにします。得られたデータをもとに、具体的な改善策を策定・実行することで、同様の理由による離職を未然に防ぐことにつながります。
離職防止や離職率改善はなぜ必要か
現代のビジネス環境において、優秀な人材の確保と定着は企業の持続的成長に不可欠です。企業にとって、離職防止のための施策や離職率の改善が必要な理由は次のとおりです。
- 人材が不足すると、従業員の負担が増えるため
- 優秀な人材が流出すれば、業績に直結してしまうため
- 新規の採用や新人の研修にはコストがかかるため
- 離職者が多いと、企業イメージに影響するため
離職防止や離職率の改善がなぜ必要なのか、詳しく解説します。
人材が不足すると、従業員の負担が増えるため
企業が離職防止や離職率改善に取り組む理由の1つが、人材不足によって従業員の負担が増加するためです。少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少によって人材確保が難しい状況にあり、ほとんどの業界で人手不足の課題があります。
内閣府が発表している「令和6年版高齢社会白書」によれば、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少の一途をたどっており、令和5年時点では7,395万人にまで減少しています。
根本的に働き手が足りていない状況において、せっかく確保した人材が離職してしまうと、新たな人材の確保が難しく、残された従業員に業務負担が増加してしまうでしょう。
そのため、企業では今いる人材ができるだけ離職しないような対策が必要です。
※出典:内閣府「 令和6年版高齢社会白書(全体版) 」(2025年3月15日閲覧)
優秀な人材が流出すれば、業績に直結してしまうため
企業が従業員の離職防止や離職率改善に取り組むべき理由として、人材の流出が業績に直結する点が挙げられます。とくに、優秀な人材の離職は自社の競争力の低下を招き、業績に直接影響を及ぼす可能性が高いです。
また、1人の従業員の離職がきっかけとなり、他の従業員が相ついで離職する流れができてしまった場合、食い止めるのはかなり難しくなります。
このような事態を避けるためにも、企業は従業員の離職を未然に防ぐための対策を取らなくてはなりません。
新規の採用や新人の研修にはコストがかかるため
新たな人材を採用したり、採用した人材を教育したりするためには相応のコストがかかるのも、企業が離職防止に取り組むべき理由です。
リクルート就職みらい研究所が発表した「就職白書2024」によれば、2019年度の新卒採用で発生した1人あたりの採用コストは約94万円、中途採用では約103万円でした。
加えて、研修や教育のためのコストもかかります。これだけのコストを費やしてもすぐに退職してしまったり、戦力化できたころに辞められてしまったりするケースがあります。
離職が起こりやすい企業では、採用コストや教育コストが膨大にかかっているほか、投資したコストを離職によって回収できないケースも多いのが現状です。
そのため、採用した人材が辞めてしまわないようなケアやサポートが必要です。
※出典:リクルート「 就職白書2020 ~冊子版 PDF~ | 就職みらい研究所 」(2025年2月4日閲覧)
離職者が多いと、企業イメージに影響するため
離職者が多い状況は、企業イメージに悪影響を与えます。
離職率の高さとは、人材の定着率の低さと言い換えられます。企業が一度でもこのようなイメージをもたれてしまった場合、新たに人材を採用しようとしてもできない状況に陥るかもしれません。
また、最近ではSNSに匿名で投稿された情報が簡単に拡散される時代です。OpenWork(旧Vorkers)などの口コミサイトでは、企業の離職率や職場環境に関する投稿が増えており、求職者が企業を選ぶ際の重要な情報源となっています。離職者が会社のことをSNSに投稿してしまうと、企業のイメージダウンに直結し、人材採用が難しくなるでしょう。
そのため、社員が離職した理由を精査して、状況に応じた対策をできるだけ早く講じる必要があります。
次からは、「職場環境の改善」と「従業員のモチベーション向上」の枠組みから、離職防止に有効なアイデアを紹介します。
離職防止のための「職場環境の改善」アイデア
快適で安全な職場環境は、従業員の満足度に直結し、離職防止につながります。物理的な環境の整備だけでなく、職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化も重要です。離職防止のために職場環境を改善するには、次のような施策を検討しましょう。
1on1ミーティングの実施
定期的な 1on1ミーティング を行うことで、従業員の悩みや不安を早期に把握し、解決できます。上司と部下のコミュニケーションを深め、信頼関係を構築することで、離職防止につながります。
サンクスカードの導入
従業員同士で感謝の気持ちを伝え合う サンクスカード を導入することで、ポジティブな職場環境を構築できます。お互いを認め合う組織文化が根付くことで、明るく働きがいのある職場になるはずです。
フレキシブルな働き方の導入
テレワークや フレックスタイム制 の導入、休暇制度の充実など、柔軟な働き方を導入することで、従業員のワークライフバランスを向上できます。個々のライフスタイルに合わせた働き方を選択できることで、ストレスが軽減され、離職防止につながるでしょう。
リーダーシップの強化
上司や経営陣のリーダーシップは、従業員の満足度や離職率に大きく影響します。管理職やリーダー層に対するリーダーシップ研修やコーチングを実施し、部下の指導やサポート能力を高めることが重要です。リーダーが従業員の意見を尊重し、適切な指導やサポートを行うことで、従業員の信頼を得ることにつながるでしょう。
福利厚生の充実
近年の調査では、従業員の健康管理、育児・介護支援、メンタルヘルスケアなどの福利厚生が、離職防止により大きな影響を与えることが示されています。
従業員のニーズに合わせた福利厚生を提供することで、長期的な勤務意欲が高まります。具体的には次のような福利厚生が考えられます。
- 育児支援制度や介護支援制度
- 資格取得支援やセミナー参加補助
- 住宅手当や家賃補助
- 社員食堂の設置や昼食代の補助
- 宿泊施設やレジャー施設などの割引制度
離職防止のための「モチベーション向上」アイデア
従業員のモチベーションを高めることは、離職防止の基本です。従業員が自身の成長を実感できる環境を提供することで、仕事への意欲が高まり、組織への エンゲージメント も強化されます。従業員のモチベーション向上のためには、次のような施策が考えられます。
公平な評価制度の構築
評価制度を透明化し、公平性を確保することで、従業員の不満を軽減でき、モチベーションを高めることが見込めます。評価基準を明確にし、従業員に周知することで、適切な努力目標を設定しやすくなります。従業員の業績や行動に対して、定期的なフィードバックを行うことで、改善点や強みを明確にし、成長を促すことが期待できるでしょう。
具体的には、複数の評価者による客観的な評価制度の制定や、 人事評価システム の導入による社員の実績やスキル、目標達成度の一元化などが有効でしょう。 タレントマネジメントシステム を導入すれば、データによる適材適所の人材配置を支援できます。
また、 OKR の導入も、従業員が会社の存在意義と自身の役割を把握しやすくなるため、業務に意欲的に取り組めるようになります。OKRとは「Objectives and Key Results」の略称で、目標設定や管理のためのフレームワークです。企業全体の大きな目標に対して、目標を達成するために紐づく必要な目標・成果指標を個々の従業員に設定します。
企業理念やビジョンの共有
従業員が組織の目標や価値観に共感し、自身の仕事に誇りをもつことは、離職防止に効果的です。企業のビジョンやミッションを明確に伝え、従業員が自分の役割と組織の目標との関連性を理解できるよう支援することが求められます。具体的な手段としては、社内報や定期的な全社ミーティング、経営層からのメッセージ発信などが効果的です。
メンター制度の導入
新しく入社した従業員が早期に離職することを防ぐためには、入社直後のサポート体制を充実させることが重要です。メンター制度を導入することで、新入社員が仕事の悩みや不安を相談しやすい環境を構築できます。年齢の近い先輩社員がサポートすることで、新入社員が職場に適応しやすくなり、早期離職を防ぐことにつながります。
キャリアステップの明確化
従業員が自社でのキャリアパスを具体的にイメージできるよう、昇進や異動の基準、スキル習得のためのロードマップなど、キャリアステップを明確に示すことが重要です。将来のキャリアが見えることで、長期的な視点で働くモチベーションを高められるでしょう。
教育・研修の充実
従業員のスキルアップを支援することで、自己成長の機会を提供し、組織への貢献意欲を高めることが期待できます。定期的な研修やセミナーの開催、資格取得支援制度の導入など、学習の機会を提供することで従業員の専門性を高め、組織の競争力向上にも寄与します。
社内公募制度の活用
社内公募制度とは、社内の従業員が希望するポジションに応募できる制度です。人材不足の部署や新規事業の立ち上げなどに活用され、組織強化や社員のキャリア形成を促進する目的で多くの企業で導入されています。
社内公募制度を活用すれば、従業員が自分の意思で仕事を選べるため、モチベーションややりがいが向上します。自分の適した仕事に就くことで生産性が向上し、離職防止につながる効果が期待できるでしょう。
従業員の声を反映する仕組みの構築
従業員の意見や提案を積極的に取り入れることで、組織の改善や従業員満足度の向上を実現できます。アンケートやサーベイの実施や定期的なミーティングを通じて、従業員の声を組織運営に反映させることが重要です。また、チームビルディング活動や社内イベントを通じて、組織内の連帯感や信頼関係を強化することも効果的です。
健康経営の推進
従業員の健康をサポートする取り組みは、離職防止において重要な要素です。定期健康診断の実施やメンタルヘルスケアの提供、健康促進プログラムの導入など、従業員の心身の健康を支援する体制を整えることで、安心して働ける環境を提供します。これにより、従業員の健康リスクを低減し、モチベーションを維持して、長期的な勤務継続が可能になります。
離職防止のアイデアを検討するには、離職防止ツールがおすすめ
従業員の離職防止のアイデアを検討したい場合は、離職防止ツールの導入がおすすめです。
離職防止ツールとは、従業員の離職の兆候や要員を把握できるツールのことで、離職を防ぐための対策を迅速に講じられます。
離職防止ツールの一般的な機能は次のとおりです。
- アンケート、 パルスサーベイ 機能
- 従業員のモチベーションや満足度の可視化
- 離職兆候や離職原因の分析
- 社内コミュニケーションの活性化
おすすめの離職防止ツールを紹介します。
タレントパレット
タレントパレットは、離職防止ツールとしても活用できるタレントマネジメントシステムです。簡単に作成・回答できるアンケート調査によって、従業員のモチベーションの可視化や分析ができます。設問内容も自由に作成可能で、従業員エンゲージメントが測れます。回答結果は組織ごとや年代ごとなどのグルーピングで比較・分析できるため、離職を防ぐための迅速なアクションにつなげられるでしょう。
また、アンケート結果や1on1ミーティングでの従業員の発言から、離職兆候をキャッチできます。離職スコアを数値化して可視化できるため、効果的な対策を講じられます。従業員同士が感謝の気持ちをポイントとして贈り合える機能もあり、組織内のコミュニケーションの活性化も可能です。
HRMOSタレントマネジメント
HRMOSタレントマネジメントは、離職防止や予兆の検知ができるタレントマネジメントシステムです。1on1ミーティングの実施記録の蓄積や状況の確認、従業員エンゲージメントや組織のパフォーマンス、従業員のコンディションを測れるサーベイなど、機能が充実しているのが特徴です。
専門家が設計した設問を使用できるため、専門知識がなくてもサーベイを始めやすく、サーベイの配布や回収も簡単に行えるのも魅力。レポートの自動作成機能により、状況の変化や解決すべき課題の優先順位も可視化されます。
カオナビ
カオナビは、離職防止ツールとしても活用できるタレントマネジメントシステムです。従業員満足度調査の結果をワンクリックでグラフ化でき、離職防止のための施策検討に活用できるほか、従業員の離職兆候の分析も可能です。また、パルスサーベイの結果の推移から、退職者の傾向を分析できるのもポイント。過去に退職した従業員のサーベイ結果をもとに、似たような傾向のある従業員の把握や、離職防止対策の実施につなげられます。
簡易ストレス調査やストレス状況の可視化、労務負荷分析やエンゲージメント分析など、従業員の現状を把握できるさまざまな機能が搭載されているため、効果的な離職防止策を立案・実施しやすいでしょう。
ミキワメAI
ミキワメAIは、従業員のコンディションを可視化できるウェルビーイングサーベイツールです。従業員の性格や心理状態をもとに、ケアやサポートが必要な従業員を可視化できるほか、従業員に適したケアやマネジメントの方法をAIが提案してくれるのが特徴です。
実名制のサーベイによって、リアルタイムでの従業員の状態を把握できるため、対話やケアによって休職・離職のリスクを低減できます。サーベイは3分間で完了するため、高頻度での調査が可能。社員や自立するためのセルフマネジメントの方法を提示できる機能が搭載されており、ウェルビーイング経営を目指す企業が導入しやすいツールといえます。
ミイダス
ミイダスは、従業員のコンディションを把握して、生産性の向上や離職率改善のための対策を実行できる組織サーベイツールです。毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員や組織のコンディションをカテゴリ別に可視化できるほか、実行するべきアクションを把握できるのが特徴です。従業員は5分程度で完了するアンケートに回答するだけのため、回答への負担はほとんどかかりません。
集計したデータは自動でレポート化されるため、従業員や組織のコンディションを一目で確認できます。また、アンケートを定期的に行うことで、従業員の変化や離職兆候をリアルタイムで確認可能。迅速なケアやフォローで離職防止につなげられます。
ラフールサーベイ
ラフールサーベイは、組織の強みと課題を可視化できる組織改善ツールです。組織全体と従業員の状態を可視化して行動の変化を促し、ウェルビーイング経営の実現をサポートしてくれます。膨大なデータを活用して設計された設問によって、組織の強みと課題が見つかり、人事施策の決定に活用可能。離職リスクの把握だけではなく、組織強化にまで利用できます。
また、サーベイ運用のプロがサーベイの実施から組織改善の対策選定までサポートしてくれるのも魅力です。従業員自身もマイページにて自身の状態を客観的に把握でき、自分と向き合うきっかけを作りやセルフマネジメントの推進をサポートします。
Geppo
Geppoは、個人と組織の課題を可視化でき、離職防止ツールとしても活用できる組織診断ツールです。個人サーベイと組織サーベイの組み合わせによって人事における個人と組織の課題を明確化し、働き方の改善を個人・組織の両面からサポートできるのが特徴です。選び抜かれた3問の設問に回答するだけで、従業員のコンディションや心身の変化を把握できます。
回答状況や回答内容は豊富なダッシュボードですぐに確認可能。組織や職種、性別などのマスターデータと組み合わせた分析も可能で、課題がどこにあるかを把握できます。わかりやすい調査結果のレポートから、エンゲージメントが悪化している要因を特定でき、重要度や緊急度などから、実行できる対策や領域を決定可能です。
Wevox
Wevoxは、従業員の心理状態や特性、組織のカルチャーなどを可視化し、満足度の高い組織づくりに活用できる組織力向上プラットフォームです。3分間で完了する負担の少ないサーベイによって、組織や個人の課題を調査できるほか、回答データはリアルタイムで自動集計されるため、人事側の負担を低減できます。
学術的裏付けのある設問が搭載されているため、組織改善に効果的なサーベイを実施できることに加え、自社にカスタマイズした設問の配信も可能です。回答結果の分析から効果的な対策を講じれば、エンゲージメントの向上により、離職率の低減だけではなく、生産性の向上まで期待できます。
LLax forest
LLax forestは、従業員のメンタルヘルスやフィジカルヘルス、エンゲージメントを測れるツールです。幅広い項目の計108問の設問で構成されたサーベイによって、従業員のストレスチェックや満足度調査を行えます。管理画面にて全体の回答結果やメンタル・フィジカル・エンゲージメントの3カテゴリの数値化、詳細結果などを確認可能です。個人の回答結果に合わせてヘルスケアの専門職が制作した動画やコラムを表示でき、工夫を学べる機会を提供できます。
また、オプションの福利厚生サービスでは、サーベイ結果から個人に合わせたセルフケアができるサービスを選択できます。各種相談窓口も用意されているため、従業員の心身の健康を保ちたい場合に利用しやすいサービスです。
いっとは、退職者の本音から離職対策を検討できるサービスです。第三者のインタビュアーが退職者に対してインタビューを実施。従業員の本音の分析に加えて、効果的な対策の立案までを提供するのが特徴です。
プロのインタビュアーが従業員の本音や言語化が難しいことまで聞き出し、課題の本質と離職の動機を明確化するほか、離職動機の分析や解決が必要な課題、対策の順序までまとめてレポートします。組織と従業員のギャップを把握でき、自社に適した対策が可能で、円満な退職や出戻りしやすい環境づくりをサポートしてくれます。
離職防止のアイデアを活用して、離職率の改善を
離職率の改善は企業における重要課題です。組織内のコミュニケーションの促進や、働き方・評価制度の改善など、さまざまな対策によって従業員の離職防止に取り組む必要があります。
また、組織や個人の状態をリアルタイムで把握したり、効果的な対策を立案したりしたい場合は、離職防止ツールの導入がおすすめです。
離職防止ツールは、次の記事でも詳しく紹介しています。
\ 稟議や社内提案にも使える!/




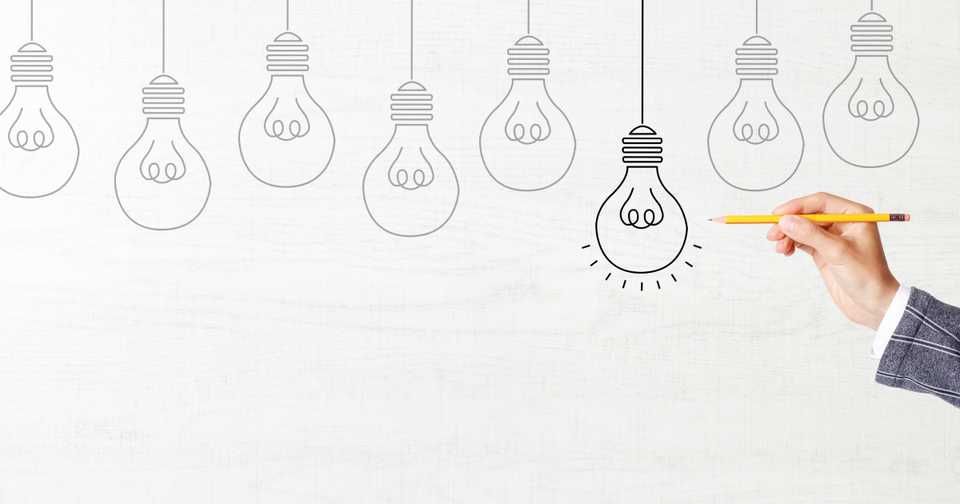







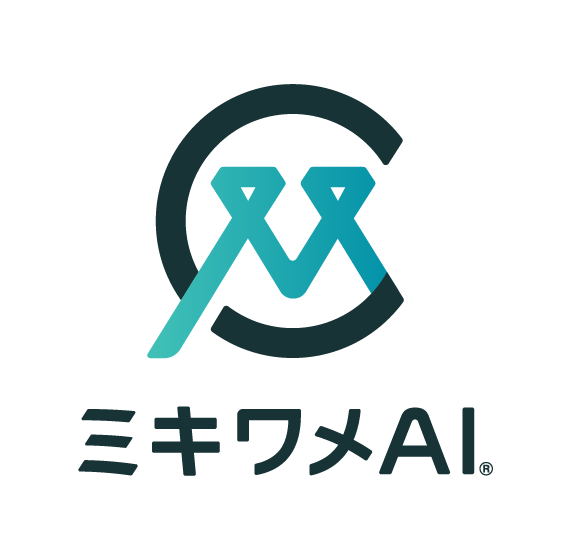







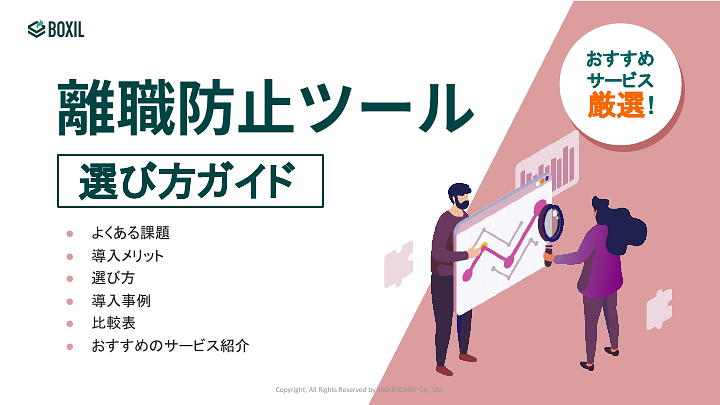
-e1767597002709-300x138.jpeg)


![[PR] 業界注目企業が語る!SaaS企業で人材が活躍するオンボーディングの極意とは? – SCTX2019特集](https://boxil.jp/mag/wp-content/uploads/2025/12/62a10ad9-ebf8-4ebe-9ca1-7c04aa47a73c.large_-300x158.jpg)











