MBO(目標管理制度)とは?課題や目的、メリット、OKRとの違い

目次を開く
MBO(目標管理制度)とは?
MBOは「Management by Objectives(目標管理制度)」の略で、グループや個人で目標を設定し、達成度によって評価する仕組みのことです。
マネジメントの父と呼ばれる経営学者「ピーター・F・ドラッカー」が提唱した考え方で、個人と組織の目標とリンクさせて、生産性向上や業績アップを目指します。
ドラッカーが説いたMBO
ドラッカーは『The Practice of Management(現代の経営)』において、適切に目標管理がなされれば、指示されることなく自ら目標に従って行動できると言及しています。
すなわちMBOを人事評価としてだけでなく、モチベーションを高める術としても利用可能であると述べているのです。人事評価の課題へと通ずる考え方ともいえるでしょう。
MBOの目的
MBOの主な目的は、(1)目標達成するための指標を設定することと、(2)個人と組織の目標と関連づけることの2つです。すなわち数値的な目標達成だけではなく、個人と組織の関わりに注目する必要があります。
具体的には、次の点に注意するとよいでしょう。
- 組織全体の目標と個人の目標を関連づける
- 自主的に目標管理するよう催促する
- 部下の目標適性を上司が確認する
単なる数値の管理ではなく、上司と部下が目標の管理という意識をもって、個人と組織、双方の目標を管理するのがポイントです。
MBOとOKRの違い
MBOとOKRはどちらも評価手法ですが、MBOが人事評価に利用されるのに対し、OKRは会社の成長を促すための指標として用います。
OKRとは「Objective and Key Result」の略であり、全従業員に、重要な組織目標を共有し、目標達成に向けて集中してもらう手法です。従業員一人ひとりの目標をたどっていくと、最終的には組織全体の目標となるよう目標を設計します。
違いをまとめると次のようになります。
| MBO | OKR | |
|---|---|---|
| 目的 | 人事評価 | 会社の目的を達成 |
| 目標の立て方 | 企業に依存 | SMART |
| 目標の共有範囲 | 上司と部下のみ | 全社的 |
| 評価・振り返りの頻度 | 半年〜1年に1回 | 四半期〜1か月に1回 |
| 期待される達成度 | 100% | 60〜70% |
OKRはコミュニケーションを活性化させる目的が強いのに対して、MBOは評価制度の趣旨が強いです。そのため、MBOはどちらかと言えば、コミュニケーションを活発化させるよりもノルマを設定して組織の人材に対する管理を強化する制度だと考えられています。
MBOとOKRの違いについては、次の記事でより詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

MBOのメリット
MBOを導入すると、2つのメリットを得られます。
能力開発・向上
自ら目標を立て管理することで、自己統制力の上昇、創意工夫による生産性の向上を図れます。
人に頼らず、スキルアップできるので、成長スピードも加速します。適切な目標を設定すれば、試行錯誤しながら目標達成する習慣も生まれます。これにより、セルフマネジメント能力が高まります。
モチベーションの向上
自主的な目標設定と創意工夫の余地は、従業員のモチベーションアップにつながり、自主性を高めます。
自ら目標を設定することで、強制的に与えられた仕事をこなすのではなく、組織に貢献する意識が芽生え、自主性やモチベーションにつながるのです。
MBOのデメリット
一方、MBOにはデメリットがあるともいわれています。
公平な評価が困難
平等に評価するのが難しいのは大きな難点といえます。
個別に目標を設定するため、そもそも公平に評価するのは難しいといえます。また数値化が難しい部門の場合、明確な目標設定は困難となるでしょう。
くわえて、個別に評価するので管理者に大きな負担がかかります。評価者を増やして主観による偏りを防ぎ、なるべく多角的な評価を行いましょう。
ノルマ管理ツール化の恐れ
冒頭でも述べたように、MBOは成果主義を実践する尺度として、取り入れられてきた側面があります。そのため、ノルマ達成を管理するツールとして位置づけられがちです。つまり、人事考課のためだけに利用されるツールになる可能性があります。
これらのデメリットは、MBOという制度が問題ではなく、間違った運用によって引き起こされることが問題です。組織全体で、MBOの仕組みやメリット・デメリットを理解し、正しく運用できるように制度を見直しましょう。
MBOの導入手順
以下では、MBOの導入手順と運用の流れについて解説します。基本的に、目標達成までのプロセスは、「PDCAサイクル」で管理します。
設定した目標(Plan)を実行(Do)して、定期的に達成度合いを確認(Check)します。当初の目標が実行できていたか、成果に結びついたのかを検証し、評価しましょう。そのうえで、明らかになった課題や問題点の改善策を検討、改善(Action)して、次の目標につなげます。
また、MBOもできる人事評価システムはこちらの記事で紹介しています。

1. 目標設定
まずはMBOに必要な「目標」の設定から始めます。
経営戦略をもとにした組織目標と、それに整合する個人目標を明らかにします。公正な評価のためには、各々の目標を正しく設定しなければなりません。目標が簡単すぎないか、難しすぎないかのチェックは重要です。組織全体の目標を共有することで、社員を一体化する狙いもあります。
目標設定に使える評価シートは、次の記事で紹介しています。無料でダウンロードできるので、すぐに使える評価シートを探している方へおすすめです。

2. 計画・実行
設定した目標に向けて行動します。計画どおりに行動できないことも多いので、目標とのズレを認識したら、適宜行動を修正しましょう。
3. 進捗確認
定期的に進捗状況を確認します。管理者は、部下との定期的な面談や日報の確認で、目標と現状に大きなズレがないかチェックしましょう。部下に、行動の振り返りを促すことも重要です。
4. 評価・評価後のフォロー
毎期、目標の達成について自己評価させ、その後、事前に決めてあった評価基準によって上司が評定します。あくまでも「目標達成度」という客観的な評価が必要となるため、事前にどういう基準で評価されるのかを明確にしておきましょう。
MBOの事例
A株式会社
A社では、目標達成を5段階の指標で明確化し、上司と部下が1on1ミーティングで定期的に振り返ることで、組織としての目標達成や個人の成長が実現できています。
同社ではMBOが次のサイクルで行われています。
| 上期 | 下期 | |
|---|---|---|
| 目標の設定 | 6~8月 | 12~2月 |
| 進捗確認 | 7~12月 | 1~6月 |
| 振り返り | 12~1月 | 6~7月 |
「目標の設定」では、提示される部門目標をもとに各社員が目標設定を行います。数値目標に留まるのではなく、「何をすべきか」というアクションベースで設定することで、目標への道筋が具体的になります。
「進捗確認」では1on1ミーティングによって、上司から部下へアドバイスを行います。
そして「振り返り」では、成果と自己評価を上司からの評価と合わせて確認し、次期へと反映させます。このように、上司と部下が対話をし目標や評価のすり合わせを行うことが、成功させるポイントの一つといえるでしょう。
MBOの課題
プロセスが考慮されにくい
MBOにて定量的な目標を多く設定すると、努力した過程が無視されてしまうという課題があります。結果を出すための行動は大事ですが、未達であった場合悪かったと評価してしまうのは問題です。
定量的な指標と定性的な指標をうまく組み合わせて、適切な評価が下せるように調整できるかが課題でしょう。
適切な目標設定の難しさ
MBOは人事評価に影響するため、あえて簡単な目標を設定する危険性があります。従業員ごとに目標の難易度に差があっては平等な評価がなされません。そのため上司は、部下の目標設定が適切かどうかよく確かめましょう。
また目標を適切に定めても、無意識に評価をゆがめてしまう可能性があります。たとえば、直近に活躍した従業員を高く評価したり、がんばりが見えづらい従業員に低い評価をつけたりしてしまいます。
自主性を軽んじた設定
「目標を設定する」という目的が先行して、上司が一方的に目標を決めつけないように注意が必要です。部下が納得していない目標を決定すると、モチベーションを下げかねません。
目標設定は評価に使用するだけでなく、従業員が自身の進捗度を測るためにも利用します。お互いがコミュニケーションを取ったうえで、目標を設定できるかが課題です。
MBO活用で従業員の能力を引き出そう
日本では、経済状況の変動や企業の人事評価ポリシー変更に伴って、導入された背景があり、MBOは成果主義に関する制度と思われがちです。しかし、個人のモチベーションや能力向上に重きを置いていることを忘れてはいけません。
単に数値目標を達成させる制度ではなく、自主性の尊重と適切なサポートが欠かせません。こうした、従業員の能力を最大限に引き出す評価制度が、厳しい環境にある日本企業にとって重要ではないでしょうか。
【関連記事】
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査




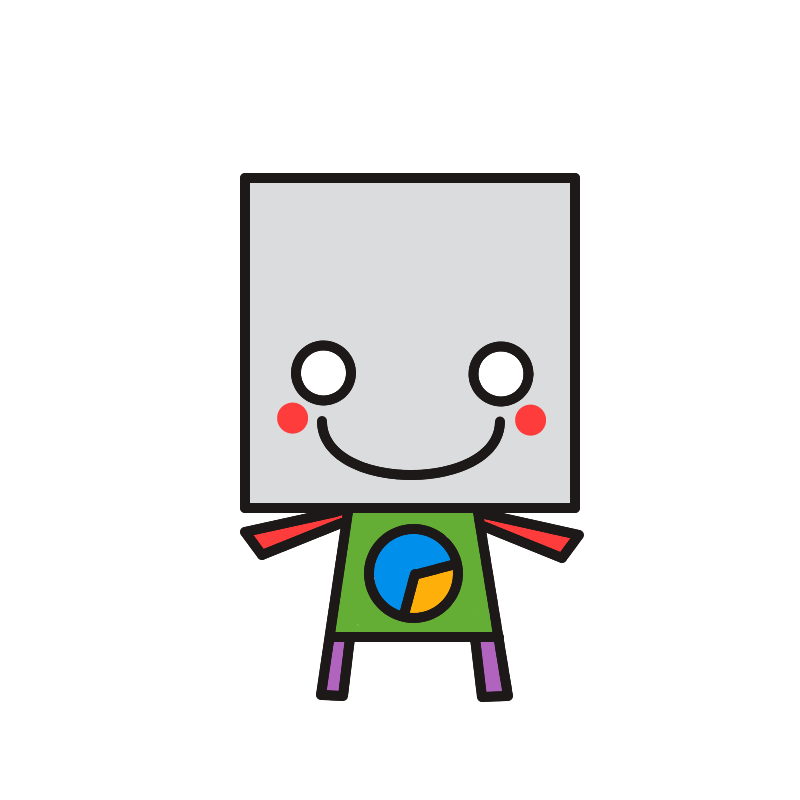



















 目次
目次

