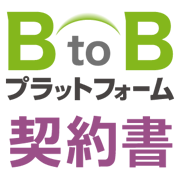電子契約とEDIの違いとは?それぞれの特徴やメリット・おすすめサービス

目次を開く
電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書ではなく、インターネット上の電子文書に電子署名を施すことで締結する契約のことを指します。
紙の契約書と同様、電子契約書にも合意内容の証拠力が求められます。電子契約の場合、電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の法的効力があるとみなされます※。
※出典:法務省「電子署名法の概要と認定制度について」(2024年3月4日閲覧)
電子署名とタイムスタンプ
電子契約で重要になるのは、電子署名とタイムスタンプです。電子署名は、「本人が署名していること」を証明します。一方のタイムスタンプは、「文書が改ざんされていないこと」を証明します。

電子契約のメリット
業務の効率化
電子契約はすべてオンライン上で業務が完了するので、契約書の発行や郵送の手間を省けます。また、契約書の保管費用や郵送費も不要になるため、契約に関わるコストの削減もできます。
コンプライアンス強化
電子契約システムで契約状況を管理すると、閲覧権限の管理やバックアップなど、コンプライアンス強化にもつながります。契約期限や契約内容を把握しやすくなるのもメリットの一つです。
電子契約とは何か、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

EDIとは
EDIとは「Electronic Data Interchange」の略称で、直訳すると「電子データの交換」の意味があります。
ビジネスにおけるEDIとは、専用回線やインターネットを通じて、発注書(注文書)・納品書・請求書などを、電子データとしてやり取りするシステムのことです。企業間における電子商取引や、決済業務をスムーズにするために導入されます。
EDIの3つの規格
EDIは識別コードの取り決め方法や通信方法によって、「個別EDI」「標準EDI」「業界VAN」の3種類に分類できます。
これらに加えて、インターネットを介して企業間取引をサポートするEDIはWeb-EDIと呼ばれており、3つのEDI規格からシェアを奪い導入が拡大しています。
個別EDI
個別EDIとは、取引先ごとに識別コードや通信方式を決定するタイプのEDIです。
取引先が少ない場合は個別EDIでも十分に対応可能ですが、取引先ごとにデータ変換のシステムを用意する必要があるので、取引先が増加すると活用しにくいデメリットがあります。
また、発注者側にあわせて取引先ごとに、変換コードや形式の設定をしなければならないケースが多いため、受注者側の負担が大きくなる傾向にあります。
標準EDI
標準EDIはEDI取引規約、運用ルール、データ交換形式などについて標準的な規格を用いたEDIです。標準的なEDIに従うので、同じ規格で複数の企業との取引が可能です。
業界VAN
標準型EDIの中でも特定の業界に特化したEDIを業界VANと呼びます。VAN(Value Added Network:付加価値通信網)とは、EDIデータのフォーマット変換サービスといった付加価値のついた通信ネットワークサービスのことです。
業界VANを活用すれば、同業者間の取引について業界共通の商品コードや取引先コードを活用できるので、取引先との諸調整の手間が省けます。
Web-EDI
Web-EDIは、インターネットを介して企業間取引をサポートしてくれるEDIのことです。従来のEDIと違い、多くがクラウドを利用したサービスであるため、専用のEDIシステムをインストールする必要がありません。比較的スムーズに導入でき、コストを抑えられるのが特徴です。
ただし、Web-EDIは標準化されていないため、独自のEDIシステムを構築している企業もあります。Web-EDIの導入にあたっては、データ変換の互換性など取引先のシステム・クラウドサービスにあわせ、調整が必要です。
EDI取引についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

電子契約とEDIの共通点
電子商取引を行う際に活用できる点において、EDI契約と電子契約は同じです。
電子契約は通信手段にインターネットを利用しますが、EDIも近年、Web-EDIの拡大によって専用線VANを活用した形態から、インターネット活用が徐々に増えつつあります。得られるメリットも同様で、商取引の迅速化、コスト削減、ペーパーレス化などが挙げられます。
電子契約とEDIの違い
取引対象や業務の違い
電子契約システムの主な目的は契約締結ですが、EDIは受発注や見積、決済など企業間取引に含まれる広範な業務をカバーしています。そのため、EDIの方が活用範囲は広いといえるでしょう。
対応している相手先としては、電子契約の場合企業(BtoB)、個人(BtoC)問わずさまざまな対象が考えられます。しかしEDIは企業間取引(BtoB)に用いるツールで、主流の業界VANは取引先が同業者間限定です。このように、電子契約とEDIでは、取引の対象やカバーしている業務が異なります。
サービスとしての違い
電子契約は、契約に特化して1対1から活用できるのに対して、EDIは業界VANに代表されるように、複数の事業者間の広範な取引に活用されるのが特徴です。
またEDIは専用線やVPNを使い、クローズドな環境をつくることでセキュリティを担保しています。一方で電子契約は、オープンな環境で利用することが前提のサービスであり、電子署名とタイムスタンプでセキュリティを担保しているのが違いです。
通信やフォーマットの違い
電子契約とEDIでは、通信やフォーマットにも大きな違いがあります。電子契約の場合書面による契約と同様の扱いになるため、特定のフォーマットや運用・通信規約は存在せず契約を行う企業が自由に決定可能です。一方EDIの場合、フォーマットは業界ごとに標準化され、通信規約も中立組織が業界ごとに定めています。
電子契約システムとEDIの使い分け
同業者間取引で活用する際にEDIは便利なツールです。とくに業界VANを活用すれば同業者間の「契約業務」だけに限定せず契約、見積、受発注、請求などさまざまな取引に関するトランザクションを処理できます。
ただし、EDIの方が便利なケースは限定されています。たとえば、業界標準に商品コードや取引先コード、取引ルールが存在しない場合は、企業間でこれらのルールを決めることから始めなければなりません。
個人との取引(BtoC)にもEDIを活用できず、業界VANが存在しない場合は、取引頻度の低い企業との間に個別EDIを設定しますが、これもコストパフォーマンスが悪いと考えられます。
また、次のようにEDIを活用できないパターンも数多く存在します。
- 異業種との取引が多い
- 図面といった大量の書類が契約の際には必要な企業
このような場合には、企業間取引であってもEDIが活用できないため、電子契約システムによって業務の効率化、コスト削減を実現できる可能性があります。EDIと並行して電子契約システムの導入も検討しましょう。

電子契約システムおすすめ3選
おすすめの電子契約システムとして、「電子印鑑GMOサイン」「電子契約くん」「Easy電子契約」の3サービスを紹介します。
そのほかの電子契約システムも知りたい方はこちらから。
電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
- 契約印タイプでの契約なら相手側のシステム導入は不要
- テンプレート機能でよく使用する契約書パターンを記録できる
- Salesforceやkintoneなどと連携できる
電子印鑑GMOサインは、電子認証局を運営しているGMOグループの電子契約システムです。
契約印タイプでの電子契約なら、相手方のシステムは導入不要で電子契約できます。テンプレ―ト機能で頻繁に使用する契約書パターンを記録でき、すぐに呼び出せるので効率的な契約業務が行えます。また、国内外問わずさまざまなサービスと連携できるのも強みです。
- 不動産取引に特化した電子契約システム
- Web会議ツールと連携して重要事項説明も行える
- 電子署名とタイムスタンプを組み合わせた長期署名規格にも対応
電子契約くんはイタンジ株式会社が提供する、不動産取引に特化した電子契約システムです。不動産の賃貸契約や更新契約、駐車場契約など不動産に関わることであればさまざまな契約に対応しています。
また不動産契約は重要事項の説明が必要であり、これも電子契約くんとWeb会議ツールを連携すれば、オンライン上から実施できます。電子署名とタイムスタンプを組み合わせた、長期署名規格のPAdESに対応しているため、契約が長期に渡る場合でも安心して活用可能です。
Easy電子契約 - コントラクトマネジメント株式会社
- kintoneと連携可能な電子契約システム
- 取引内容に応じてデータ項目をカスタマイズできる
- タイムスタンプ追加で電子保存可能、電子帳簿保存法に規定された一括検証機能あり
Easy電子契約は、業務改善プラットフォームとして有名なkintoneと連携できる電子契約システムです。自由度の高いシステムで取引内容に応じてデータ項目を完全にカスタマイズでき、取引先への公開ページは自由にレイアウトが変更できます。
タイムスタンプ付与アプリを組み合わせることで、対象文書の電子保存も可能です。また電子帳簿保存法に規定された、一括検証機能をあわせて提供しています。
その他の電子契約システム比較は、こちらの記事で紹介しています。

EDIシステムおすすめ3選
おすすめのEDIシステムとして、「EdiGate/POST」や「クラウドEDI-Platform」、「MCS(マルチ・コネクション・サービス)」の3サービスを紹介します。
EdiGate/POST - 大興電子通信株式会社

- Web画面上で納期の回答・照会が可能
- SSL通信による暗号化やID、パスワード、ウイルスチェックでアカウントを保護
- 紙の帳票業務を大幅削減
EdiGate/POSTは、大興電子通信が開発・提供しているWeb型EDIサービスです。Web型のEDIなので他のEDIシステムと比較すると導入が容易です。
SSL通信による暗号化やID、パスワード、ウイルスチェックなどでアカウントを保護して、一定のセキュリティを担保しています。紙の帳票業務が大幅に削減できるので、書類仕事に必要だった人件費を圧縮でき、業務全体の生産性を高める効果があります。
- 標準EDIはもちろんWeb-EDIやJCAにも対応
- シンプルで効率のいい通信環境を実現
- 国内3拠点でデータを分散処理、24時間・365日専属スタッフが運用・監視
クラウドEDI-Platformは、サイバーリンクスが開発・提供している、EDIプラットフォームサービスです。JCA手順や全銀協手順といった従来の手順、流通BMSの各バージョンが用意され、標準EDIはもちろんWeb-EDIやJCAにも対応しています。
加盟企業、取引先ともに通信先はクラウドEDI-Platformだけになるので、シンプルで効率のいい通信環境を実現可能です。国内3拠点でデータを分散処理し、24時間・365日専属スタッフが運用・監視しており、セキュリティにも力を入れています。
MCS(マルチ・コネクション・サービス) - 株式会社東計電算
- 取引先ごとにEDIシステムを構築する必要がない
- Web-EDI代行オペレーションにも対応している
- セキュリティー対策と障害対策を実施
MCS(マルチ・コネクション・サービス)は、東計電算が提供しているEDIサービスです。MCSは取引ごとにEDIシステムを構築する必要がないので、導入・運用費用を抑えられます。
Web-EDIの代行オペレーションにも対応しているので、利用することにより業務効率化が可能です。プライバシーマーク、ISMSを取得しておりセキュリティ対策も充実しています。
その他のおすすめEDIサービスは、こちらの記事で比較しています。

EDI導入企業にも電子契約は役立つ
電子契約とEDIの違いについて説明しました。
EDIは、企業間取引における発注書・納品書・請求書などを、電子データとしてやり取りするシステムです。電子契約は、企業や個人を問わず、インターネット上で電子文書に電子署名をして契約できます。
企業によっては、EDIに対応していない異業種との取引や契約を行うケースは少なくありません。まだ、紙の契約書でやり取りを行っているのであれば、電子契約システムを導入を検討しましょう。

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査