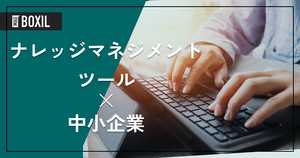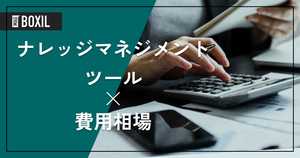社内ノウハウ共有ツール比較12選!ナレッジの管理・蓄積におすすめ

ナレッジマネジメントツールを導入しようと思っても、種類がたくさんあってどうやって選べばいいの?と迷いますよね。そんな声にお応えして「SaaS導入推進者が選ぶサイト第1位※」のBOXILがおすすめナレッジマネジメントツールを厳選。チェックしたいサービスの紹介資料をまとめてダウンロードできます。
⇒【特典比較表つき】ナレッジマネジメントツールの資料ダウンロードはこちら(無料)
※2020年9月実施 株式会社ショッパーズアイ「SaaS比較メディアに関するイメージ調査」より

おすすめナレッジマネジメントツールの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なナレッジマネジメントツールを含むサービスを徹底比較しています。ぜひナレッジマネジメントツールを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
目次を開く
ノウハウとは
ノウハウとは、英語の「know(知る)」と「how(方法)」を組み合わせた造語で、ビジネスにおいては業務をスムーズに進めるための経験や知識、技術を総称した言葉です。社内にはさまざまなノウハウが存在しています。しかしファイルが散在していることや、そもそも可視化されていないケースも多く、この貴重な資産をうまく共有・活用できていない企業が多く存在します。
可視化された知識・ノウハウは「ナレッジ(knowledge)」とも呼ばれ、企業においてはこのノウハウやナレッジをいかに収集・集約・管理して、共有できる仕組みをつくれるかが重要です。
社内でノウハウ(ナレッジ)を共有するメリット
社内でノウハウ(ナレッジ)を共有するメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 属人化の解消
- 業務の標準化
- 教育の手間・コスト削減
それぞれ詳しく解説します。
属人化の解消
社内でノウハウ・ナレッジが共有できるようになると、属人化の解消が可能です。ノウハウやナレッジを個人だけで所有していると、この従業員だけ対応できる仕事が増えます。すると、この従業員が休んだ日に対応できる人が存在せず、業務が滞ったり顧客を待たせたりするケースが発生するでしょう。
またこの従業員が退職すると、培ってきたノウハウ・ナレッジはすべて失われるため、企業は貴重な財産を失います。最悪の場合にはシステムが使えなくなった、業務ができなくなったといったトラブルに発展する可能性もあります。
しかし社内でノウハウ・ナレッジが共有されていれば、従業員の休日や退職後でも、引き継ぎや業務がスムーズに行えるでしょう。
業務の標準化
社内でノウハウ・ナレッジが共有できれば、従業員全体のスキルを底上げできるため、業務の標準化が可能です。ベテランの従業員や成績の優秀な従業員は、それぞれ経験から培ったノウハウやスキルをもち合わせています。
しかしこれは可視化されていないケースも多く、結果従業員ごとに能力や成績が偏りやすくなります。一方でこれらのノウハウ・スキルをテキストやイラスト、動画などでナレッジ化し、ほかの従業員と共有できるようになれば、このノウハウ・スキルを参考にして各個人の業務改善を行えるでしょう。これにより、従業員ごとの顧客対応や業務対応の差を埋め、業務を標準化できます。
教育の手間・コスト削減
従業員の教育にかかる手間やコストを削減できることも大きなメリットです。新入社員の入社直後や、人事異動で新しい仕事を始めるときなどは、業務についてわからないことも多くあります。そのため先輩従業員や同じ部署の従業員はやり方のレクチャーや資料の準備、質問への対応など行いますが、代わりに自身の業務が滞りやすく残業も増えがちです。
しかし社内のノウハウ・ナレッジが共有され、いつでも見られる状況にあれば、教育される側の従業員はこれを使って多くの課題を自己解決できます。これにより、教育する側の従業員は手間や負担が軽減されるため、自分の業務に集中しやすく、残業時間も削減できるでしょう。
また人によって言っていることが違ったり、教育担当者によって教育される側の業務品質にばらつきが出たりといった事態を未然に防ぎ、教育を標準化できることもメリットの1つです。
失敗しないための社内ノウハウ(ナレッジ)共有ポイント
社内でノウハウ・ナレッジの共有を失敗しないためのポイントは次のとおりです。
- 目的を明確にし、周知する
- 保管場所を決める
- 共有方法をマニュアル化し、活用を促す
- ノウハウ・ナレッジの共有を賞賛・感謝する仕組みづくり
- ITツールを導入し効率的に管理する
目的を明確にし、周知する
社内ノウハウ共有を成功させるためには、目的を明確にして、組織全体に周知するのが大切です。ノウハウ共有の目的を具体化すれば、どのような課題を解決したいのか、何を達成したいのかを明確にできます。
たとえば、新人教育の効率化や業務プロセスの改善、イノベーションの促進など、目的に応じた具体的な目標設定が必要です。また、目的を周知することで、従業員はノウハウ共有の意義を理解しやすくなり、モチベーションを高められます。
経営陣からの支持を得ることも重要です。組織全体での協力体制が強化され、ノウハウ共有の文化を定着させやすくなります。これらを怠ると、情報共有が形骸化し、効果を発揮できない恐れがあります。
保管場所を決める
社内でのノウハウ共有を成功させるためには、適切な保管場所を決めることも大切です。情報の保管場所を統一することで、探さなくても必要な情報がどこにあるかがわかりやすくなり、スムーズにアクセスできるようになります。
また保管場所を決める際には、ナレッジの分類に関するルールを明確にすることも重要です。これにより、情報の整理が容易になります。たとえば、「システム→マニュアル→各部門ごとのフォルダ→各マニュアルファイル」とフォルダ階層をつくり、マニュアル関連のファイルは部門ごとのフォルダにすべて保管するルールを定めます。
これが企業全体で周知されていれば、違う部門のファイルが必要になった場合でも、求めるファイルがすぐに見つけられるでしょう。
共有・蓄積方法をマニュアル化する
ノウハウ共有の失敗を避けるためには、情報の共有方法をマニュアル化することも大切です。共有方法をマニュアル化することで、ノウハウ共有の手順やルールを明確にでき、作成者・閲覧者双方の負担を減らせます。新入社員や異動者もスムーズにノウハウ共有へ参加できるでしょう。
たとえば、情報の投稿方法やフォーマット(テンプレート)、レビュー手順、更新頻度などが記載されたマニュアルを作成します。もしツールを導入する場合には、このツールの使い方もマニュアル化するといいでしょう。
また蓄積させるノウハウ・ナレッジの基準・範囲を定めるのも重要です。基準を定めなければ不要な情報が蓄積されたり、逆に必要な情報にもかかわらず、本人は不要と考えて投稿しなかったりする可能性があります。そのため、各部門ごとにどういった情報が必要かを洗い出し、具体的な例とともに紹介することで、わかりやすく案内を行いましょう。
ノウハウ・ナレッジの共有を賞賛・感謝する仕組みづくり
ノウハウ・ナレッジを投稿した際に賞賛・感謝される仕組みをつくるのも重要です。たとえノウハウ・ナレッジの共有が有効と理解できても、投稿したものに対してなんのリアクションもなければ、モチベーションの維持は難しいでしょう。とくに営業職といった、個人の成績が給与や昇進に深く関連する職種では、ナレッジの共有を出し惜しみしがちです。
そのため投稿されたナレッジに対して、賞賛や感謝が可視化される仕組みをつくる必要があります。たとえば全体会議や定例会において、とくに優れたナレッジを表彰したり、人事評価の項目に組み込んだりします。優れたノウハウをナレッジ化して共有すると、自分にとって得になると理解してもらいましょう。
ITツールを導入し効率的に管理する
本格的にノウハウ・ナレッジの共有体制を構築したい場合は、ITツールを導入するのがおすすめです。ノウハウ・ナレッジは1か所に集約することで力を発揮するものであり、定期的な更新も必要です。
しかしアナログな管理方法では、ノウハウ・ナレッジの数が増加すると正確に管理を行うのは難しくなるでしょう。一方でナレッジ共有ツールといったITツールを導入できれば、ノウハウ・ナレッジを苦労せずに蓄積・集約でき、共有や管理を効率的に行えます。
ナレッジ共有ツールとは、ナレッジの蓄積や管理を効率的に行うためのシステムで、ナレッジマネジメントツールとも呼ばれます。ナレッジを1つにまとめられ、検索機能で簡単に見つけられたり、更新が簡単にできたりするため、手間をかけずにナレッジ共有を社内に浸透できるでしょう。
システムによっては、「いいね」機能といった、前述した賞賛・感謝の仕組みを支援する機能が搭載されているケースもあります。
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを導入するメリット
社内ノウハウ共有ツールの導入メリットは次のとおりです。
- ノウハウ・ナレッジを一か所に集約できる
- ノウハウ・ナレッジの検索・更新が容易になる
- ノウハウ・ナレッジ共有のルールを定めやすい
ノウハウ・ナレッジを一か所に集約できる
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを導入するメリットの1つが、ノウハウ・ナレッジを一か所に集約できることです。
ツールを導入すれば、ノウハウ・ナレッジをどこに投稿・集めればいいかがわかりやすく、情報の散在防止や、必要な情報にスムーズにアクセスできる環境の整備につながります。またツールの多くはクラウド型であり、インターネット環境があればデバイスを問わず、いつでも閲覧・共有ができるのも便利です。
ノウハウ・ナレッジの検索・更新が容易になる
情報の検索と更新が容易になるのも、ナレッジ共有ツールを導入するメリットです。社内ノウハウ共有ツールは全文検索やタグづけなど検索・分類機能が充実しているため、必要な情報にスムーズにアクセスできます。
これにより、マニュアルや文書の場所がわからないといった問い合わせも減るため、それらの対応にかかる時間の削減にもつながります。またシステムから直接ファイルが編集できるといった機能があり、ノウハウの更新を簡単に行えるのもメリットです。
複数の拠点を構えていて紙媒体でマニュアルを管理していた場合、ノウハウの更新があるたびに印刷や配送をしなければならず、情報にタイムラグも発生します。しかし上記の機能にくわえ、クラウド上でノウハウを管理できれば、どこからでも自由に更新ができるため、手間をかけずに常に最新版の情報が閲覧できます。紙に印刷するコストを削減できるのもメリットです。
ノウハウ・ナレッジ共有のルールを定めやすい
ノウハウ共有ツールを導入することで、情報共有のルールを定めやすくなるのもメリットです。ノウハウ共有ツールには、テンプレートの設定やタグづけ機能、ファルダわけ機能など、共有方法をマニュアル化しやすい機能が豊富に搭載されています。
また投稿フォーマットやアクセス権限などを設定することで、情報の質を一定に保てるほか、誰もが簡単に情報を投稿、利用できる環境を整えられます。ルールにもとづいた情報の管理によって、コンプライアンスの強化にも役立つでしょう。
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを導入するデメリット
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを導入するデメリットとしては、導入に時間や費用がかかる点が挙げられます。ツールの導入には、基本的に初期費用と月額利用料がかかります。無料トライアルを実施しているツールも多くありますが、期間は決められているため、無料で使い続けるのは現実的でないでしょう。
またツールの選定を行うため導入製品の決定までに時間がかかるのはもちろん、従業員へ定着できるようマニュアルの作成や運用ルールの策定が必要であり、利用を開始するまでにも時間がかかります。くわえて、導入してすぐに効果が出るようなツールではないため、事前にしっかりとコストや機能性を確認し、自社に最適なツールを導入するのが重要です。
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールの選び方
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールの選び方のポイントは次のとおりです。
- 導入目的と合致するか
- 操作しやすいか
- セキュリティ対策は十分か
導入目的と合致するか
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを選ぶ際には、導入の目的とツールの機能が合致しているかが重要です。たとえば、業務効率化を目指すのであれば、情報の検索や共有がスムーズにできるツールが適しています。
また社員のスキルアップを図りたい場合は、タスクやプロジェクト管理機能をもつツールが役立つでしょう。このように、目的に応じてツールの機能や特徴を確認し、組織のニーズに最適なものを選ぶのがツール導入成功の鍵です。
操作しやすいか
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを選ぶ際には、操作性を確認するのも大切です。ユーザーインターフェースが直感的で使いやすいツールを選べば、従業員が抵抗感なくツールを利用できます。
さらに、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスに対応していれば、場所を問わず情報にアクセスできるため、利便性が大きく向上するでしょう。実際にツールを導入する前に、デモや無料トライアルを活用して、操作感を確認するのがおすすめです。
セキュリティ対策は十分か
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールを選定する際には、セキュリティ対策が十分に施されているかも確認しましょう。ノウハウ・ナレッジ共有ツールには、情報漏えいを防ぐためデータの暗号化やアクセス制限、認証機能などが備わっています。
ツール上で機密情報を扱う場合は、セキュリティ対策の性能を確認し、自社のセキュリティ要件を満たすかを確認しましょう。クラウド型のツールを選ぶ場合は、データセンターのセキュリティ基準や運用体制も要チェックです。
おすすめの社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールの比較表
ナレッジ共有ツールやナレッジマネジメントツールのなかで、おすすめのクラウド型ツールを一覧にまとめました。サービスを比較検討する際の参考にしましょう。
【特典比較表つき】『ナレッジマネジメントツールの資料8選』 はこちら⇒無料ダウンロード
また、一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。
【特典比較表つき】『ナレッジマネジメントツールの資料8選』 はこちら⇒無料ダウンロード
※ダウンロード可能な資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。
社内ノウハウ・ナレッジ共有ツールのおすすめ比較12選
Quipは、営業プロセスの刷新やリアルタイムでの共同作業、アクションを起こすための状況把握などを一元管理できるドキュメント共有ツールです。CRM(顧客関係管理)との連携が可能で、顧客の情報や商談の状況に応じた営業戦略の更新が可能です。必要なタイミングで必要な行動を起こすための情報を共有できます。アプリを使用すればスマートフォンからも情報にアクセス可能です。
ナレカンは、社内のナレッジデータベースにすぐにアクセスできるナレッジ共有ツールです。自然言語での検索が可能なほか、AIが搭載されており、社内のナレッジを横断して最適な回答を自動生成してくれます。複数のキーワードやタグからも検索できるほか、添付ファイル内のキーワードでの検索もできるなど、ノウハウをさまざまな方法で検索可能です。ほかにも、チャット内容をワンクリックで蓄積・情報共有できる機能、社内版知恵袋で質問や回答ができる機能などが搭載されています。
CrewWorks - テクノ・マインド株式会社

CrewWorksは、プロジェクトやタスク、ファイルごとに自動作成されるチャットルームにより、情報とコミュニケーションを一元管理できるビジネスコミュニケーションツールです。業務に関する情報とチャットを1つのツールで管理でき、検索もプロジェクトやチャットなど機能を横断して1回で済ませられます。
Confluence - アトラシアン株式会社
Confluenceは、複数のチームで社内ナレッジの作成や共有ができる、ナレッジ蓄積ツールです。ミーティングの議事録やプロジェクト計画書など、さまざまな文書を作成できます。ナレッジの共有も簡単に行えるため、部署内はもちろん、部署を越えたノウハウ共有が可能です。コメント機能やフィードバック機能を使えば、従業員同士の交流を活性化できます。
NotePMは、マニュアル作成や社内ナレッジ管理ができるナレッジマネジメントツールです。機能性の高いエディタとテンプレートが搭載されており、標準化されたマニュアルやノウハウをWeb上で簡単に作成できます。登録されたファイルの中身は全文検索できるため、欲しい情報に柔軟にアクセス可能です。アクセスが多いページやナレッジ共有への貢献度が高い従業員の抽出など、利用状況の定量的な分析もできます。
Pitchcraft - 株式会社ヴァリューズ

Pitchcraftは、営業資料や提案資料などを自動整理し、管理できる提案型ナレッジシェアクラウドです。取り込んだ資料のタグづけと、要約を自動で実施してくれます。タグやフリーワード、PV数などの検索軸で資料を探せるほか、文章形式の質問に対し資料の内容を参照して回答してくれる機能も備えています。資料の格納やバージョン管理をドラッグ&ドロップで行えるため、専門知識不要で利用可能です。
SolutionDesk - アクセラテクノロジ株式会社

SolutionDeskは蓄積されたナレッジとAIを活用することで、業務革新が実現できるナレッジ管理ツールです。日々の業務で利用するFAQや対応マニュアル、説明書、顧客の応対履歴などを一元管理できます。組織や部門の壁を越えて活用できるため、組織全体のスキルの平準化や技術の伝承、生産性向上を期待できます。ナレッジにタグをつけることで、ドリルダウン検索の絞り込み項目を自動生成できる点も魅力です。
Video Questor - NDIソリューションズ株式会社

Video Questorは、動画コンテンツを自動解析し、ノウハウや暗黙知を抽出、共有できる生成AIツールです。要約やマニュアル作成、質問応答などの指示出しをチャットで行えば、動画の内容と指示をもとに文章を生成してくれます。特定の指示により、動画の一部をピックアップして視聴できます。
flowzoo - BUSINESS‐ALLIANCE株式会社

flowzooは、ノウハウやナレッジをフロー化し、進捗管理も行える業務管理クラウドです。人事やITなど、多様な業務の手順やタスクを一画面に集約し、作業手順を確認しながらの業務遂行が可能です。マニュアルは画像や動画、テキストなどを組み合わせてタスクごとに作成できます。細かなタスクを多く含む業務の可視化、標準化、進捗管理におすすめです。
Video BRAIN - 株式会社オープンエイト
Video BRAINは、動画によるコミュニケーションの推進によって、企業の経営課題を解決できる動画編集クラウドツールです。動画コンテンツの作成・編集、一元管理できるのが特徴で、社内ナレッジやノウハウを動画で共有するといった活用ができます。PowerPoint感覚で簡単にマニュアル動画が作成できるほか、過去に制作した動画のテンプレート化や複製編集が可能なため、マニュアル動画を多く制作したい場合でも使いやすいでしょう。
Qastは、組織内の個人の知識や経験を集約し、社内ナレッジを構築できるクラウドサービスです。部署を横断した情報共有も可能で、組織全体の生産性向上が期待できます。検索性も高く、必要な情報に素早くアクセスできるほか、システムの活用状況の把握や分析も可能です。経験豊富なコンサルタントにより、システム導入から活用までのサポートを受けられます。
DocBaseは、誰でも簡単にドキュメント作成・編集ができるナレッジ管理ツールです。さまざまなドキュメントをマークダウン形式とリッチテキスト形式のどちらでも作成できるため、デジタルツールに明るい方だけではなく、苦手な方も利用しやすい点が魅力です。また、画像編集と文書作成がワンストップで行えます。
社内ノウハウ・ナレッジ共有の導入事例
最後に、ナレッジ共有ツールの導入を検討している方に向け、実際にツールを導入して成功した企業の事例についていくつか紹介します。
アイリスオーヤマ株式会社
生活用品の企画・製造・販売を行うアイリスオーヤマは、ナレッジ共有ツールの導入により、情報検索の手間を大幅に削減し、従業員の成長を加速させました。アイリスオーヤマでは、これまで情報共有に社内サーバーを利用していましたが、ファイル名でしか検索ができなかったため、欲しい情報をなかなか見つけ出せない状況でした。
また3年目以下の従業員構成比が高い組織であるため、業務ノウハウやナレッジで常に学び続ける必要があったことから、ナレッジ共有ツールを導入。結果アプリの知識やメーカー固有の特性、機器情報などがすべてツール上で確認できるようになり、検索工数が約70%も削減されました。
くわえてチームメンバーから質問を受ける頻度も半減。従業員の成長スピードも向上し、ツールを利用して能動的に学習を行うようになったそうです。
※出典:NotePM「【導入事例】情報検索の手間が7割削減。NotePM導入で、業務効率化と社員成長を加速 – アイリスオーヤマ株式会社」(2024年11月26日閲覧)
株式会社識学
ビジネスで勝つためのコンサルティングやトレーニングなどを提供する識学は、ナレッジ共有ツールの導入で知見を共有できるようになり、業務の手間を軽減しました。識学では、これまで社内ポータルサイトを利用していましたが、タイトルしか検索できないため、欲しい情報にたどり着けないことが課題でした。
またマニュアルの保管場所がわからず、都度知っている人にURLを共有してもらうといった手間がかかていたことから、ナレッジ共有ツールを導入。結果検索性が高く、情報を見つけやすくなったことで、ファイルの共有・保管場所を気にせずすむようになりました。
また更新履歴を確認でき、変更箇所もすぐにわかるため、部下の更新したファイルの内容をチェックする際に、かかる時間を短縮できました。Slackと連携させたことで、自動でSlackに更新内容が通知されるようになったのも、業務の手間を軽減できて便利とのことです。
※出典:NotePM「【導入事例】コンサルティングの知見を共有!チャット連携も活用し、業務の手間を軽減 – 株式会社識学」(2024年11月26日閲覧)
株式会社集英社
「週刊少年ジャンプ」をはじめ、さまざまなコミック・書籍の出版を行っている集英社は、ナレッジ共有ツールの導入で、分散していたデジタル資産や知見を集約し、有効活用できるようになりました。集英社はメディアや編集部ごとにノウハウや文化があり、いい面もあったものの、システムの統一化や共通基盤の構築に課題がありました。
そこでこれらの課題を解決するために、デジタルソリューション部を立ち上げます。デジタルソリューション部は各編集部に分散したデジタル資産や知見を集約し、課題を解決するために、一部の事業部で導入していたナレッジ共有ツールを引き継ぎ、企業全体へ拡大しました。
担当者の利用呼びかけや、利用促進へ積極的に取り組んだこともあって、ツールの利用は現場に浸透。結果新人スタッフの研修・オリエンテーションの予習に利用できるようになり、オンボーディングから1週間程度で自走できるようになりました。また教育担当者はスタッフから質問される頻度が減り、対応の負担も軽減されたそうです。
※出典:Qast「Qastの浸透でナレッジマネジメントの有用性を実感しました」(2024年11月26日閲覧)
社内ノウハウ・ナレッジ共有はツールで効率化
個人がもつノウハウ・ナレッジを組織内や全社で共有できれば、部署間の連携強化や新しいアイデアの創出につながる可能性があります。
社内でノウハウ・ナレッジを効率的に共有したい場合は、専用ツールの導入がおすすめです。情報の作成や更新、共有が簡単に行えるため、データの積極的な活用や社内ナレッジの蓄積が期待できるでしょう。
ナレッジ共有ツール(ナレッジマネジメントツール)は、次の記事でも詳しく紹介しています。


おすすめナレッジマネジメントツールの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なナレッジマネジメントツールを含むサービスを徹底比較しています。ぜひナレッジマネジメントツールを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。