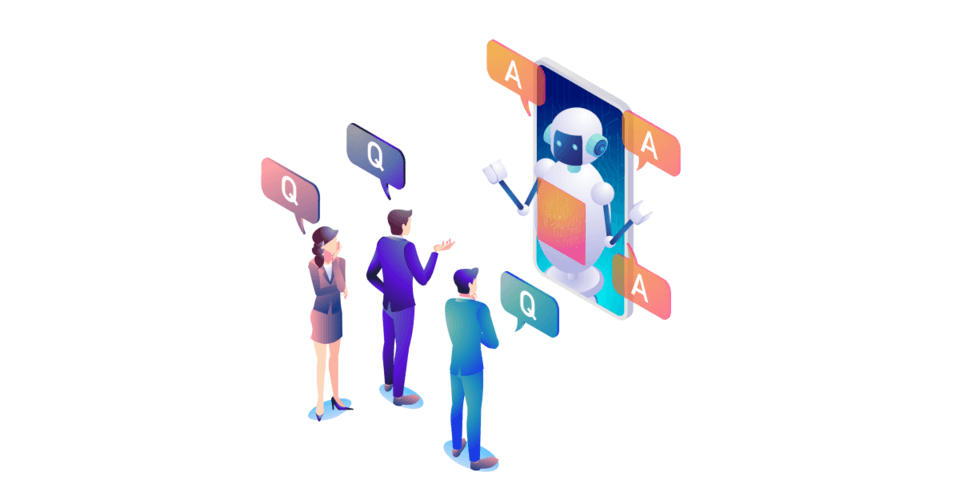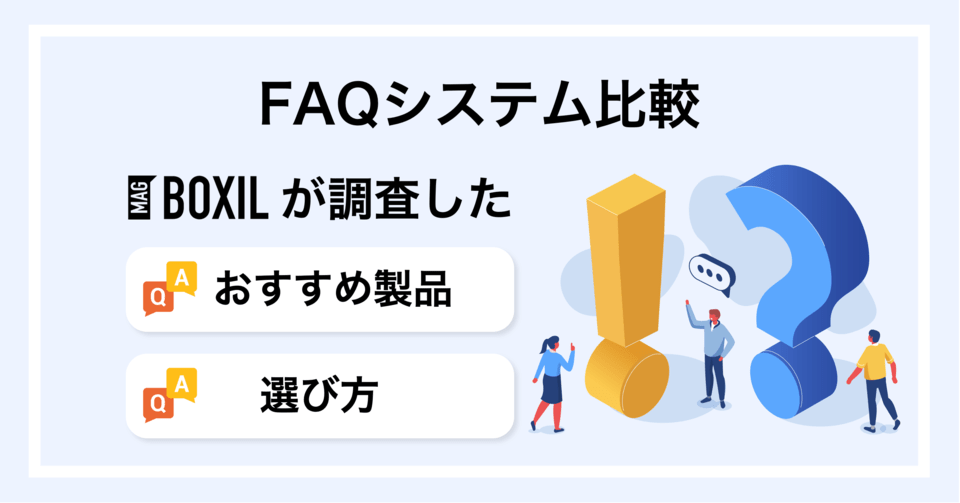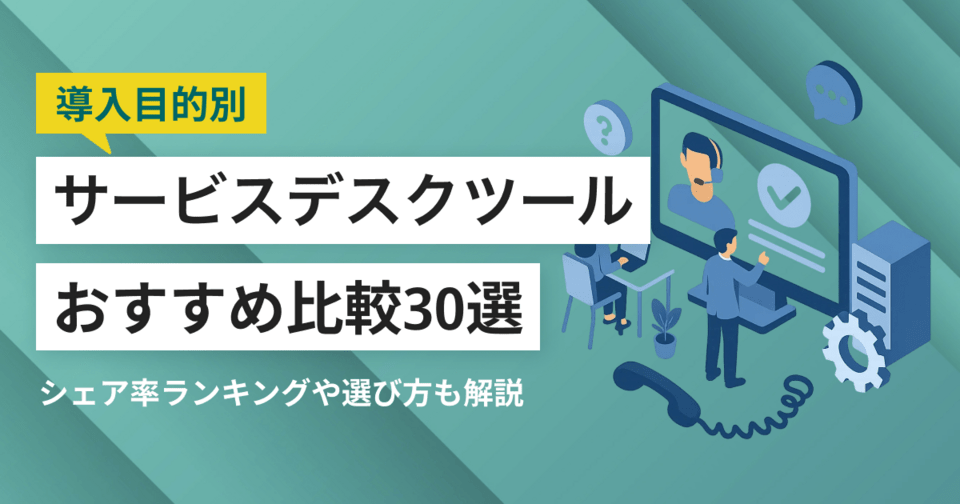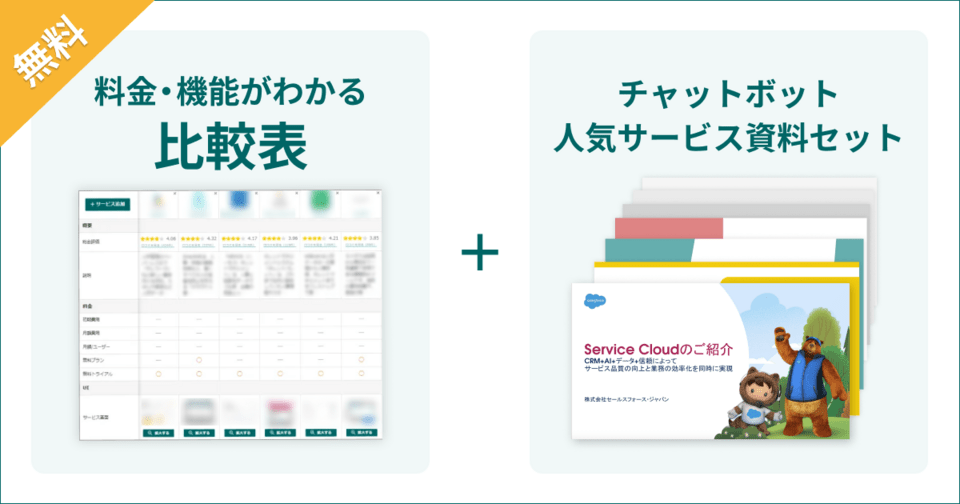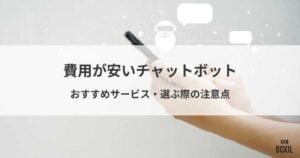チャットボットとは、テキストや音声を通して自動でコミュニケーションを行うプログラムのことです。
チャットボットとは何か、導入するメリットや種類など、基本的な内容に関しては次の記事で詳しく解説しています。こちらを参考にしてください。
チャットボットの失敗事例
顧客とのコミュニケーションを効率化できたり、自社のオペレーター負担が軽減されたりといったメリットから、多くの企業がチャットボットを導入しています。一方でチャットボットの導入に失敗する企業も少なくありません。導入の失敗事例として次のものがあげられます。
- 細かなカスタマイズができなかった
- 設定が難しかった
- チャットボットが使いにくかった
- そもそも利用されていない
- 回答精度が低すぎる
- 問い合わせの内容がチャットボット向きではない
細かなカスタマイズができなかった
自社の目的やニーズに合わせてカスタマイズできずに後悔するケースが少なくありません。
SaaSであれば一定の制限内での利用を念頭に置くべきですが、最低限の要件を満たしていない場合、そもそも導入するシステムを間違えている可能性があります。利用シーンを想定し必要な機能を洗い出して「こんなはずではなかった」となるのを防ぎます。
設定が難しかった
シナリオの細かな設定や自動返信の設定を難しいと感じるユーザーは一定数いるようです。
システム設計の考え方はもちろん、ツールによってはプログラミングのスキルも求められます。担当者のリテラシーとシステムの使いやすさを照らし合わせて、導入後に課題が生じないか確かめましょう。
【改善点】
自動返信によるチャットの返信などは、やや設定が難しい印象があります。とくに細かいシナリオの設定などは骨が折れます。
ChatPlus(チャットプラス)の評判・口コミ より
チャットボットが使いにくかった
顧客はもちろん、社内スタッフでも使いにくいチャットボットを導入した場合も、失敗するケースが多くなります。チャットボットの初心者やIT関連スキルが低くても使いこなせるかが重要です。
そのため、誰でも簡単に使いやすく、直感的に操作できるチャットボットを導入するのがポイントです。たとえば、入力するとサジェストが表示される、何となく触っていても会話が成立する、など扱いやすいチャットボットを選びましょう。
そもそも利用されていない
機能に優れたチャットボットを導入しても、従業員や顧客が使っていなければ意味がありません。チャットボットが使われない理由は次のとおりです。
- チャットボットとの会話が成立しない
- こちらが期待する応答をチャットボットがしてくれない
- チャットボットの存在自体に気がついていなかった
- チャットボットを利用するより、他の手段で連絡したほうが早いと感じた
導入して終わるのでなく、導入後「いかに定着させるか」を踏まえた施策を講じる必要があります。
回答精度が低すぎる
AIチャットボットの回答精度が低すぎる場合、利用者はストレスを感じます。精度が低くなる原因としては、チャットボットを十分に学習させていないケースが考えられます。本来ならリリース前に時間をかけて学習させるところを、学習期間を設けずに導入し、失敗してしまうケースが少なくありません。
テストを十分に行っていても精度が低い場合は、学習させる情報の内容やチャットボット自体の性能に問題がある可能性が高いです。
問い合わせの内容がチャットボット向きではない
問い合わせ対応でチャットボットを導入したものの、チャットボットでは対応できない質問が多い場合、失敗する確率が高くなります。
たとえば、「パソコンの細かいトラブルシューティング」「複数条件を組み合わせた注文」など人による回答が必須となる場合は、チャットボットでは対応しきれません。
逆にチャットボットのフォローを人間が行うことになり、かえって業務の負担が大きくなってしまうリスクもあります。チャットボットを導入する前に対応可能な内容であるかどうかの見極めも重要です。
導入後の成功事例や活用事例については、次の記事をご覧ください。
【関連記事】
・
チャットボットの導入事例
・
チャットボットの導入事例(コールセンター編)
チャットボットの導入に失敗する原因
チャットボットの失敗事例から、失敗原因としては次のものが考えられます
- 課題に合っていない
- チャットボットでは対応できない問い合わせが多い
- 回答の種類が多すぎて精度が上がらない
- 必要なFAQが揃っていない
- メンテナンスができていない
課題に合っていない
チャットボット導入失敗の大きな原因として、課題解決につながるチャットボットを導入できていないケースが考えられます。
たとえば、シニア層が顧客の中心の場合、チャットシステムを設置したとしても電話で問い合わせされる可能性が高いです。チャットボット導入で本当に課題が解決されるかよく検討しましょう。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| システムを活用できそうな若年層からの問い合わせが多く、大半の質問へ回答できそうなため導入 | 問い合わせが多いからとりあえずチャットボットを導入 |
チャットボットでは対応できない問い合わせが多い
申し込み手続きや申請のための問い合わせが多いと、チャットボットではうまく対応できないことが多いです。
申し込み手続きや申請は、チャットボットでの自動応答が難しく、結局人力で対応しなくてはなりません。チャットボットの対応で改善されるパターンなのか、よく確認しておきましょう。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 問い合わせの内容を確認し対応できるチャットボットを導入する | チャットボットを導入してから問い合わせの内容を確認する |
回答の種類が多すぎて精度が上がらない
自動応答させたい回答の種類が多すぎて、精度が向上しないパターンです。
あれもこれもとニッチな質問にまで回答するシステムを構築すると、回答率が下がりかえって精度が低下します。用意すべき質問を見極めたり、他システムを検討したりといった対応が必要です。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 問い合わせの内容によって FAQシステム や音声案内システムも検討する | 問い合わせを解決するにはチャットボットしかないと決めている |
必要なFAQが揃っていない
チャットボットを運用するためには、FAQが必要です。FAQは頻繁に寄せられる問い合わせとその答えのことで、FAQが十分にそろっていなければ、チャットボットの対応は的外れなものになります。
メンテナンスができていない
メンテナンスができていないのも、チャットボットがうまく機能しない原因になります。
運用がうまくいっても、時間の経過とともにFAQの不足や情報の陳腐化が起こり、チャットボットの対応が不適切になる可能性があります。一度チャットボットを設置したから終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要です。
チャットボットの存在がわかりにくい
適切にメンテナンスがされていても、そもそもチャットボットへのアクセスがわかりにくいとうまく活用できません。
ホームページのわかりやすいところに設置してあるか、そもそもアクセスしやすい場所にあるかなどユーザー目線で確認しましょう。
チャットボットを成功させるためのポイント
チャットボット の導入に失敗しないためにも、あらかじめ次のポイントを確認しておきましょう。
- 業務がチャットボットに向いているかどうか検討する
- KPIを細かく設定する
- 運用の責任者を決める
- 想定される質問を洗い出す
- 回答率100%を目指さない
- 運用のアドバイスをしてくれる会社を選ぶ
- FAQシステムを検討する
- テストとデプロイを入念に行う
業務がチャットボットに向いているかどうか検討する
チャットボットは単純な会話のやりとりが得意です。そのため、本当にチャットボットで対応できるかどうか、回答させたい内容を洗い出してみることをおすすめします。
検討の結果、チャットボットの導入を決めた場合は、さらに必要な機能を搭載しているかどうかで、チャットボットを選ぶようにしましょう。
KPIを細かく設定する
チャットボット導入時は、KPI(Key Performance Indicators=重要業績評価指標)を設定しましょう。KPIとは目標の達成度合いを定量的に計測する方法で、ビジネスシーンで広く使われています。チャットボットでは次のようなKPIが考えられます。
- チャットボットの起動数
- チャットボットに対するアクション数
- チャットボットの利用開始率
- チャットボットによる誘導ページへのアクセス率
- コンバージョン数
これらのKPIとして設定し、週単位、月単位で数値をチェックすることで、課題や改善方法が見えるようになります。
運用の責任者を決める
チャットボットを導入する際は、運用責任者を明らかにしましょう。責任や意思決定の所在が不明確だと、システム運用の方向性が定まらなかったり、トラブル時の対応が遅れたりします。KPIを観察し、目標を達成するためにも、誰が陣頭指揮を取るのか明確にしましょう。
想定される質問を洗い出す
どのような問い合わせ・質問が考えられるか、これまでのデータから洗い出しましょう。その後、どのような回答形式であれば回答率を向上できるのか精査していきます。
チャットボットのタイプは、特定のフレーズを検知できる簡易的なチャットボットか、文意を分析するAI型のチャットボットか、電話やLINEと相互的に連携できるチャットボットなどさまざまです。適切なものを選びましょう。
回答率100%を目指さない
たとえチャットボットを念入りに改修しても、回答率を100%にするのは難しいです。
目標とする回答率を設定し、目標の回答率に近づけるためには、どのシステムが適しているのか、また自動応答で解決しない場合は有人対応に回せるかなどをチェックしましょう。
運用のアドバイスをしてくれる会社を選ぶ
チャットボットは運用と改善の繰り返しで効果が高まりますが、社内スタッフだけでは十分な成果を得にくいことがあります。
そこで、運用や改善策のアドバイスまでサポートしているベンダーを選ぶことをおすすめします。プロに運用を任せることで、社内リソースの負担が減り、早い効果が期待できるでしょう。予算と相談して余裕があれば、サポートまでパッケージに含まれているプランを選択してみてください。
FAQシステムを検討する
ニッチな問い合わせ内容へ対応するには、FAQシステムを検討すべきです。類似した問い合わせへ回答し分けたいケースや、手順を詳細に記述したいケースはチャットボットよりFAQシステムが優れています。
また、電話による対応が主であれば音声案内システムを検討しましょう。いずれにしても、課題を明確にしそれを一番解決できる方法を柔軟に探すのが導入に成功する近道です。
テストとデプロイを入念に行う
チャットボットをリリースする前に、必ずテストとデプロイを行いましょう。テストはバグや不具合を見つけるために重要です。デプロイとは、システムを実際の環境に合わせて利用するプロセスを指します。
テストやデプロイに手を抜けば、システムに不具合が起きたり、使いにくいままリリースしたりといった事態になりかねません。ユーザーの満足度低下につながるため、テストとデプロイは入念に行いましょう。
チャットボットの導入手順
導入に失敗しないためにも、正しいチャットボットの導入手順を紹介します。具体的な導入手順は次のとおりです。
- 目的を定める
- 設置場所を決める
- 責任者や担当者を任命する
- ツールを選定する
- ベンダーに相談する
- FAQとシナリオを作成する
- テストを行う
- 運用を始める
目的を定める
まずは、チャットボットの導入目的を定めましょう。たとえば、問い合わせ対応を自動化させて担当者の負担を減らしたい、社内ヘルプデスクを最適化したい、など目的は企業によって異なるでしょう。
また、「社内ヘルプデスク向けツール」や「ECサイト向けのWeb接客ツール」など、目的に特化したチャットボットもあります。自社に最適なツールを選ぶためにも、まずは目的を明確にすることが大切です。
設置場所を決める
目的が定まったら、次にチャットボットの設置場所、いわばプラットフォームを決めましょう。自社の公式ホームページやECサイト、アプリケーションなど設置場所はさまざまです。社外向けのチャットボットであれば、顧客がよく利用するプラットフォームを選定すれば問題ありませんが、社内向けの場合は注意が必要です。
社内向けチャットボットは、あくまで従業員が利用するものなので、自社サイトに設置しても利用されないでしょう。そのため、ビジネスチャットツールやビデオ会議ツールなど、よく利用するツールに設置するのがおすすめです。
責任者や担当者を任命する
チャットボットの導入・運用には、ツールの選定やベンダーとのやり取り、FAQやシナリオの作成など、多くのプロセスや作業が発生します。そのため、陣頭指揮を取る責任者と、チャットボットに携わる担当者を決める必要があります。
導入した後も、利用状況を分析したり、FAQの内容をアップデートしたりと作業量は多いです。スムーズにチャットボットを運用するためにも、責任者と担当者を明確にしておきましょう。
ツールを選定する
責任者と担当者が決まったら、チャットボットツールの選定に移ります。代表的な選定基準は次のとおりです。
- AI機能が搭載されているか
- 目的に合った機能は搭載されているか
- サポート体制は充実しているか
- 無料トライアルは利用できるか
- セキュリティ体制は強固か
チャットボットを初めて導入する場合は、無料トライアルの有無は要チェックです。自社の目的を満たした機能がある、かつ予算内に収まるツールを選定しましょう。顧客や従業員にとって使いやすいインターフェースかどうかも重要です。
ベンダーに相談する
自社の目的やニーズに合ったチャットボットツールが見つかったら、電話やメールなどでベンダーに問い合わせましょう。そこで資料の請求をしたり、ツールの機能や費用感について聞いたりします。気になるツールが複数ある場合は、比較検討するためにも、それぞれのベンダーに相談することが大切です。
なお、この際に無料トライアルについても詳しく聞いてみてください。公式ホームページには無料トライアルの旨が記載されていなくても、実際に問い合わせてみるとデモを使わせてもらえるケースもあります。
FAQとシナリオを作成する
チャットボットツールが決まったら、FAQやシナリオを作成します。FAQとは、ユーザーからの「よくある質問」をまとめたものです。シナリオとは、ユーザーとチャットボットの会話の流れをいいます。たとえば、この質問がきたらこの回答を提示する、これがシナリオ作成です。
チャットボットではシナリオ作成を行うのが普通ですが、コンピューター自体が回答を考える「AI型」の場合、シナリオ作成が不要なケースが珍しくありません。ユーザーに対して精度の高い回答を届けるためにも、FAQやシナリオを充実させましょう。
テストを行う
FAQやシナリオが完成したら、期間や利用者を限定したテストを行いましょう。時間をかけてFAQやシナリオを作っても、ユーザーからの質問や回答を完璧に用意できるわけではありません。実際にテストを行うことで、「不足しているFAQ」や「精度の低い回答」を洗い出せます。テストが無事に完了したら、本番環境に備えたデプロイも行いましょう。
運用を始める
テストとデプロイが完了したら、いよいよチャットボットの運用開始です。運用にあたっては社内外を問わず、利用者への周知が重要です。あらかじめチャットボットを知ってもらうことで、利用促進や定着につながります。
正しい手順と運用でチャットボットの失敗を防ごう
チャットボットでよくある失敗事例と対応策について紹介しました。回答率の低さをはじめ、利用者がチャットボットに不満を感じて使われなくなっては、費用対効果を得られません。何のためにチャットボットを導入するのかといった目的を定め、責任者を設置し、自社に合ったツールを選びましょう。
チャットボットを初めて導入する方は、チャットボットの使用感を確かめるためにも、無料トライアルの利用がおすすめです。複数のチャットボットを比較検討しながら、自社の目的やニーズ、予算に合ったツールを選びましょう。
どのようなチャットボットがあるのか確認したい方や、効率化したい問い合わせを整理できている方は、次のボタンより資料請求してみてください。
\ 稟議や社内提案にも使える!/
チャットボットをより多く比較したい方は、次の記事をチェックするのもおすすめです。
BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
-
累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査