電子契約とは?契約書を電子化するメリット・仕組み・締結方法
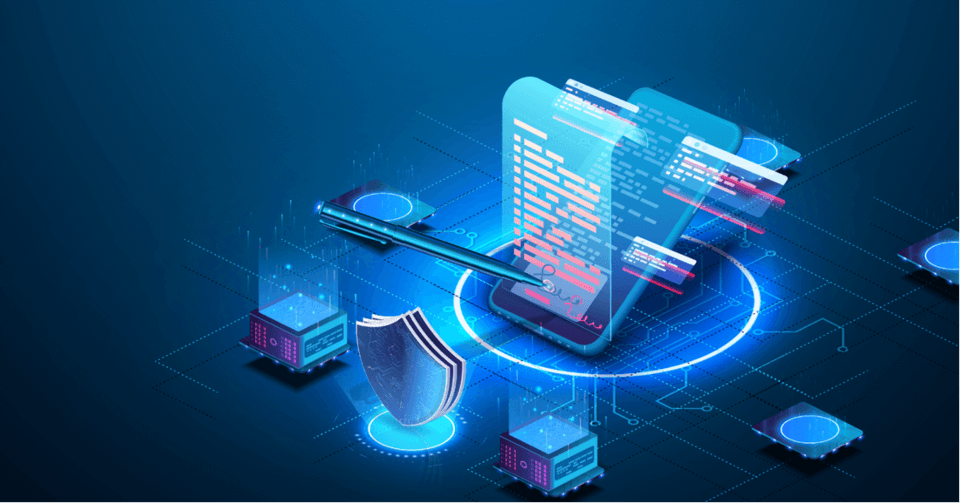
目次を開く
電子契約とは
電子契約とは、電子ファイルに電子署名または電子サインを行うことで締結する契約のことを指します。
日本は商取引の文化として「紙と印鑑」を重要視してきました。しかし、リモートワークをはじめとした働き方が多様化するにつれ、電子取引サービスの需要が高まっています。
また、2020年春のJEPDECの調査によると、従業員数50人以上の国内企業では約43%が電子契約化に取り組んでいて、企業全体における普及率は14%程度と言われています※。今後も導入する企業は増えていくでしょう。
※出典:JEPDEC「企業IT利活用動向調査2021」(2023年10月19日閲覧)
>>電子契約サービス比較|料金・導入事例・無料トライアルあり
電子契約と紙契約の違い
電子契約と書面契約の主要な相違点について、表に簡単にまとめました。
| 項目 | 電子契約 | 書面契約 |
|---|---|---|
| 書類形式 | 電子データ(PDF) | 紙媒体 |
| 書類の送付 | オンライン | 郵送(切手代が必要) |
| 記名・署名・押印 | 電子署名 | 記名:スタンプや印字 署名:肉筆 押印:物理的な印鑑が必要 |
| 印紙税 | 不要 | 必要 |
| 保管・紛失リスク | 電子データを原本として保存可 | 紛失すれば原本の復元は不可 |
電子契約ではWeb上で契約締結が完結するため、紙の契約と比較すると製本・郵送・返送・締結の各段階で、コスト削減と業務効率化の効果を同時に期待できます。契約書締結までのプロセスを効率化できるのが大きな魅力です。
契約書の正しい郵送方法についての解説はこちら
契約書の書き方/雛形はこちら

電子契約が普及するまでの過程
電子契約法の成立
2001年12月25日では「電子消費者契約における錯誤無効制度の特例」ならびに「電子商取引における契約の成立時期の明確化(発信主義から到達主義に変換)」を定める「電子契約法」※が施行されました。
電子契約法のポイントは、消費者の操作ミス救済と契約のタイミングです。ネットショッピングでは、操作ミスで違う商品を注文したり、個数を間違えたりすることもあり得ます。もし事業者側が注文の最終確認画面の用意をしていなかった場合、消費者側の注文ミスによる申し込みは無効になるとされています。
また、契約のタイミングについては注文内容を事業者側が確認し、注文受諾の通知が消費者に届いた時点で契約が成立とみなされるとされました。
※出典: 法令検索「平成十三年法律第九十五号 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」(2023年12月5日閲覧)
事業者署名型サービスの普及
当初は電子認証局による電子証明書を利用する「当事者型署名型」が主流であったものの、2015年以降クラウド事業者が署名鍵を提供する「事業者署名型」電子契約サービスが普及しました。
当事者型署名型で必要だった署名鍵や電子証明書を用意する手間やコストがかからなくなったため、現在では事業者署名型が一般的な方式となります。
その後ペーパーレスやテレワークが推奨されるようになり、電子契約を取り入れる企業が増えました。書類処理や印鑑捺印のために出社するコストを抑えるため、市場規模も大きく拡大しています。
電子契約の証拠力
電子契約の証拠力として使われるのが「電子署名」です。
電子署名とは、電子署名法で認められた電子サインのことを指します。
電子署名法では、電子署名として認められる要件として、「署名が本人に作成されていることを示すもの(本人性)」「改ざんが行われていないかどうかを確認できるもの(非改ざん性)」と定義しています。
そのため、電子署名を作成するには、電子証明書やタイムスタンプといった仕組みにより、本人性と非改ざん性の担保が必要です。これらを満たすことで、電子契約でも法的効力があると認められます。
電子契約のメリット
契約手続きの手間が省ける
押印・印刷・封入・発送の費用および手間を要しないため、業務のスピードアップが期待できます。工程をオンラインで管理できるのも大きなメリットと言えるでしょう。
検索が容易になる
契約に関する情報をデータ化できるので、検索や閲覧が簡単になります。コア業務に集中できるようになり、より業務の効率化が期待できます。
コスト削減
契約書の送信料や保管コストなど契約に関連したコスト削減ができます。また電子契約にすると書面契約で必要だった印紙税がかからなくなるのもメリットと言えます。

電子契約のデメリット
システム料がかかる
新しいシステムを導入する以上、コストがかかります。
初期費用や月額費用、オプションを加えると高額になることもあるので、現在の業務からどのような電子契約システムが必要か精査し、コストパフォーマンスにすぐれたシステムを選びましょう。
システム普及まで時間がかかる
新しいフローに現場のスタッフが慣れるまで、ある程度時間がかかります。マニュアルや研修を準備し、スタッフが新しい業務フローに慣れるようフォローアップしていきましょう。
電子契約に関する法解釈
従来の契約は、紙媒体の契約書に署名や捺印をして行われてきました。この紙媒体の契約書への署名や捺印と同様の効力を電子契約にももたせて、電子契約による取引の安全性を確保する必要があります。電子契約導入を検討している場合は、関連する法律も確認しておきましょう。
契約に関する前提
電子契約による取引の安全性確保のために現在使われているのが、電子署名です。電子署名は、あくまでも従来の紙媒体の契約書に対する署名や捺印の法解釈を基礎としています。
合意の要素となる意思表示の形式は、法律上問われていません。口頭での意思表示でも、「合意」となります。
しかし口頭での合意の場合、後々一方の当事者から「そんな内容では合意していない!」と主張された場合、押印がある契約書の場合と同様の法律の保護が与えられません。なぜなら、口頭による合意のため、当事者が所有する印鑑による押印がなく、民事訴訟法228条4項が適用されないからです。
電子署名法第3条
電子データとして作成された契約書であれば、電子署名法第3条によって、民事訴訟法228条4項と同様の保護が与えられます。電子署名法第3条には、民事訴訟法228条4項と同様の保護を受けるために必要な要件が、次のように定められています。
末尾の「真正に成立したものと推定する。」は、民事訴訟法228条4項と同じです。この推定を受けるために必要な要件に、電子署名法3条が求めている「電子署名」が該当します。
電子署名法2条1項
電子署名は電子署名法2条1項にて、次のように定義されています。
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一:当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二:当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律

電子帳簿保存法
電子署名法のほかに、電子契約の導入には電子帳簿保存法にも注意が必要です。
電子帳簿保存法は、電子契約で取り交わした契約書の保存について定められた法律です。電子契約で締結した契約書を法的効果がある状態で保存する場合は、この法律に則って保存が必要になります。
電子契約システムでは電子帳簿保存法に対応しているものもありますが、機能は各サービスごとによりさまざまなため、電子契約を導入する際には、法律に対応したシステムかどうかを確認して導入する必要があります。
認定スタンプの付与や改ざん防止といった法律に対応できる機能があるのかどうかを確認しましょう。
e-文書法
e-文書法は2005年に施行された文書の電子保存に関わる法律の一つです。e-文書法より、商法や法人税法などにおいて紙媒体での保存が必要だった文書に対し、スキャナ保存した電子化データとしての保存が認められるようになりました。
e-文書法と電子帳簿保存法との違いには、対象となる文書や保存要件があります。e-文書保存法の対象は、見積書や契約書など250の法律で管理されている書類ですが、電子帳簿保存法の対象文書は国税関係書類や帳簿などです。
電子保存を検討する場合は、対象の文書がどの法律に準拠が必要かを確認する必要があります。
印紙税法
印紙税法は1899年に制定された法律で、一定金額以上の取引や領収証に課税される税金について法律です。
印紙税法第2条には、課税対象となる文書には印紙税を収める義務があると規定されています。ただし、印紙税法で規定されている課税対象となる文書は「紙で印刷された文書」であり、電子文書は該当しないため、印紙税は課税されないことになります。
しかし、電子契約を締結しても、書面に印刷して交付する場合は課税文書に該当し、印紙税がかかることに注意しましょう。
電子契約で必要になる機能
電子署名の役割は、電子契約書に記載されている契約名義人によって電子契約書が作成されたことを示すことです。
この電子署名の役割を果たすための機能として、「電子証明書」や「タイムスタンプ」があります。
電子契約書の作成名義人が契約内容をめぐってトラブルに遭った場合、電子署名が契約名義人によってなされたことを証明する必要があります。この証明に用いられるのが、契約当事者以外の第三者(電子契約サービス事業者)が発行する電子証明書です。
また、電子契約が成立しても、事後的に電子データが改ざんされる可能性もあります。そのため、電子データが該当日時に存在していたこと、それ以降に当該電子データが改ざんされていないことを証明するのが、タイムスタンプです。
つまり電子契約には、紙媒体の契約書と同じように、証拠としての法律上の保護を得るために、電子署名が必要です。そして、電子署名が本人になされたものであり、作成後改ざんされたことがないことを示すものとして、電子証明書やタイムスタンプが用いられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子署名 | 押印の代わりに、文書が作成名義人によって作成されたことを示すための措置(詳細な要件は電子署名法2条参照) |
| 電子証明書 | 電子署名が本人によって行われたことを第三者が証明する証明書。事後的に電子契約が当事者間で真正に成立したことを示す。 |
| タイムスタンプ | 電子データがある日時に存在していたこと、および以降に当該電子データを改ざんされていないことが証明できる機能を有する時刻証明情報 |
電子署名
電子署名とは、サインや印鑑にあたるものです。作成者と日時を証明するとともに、署名されると第三者による変更ができなくなる仕組みになります。主に当事者署名と立会人型署名があります。
当事者署名
電子署名のうち、当事者型署名は契約を行う当事者自身が署名鍵を作成するものです。認証サービスを取り扱う会社に、本人証明ができる書類を提出し、発行された電子証明書を用いて電子署名を行います。
身近な例では、マイナンバーカードを用いた「署名用電子署名書」が当事者型署名型にあたります。当事者署名型であれば、紙媒体の契約書と同様の法的効力を有する点も重要なポイントです。
立会人型署名
立会人型署名とは、契約を行う当事者以外の第三者が電子署名を付与することです。基本的にメール認証で本人確認を行います。
立会人型署名は第三者が署名を行っているように思われがちですが、経済産業省は電子署名が本人の意志にもとづいて行われた場合、電子署名法第三条の「本人による電子署名」に該当するとしています※。
※出典:経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)」(2023年10月19日閲覧)
電子証明書
電子証明書とは、認証局によって発行される、インターネットにおける印鑑証明のようなものです。認証局には、公的な認証局と私企業(電子契約サービス事業者)の認証局があります。
当事者型の電子署名を行う際に、サービス事業者から電子証明書を取得したうえで署名を行うことで、当該電子署名が本人によって行われたことを証明する役割があります。
タイムスタンプ
タイムスタンプとは、電子データがある日時に存在していたこと、それ以降に当該電子データが改ざんされていないことを証明できる時刻証明情報のことです。タイムスタンプは、電子契約が締結された後、内容が改ざんされていないことを示すために必要な措置です。
タイムスタンプの有効期限は、一般的に10年とされています。電子証明書の有効期限はサービス事業者によるものの1〜3年とされているため、電子証明書の有効期限が経過すると、契約内容の真実性を証明する役割はタイムスタンプが担うことになります。
タイムスタンプの仕組み
まず、利用者が電子データをハッシュ関数と呼ばれる関数で演算した、ハッシュ値を算出し(算出は各サービスにおいて自動化されています)、これを時刻認証局に送信してタイムスタンプを要求します(下表1)。
これに応じて、時刻認証局は、受信したハッシュ値に対し、時刻情報を偽造できないようにして結合したタイムスタンプを利用者に発行します(下表2)。事後的に電子データの改ざんの有無を調べるには、当該電子データのハッシュ値と、認証局から発行されたタイムスタンプに結合されたハッシュ値を比較し、整合しているかどうかを確認する(下表1)ことになります。
少しでも電子データについて改ざんがされていれば、「3」のステップにおいて、両ハッシュ値は異なるものとなります。


おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
電子契約書の署名とやり方
上述したように、電子契約サービスの署名方法には、当事者型、事業者型があります。
類型ごとの契約締結フローを解説します。
当事者署名型署名方法
当事者署名型の署名方法は次のとおりです。
1.契約書についての電子データの作成
2.認証局に対し、本人性が証明できる書類を提出
3.電子証明書の発行(ICカードや電子ファイルに組み込まれている)
4.送信者において発行された電子証明書を用いて電子署名を行う
5.送信
6.受信者においても、電子証明書の発行と電子署名を行う
7.契約完了/電子契約書を保管
事業者署名型署名方法
事業者署名型の署名方法は次のとおりです。
1.一方当事者が契約書の電子データをサービス事業者ほかのサーバーにアップロードし、他方当事者のメールアドレスを入力する。
2.サービス事業者において契約締結のためのURLを作成し、他方当事者のメールアドレスに送信する。
3.他方当事者が送られてきたURLにアクセスして、契約内容を承諾する。
4.契約完了/電子契約書を保管
【契約締結までのイメージ】
 電子契約の流れ
電子契約の流れ
電子契約の導入方法
電子契約サービス事業者との契約
電子契約を導入するには、電子契約サービス事業者と利用契約を締結する必要があります。
まず、契約書の保管方法が紙媒体から大きく変更するため、契約書保管の担当部署(総務部門や法務部門など)にて、電子契約サービスの周知徹底を行う必要があります。また、文書管理規定や印章管理規程なども改訂する必要があるでしょう。
各部門との確認
電子契約を導入すると、さまざまな業務フローが新しくなります。主に次のような点を確認しておきましょう。
| 部門 | 内容 |
|---|---|
| 総務・法務部門 | 契約書の保管方法・文書管理規定の改訂 |
| 経理部門 | 税務申告における電子データの扱いについての処理フローの改訂、顧問税理士との連携 |
| 情報システム・セキュリティ部門 | 既存システムと電子契約サービスとの適合性チェック、セキュリティ上の問題点の洗い出し |
電子契約の注意点
電子契約では、契約を有効に成立できない契約類型があるので、注意が必要です。契約を成立できない契約類型は、公正証書の作成が必要となるような類型(定期借地権の設定や、事業性貸金の保証契約など)です。
不動産業・建設業においては、一取引当たりの取引額が大きく、契約にかかる事項を当事者間で共有する必要性がより高いため、契約書を書面で交付することが法律上求められています。この書面交付義務も、電子契約の方式では満たされないと考えられています。
訪問販売においても、クーリングオフの権利を行使するきっかけとなる契約内容について記載した書面の交付義務にも、電子契約の方式では満たされないと考えられているため注意しましょう。
電子契約によって締結できない契約の類型の例をいくつか記載します。
【公正証書の作成が必要とされる類型】
- 事業性貸金契約の保証契約(民法465条の6)
- 定期借地契約(借地借家法22条)
- 定期建物賃貸借契約(借借家法38条)
【書面交付が必要とされる類型】
- 宅地建物売買等の媒介契約書(宅建業34条の2)
- 宅地建物売買等契約における重要事項説明時に交付する書面(宅建業法35条)
- 宅地建物売買等契約締結時に交付する契約書等の書面(宅建業法37条)
- マンション管理業務の委託契約書(マンション管理法73条)
- 訪問販売等において交付する書面(特定商取引法4条)
主要3社の電子契約サービス比較表
国内シェアが大きい各電子契約サービス提供事業者の一例を、当事者型・立会人型でそれぞれ紹介します。
どのようなサービスが必要であるか(コストや手間を削減することに重きを置くか、事後的紛争に備え、証拠として安全なサービスを選択するかなど)を検討しながら、各サービスを比較検討してください。
| 項目 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン | Adobe Acrobat Sign |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月額料金 | 10,000円~ | 8,800円~ | 1,848円~ |
| 電子契約種別 | メール認証型(立会人型/指図型) | 当事者型 | 当事者型/立会人型 |
| タイムスタンプ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テンプレート機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ワークフロー・タスク管理機能 | ― | ― | 〇 |
| 契約書管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特徴 | 1. 受信者アドレスごとの個別URLによるメール認証 2. アクセスコードによる2要素認証 |
証拠としての信用性が高い電子契約書を作成できる当事者型を採用しながら、費用が比較的廉価。 | 当事者型/立会人型両方を採用しており、料金体系が豊富。 |

ボクシルおすすめ電子契約システム 【Sponsored】
| 電子印鑑GMOサイン |
|---|
 ・導入企業数No.1※1 ・契約社数No.1※2 ・安全な電子契約、仕事が楽になる、法務選ぶNo.1※3 |
 |
※1 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※2 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」2023年5月時点の数値(2023年6月1日閲覧)
※3 GMOグローバルサイン・ホールディングス「電子印鑑GMOサイン」日本マーケティングリサーチ機構の2020年2月期の調査(2023年6月1日閲覧)
電子契約でコスト削減につなげるために
ここまで電子契約について、紙媒体の契約との締結フローの違いや法的課題、実務で運用されているシステム、導入にあたってのメリット・デメリットを解説してきました。
電子契約は正しく導入すれば金銭的コストおよび工数コストを削減できる新技術であり、また、証拠価値も紙媒体の契約書と同様に認められます。
ただし選択するサービスによっては、紙媒体の契約と同等の法的効力を得られない可能性もあります。自社の文化や取引類型、取引先などの諸条件と照らし合わせて最適なサービスを見つけてください。

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
監修者

BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査























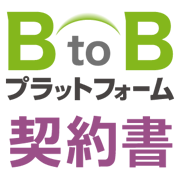

 目次
目次
