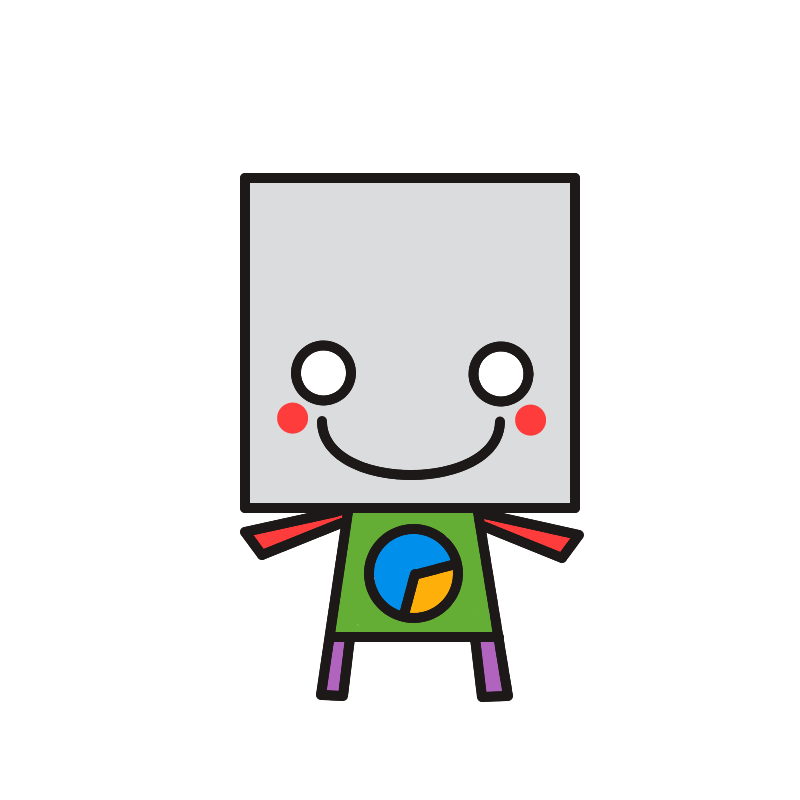採用力とは?ある企業とない企業は何が違う?強い企業の事例も
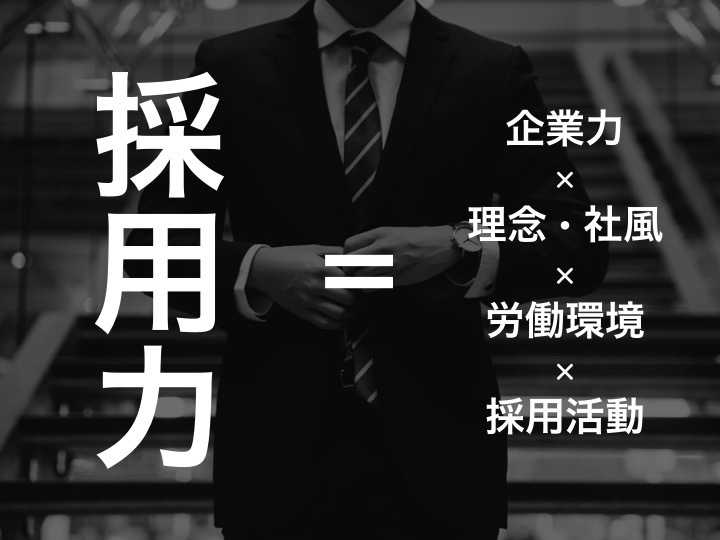
目次を閉じる
採用力とは
一般社団法人 日本採用力検定協会の定義によると、採用力とは「組織および社会に有益な採用活動を設計・実行する力」とされています。一般社団法人 日本採用力検定協会は、企業の採用にかかわる人に向けて、知識やスキルを身につけるための取り組みを行う社団法人です。
また、同協会は採用力を「パースペクティブ」「スキル」「ナレッジ」「アクション」「マインド」の5つから構成されるとも言及しています。
つまり、採用力とは「自社の組織、そして社会に貢献する人材を採用する力」を言い、採用に関するスキルや知識のほかに、採用に向きあう姿勢を含め包括的な能力のことだと言い換えられるでしょう。
採用力の重要性
人材は企業に必要な経営資源の一つです。能力が高い優秀な人材を採用することで、企業の発展につながります。そのため、新しい人材を雇うための採用力は、企業にとって最も重要な能力の一つです。
近年、就転職は売り手市場が進んでいます。今後も採用の競争率はさらに高まっていくでしょう。採用力の低い企業は、今後人材の雇用が難しくなると推測されます。
採用力について理解を深め、「労働条件(給与や福利厚生など)」「企業力(ブランド力)」「採用活動力(広報活動)」といった要素を高めることが必要です。
近年の人材・採用状況
近年の日本では少子高齢化が進み、労働人口減少が進んでいます。優秀な人材をどう確保するかは、どの企業にとっても課題の一つです。

新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスのパンデミックが全世界に広がり、日本の就労環境にも大きな影響を与えています。この状況は、リモートワークの導入や、新しい労働スタイルの採用、働き方改革に対する加速など、労働市場に一連の変化をもたらしました。
とくに、テクノロジー分野やIT関連の職種では、デジタルトランスフォーメーションの需要の高まりとともに、これらの分野で働く人材に対する需要が急増しています。しかし、一方でサービス業や小売り、旅行業など一部の分野では厳しい状況が続いており、人材の流動性や求職者の意向にも変化を見られるのが現状です。
業種間・企業規模による格差
また、業種や企業規模に着目してみると、人気度によって有効求人倍率には大きな違いが表れています。多くの応募者が殺到する人気業種や大企業の競争率がますます高くなる一方、不人気業種や中小企業では、応募者を充分に獲得できない格差が明確に表れているのです。
このような状況のなかで、十分な母集団形成ができずに人材採用までいたらない企業がある一方、多くの候補者のなかから優秀な人材を確保できている企業もあり、両者の違いに注目が集まっています。
次の記事では、就職の売り手市場の現状についてより詳しく解説しています。

採用活動の課題
母集団形成が難しい
採用活動で重要になるのは母集団の形成です。競合他社に後れを取っていたり、知名度がなかったりすると、採用活動の第一ステップである母集団形成がままならい状況に陥りがちです。
求人広告掲載でも応募がなく、結果的に人材採用ができずに再掲載といった悪循環に陥り、採用コストばかりがふくれあがるケースも珍しくありません。

応募者対応の迅速化
スタートアップや中小企業など、人的リソースが少ない企業の場合は、人事担当者を専任させるのは難しくなるでしょう。
このため、採用プロセスにおける担当者の負担は相応のものとなり、応募者へのレスポンスや意思決定が迅速に行えないことが要因となり、結果的に採用にいたらないケースが増加しています。
採用力が高い企業の特徴
採用力が高い企業には、どのような特徴があるのでしょうか。採用力の高い企業に共通した特徴として、次の4つが挙げられます。
採用したい人材が明確
採用力の高い企業は、どのような人材が必要なのか、採用したい人材が明確である特徴があります。
事業計画と現状を把握し、両者の間にあるギャップを埋めるには、どのようなスキルをもった人材が必要なのか、言語化できるようにしておきましょう。
さらに、面接においては、求める人材と求職者がどの程度マッチしているのかを見極める能力も必要です。あらかじめ、面接担当者と現場の社員ですり合わせをして採用基準を明確にしておくと、入社後のミスマッチ防止に役立ちます。
自社の魅力を適切に伝えられる
採用活動においては、自社の魅力を求職者に適切に伝えられる能力も必要です。
仕事内容や給与・休日といった条件面けだけでなく、職場の雰囲気や社員の人柄など、どのようなところに自社の魅力があるのかを理解して、適切にアピールできるようにしておきましょう。
また、「求めている人材から見た自社の魅力」がどのようなものかを把握することも大切です。競合他社にはない、自社ならではの魅力を伝えられるようになることで、多くの応募者から、自社にマッチした人材を採用できるようになるでしょう。
入社後に人材が定着・活躍している
採用力が高い企業は、採用した人材から、入社後に定着・活躍している社員が多いことも特徴です。たとえ自社に合った人材を採用できたとしても、そこで採用が終わりではありません。人材が入社したあと、定着して活躍した段階で、はじめて採用活動が成功したと言えます。
採用後に、早期退職を招く要因には、「ギャップ(Gap)」「リレーション(Relation)」「キャパシティ(Capacity)」の3つがあります。つまり、入社前の期待と現実とのギャップや、上司との関係性、仕事量の多さや少なさといった要素です。
入社後の定着・活躍させるには、採用後の定着まで成し遂げるよう意識して採用活動を行うことが必要です。自社のよい点ばかりを強調して、求職者が過度な期待を抱かないよう、注意しましょう。
自社に合った採用手法を行っている
近年、自社のWebサイト以外にも、人材紹介サービスやリファラル採用など、採用活動を行う方法は数多くあります。採用力のある企業は、数ある手法から自社に合った採用手法を実践していることも特徴です。
たとえば、人材紹介サービスにはエンジニアやコンサルタントなど特定の職種に特化したサービスや、20代向け・ミドル・ハイクラス向けなど、サービスごとに特徴があります。
効率的に求める人材の採用ができるのか、また採用したい人数や予算はいくらまでかけられるのか、いつまでに採用したいのかなどを踏まえて、自社に最適な方法を選びましょう。
採用力が低い企業の特徴
一方、採用力が低い企業には、どのような共通点があるのでしょうか。採用に苦労している企業が陥りがちな問題点として、次のような点が挙げられます。
採用戦略が不明瞭
採用力が低い企業の多くは、採用戦略が不明瞭である問題を抱えています。どのような人材を求め、どのようにして人材を引き寄せ、育成し、長期間保持するかについての明確な計画がない場合、採用活動が無計画かつ反復的になるでしょう。
応募者に求めるレベルが高い
採用力が低い企業の一つの特徴は、求める応募者のレベルが現実的ではないことです。理想の候補者像を追い求めるあまり、求職者のスキル要件を過度に設定してしまい、実際には要件を満たす人材が市場にほとんどいない、あるいは他のより魅力的なオファーに流れてしまっていることがあります。
ほかにも、求めるレベルに対して給与額が適切でないパターンもあります。この場合も応募者は求人に見切りをつけ、すぐに離脱してしまうでしょう。
企業は業界標準を理解と、現実的な求人要件の設定が必要です。
現場とのミスマッチが発生している
就労環境や求めるスキルを最も理解しているのは、現場で働いている従業員です。採用プロセスにおいて、現場の実情と求人情報や採用方針が乖離していると、入社後に仕事内容や職場の雰囲気に適応できず、早期離職を引き起こす「現場とのミスマッチ」が発生します。
これは現場の声を十分に反映せず、現実と異なる職務内容や企業文化をアピールしてしまうことに起因する場合が多いです。
採用活動において現場の意見を積極的に取り入れ、このようなミスマッチを未然に防ぎましょう。
求人の内容が時代に合っていない
時代のニーズに応じて、求職者が重視する点は変化します。たとえば、リモートワークやワークライフバランス、福利厚生の充実などがそれにあたります。
しかし、採用力が低い企業はこれらのニーズに対応した求人内容の更新を怠っていることがしばしばです。とくにテクノロジーの進化や世代交代がもたらす価値観の変化に敏感でない場合、企業は時代遅れの求人情報で優秀な人材を逃してしまうことになります。
求人情報や企業文化を現代の労働市場の傾向に合わせて定期的に見直し、革新的な福利厚生やキャリア開発機会を提供することで、企業はより多くの才能ある候補者の注目を集められるでしょう。
自社の魅力が活用できていない
企業が自身の提供する価値や文化、強みを正しく理解し、それを効果的に外部に伝えられない場合、優秀な人材を引きつけることは難しくなりがちです。自社の魅力が不明確である、または活かせていないと、採用活動はうまくいかないでしょう。
従業員の定着率が低い
入社後の離職率が高いことは、採用力の低さを示すサインの一つです。職場環境の問題やキャリアパス、または報酬体系が不平等といったように、企業内の深刻な問題が原因です。せっかく採用が成功してもすぐに離職してしまうと、常に人材を募集しているように見えてしまい、採用活動も悪循環に陥ってしまうでしょう。
候補者への対応が非人間的
応募者に対して非人間的なアプローチを取る企業は、とくに優秀な人材を失いがちです。たとえば候補者の名前や経歴を把握していなかったり、面接を相互理解の場とせず一方的な質疑応答を行ってしまったりする採用プロセスは、企業の評判を傷つけ、将来的に人材獲得の機会を損なうことにつながってしまうでしょう。
採用力を強化する方法
採用強化を実現するには、注目すべきポイントや対策方法があります。採用力を向上させるためのポイントを順に紹介します。
基本的なポイント
優秀な人材を確保する採用活動とはなにか、まずは基本となる要素を整理してみましょう。
応募者の注目を集める
採用活動は、まず応募者の注目を引くことから始まります。より多くの候補者を集めることで、最適な人材を選べる確率が高まるからです。
そのためには、大きな母集団を形成するために求人広告を利用して応募者を「集めて」、応募者の興味を自社に「引きつけて」おきましょう。
競合他社の存在を意識する
次に重要になるのは、同業他社との競合を意識して採用活動を行うことです。
新卒・中途を問わず、求職者が職を求める場合は、同時に複数の候補を視野に入れて活動するのが通常です。つまり、企業ができるだけ多くの候補者から最適な人材を採用したいと考えるのと同様、求職者もできるだけ多くの企業から最適な職場を選びたいと考えています。
これは企業が選ぶだけでなく、選ばれる立場にもあることを意味しているのです。このポイントを企業側は常に覚えておくべきでしょう。
採用担当者の業務軽減
近年応募者はさまざまなSNS・プラットフォームに触れるようになり、採用側からのアプローチや応募手段は多様化しています。そのため採用担当者の業務は増加の一途をたどっています。
紙ベースやExcelベースではなく、採用管理システムやツールを利用し、業務負担を軽減することで、質の高い採用活動ができるようになるでしょう。
採用力を可視化するための表現方法

企業によって大きな差が現れる人材採用力は、次のような表現が可能です。
採用力=「企業力」x「理念・社風」x「労働環境」x「採用活動」
この4つのそれぞれの項目を強めていくことで採用力をアップさせられるのです。
Business & Company(企業力)
企業のもつ知名度・イメージ・資本力・業種を含む、企業全体の力であり、ブランド力とも言い換えられます。
採用力要因における企業力は、簡単に改善できるものではなく、長い期間と継続した努力が必要です。
Mission & Culture(理念・社風)
企業の理念やミッション、企業文化や環境を含めた社風など、企業がもつ仕事に対する意味合いを指します。
生活のために仕事をしなければならない側面は、もちろんあるでしょう。しかし、若い世代を中心に働くことの意味が見直されている傾向にあり、社会貢献といった理念が明確にされている企業が注目されがちです。
Working Conditions(労働環境)
労働に対する待遇や処遇、制度のことを指します。
給与や雇用形態などが求職者にとって大きな関心ごとであることに加え、働き方の多様化が著しい現代では、多様な働き方を促進する制度や福利厚生なども重要な要因となりつつあります。
Recuruiting Activities(採用活動)
上述した採用活動全般です。
企業に最適な人物像の洗い出しから、募集・面接・採用にいたるまでの多くのプロセスが存在するものの、採用力を高めていくために一番工夫がしやすく、改善が可能な領域だと言えます。
スタートアップ・中小企業が採用力を強化するには
企業が採用力を高めていく要素には、上述した4点が挙げられます。
それでは、大企業のように企業力が高くないスタートアップや中小企業は、どのような対策を行っていけばよいのでしょうか。
たとえば企業力の高い大企業の場合でも、採用活動に力を入れていなければ計算式は、
「企業力」10 x「理念・社風」5 x「労働環境」5 x「採用活動」1 = 250
となるのに対して、中小企業の場合でも企業力以外に力を入れていれば、
「企業力」1 x「理念・社風」6 x「労働環境」6 x「採用活動」10 = 360
といった計算式が成り立ち、採用力が大企業を上回ることも可能です。
それでは、そのためのポイントとなる要素を各項目ごとに見てみましょう。
企業の魅力を高める
すでに解説したように、企業の魅力と価値を高めてブランディングを行うのは長い期間を要するだけでなく、継続した努力が必要です。
もちろん、そのための努力は各企業で行われているに違いありませんが、成長過程のなかでも自社が誇れる魅力は存在するはずであり、これを明確にして採用活動と結びつけていく必要があるでしょう。

候補者へメッセージを届ける
理念やミッションは企業の存在意義にかかわることであり、簡単に路線変更できるものではないでしょう。しかし、それを候補者へメッセージとして伝える工夫はされているでしょうか?
たとえば、家屋の耐震構造強化の業務を行っている企業が、直接的な業務内容を伝えるのと、「国民すべてに安心を与える」業務と伝えるのとでは、候補者へのメッセージ性が変わってきます。
働くことに意味を求める傾向のある現代では、理念やミッションに共感をもつ候補者がより多く現れるかもしれません。
働きやすい環境を整える
同業種であれば、給与といった待遇面は、それほど優遇できないかもしれません。
しかし、働き方の選択を広げ、環境を整えることによってより多くの母数形成を行うことは可能でしょう。
しかも、個々の事情によってフルタイムの勤務ができない優秀な人材は多く、適材適所の人員配置を企業側がいとわなければ、大きな効果が期待できます。
採用活動を改善する3つのポイント
採用力を高めるのに効果的で、工夫の余地があり、すぐに改善に取りかかれるのが採用活動です。
そのため、さまざまなアイディアを試すことも可能ですが、まずは基本的な要素に関しての改善ポイントを解説します。
候補者へのレスポンス
企業がより多くの候補者から人材を選びたいのと同様、候補者もより多くの企業から最適な職場を選びたいと感じています。このため、候補者に対する人事担当者の対応が非常に重要です。
最終的な入社理由のアンケートでは、人事担当の対応や人柄が上位に挙げられることも少なくなく、 なかでもレスポンスの速さが最も重視されています。
これはビジネスパーソンの日々の営業活動でも重視されることであり、もちろん採用活動においても同様です。候補者に対しては必ず迅速なレスポンスを心がけましょう。
一人でも多くの候補者と会う
レスポンスの速さと同様に重視しなければならないのは、一人でも多くの候補者に会うことです。
候補者の人柄や自社とのマッチングを見極めるためには、実際に面談するしか方法はなく、この点にフォーカスすることによって、母集団を形成するためにどうすべきかも見えてくるはずです。
面接のポイント
企業側が買い手市場であった時代、充分な母集団のなかから、最適な人材を選び出すのが面接でした。
しかし、状況が一変した現在では面接のもつ意味合いも変化しており、面接官にも対応が迫られています。
つまり、お互いが選び・選ばれる立場である企業と候補者の面接では、自社の魅力について熱意をもってアピールし、候補者のパーソナリティを引き出したうえで判断することが面接官に求められていると言えます。
優秀な人材を集めるには
採用力が高くなるような優秀な人材を集めるためには、ただ待っているだけでは不十分です。企業は上述した改善ポイントを能動的に取り組んだうえで、自社を魅力的な働き先として位置付ける必要があります。これを実現するためには、次の4つが大切です。
企業文化の明確化
企業文化は、優秀な人材を引き寄せるための磁石のようなものです。明確で、個性的で、共感される企業文化をもつことが、自社を市場で際立たせ理想的な候補者の興味を惹きつけることにつながります。
ブランディング戦略の強化
ポジティブなブランディングは、採用市場で優位に立つための鍵です。これには、Webサイトやソーシャルメディア、仕事紹介サイトなど、さまざまなプラットフォームで一貫したメッセージを伝えることが含まれます。
従業員と交流する機会を設ける
従業員が企業の大使として機能することで、企業の魅力を間接的に伝えられます。みずからの経験を共有し、候補者と対話する機会をもつことで、リアルな職場のイメージを提供できるでしょう。
採用プロセスの人間味あるアプローチ
採用プロセスは、候補者にとって忘れがたい経験でなければなりません。一人ひとりに対する個別の対応や、面接後のフィードバック提供など、人間味のあるアプローチを取り入れることが重要です。
これらの戦略を実施することで市場における競争力を高め、優秀な人材を引き寄せ、そして保持できるようになります。
採用に力を入れている企業の事例(リファラル採用)
ここまで採用力とはなにか、違いがある理由、基本的な対策を解説してきました。いかにして採用力を高められたのか、成功事例をいくつか紹介します。
まずはリファラル採用に力を入れて実績に結びつけた事例です。
事例1:アカツキ

事業内容:モバイルゲーム事業、ライブエクスペリエンス事業
施策:企業の採用力は「採用活動力」と「企業価値」の掛け合わせ
アカツキが考える採用力とは、「A:採用活動力」と「B:企業価値」の掛け合わせであり、「Aの拡大のためにとにかく動く」「Bの拡大のために経営者がみずから発信する」を基本に、次の施策を実施。
- A:経費補助金制度・インセンティブ制度で社内周知
- A:新規入社者へもリファラル採用を周知
- A:採用進捗の定期的な管理
- B:経営者の高いコミット、東証マザーズ上場・新オフィスへ移転
効果:中途入社者の3割強がリファラル採用
従業員の負担を軽減しつつ採用活動力を高める一方、経営者みずからの企業価値発信、具体策の実行を行った結果、大きな成果を実現。
優秀な人材が幸せに働ける環境は、優秀な人材が集まる信念のもと、これからまだまだやれることがあるとの認識だ。
採用に力を入れている企業の事例(採用活動)
次に、スタートアップとして従業員2名から5年で400名まで拡大した採用力の秘密は、「営業アポイントと同じ感覚だった」といった事例です。
事例2:ビズリーチ

事業内容:インターネットを活用したサービス事業
施策:代表みずからKPI設定、1,300人以上と面接
5年前にスタートアップとして、従業員2名で出発したビズリーチは、当然のことながら小さい企業力によって採用力の弱さに悩んでいた。
しかし、代表みずからがKPI設定して面接数をノルマ化、人材の質に妥協しないといった信念をもち、営業アポイントと同様の感覚で1,300人以上との面接を行うまでにいたった。
効果:現在の従業員数400名、採用力=面接数
代表みずからの熱意と信念が実り、徐々に従業員数が拡大。優秀な人材のいる組織には、それが要因となり優秀な人材が集まる好循環を生み出し、現在の従業員数400名を実現、採用力=面接数との認識にいたっている。
すべての要素が重要な採用力の向上
採用力を構成する要素には「企業力」の他、「理念・社風」、「労働環境」、「採用活動」があることを紹介してきました。
それぞれは密接に関連しており、長い歴史をもち、大企業としてのブランド力があっても、バランスが崩れていれば優秀な人材を確保できないことがわかります。
また、事例からも学べるように、優秀な人材のいる組織は、それが理由で優秀な人材が集まる好循環も起こっています。そのためには、従業員が力を発揮して、幸せに働ける環境と社風が必要です。
そして、これらは長い時間をかけて培っていく企業力の強化につながっていくことでもあり、将来を見据えた活動とも言えるでしょう。
採用力をより上昇させるために採用管理システムの導入を検討してみましょう。効率が上がること間違いなしです。


おすすめ採用管理システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な採用管理システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ採用管理システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
関連記事






BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査