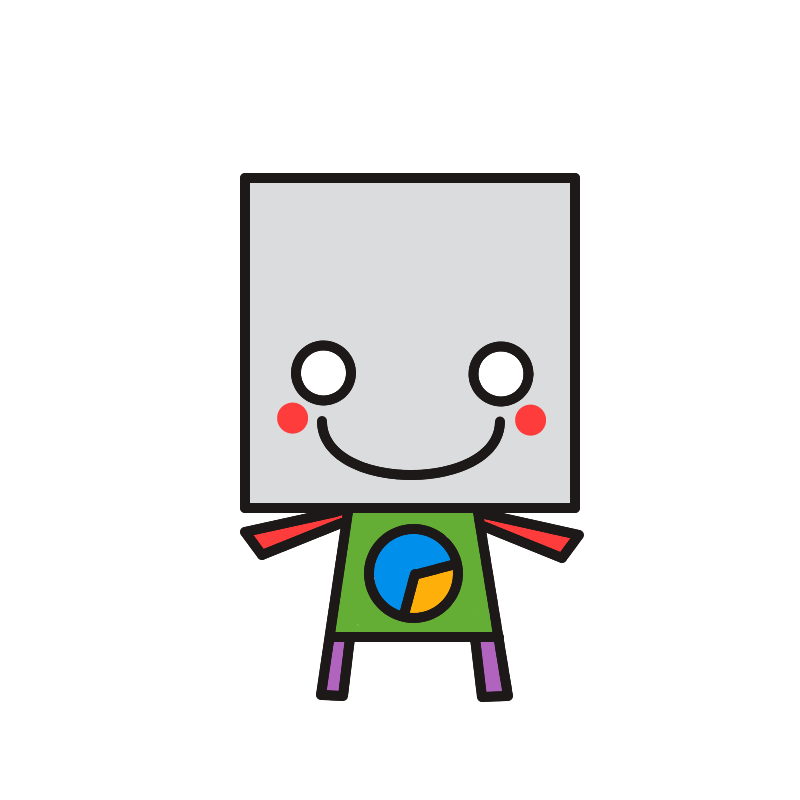人材育成とは?目的や方法、人的資本で成長するポイント

目次を開く
人材育成とは
人材育成とは、社員を企業のビジョンやミッションの実現と持続的成長に貢献できる人材に育てることです。
現在の人材育成は、利益を上げるための能力やスキルの習得だけでなく、企業文化や社会的パーパスを深く理解して行動できる人材を育むことが求められています。
人材開発・能力開発との違い
人材開発・能力開発とは、研修や人材教育により、従業員の能力を引き出したり、スキルアップさせたりする、人材育成のための具体的な施策を意味します。
人材育成には、企業が実施する人材教育のほか、従業員個人の自己啓発や職場での経験、目標管理といったことも含まれています。
人材育成の目的
人材育成は、企業が長期的かつ戦略的に取り組むべきものです。人材育成の取り組みは、企業に次のような成果をもたらします。
- 従業員のパフォーマンスの向上
- 離職率の低下
- 企業の持続的な成長
- 企業ビジョンの実現
- コンプライアンスの強化
従業員のパフォーマンスの向上
従業員のパフォーマンス向上は、人材育成の大きな目的の一つです。
人材育成により現状の仕事内容が改善され、生産性が向上すれば企業の業績アップへ直結します。個人が自律的に学ぶようになれば、成長するための企業文化が形作られていくでしょう。
離職率の低下
人材育成を進めると、離職率の低下の効果も期待できます。
企業が人材育成を積極的に促進してくれることは、従業員のエンゲージメントを高めます。そのため、成長意欲をもったモチベーションの高い社員は、企業ビジョンの実現のために貢献しようと考えるようになり、離職率の低下につながるでしょう。
企業の持続的な成長
人材育成は、企業の持続的な成長に貢献します。
消耗品費や広告費のように一度投資したら効果がなくなるものと比べ、人的資本である社員は、離職するまでバリューを発揮します。人材育成によって、危機の際に的確な判断でビジネスをサポートできたり、今までになかった発想で新規事業を立ち上げたりなど、企業の持続的な成長に貢献する人材を育むことができます。
企業ビジョンの実現
人材育成によって、各社員が企業のミッションやパーパスを深く理解しながら、パフォーマンスを発揮することで、ビジネスが利益を上げるとともに、目標となる企業ビジョンの実現につながっていきます。
コンプライアンスの強化
人材教育に、コンプライアンスや情報セキュリティに関する教育を含めることで、企業は大きなダメージにつながる危機的状況を予防できます。
コンプライアンスを重視する人材が育つことは、幹部やリーダー候補の育成という意味でも、企業にとって大きな価値があります。
人材育成の代表的な方法

人材育成の代表的な手法について紹介します。
【関連記事】
・チームビルディングとは
・組織活性化とは
・モチベーション管理システムの比較
・社内アンケートツールの比較
OJT
OJTとは、On the Job Trainingの略称で、実際に職場で業務を行いながら、仕事に必要なスキルや知識を習得していく人材育成の方法です。一般的には、入社時や新しい部署に配属されたときに行われることが多く、配属先の先輩社員や上司が指導を行います。
指導方法は、OJT担当者のスキルに依存しますが、実践的な人材教育ができるメリットがあります。また、後輩社員を育成することで、OJT担当になった社員自身の成長につながる組織的な人材育成効果もあります。
Off-JT
Off-JTとは、Off the Job Trainingの略称で、社内の集合研修や外部講師を招いてのセミナーや講座などで、知識や技術を習得していく人材育成方法です。Off-JTの期間や回数は人材育成の目的によってさまざまで、専門的なスキル習得からビジネスマナー研修、マネージメント研修、管理職研修などがあります。
Off-JTは職場から離れて行うので、日々の業務を見直せる機会にもつながります。また、普段顔を合わせる機会の少ない他部署や支社同士が合同で行うことで、交流を図れるメリットもあります。現場社員と管理職が合同でOff-JTを行うことで、職場でのギャップを埋め、課題解決をしていくケースもあります。
SD(自己啓発)
SDは、Self Developmentの略称で、自己啓発の一環として自らセミナーに参加したり、書籍で学びの機会を得たりすることです。企業は、業務に関係ある資格取得やスキル習得の費用を援助することで、自律的な人材育成を促進できます。
eラーニング
eラーニングは、インターネットを利用した学習方法です。時間や場所の拘束がないため、従業員が都合のよい時間に受講できるのが大きなメリットです。企業側も対面研修よりもコストが少なく済み、学習の進捗やスキルのレベルが把握できます。
【関連記事】
・eラーニングとは
・eラーニングの導入事例
・eラーニングシステムの比較
ただし、eラーニングのみでは、従業員の学びのモチベーションをどのように維持させていくかという課題があります。このため、eラーニングを集合研修と組み合わせるハイブリッド研修や、オンラインとオフラインの複数の教育方法による「ブレンディッドラーニング」を人材育成に取り入れている企業もあります。
ジョブローテーション
ジョブローテーションとは、社員の能力開発のために定期的に配置転換を実施する人事制度のことです。単なる人事異動とは異なり、企業の戦略的な人材育成計画にもとづいて行われます。
ジョブローテーションの期間はさまざまで、1つの部署・職種で働く期間は半年から数年と、企業の人材育成計画によって異なります。
ジョブローテーションでは、従業員がさまざまな配置転換先の部署を経験することで、ゼネラリストを育成できるメリットがあります

社内公募制度
社内公募制度とは、人材を必要としている部署に社員が自発的に応募する制度です。人手不足の解消が目的ではなく、社員の人材育成の支援を目的としています。
社内公募制度を導入すると、社内の人材が流動的になり、従業員の仕事に対するモチベーションとエンゲージメントの向上につながります。
1on1ミーティングとコーチング
上司と部下の間で定期的に1on1ミーティングやコーチングを実施するのも、人材育成に役立ちます。
コーチングでは、上司は部下に命令するのではなく、部下が自ら課題や解決策に気づけるよう促す役目を担います。
1on1ミーティングとコーチングを積極的に実施することで、個人のパフォーマンスが高まり、離職率の低下と人材育成につながります。

バリュー評価
バリューとは、企業のミッションやビジョンを実現するための、大切している価値観や行動指針を示す企業理念です。
人事評価の際に「バリュー評価」を実施することで、従業員がどの程度自社のバリューや行動規範に沿って活動を行っているかを評価できます。バリュー評価を継続していけば、企業理念やコンプライアンスを重視する人材の育成につながります。

MBO(目標管理)
MBOとは、「Management by Objectives and Self Control」の略称で、従業員個人が目標を設定して、その達成度で評価を決める人事評価方法のことです。従業員が自身で立てた目標に向かって努力するため、自律的な人材の育成が可能になります。
MBOでは、個人が設定した目標に向けて行動し、定期的にその達成度合いを確認します。MBOで目標達成のためのPDCAサイクルを継続することで、従業員のパフォーマンスと生産性が向上していく効果がもたらされます。

OKR
OKRとは、「Objectives and Key Results」の略で、「目標と成果指標」を意味する目標管理のためのフレームワークです。OKRを導入することで、個人と企業の目標を連動させて、人材の能力を最大限に引き出すことが可能なため、経営効率を高める効果的な人材育成が実現できます。
OKRは、企業が定めた目標に対して、部署やチーム、個人単位へと目標を細分化します。このため各従業員は、企業の目標に外れることなく果たすべき目標を定められます。
また、1つの目標に対していくつかの定量的な指標を定めるので、進捗状況を測ることも可能です。OKRは、MBOよりもスピード感があり、個人のパフォーマンス評価は短期間で実施されます。

階層別の人材育成方法
人材育成は、どの階層の社員に対しても一律に行えばよいわけではありません。新入社員、中堅社員、リーダー・管理職の各階層に求められる能力やスキルに合わせて、人材教育や能力開発を実施する必要があります。
新入社員
新入社員の人材育成には、働き方の基本やビジネスマナーといった業務一般で役立つ内容を、OJTやOff-JTで教育するとよいでしょう。
新入社員が今後どのような職種で働いても問題がないよう、ベースとなるスキルを学んでもらい、その後に個別のスキルを習得するよう人材育成を進めます。
中堅社員
中堅社員は、部下をマネジメントするのに必要なスキルが要求されます。自身が成果を上げるためにという考え方から、部下が効果を最大限発揮するためにという考え方へスイッチできるよう促しましょう。
中堅社員の人材育成には、Off-JTの研修やセミナーによる能力開発、目標管理のためのMBOやOKRの活用、1on1ミーティングとコーチングによるサポートが有効です。
リーダー・管理職
リーダーや管理職の方が学ぶべきことには、幅広い部門の知識やマネジメント、経営知識などが挙げられます。
リーダー・管理職の人材育成には、ジョブローテーションによる幅広い部門の知識、Off-JTのマネジメント研修やセミナーによる経営知識の修得、MBOやOKRによる目標管理などが有効です。
人材育成で重要なポイント
ビジョンやミッションの共有
企業文化を理解して、企業成長に貢献できる人材を育成するためには、ビジョンやミッションの共有が前提として必要です。
企業の中長期的な目標であるビジョンは、環境やビジネスモデルの変化により変更されることがありますが、新たなビジョンの策定に社員の声を反映させるのもよい取り組みです。
人事評価の際にバリュー評価を実施して、従業員のビジョンやミッションを実現させるための行動規範について、定期的に評価を行うのもよいでしょう。
社員の自発性を高める
社員の自発性を高めることも、人材育成において重要なポイントです。
社員の自発性を高めるためには、自己啓発の研修なども必要ですが、さらに重要なのは社員が自発的に学びやすい環境と、それを公平に評価する制度を整備することです。
社員の資格取得やセミナー参加を会社として補助したり、人事評価の中に自主的な学びを評価する項目を設けたりして、自発的に行動する人材が評価される環境を構築しましょう。
育成目標を立てる
人材開発や能力開発によって達成したい目標を明確にして、社員と共有することも重要です。各個人の強味を引き出す場合も、弱みを克服する場合も、目指す目標の形を明確にすることが重要です。
これにより、人材育成の到達地点が明らかになり、企業が必要とする戦略的な人材育成計画が可能になります。
効果測定を行う
人材開発や能力開発を行ったら、必ずその効果を把握しましょう。実施した研修や教育プログラムは、「社員の意識をどのように変化させられたか」、「どのような行動変容をもたらしたのか」など、人材教育後の変化をさまざまな手法を使って評価します。
人材教育の効果測定を行うことで、PDCAによる人材育成計画が構築でき、人的資本経営につながっていきます。
コンプライアンス教育を含める
人材育成には、必ずコンプライアンス教育を含めることが重要です。
近年は、企業のコンプライアンスが重視されるようになり、株主や投資家も厳しくチェックしています。従業員のコンプライアンスへの意識が低いと、企業の信用を大きく損ないかねないコンプライアンス違反が発生してしまうリスクがあります。
また、情報漏えいやサイバー攻撃が増加しているなか、コンプライアンス教育とともに情報セキュリティ教育の必要性も高まっています。
コンプライアンスや情報セキュリティに関する人材教育は、企業が大きな代償を払うことになる危機的状況を避けるために、定期的に実施することが必要です。
人材育成に役立つサービス
現代のビジネスシーンに役立つ、人材育成サービスを紹介します。
- 組織心理学の観点を踏まえて考案された100種類以上※1のプログラム
- 参加者満足度97%※2の参加型プログラム
- 企画から講師の手配、運営、報告まで一括対応
バヅクリは、教育研修とコミュニケーション支援を組み合わせたイベントを開催できるサービスです。プログラムは対話、学び、アソビをベースに考案され、スキルアップや社内の関係構築につながるプログラムを利用できます。
オンライン営業研修や管理職向け指導研修、内定者フォローや労働組合イベントなどのプログラムがあり、課題に応じて利用可能です。企画から運営、実施後の結果をもとにした解決企画の提案まで、ワンストップで対応してくれます。
※1,2 バヅクリ公式サイトより(2022年11月29日閲覧)
7つの習慣®︎SIGNATURE EDITION4.0 - フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

- 書籍「7つの習慣®️︎」をベースにした研修プログラム
- 定着と実践に焦点をあてた研修構成
- 知識やスキルだけでなく、受講者の人格を磨く
7つの習慣®️︎SIGNATURE EDITION 4.0は、現代のライフスタイルやビジネスシーンをイメージしやすい内容を盛り込んだ研修プログラムです。課題や日々の生活を通して応用できる内容です。知識やスキルだけでなく、受講者の人格を磨くことを重視したプログラムなので、受講者の高い満足度も期待できます。
mentor - 株式会社サイダス
- 新入社員が抱える課題や体調の変化を把握
- 体調やメンタルまで把握し、離職を防止
- メンター制度、OJTを仕組み化し新入社員の成長を支援
mentorは、新入社員の状態や課題を見える化し、人材育成を支援するサービスです。OJTの後に実施するアンケートで新入社員の課題や弱点を可視化。メンターにもアンケートを実施することで、新入社員とのギャップを把握し、マネジメントの改善につなげます。
また、健康状態を週次で見える化できるので、テレワーク下でも新入社員の悩みや体調の変化に早く気づけます。適切な対応をすることで新入社員の早期離職を防止できます。
クアルトリクス 従業員エクスペリエンス(EX)|Qualtrics - クアルトリクス合同会社
- アンケートをもとに、従業員の現状を把握
- アンケートや多角的な評価を自動で実施
- 従業員一人ひとりに合った能力開発を目指せる
クアルトリクス 従業員エクスペリエンス(EX)は、従業員の企業に対する意見や感情を把握し、人材育成に役立てるシステムです。従業員アンケートを任意のタイミングあるいは一定の期間ごとに実施しデータを収集。集めたデータをもとにそれぞれの従業員の考えを把握したり、改善につなげたりできます。従業員への研修を最適化し、効果的にスキルアップさせましょう。
働く女性に特化した研修プログラム
働く女性に特化した、仕事とプライベートを通して成長し続けるための研修サービスを紹介します。
ビジョナリー・ウーマン - フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

- 書籍「7つの習慣®️︎」をベースにした女性向け研修プログラム
- 働く女性の自立とやりがいをアシスト
- 実際のビジネスシーンをイメージしやすい実践形式の研修
ビジョナリー・ウーマンは、働く女性がやりがいを持って自立的に仕事へ取り組むための研修プログラムです。スキルや知識を身に付ける研修とは異なり、人格を磨き、主体性をもってさまざまなことに取り組む姿勢が身につきます。ビジネスシーンで遭遇しやすい課題を元にした研修構成なので、内容が定着しやすく研修後すぐ実務に活かせます。仕事とプライベートの両立を目指すことで、業務のパフォーマンスアップにもつながります。
人材育成によって企業を持続的に成長させよう
企業は人材育成を戦略的に行うことで、ビジョンやミッションの実現と持続的成長に貢献できる人材を得ることができます。
企業に求められる行動規範や、コンプライアンスを重視した人材を育成することは、人的資本経営のベースとなり、企業の長期的な競争力の強化につながるでしょう。
人材育成に役立つサービスとして、社員一人ひとりの能力やスキル、成果を確認できるツールがあります。次の記事ではそんな社員の特性を把握する考え方やシステムを紹介します。


BOXILとは
BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。
- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!
BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。
BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。
BOXIL SaaSへ掲載しませんか?
- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※
- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心
※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査